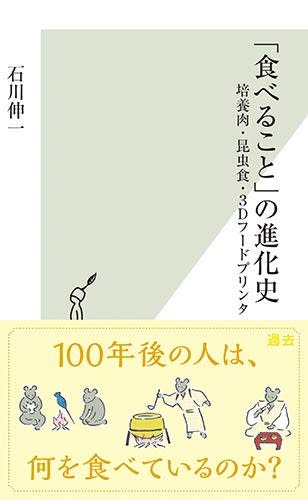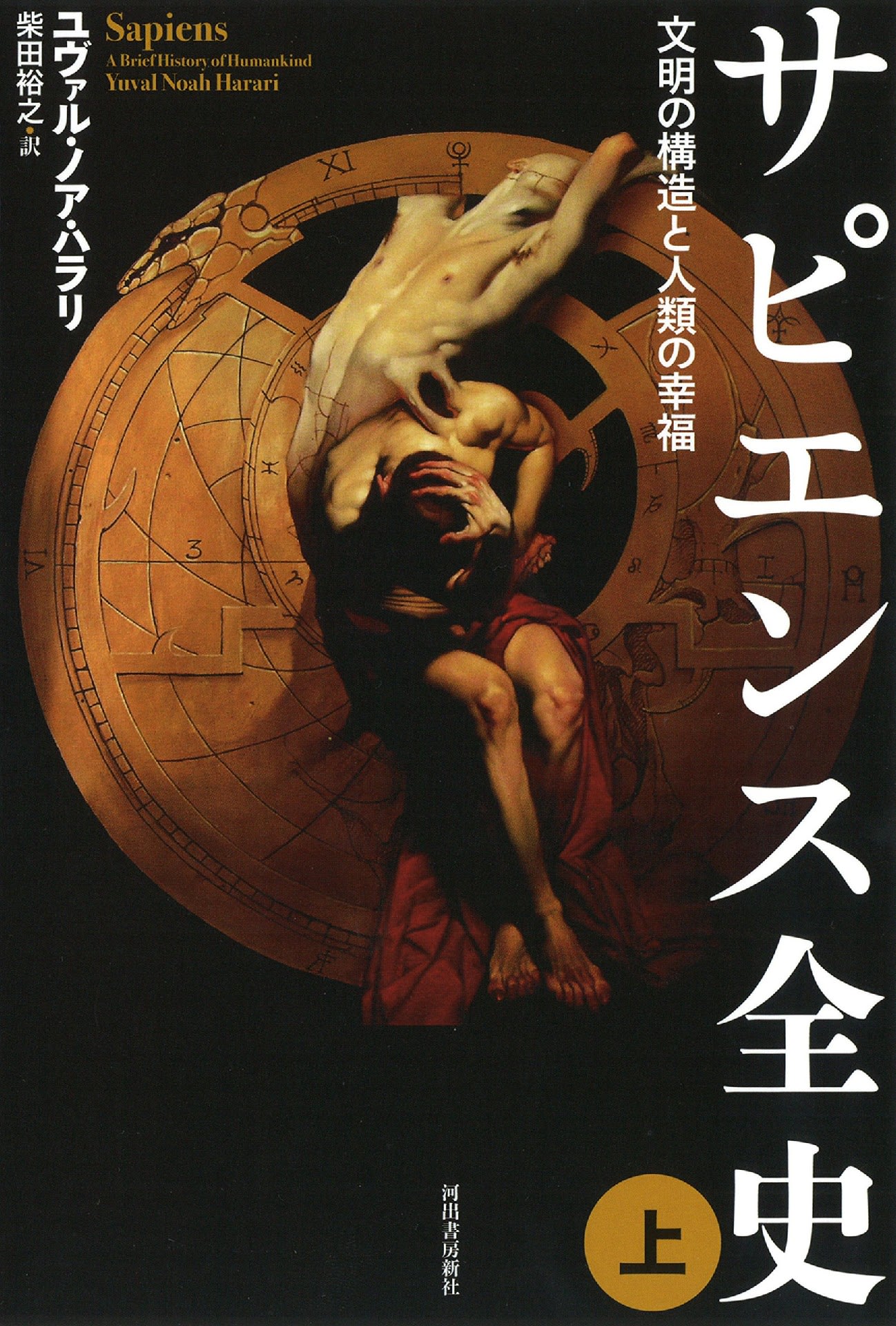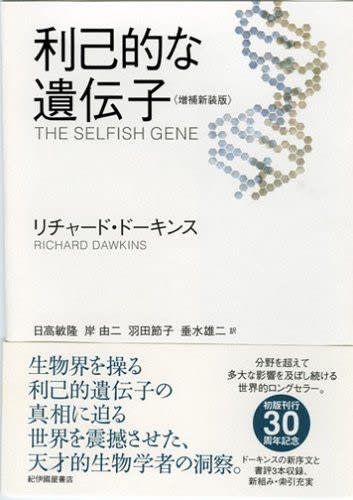帯に、ジャレド・ダイアモンド絶賛!!などと書かれているので、間違いないだろうと思って買ってしまったが、ちょっと判断を誤ったか?当初、食の進化の系統的な説明を読みたいと思っていたのだが、いざ読んでみると旅のエピソードやら様々な説やらがグルグル渦巻いていて、結局結論はなんだったんだ?という感じが最初から最後まで続く本であった。それでも、興味深い内容はいろいろと抽出できたので、気を取り直してなんとかまとめてみる。
本書は、著者の自然人類学の研究のための世界の旅で得たたくさんの知見や、食に関わる多くの人たちへの取材で得られた情報を絡めながら、食の健康への影響を考えていく。現代では、食が関連して数多くの健康問題が浮上してきているが、それを解決する上で非常に重要なことが「進化」の視点であるという考えのもと、論考が進められていく。本書で対象とされているのは、昆虫食、果物、肉、魚、植物性食品、アルコール、乳製品、アレルギー・感染症、肥満、伝統食である。
昆虫食:昆虫はかつて人間社会の主要なカロリー源だった。昆虫には必須アミノ酸、オメガ3、オメガ6脂肪酸、ビタミンB、βカロチン、ビタミンE、カルシウム、鉄、マグネシウムなどが含まれ、それらの含有濃度は肉を上回る場合もある。そして、食用昆虫の養殖は、環境への影響がずっと少ない。コオロギは、体重1単位量を増やす際の二酸化炭素排出量が畜牛の50%で、飼料を効率的に食料に変換する割合は、鶏の2倍、豚の4倍、畜牛の12倍だという。あなたも自分好みの昆虫を見つけて食べていいのだと勧めている。
果物:スティーブ・ジョブスのすい臓がんは、彼が実験的に行っていた極端な果食主義と関りがあると推測する人たちがいる。映画でスティーブ・ジョブス役を演じる役作りのために1ヶ月間果食主義を続けた俳優のアシュトン・カッチャーはインスリンとすい臓の異常で入院することになったという。
進化における遺伝子の変化:
①我々の霊長類の祖先はビタミンCを合成する能力を失った。ビタミンC合成の最終段階に関わる酵素GLO(Lグロノラクトン酸化酵素)遺伝子が働かなくなったためである。熱帯多雨林で暮らしていた我々の祖先は、十分な果物や昆虫からビタミンCを得ることができたからだという。
②4千万年前から1千6百万年前までの間に、我々の祖先は、ウリカーゼという尿酸の分解を助ける酵素の遺伝子を徐々に失い、そのために尿酸値が上昇しはじめた。それにより、痛風の疾病素因を持つようになった。尿酸の進化についての一つの仮説は、ビタミンCを生成できなくなった代わりに、尿酸を抗酸化剤として利用するようになったというものだ。
③アルコール・デヒドロゲナーゼ(ADH)遺伝子は、アルコールをアセトアルデヒドに変換するのを助ける遺伝子だ。1万年から7千年前に、人類にADH遺伝子の変異体が出現し、とくに東アジアで広まった。この変異体は、有害なアセトアルデヒドを大量に生成することで、アセトアルデヒドの分解が間に合わなくなり、顔が赤くなる、頭が痛くなる、二日酔いになる、といった症状を引き起こす。これらの症状が、ADH変異遺伝子保持者に飲み過ぎを控えさせ、彼らを守っているという。この遺伝子変異体の出現率は、コメの栽培が最初に始まり、そのすぐあとに米を使った酒が生まれた場所で高まった。
④酪農の歴史をもたず、乳製品からカルシウムを摂ることのない民族では、カルシウムをより効率的に吸収することを可能とする遺伝子の変異を持ち、骨密度を高めるのに役立っている。一方、毎日大量のカルシウムを摂取する現代の食事においては、カルシウムの影響を受けやすい前立腺がんのリスクが高まる。こうした遺伝子は、アメリカ南西部に住むアフリカ系アメリカ人の71%、東京に住む日本人の45%、ヨーロッパ北西部を出自とするユタ州の住人の20%が持っている。
⑤牛乳と大量の肉を摂取している牧畜民は、それらの食物に含まれる大量のコレステロールに対処できるように遺伝子的適応が生じている。マサイ族の1日当たりコレステロール摂取量は、欧米人の4~6倍にのぼるが、コレステロールの血中濃度は、欧米人よりもはるかに低い。マサイ族では、コレステロールの代謝と合成、アテローム性動脈硬化症(コレステロールの沈殿による動脈の硬化)に関わる遺伝子の変異が認められる。
⑥ラクターゼ持続性は、成人になっても乳糖を分解するラクターゼの生成が衰えないことである。ラクターゼ持続性は、伝統的に乳製品に頼ってきた、イギリス人、スカンジナビア人、北インド人、東アフリカや中東の人々で高い。南インドや地中海東部では15%程度あるが、西アフリカ、東アジア、アメリカ大陸ではほとんど見られない。全体的には、世界の3人に2人がラクターゼ生成能をもっていない。
食の民族間の違い:食べ物に関する文化的習慣が民族的対立に発展し、よそ者を排除するために使われることもある。例えば、かつてエジプトの都市オクシリンクスでは、エレファントノーズドフィッシュが崇拝されていた。ある日、キノポリスの住人がエレファントノーズドフィッシュを食べているところを目撃したオクシリンクスの住人が、仕返しにキノポリスの人々が神聖視していた犬を食べ、それがきっかけで内戦が始まったという。また、ベトナム人が1970年代にマレーシアのある島の難民収容所に収容されていた時、所内で豚を捕まえて食べているのを見つかった収容者は、地元当局によって鞭打ちの刑に処されていたという。ある人にとって崇拝の対象が、他の人には食事の対象となるということがあるのだ。
日光の影響:日光に当たることはホルモンやビタミンを介して、体に様々な良い影響を及ぼしている。そうしたものとして、ドーパミンを介した近視、セロトニンを介した季節性情動障害(SAD)や抑うつ、メラトニンやビタミンDを介した統合失調症や自閉症などの抑制が、考えられている。日光はビタミンDを生成する。ビタミンD不足と喘息、アレルギー性鼻炎、食物アレルギー、アトピー性皮膚炎の関係は長年研究が行われている。血中のビタミンD濃度の高さとこれら疾患の発症率の低さは相関するが、日光に当たるのはよくても、ビタミンDを摂取すればこれらの疾患の抑制につながるわけではないという報告も多く複雑である。
肥満の原因:肥満の原因は、過剰な食物摂取だと言われているが本当にそうだろうか。現代人の食物の摂取量やエネルギー消費の程度は祖先たちの時代とほぼ同じである可能性がある。著者は、身体的不活動が鍵だと考える。人類の祖先は長時間じっとしていることはめったになかった。一方、現代人は、テレビを見る、机の前に座る、運転する、などと動かない時間が長い。
栄養学的研究の限界:これまでの栄養学的研究の主な欠点は、進化理論がもたらす洞察を無視してきたことだ。人類の背後にある進化の歴史を理解せずに最適な食事法を決定しようとするのは、無理がある。進化の理論だけが、栄養や健康も含めて、生物体の構成要素のすべてがどのようにつながり合っているかを理解する方法を提供してくれる。
食べ方と生き方のルール:最後に、上記の視点に立って食と健康に関する普遍的な真理が挙げられている。
①よく歩く
②アルコールは適量を
③若いときは肉と乳製品は控えめに
④伝統食を(自民族の祖先が食べていたものを)食べる
⑤持続可能なやり方で食べる
⑥自分の肌タイプが必要とするだけの日光を浴びる
⑦安全な菌や寄生虫に感染する
⑧料理は低温で
⑨流行りのダイエットは効果がない(運動不足を補おうとして食事法を変えても望む結果は得られない)