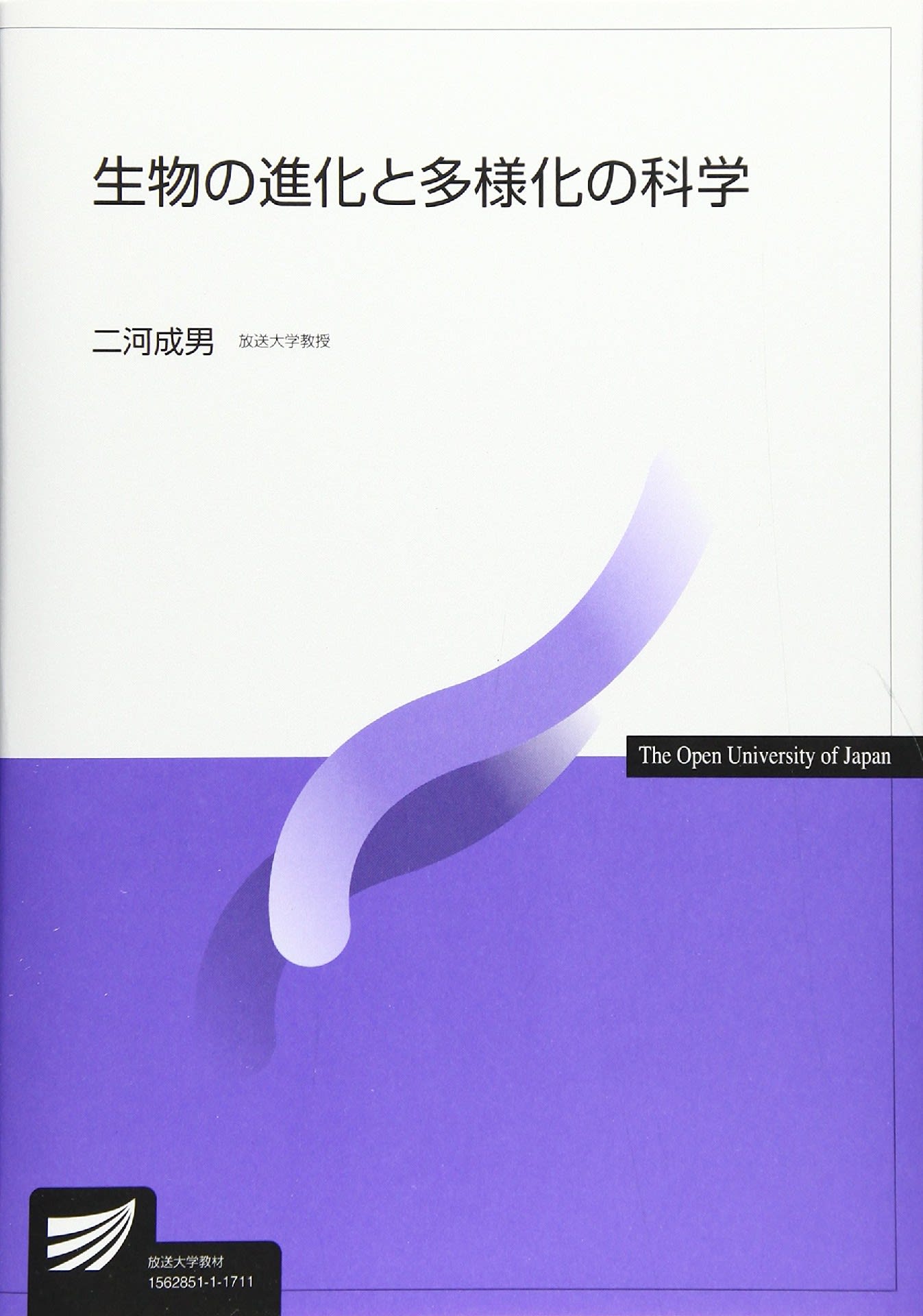とうの昔に絶滅してしまった古生代の動物(一部植物もあり)たちの姿を、精細かつ大きさを考慮して復元させて、現代の風景に出現させてみせたタイムマシーンのような図鑑である。2018年7月21日に発売されたが、Amazonの売れ筋ランキングでは、地球科学と生物学のカテゴリーで、今でも(2018年10月13日現在)第3位である。しばらくは第1位を続けたのだと思う。この分野の本としては大ヒットじゃないだろうか。アイデアが良かったが、これだけ精細な古生物のイラストを多数(207ページの本)制作した労力も貢献している。CGを使って描いているのだろうか。かなり想像も入っているのだろうが、とても生き生きとあたかも今も生きている生物のように描かれている。いわゆる進化学の教科書では、ここまでしか分かりません、といわんばかりのそうとう単純なイラストしか載っていないのと対照的である。背景の多くは、istock(ゲッティイメージズ)の画像を使用している。つまり出来合いの写真を購入して使っているのであるが、そこはコストのこともあり仕方ないのだろう。ただし、出てくる人物がほとんど白人なのがすこし気になった。それで絵としては映えるのだが、なんか広告のようでもある。まあ、これらの化石がヨーロッパやアメリカを中心に世界中から見つかっていることも確かなのだが。
99ページに各種のウミサソリ類が並べて描かれているが、ほとんどケジラミのように見える。これが現代の風景に合体すると、数十cmから2m近くもあるのだからおそろしくなる。それにしても、古生代にはみょうな形の動物が多かったと実感する。しかし、あるていど一定の形には収まっているとも思う。現代の生物と共通な原理で形作られてれていたのだなと思うのである。