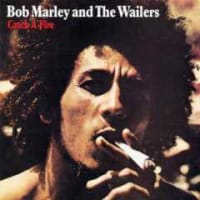ベートーヴェンの弦楽四重奏曲に関しては、このブログでこれまで、変ホ長調第10番、へ短調第11番とレビューを書いて、おっとやはりラズモフスキー無くしては先に進めないとちょっと元に戻って、ヘ長調第7番、ホ短調第8番、ハ長調第9番の鑑賞を書いた。そして今、12番に戻ってきたという順番で書いている。
しつこいようだが、ベートーヴェンは古典派音楽を完成させたという言い方よりも、ソナタ形式を極めたという言い方が正しいと勝手に思う。理由はふたつ。前者に関しては、既にこの楽曲を書いた時代には、ハイドンとモーツァルトが完成させた音楽より、一歩も二歩も次の段階にいたと言って良い。また、彼の後継となる音楽家たちは、彼より新しいものの提示はまだなかった。具体的に言えば、ロッシーニやシューベルトは表現方法が違うだけで、モーツァルトより新しくない。どころか、ことソナタ形式で言えば、ベートーヴェンの域にない。メンデルスゾーンで漸く新しい試みが出始めて、所謂本当に目新しい試みというのはシューマンとショパンである。従って、古典とロマンの境界線はベートーヴェンの途中になるか、若しくはシューマンである。私の説は後者である。そしてその理由がもうひとつのベートーヴェンを象徴する表現、ソナタ形式を極めたことである。無論、ハイドンが量産した交響曲と弦楽四重奏曲で、ソナタ形式は殆ど完成し、モーツァルトはそれに更に多くの楽器を用いるという観点で望んだ。だからソナタは完成していたのであるが、モーツァルトは本当に新しいソナタ形式の構造的にチャレンジはしなかった。彼はそれ以上に楽器というものに興味をもち、その最終形として出会ったピアノ楽器に心髄した。つまりはピアノ協奏曲の完成度が大変高い。だが、ベートーヴェンは更に進化していくピアノ楽器を、オケの一員としてではなく、オケの代行になると考えたために、モーツァルトがやったことはピアノソナタという形式を持ち、つまりはピアノ1台で全て完結させてしまった。その後に交響曲と、残った弦楽四重奏曲という形式の中で、更にソナタ形式を極めるところに音楽人生の最後の終着点を見つけたのである。これは、第11番を作曲して、なんと14年間の時間が経っていたのである。しかも変ホ長調という、そう、これは「英雄」の調である。交響曲第3番「英雄」と、更に、前述したモーツァルトが極めたピアノ協奏曲を、簡単に上回ってしまったピアノ協奏曲第5番「皇帝」の調である。敢えて、この十八番の調を使ったところにベートーヴェンらしい音楽のあくことなき挑戦と揺るぎない自信の両面を窺うことができるのだ。何が素晴らしいかというと、この曲は第2楽章に尽きる。ここはまさにベートーヴェンの後期様式の特徴が随所にみられる変奏曲形式である。特に後半第4変奏のアダージョは見事であり、一転した第5変奏は素晴らしい。勿論、モーツァルトの弦楽四重奏曲も素晴らしいが、一方でモーツァルトは例えば、クラリネット協奏曲や、クラリネット五重奏曲とくらべると、弦楽はどうなのかと思うと、残念ながら見劣りしてしまうが、ベートーヴェンは既にラズモフスキーでモーツァルトのハイドン・セットを楽典的に上回り、さらにこの14年ぶりの12番で、4楽章構成の弦楽四重奏曲でこの領域の音楽を完成させた。そして、この後は、もう4楽章とか、そういうこと拘るのではなく、全く新しい世界の発掘・発見に勤しむのである。実は、そう考えると、これは、交響曲第9番「合唱」も同じような試み、というはある意味で反則をしていて、同時期のこの12番も同じであるから、ソナタ的に言うとここが境界線であり、これで後継者のために新しい音楽への足がかりを作ったという言い方が正しい。実に桁違いの曲である。
映画にもなったが、実はペートーヴェンの苦悩とは、第九での大喝采が分からない程、耳が不自由だったことではなく、最晩年に挑んだ大フーガを含む弦楽四重奏曲との格闘で、それは今までに誰も聴いたことのない、新しい音楽へのチャレンジだったのである。特に、楽器マニアのモーツァルトのようにどんな楽器でも主役になれるだぞパターンではなく、アンサンブルである以上、それぞれの楽器のやり方はその楽器が一番良く知っているというジレンマ、その部分との戦いが最後の苦悩になったのであり、勿論、彼の晩年、いや、古典派音楽の晩年を飾るのにふさわしい楽曲を世に送り出したのであった。
こちらから試聴できます