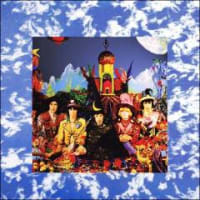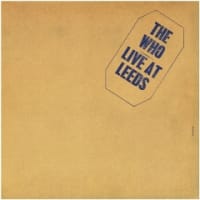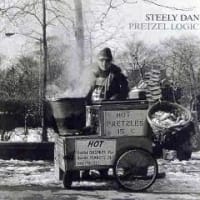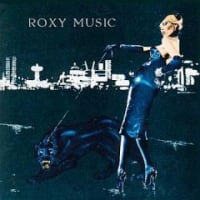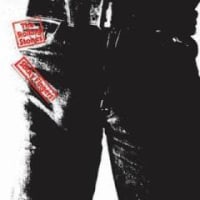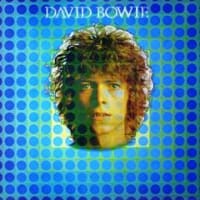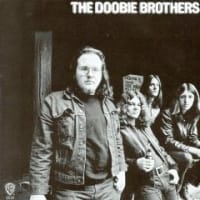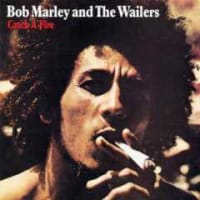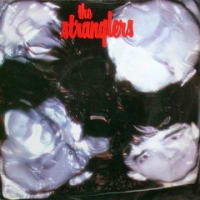いま始めて気づいたが、このブログでモーツァルトの楽曲を取り上げるのは初めてのことである。過去に何度もチャンスがあったし、幾ら、ベートーヴェン、ブラームス好きであっても、如何せん作曲の絶対数が違う訳だから、私のライブラリーも、レコードも入れて100枚を越えているのは、クラシックではこの3人とバッハくらいのものだし、モーツァルトに関して言えば、300枚は越えていて断トツであると思う。しかし、逆にそのせいか、今まで、「どこから始めたら良いのだろうか」と迷ってしまい、中々スタートできなかったのだと思う。だから自分的には良いきっかけになったと思う。
しかし、当時は数ある彼の名曲から、良くこんな曲を選んだと自分のことながら感心してしまう。やはり神童だったんだなぁと、今の自分を省みるとお恥ずかしい。ディヴェルティメントとは、日本語では「嬉遊曲」と訳されていて、語源はイタリア語の「divertire(楽しい、面白い、気晴らし)」、そもそもは貴族の社交や娯楽の場で演奏されている。楽器編成に指定はなく、三重奏、四重奏、弦楽合奏、管楽合奏、小規模のオーケストラなど様々、それに、形式・楽章数にも定まりがない。要するに、セレナーデと似ていて、そういえば、セレナーデが屋外での演奏用であるのに対し、ディヴェルティメントは室内での演奏用だとされるているのが定説である。私などは嬉遊曲と聞くと、島田雅彦氏の名作「優しいサヨクのための嬉遊曲」を思い出してしまい、当時はタイトルの韻の上手さに感動し、内容とか、文中にどんな嬉遊曲が奏でられていたのかは全く覚えていないが、やはり日本語訳より、ディヴェルティメントと言った方が分かり易い。この曲も、ハイドンの17番やバッハのアリア同様、「モーツァルトのメヌエット」として有名な第3楽章を小品として知っていてそこから入った。この曲は良く妹が弾いていたから、それで安易に選んだのであるが、今回自分でも驚いたのは、この楽曲のレコード、CDを3枚も持っていたこと。勿論、ベートーヴェンやブラームスのように意識的に同じ楽曲でも色々な人の演奏アルバムを買っているのでなく、無意識にライブラリーに増えているのであるが、それもこれも、モーツァルトなんだと思う。因みにモーツァルトはこういうケースが非常に多い。
この曲はホルン2、弦五部(ヴァイオリン2・ヴィオラ1・チェロ1・コントラバス1)で演奏され、全6楽章。前述のメヌエットは余りにも有名だが、私はやはり第1楽章のアレグロが圧倒的に好きだ。というか、やはり私はソナタ形式が好きなんだと思う。実は、第4楽章にもエピソードがあって、良く、朗読のバックや自主作品映画のBGMにも使っている。これはアダージョだが、やはりソナタ形式である。また妹が練習していたメヌエットは、後年、ギターでも指の練習で良く弾いた。とても難しくて、ロックしかしらない音楽仲間にその曲はなんだと聞かれたことも多々あった。モーツァルトの旋律は時代を超えて感動を与えるのだと実感したものである。第5楽章で再びメヌエットだが、こちらはロンド形式で軽快だ。
モーツァルトはディヴェルティメントと題している曲は17曲書いていて(「ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロのためのディヴェルティメントK.563」という言い方をされる曲もあるが、これはまた別の機会に)いわば、この曲はディヴェルティメントの集大成に当る。彼自身も、この時期を最後に大司教と訣別しウィーンに住むようになる。いよいよ、天才宮廷音楽家がその才能を一般大衆にも知らしめることとなり、そういう意味では最後の「宮廷音楽」だったのかもしれない。彼の経歴の中でも重要な曲だが、西洋音楽史的にもターニングポイントにある時期であり、だからこそ静かな名曲なのである。
こちらから試聴できます