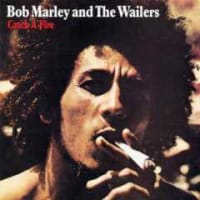ラズ1番とラズ2番のところでも既に触れたが、この時期のベートーヴェン音楽の総括としてこの弦楽四重奏曲が作成されたということは、どうも疑いの無い事実のようだ。前後して可也有名な楽曲が揃っているみの時期であるが、どうも交響曲第3番「英雄」がその始まりで、このラズモフスキー3曲(何れも作品番号が59で統一)が、ベートーヴェンのある意味での到達点である。それが証拠に、ベートーヴェンが生涯拘ったのは、交響曲でも協奏曲でもなく、やはり弦楽四重奏曲であったことに帰着する。
さて、まずその第3番についてだが、この楽曲はラズ1番にある「構成の大きな広がり」と、ラズ2番にある「内省的」の何れもが中期ベートーヴェンの2面的な表現といわれるが、その何れもを取り入れた解決点として、この楽曲で結論づけている。それが表現されているのが、まず第1楽章にみられる減七の和音の強奏に始まる和声的な緩やかな序奏部と、主題の動機は楽章全部に渡って労作されるところである。さらに第2楽章では和声短音階が用いられ民族的、第3楽章はスケルツォを用いず、メヌエットで書かれていて古典に回帰した印象があるが、一方でコーダから終楽章にアタッカされたフィナーレての橋渡しは見事である。第4楽章 はソナタ形式で、その曲想と構成は全曲の力点となるだけでなく、ラズ3曲四重奏曲全曲のフィナーレを成すものである。主題はフーガ風に構築され、精力的かつ流動性の高い旋律で、しかし一方で音がひとつずつ積み重なっていく印象が強く、更には別々に奏でていた4つの弦楽器がいつのまにか合奏でひとつのフーガを奏でている。最後まで延々と前学期等しく八分音符となり恐るべき迫力を醸し出したまま曲は終わりを告げる。この3~4楽章は唖然である。この楽曲がまたの名を「英雄弦楽四重曲」とも呼ばれるように、ベートーヴェン自身は誰を模して作曲している訳ではないが、ここに中期完成期のバッハその他の偉大なの先人たちの音楽に対しての総括と終止符を打っている。つまりは、この曲の完成が、ベートーヴェン前半生のケジメをしっかりつけているところである。そしてもうひとつはっきりと言えることが、ハイドン、モーツァルトという偉大な先代の弦楽四重奏曲作曲の大家の考えとは全く違う弦楽四重奏曲の確立をここに為しえたのである。勿論、それは彼の音楽観だけでなく、聴衆の変化ということもあるが、この時点でベートーヴェンはこのジャンルの楽曲を宮廷音楽としてだけでなく、外の開こうという準備をしていたのである。ベートーヴェンはこの楽曲によって、明確に新しいクラシックの聴取層に確実にアピールをし、そして新しい音楽を完成できたのである。そしてこの自身は、これから以降すべて音楽に活かしさけていくのだが、皮肉なことに、その確立できた弦楽四重奏曲というジャンルではかくも長きスランプに陥ることになるのであるが、これはまた、別の曲の鑑賞で触れたいと思う。
私がこの楽曲に出会ったのは、最初にベートーヴェンファンだった頃ではない。つまりはブラームスに出会う前である。もし、最初のベートーヴェンに影響を受けたときにこの3曲の存在を知っていたら、出会っていたら、もしかしたらあれほどブラームスに影響を受けなかったかもしれない。だからこそ、1個人とクラシック音楽との出会いというのは本当に面白いものなのだ。
こちらから試聴できます