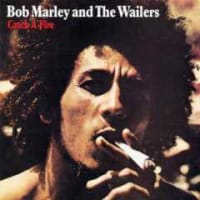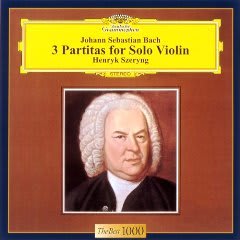
私の場合、バッハの曲を聴くときのステュエーションの殆どは、取り敢えず「音が欲しい」という時や、ライブラリーを眺めていて、中々聴こうと思う曲が決まらない時である。だから、例えば、SDメモリーに持ち歩きように入れてある音源も、そのメディアの最初の方はずっとバッハが続いて録音されている。その中でも、この「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」全6曲は、実に聴く機会が多い。ここではパルティータ(そもそもは変奏曲という意味であったが18世紀のドイツでは、統一性をもった組曲という意味に変化してきた)の第1番から3番について書く。
新古典主義は「バッハに帰れ」が合言葉であったが、西洋音楽界では、別に彼らだけでなくとも、やはりその時代毎に、或いは殆どの音楽家が必要な時に「バッハに回帰」している。回帰という表現を使いたいほど、バッハはイコール原点なのである。そしてバッハの音楽は、音楽を志す者に取っては全てがバイブルだといえるだろう。このパルティータ全3曲の中でも、中心となるのは、ニ短調で書かれた第2番であり、これは「無伴奏ソナタ」も含めた全6曲の中心に位置しているといえる。だから私もこの第2番が一番好きだし、音楽家にとっては必須の曲である。そして、ヴァイオリニストといわれる人たちは、大体この難曲を全曲録音することが多いので、私のライブラリーにもバッハに関しては「ゴルトベルク変奏曲」に次いで、種類が多い。ブランデンブルグ協奏曲よりも多いから自分でも驚きであるが、かといってバッハのアルパムの場合は、ベートーヴェンやブラームスのように、そもそもそれぞれの楽曲に演奏・録音を試みようとするアーティストの絶対数が多いわけではないから、音楽家ではない私にとっても、音楽の原点であることは変わりないのかもしれない。だから、いつもバッハとの出会いは衝撃的なのかもしれない。そしてパルティータの中でも、やはり第2番は最高であり、特に名曲である3曲目のサラバンドと、5曲目のシャコンヌは芸術である。特にシャコンヌはもともとスペインやイタリアで流行した3拍子の舞曲であったが、18世紀に8小節のオスティナート主題に対位法もしくは和声的に変奏を繰り返していく変奏形式の呼称になった。後にブラームスが交響曲第4番でもこの技法を取り入れているが、主題のニ短調に30の変奏を展開している。ちなみに第1番の聴きどころは、それぞれの舞曲のあとにドゥーブルという変奏がついている。また第3番に関しては定番舞曲の間にガヴォット、ルールという新舞曲を加えた構成を取っている。3曲目のガヴォットは誰もが一度は聴いたことがあるだろう人気曲である。
バッハは前述した「無伴奏ソナタ」の他にも、チェリストのバイブルとして「無伴奏チェロ組曲」も作曲している。これも実に素晴らしい。こうして後世の一リスナーとして勝手に評論するとしたら、バッハという人は、単に沢山の音楽を作っただけでなく、まず、音楽を宮廷から外に持ち出す準備をこのように体系的な曲を作ることで考え、誰でもが解釈・演奏できるようにした一方で、後々に大衆化するだろうクラシック音楽の行く末を予測し、芸術として格上げをするために、系統立てたものを譜面として残したのである。だからこそ「音楽の父」とか「バッハで終わり、バッハで始まる」と色々言われるが、その表現が賞賛の意だとすればすべて正答だと思う。
こちらから試聴できます