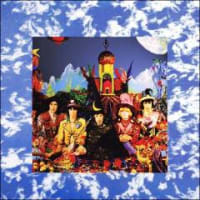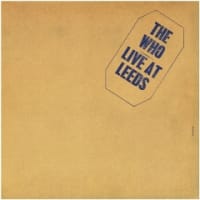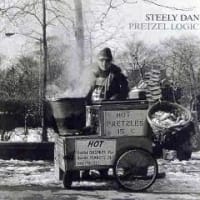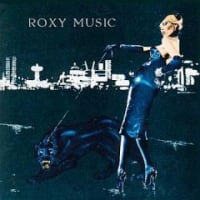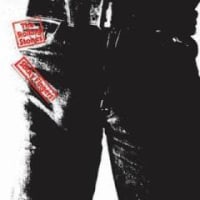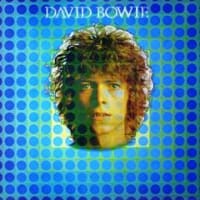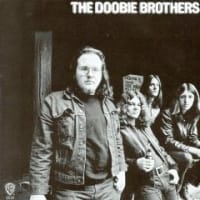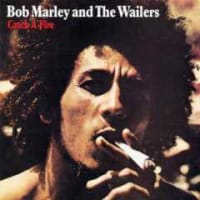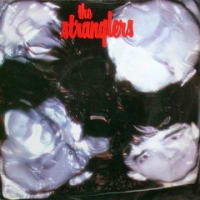交響曲第3番「スコットランド」の鑑賞で少し書いたが、メンデルスゾーンはこの最初の交響曲の前に、「12曲の弦楽のためのシンフォニア」を作曲していた。これは、彼自身が12歳から14歳にかけての弦楽合奏曲の習作作品集である。バッハの対位法に習い、和声を用いた高度な作品集らしいが、私は残念ながら聴いたことがない。交響曲は、17世紀イタリアでオペラの序曲がシンフォニアと呼ばれていて、G.B.サンマルティーニがこの序曲のみを独立させ、演奏会用に演奏したのが起源とされるが、これだけ沢山習作を書いた作曲家は少ない。さて、その成果かどうかは別として、メンデルスゾーンの第1番は、15歳の若さで発表されたが、その後も何度も自身の手で書き直されている。但し、この曲は先に述べたシンフォニアとの関係から、交響曲としては最初に出版されたので、完成と出版が同じ第1番である。
15歳で書いた曲だから、当然、多くの諸先輩の影響を随所に受けており、だから3番や4番とは比べものにならない。音楽形式も、第1楽章・アレグロ・ディ・モルト、第2楽章・アンダンテ、第3楽章・メヌエット、アレグロ・モルト、第4楽章、アレグロ・コン・フォーコ と、定石通りの編成であるが、第3楽章は、3拍子でなく6拍子で書かれており、スケルツォの要素もある。よくよく聴いてみると、ベートーヴェン以外にも、モーツァルト(ピアノ協奏曲や40番)、ウェーバー、ハイドン(95番?)を真似たフレーズが出てきている。だが一方で15歳で書いた曲だとは思えないスケールの大きさには驚く。しかし、まだ、メンデルスゾーンらしい「旋律の妙」はこの時点では現れていない。ここでひとつ疑問があるのは、メンデルゾーンはなぜ交響曲を作ろうとしたのかとういうことと、どういうところを目指したという2点だ。つまり、それまでシンフォニアの勉強をひたすらしてきたのだが、この第1番でそれが生かされているとは思わない。交響曲に対する独自性がないのである。この曲を聴いて、まず前者に関しては、ソナタ形式の勉強をした、とか、独学でシンフォニアを学んだが、先人たちの交響曲の解釈に同意したというふたつの理由で、この曲になったということかもしれない。ただ、後者については中々的確な回答は得られない。というのは、「第2番変ロ長調 讃歌」などという曲に関しては、色々と試行錯誤としているのであるが、だからといって何を目指しているのは良くわからない。私の仮説として、メンデルスゾーンは交響曲の作曲について、「然程、高尚な内容も高い志も持たなかった」というのがひとつの結論である。一方で、ベートーヴェンで略完成してしまった交響曲を「絶やすことをしない」のではなかったのだろうか。だから、彼は特有の美しい旋律も、あまり、交響曲には用いていないし、この最初の交響曲もわざと「諸先輩の真似」でお茶を濁しているのかもしれない。それよりも、頻繁に交響曲が演奏されることを願ったのだと思う。それにしては人生や人間の本質を語っているべートーヴェンの楽曲は一般には重々しいし、もっと気軽に聴ける、また簡単に公演が開かれるためには曲も然程難しくなく、回数も増やせる。そんな演奏会の一般への普及を目指したのだと思う。そのひとつの選択肢であっただろう。
メンデルスゾーンくらい「5曲の交響曲」に統一性が感じられない作曲家もほかにいない。だか、彼は、自身の立場の点からも、音楽の普及ということに努めていたのだという結論では、おかしいだろうか??
こちらから試聴できます