(2月25日)
序数詞をWikiで開くと英語、フランス語などヨーロッパ系言語にはそれなりの体系があるとされる。例にfirst, second, third, fourth(英語)premier, second(フランス語)を挙げている。しかし、その後が続かない。英語で5番目はfifthとなるが基数詞5のfiveからの変様である。するとthird, fourthにしてもthree, fourの変化形であろう。フランス語では3番目はtroisieme,4番目quatriemeとなり、接尾辞で序数を示す日本語「番目」の用法とすっかり同じである。前回(21日)投稿の最終段「科学思考は基数詞優先、それを序数としても用い「絶対数」を常にコンセプトとして内包」これが、基数の5を序数5番目に用いるやり方で、序列と数量が一目で分かる「科学的」進数法である。レヴィストロースのこの解析には納得する。
一方、「イチニィサンシー」とは別系統の「ヒイフウミイヨゥ...」の数え方から類推し、日本語とはかつて序数詞を用いており、新大陸先住民らが特別視していたと同様に「トオ、10番目」に力のみなぎり、覇権といった「数の魔力」が内在するとの説を誰ぞか先学が主唱していたなら、投稿子は両手を挙げて賛成する☆。
こんな例が;
自転車競技スプリント。
選手二人が円錐状に凹んだアリーナを5周して勝敗を決める。脚力に自信があってスタートから前にたって全力で回周し続けたとしたら。速く走るほど選手は風圧を受ける。後ろについて風圧を避けていた敵手に最後のスパートでうっちゃられてしまう。4周目までは力を温存、敵手の後ろで漕ぐのが作戦となるが、相手も同じ戦術なので駆け引きがでてくる。この駆け引きに加え自転車の性能が絡むが、決め手はやはり体力、脚力となる。
世界自転車競技会スプリント(プロスクラッチ)10連勝(1977~86年)中野浩一。
おおよそ人の体力勝負の競技において世界大会で10連勝した例を他に知らない☆☆。これに近い戦績は、同じく自転車競技ツールドフランス7連勝のランス・アームストロング(米)を挙げたい。しかし彼はドーピング疑惑を釈明しなかった事で、7連勝を含め自転車競技すべての戦績が消去された。比較するも僭越ながら、陸上短距離で断トツの成績を残したウサインボルト選手。一競技大会で100メートル以外に出場しているから、獲得している金メダルあるいは1位の数は多い。連続した一位の記録(世界陸上、オリンピック)では2008年から7回である。

写真:スプリント決勝に挑む中野浩一選手。彼の漕ぎ方はペダルを踏む(押し下げる)ではない。前のペダルを踏みながら、後ろに回ったペダルを引き上げるのである。このペダル技法が今は長距離も含めて基準になっている。
ヨーロッパには中野選手の走り様を目の前にみてスプリント競技を断念した選手が多いと聞く(ウルリッヒ選手など)。ナカノが出てこない長距離に目標を変えた、才能ある選手がスプリントから抜けて、長距離競技に集まりツールドフランスが栄えた。一方のスプリント、十連勝を決めた最終の競技で決勝に残ったのは中野選手ともう一人の日本人選手となった。翌年に11連勝、さらには12連勝の体力が彼に残っていた。しかし10で止めた。
10とそろえば力のみなぎり、覇権である。10の集団が他者にもたらす作用とは破壊、殲滅である。行く先々の不毛をかならずもたらす。10はもう一つの10を求める。10が20を求めても敵対の10に敗北したら殲滅は己にかぶさるーこれが先住民Menomini族の序数10の思想であり、今にしてもこの魔力は残っている。
レヴィストロース「食事作法の起源」を読む(続き) 17の了
(次回予定は2月27日)
☆ネットでググると「ヒイフウミイヨゥ...」は古来の数え方とする投稿が見られる。しかし11以降(の序数)がないことから、昔の日本人は多数の数を数えられなかったなどの誤解も見られる。序数詞はあくまで順列、数量とは別個なので、トオ10でそろえば一括りとするので11、12を示す序数は要らない(チュウチュウタコも同様)。10と仕舞って次に必要なのは、もう一組の10なのである。本ブログを訪問している方にはお分かりかと。
☆☆ステートアマと呼ばれたソ連、東ドイツに強豪選手がひしめいていた時期と重なる。彼らはアマチュアなのでプロスクラッチに参加出来ない。もし出場していたなら中野10連勝はなかったとの憶測がある。おそらく正しい。しかし当時のソ連東欧圏の陸上などでの強さは「ドーピング」によると今は判明している。
序数詞をWikiで開くと英語、フランス語などヨーロッパ系言語にはそれなりの体系があるとされる。例にfirst, second, third, fourth(英語)premier, second(フランス語)を挙げている。しかし、その後が続かない。英語で5番目はfifthとなるが基数詞5のfiveからの変様である。するとthird, fourthにしてもthree, fourの変化形であろう。フランス語では3番目はtroisieme,4番目quatriemeとなり、接尾辞で序数を示す日本語「番目」の用法とすっかり同じである。前回(21日)投稿の最終段「科学思考は基数詞優先、それを序数としても用い「絶対数」を常にコンセプトとして内包」これが、基数の5を序数5番目に用いるやり方で、序列と数量が一目で分かる「科学的」進数法である。レヴィストロースのこの解析には納得する。
一方、「イチニィサンシー」とは別系統の「ヒイフウミイヨゥ...」の数え方から類推し、日本語とはかつて序数詞を用いており、新大陸先住民らが特別視していたと同様に「トオ、10番目」に力のみなぎり、覇権といった「数の魔力」が内在するとの説を誰ぞか先学が主唱していたなら、投稿子は両手を挙げて賛成する☆。
こんな例が;
自転車競技スプリント。
選手二人が円錐状に凹んだアリーナを5周して勝敗を決める。脚力に自信があってスタートから前にたって全力で回周し続けたとしたら。速く走るほど選手は風圧を受ける。後ろについて風圧を避けていた敵手に最後のスパートでうっちゃられてしまう。4周目までは力を温存、敵手の後ろで漕ぐのが作戦となるが、相手も同じ戦術なので駆け引きがでてくる。この駆け引きに加え自転車の性能が絡むが、決め手はやはり体力、脚力となる。
世界自転車競技会スプリント(プロスクラッチ)10連勝(1977~86年)中野浩一。
おおよそ人の体力勝負の競技において世界大会で10連勝した例を他に知らない☆☆。これに近い戦績は、同じく自転車競技ツールドフランス7連勝のランス・アームストロング(米)を挙げたい。しかし彼はドーピング疑惑を釈明しなかった事で、7連勝を含め自転車競技すべての戦績が消去された。比較するも僭越ながら、陸上短距離で断トツの成績を残したウサインボルト選手。一競技大会で100メートル以外に出場しているから、獲得している金メダルあるいは1位の数は多い。連続した一位の記録(世界陸上、オリンピック)では2008年から7回である。

写真:スプリント決勝に挑む中野浩一選手。彼の漕ぎ方はペダルを踏む(押し下げる)ではない。前のペダルを踏みながら、後ろに回ったペダルを引き上げるのである。このペダル技法が今は長距離も含めて基準になっている。
ヨーロッパには中野選手の走り様を目の前にみてスプリント競技を断念した選手が多いと聞く(ウルリッヒ選手など)。ナカノが出てこない長距離に目標を変えた、才能ある選手がスプリントから抜けて、長距離競技に集まりツールドフランスが栄えた。一方のスプリント、十連勝を決めた最終の競技で決勝に残ったのは中野選手ともう一人の日本人選手となった。翌年に11連勝、さらには12連勝の体力が彼に残っていた。しかし10で止めた。
10とそろえば力のみなぎり、覇権である。10の集団が他者にもたらす作用とは破壊、殲滅である。行く先々の不毛をかならずもたらす。10はもう一つの10を求める。10が20を求めても敵対の10に敗北したら殲滅は己にかぶさるーこれが先住民Menomini族の序数10の思想であり、今にしてもこの魔力は残っている。
レヴィストロース「食事作法の起源」を読む(続き) 17の了
(次回予定は2月27日)
☆ネットでググると「ヒイフウミイヨゥ...」は古来の数え方とする投稿が見られる。しかし11以降(の序数)がないことから、昔の日本人は多数の数を数えられなかったなどの誤解も見られる。序数詞はあくまで順列、数量とは別個なので、トオ10でそろえば一括りとするので11、12を示す序数は要らない(チュウチュウタコも同様)。10と仕舞って次に必要なのは、もう一組の10なのである。本ブログを訪問している方にはお分かりかと。
☆☆ステートアマと呼ばれたソ連、東ドイツに強豪選手がひしめいていた時期と重なる。彼らはアマチュアなのでプロスクラッチに参加出来ない。もし出場していたなら中野10連勝はなかったとの憶測がある。おそらく正しい。しかし当時のソ連東欧圏の陸上などでの強さは「ドーピング」によると今は判明している。












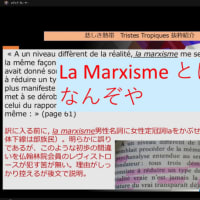




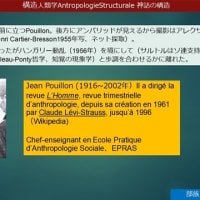

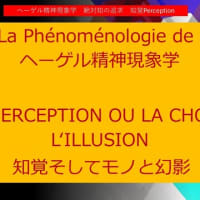






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます