(2025年7月2日)Gooblog愛好の皆様、部族民通信渡来部です。表題動画のYoutube投稿をお報せします。動画は10分程度でいつも通りPaulとHortenseの軽快な原本仏語の朗読も聞こえてきます。概要を下に張ります。
余はいかにして人類学をえらんだか上
本書人気の理由 1軽妙な語り口。第一行目から一人称単数Jeを用いる « Je hais les voyages et les explorateurs »「私はあらゆる旅が嫌いだ、探検家も嫌いだ」読者の意表を覆す言い回し。 その2 民族学の一級資料を提供する。圧巻はBororo族の訪問、ブラジル中央高地有力部族ながら資料はなかった(サレジオ修道会が調査を排他していた)。民族学者として初めて(教導が失敗し族民が「文化村」から大脱走)の訪問と報告。 3 熱帯ではない温帯社会の悲しみ。当時(二次大戦前)のパリ、大学、教師、学生の行動風景が広がる。例えば「幼稚な論理に凝り固まって、腕を大振りして自説を強弁するソルボンヌ哲学教授」の描写は、それまでの書物には絶対に出てこない。 さらには哲学とか構造主義とかが頻繁に出てこない配慮は大きい。しかし部族民は彼自身(哲学者としての)内面、理性観、世界観を述懐するいくつかの文節を採り上げます。これらが非常に面白い。 他著作(野生の思考など人類学文献)でも思索を述べる段はあるのですが、あくまでその書の表題からは踏み外せない。一方で本書の建前は紀行文、学術文にはありえない思いつくまま、自由闊達な主張が散見される。それらにやはり哲学者、含蓄深い訴えかけに出くわす。このあたりが本書の読みどころであります。

Youtubeのサムネ画像

Youtubeリンク:https://youtu.be/B8sjDqsqDjY
部族民通信のHP www.tribesman.net













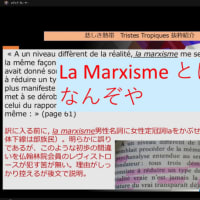




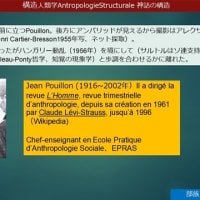

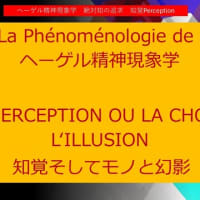





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます