
五月の初旬に裏庭に白い花の温州ミカンと中旬から夏みかんの花が木の枝に可憐に多数咲き甘い香りが漂っていました。
花は直径3㎝くらいの5弁花ですが、開花時期は2~3週間咲き今はほとんど散ってしまいました。
温州ミカンと夏みかんの花びらの形は少々違い、温州みかんの花は長めでちょっと星形のようです。
花柱は長めで柱頭がちょこんと付いています。夏みかんの花びらは桜の花のようにふっくらしておりました。
ウンシュウミカン(温州蜜柑)について

ミカン科・ミカン属 落葉果樹 開花期 5月 収穫期 9~2月
花、葉、果皮に半透明の油点があるのが特徴です。ミカンの皮がオレンジに見えるのは「フラベド」と言われ外果皮のせいで、
果実が成熟するにつれて緑色から黄色、オレンジ色に変化していきます。
皮を剥ぐと表われる白い繊維は、「アルベド」と呼ばれ、実と外皮の間の中果皮の部分です。
アルベドは根や葉っぱから吸収した水や養分を全体に回す役割をはたし、収穫期は11月~12月頃です。
みかんは直径6.5㎝~7cm前後で酸味が少なく多汁で糖度高いのが特徴。冬の人気の果物で果物籠にはいつも入れています。
効能
●血行の改善
栄養素:ビタミンA・C、ペクチン、ヘスペリジン、葉酸、カリウム、
ヘスペリジン「別名ビタミンP」フラボノライドの一種。ビタミンCの働きや吸収を助け、毛細血管を丈夫にして
血流を改善する働きがあります。
●風邪予防、下痢の改善
水溶性植物繊維のペクチンは、血糖値の上昇を防ぎ、コレステロールの吸収を抑える成分です。
消化管の壁に貼りついて胃の消化を遅くするので、糖尿病や肥満、高血圧といった生活習慣病に効果的です。
これらの成分はミカンの果皮の部分に多く、果肉の部分と比べるとペクチンが約4倍、
ヘスペリジンが約10倍も含まれているそうです。
温州みかん系の柑橘類だけに含まれている成分にシネフィリンがあって気管支を広げる作用をもち
のどからくる風邪の予防に役立ちます。
夏みかんの特徴

果実の成長期は9月~12月
5㎝~7,5㎝ほどの扁球形の実は熟すにしたがって緑色から橙黄色に変色します。
一般的に花粉は少なく単為結果性のため受粉がなくても結実します。自家和合性ですが
受粉しても雌性不稔性が強いことから、通常は種なし(無核)です。
晩秋に色付いても春先までは酸味が強くため食せず、酸味が減じさせるため木成りや貯蔵で完熟させたものを
初夏に販売しているみたいです。
我が家は真冬にサルがやって来たら取られないためすぐ収穫します。きれいな葉っぱを箱の中で入れて乾燥しないように
暗い物置で甘くなるまで待ち、食べごろになるとそのまま皮をむいて食べます。
そしてマーマレードや砂糖菓子、冷凍してジュースにもします。

夏蜜柑と聞くと山口県の萩市の旅を想い出します。武家屋敷の土塀から黄色の夏みかんが見えて落ち着いた景観でした。
今は平安古伝建地区にかんきつ公園があって萩で栽培される夏みかん・甘夏・橙などを身近に見ることが出来きて
5月は香りも楽しむことができます。「かおり風景100選」
明治維新胎動の地として史跡めぐりをお勧めします。





























 昨年は小鳥にほとんど食べられしまいましたので今年は早く網をかける予定です。
昨年は小鳥にほとんど食べられしまいましたので今年は早く網をかける予定です。






 元旦に氏神様へお参りに行きましたら、イノシシが近所で捕獲されたことが話題になっていましたので早速見に行きました。
元旦に氏神様へお参りに行きましたら、イノシシが近所で捕獲されたことが話題になっていましたので早速見に行きました。



















 花菖蒲でしょうか
花菖蒲でしょうか






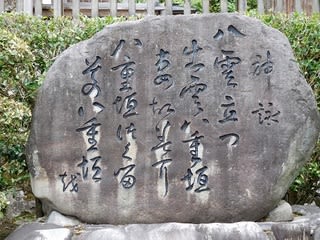














































 子供の頃、母の実家に行くと裏山に大木があって「猿の腰掛」と言って、いとこたちと奪い合って座り良く遊びました。
子供の頃、母の実家に行くと裏山に大木があって「猿の腰掛」と言って、いとこたちと奪い合って座り良く遊びました。
 『自然を愛して』の中に2013年ー06-19日に〈浜田城跡〉を書いています。
『自然を愛して』の中に2013年ー06-19日に〈浜田城跡〉を書いています。