私が養殖ベンチャーに転職した理由。持続可能な漁業を目指して

2年前までIT企業でシステム開発をリードしていた女性の生活は、船で沖に出る日々へと変わった。
【全画像をみる】私が養殖ベンチャーに転職した理由。持続可能な漁業を目指して
水産養殖×テクノロジー取り組むスタートアップ、ウミトロンで働く野田愛美さんの肩書きは、Field Success/Product Manager。水産養殖の成長に必要なサポートを、現場の事業者から聞き取りし、自社の製品開発へフィードバックするプロセスをリードしている。
大雨の中、生産事業者と生け簀から魚を取り出して成長スピードを確認したり、新しく導入した機材を試験的に運用したり……月の半分は海で過ごしているという。
持続可能な環境に養殖業が重要な理由
世界の魚介類の生産・消費量は、増加の一途を辿っている。国連食糧農業機関(FAO)によると、魚介類の消費量はこの30年で倍増した。2030年までに、1人当たりの年間消費量は21.5キロに達すると予測されている。
私たちが食べる魚は漁獲される天然のものと、養殖のものの2種類がある。年間1億7900万トン生産されている魚介類の半分近くは養殖によるもので、世界的にみると、魚介類の養殖はこの30年間で527%も増えている。
中国やインドネシアでは漁業生産の7ー8割を養殖が占めており、全体の生産量が減少傾向にある日本でも、養殖の割合は高まっている。日本ではマダイは8割、ブリ類は5割が養殖だ。
健康志向や食習慣の変化により魚介類への需要が増える中、水産資源の保護も重要な課題となっている。実際、持続可能でない水準で漁獲されている魚介類は35%にものぼる。世界的な人口増加によって食料需要がさらに高まる中、栄養価の高い魚介類の養殖生産には、期待が寄せられている。持続可能な方法で養殖業が広がれば、環境保護、そして食料供給の両方を実現できるかもしれない。
「生き物とかかわるスタートアップありませんか」
野田さんが働くウミトロンは、この養殖の可能性に注目したスタートアップだ。「持続可能な水産養殖を地球に実装する」ことを目指すウミトロンは、IoT、衛星リモートセンシング、機械学習などの技術を活用して、持続可能な水産養殖のコンピュータモデルを開発している。
「生き物とモノづくりが大好きなので、今の仕事は本当に楽しい」と話す野田さんは鹿児島県の出身。幼少期は、側溝に溜まった泥の中のトンボの幼虫を捕まえて、何を食べるのか観察するなど、身近な自然と触れ合う日々だった。
「ザ・美しい自然風景というのは実は、あまり好きではないんです(笑)。それぞれの生き物がどういう風に生活し、何を食べ、どうやって生きているのかを知ることが、昔から好きでしたね。小学校の校庭で拾ったドングリがつるつるしてかわいいから机に入れていたら、ある日、穴が開いて虫がたくさん出てきて。わー虫だ!と思いつつ、小さな空間でどうやって虫が育ったのか考えるが面白くて」
大学では環境心理学を選考し、近くの小学校でフィールドワークに励んだ。小さな池や草花が生える校内のビオトープで、子どもたちがどのようにして小さな自然と出合って遊ぶか、観察をする日々だったという。それでも卒業後選んだ道は、決して興味があったわけではない、IT分野だった。










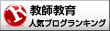
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます