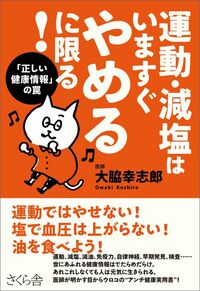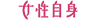年を取るほど血圧が上がりやすい」のは本当? どう防ぐ? 医師が解説

高血圧になると、心筋梗塞などの病気を引き起こしやすくなると言われています。健康診断などで血圧測定をしたときに「血圧が高い」と指摘され、気にしている人も多いのではないでしょうか。ところで、年を取ると血圧が上がりやすくなると言われていますが、本当なのでしょうか。また、高血圧をできるだけ防ぐには、どのような取り組みが大切なのでしょうか。あんどう内科クリニック(岐阜市)の安藤大樹院長に聞きました。
【あなたもチェック】高血圧症になりやすい年代、高血圧の合併症を解説
糖尿病患者は高血圧になりやすい
Q.年を取ると血圧が上がりやすいと言われていますが、本当でしょうか。また、高血圧になりやすい年代はあるのでしょうか。
安藤さん「血管はもともとしなやかな弾力性を持っています。しかし、長い間血管の壁に圧力を受け続けると、血管の壁に傷ができます。そこが修復される過程で硬くなったり、もろくなったりしますが、さらに進行すると内側が狭くなります。この状態が『動脈硬化』です。動脈硬化が起こった結果、血の流れが悪くなり、特に心臓が収縮して血液を送り出す際の『収縮期血圧』が高くなります。
また、年齢とともに増える脂質異常症や糖尿病などの生活習慣病も、血管のしなやかさを損なう原因になります。特に注意が必要なのは、糖尿病の場合です。糖尿病の患者さんはそうでない人に比べ、高血圧になる頻度が約2倍も高いことが分かっています。
2018年に厚生労働省が発表した『国民健康・栄養調査』の結果によると、全体的に男性の方が女性より高血圧症の有病率が高く、かつ早い時期から血圧が上がりやすい傾向があります。結果を見る限り、『男性は40代から、女性は50代から高血圧症に注意』と言えますが、『20代や30代でも高血圧症になり得る』ということにも注意してください。『自分はまだ若いから、高血圧症にならない』というのは間違いです」
Q.高血圧と診断されたにもかかわらず放置した場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。
安藤さん「高血圧症は特有の症状がなく、本人の知らないうちに体の各部位で恐ろしい病気が進行していくことから、『サイレント・キラー(沈黙の殺し屋)』と呼ばれています。それにもかかわらず、厚労省の調査によると、実際に高血圧で治療を受けている人は、全高血圧患者約4300万人中、1000万人程度です。つまり、高血圧の人の4人に3人が高血圧の状態を放置しているのです。
合併症の起こり方は、人によってさまざまです。頭痛や吐き気、動悸(どうき)などが先行することもありますが、ある日突然発作が起こって、亡くなることもあります。起こる病気も多種多様ですし、いくつかの病気が複合して起こることがほとんどです。合併症予防は、『早期発見・早期治療』が大事です。生命に関わる病気もたくさんあるので、健診で血圧について指摘を受けたときは、たとえ症状がなくても一度医療機関を受診してください」
高血圧を防ぐには?
Q.高血圧を防ぐためには、どうすればよいのでしょうか。
安藤さん「高血圧の予防にとって大切なのは『生活習慣の修正』ですが、一般的な食事制限では長続きしません。大切なのは、今までの自分の生活習慣を振り返り、問題点を認識した上で、自分で続けられるよう、適切な生活習慣を日常生活に刷り込んでいくことです。ポイントを説明します。
【(1)食塩制限は「無理なく」「気長に」頑張る】
高血圧の場合、1日の塩分摂取量を6グラム未満に抑える必要があります。ただ、1日平均10グラム以上の塩分を取るわれわれ日本人が、いきなり6グラム未満を目指すのは大変です。濃いめの味付けに慣れた人が急に減塩食に切り替えると、食事は味気なくなり、ストレスがたまって逆効果です。
味覚から得られる満足感や楽しみを維持しつつ、減塩に取り組むには次の方法に取り組んでみてください。
・減塩料理に取り組むときは、(1)新鮮な旬の食材を使う(2)酸味やだし、香りを利用(3)ドレッシング類は『付けて食べる』(4)副菜一品は塩気の効いたものを選ぶ
・塩分の多い食品・料理(漬物、練り物、魚介類の干物、ハムやベーコン、麺類、丼物、みそ汁、煮物など)を把握し、我慢できそうな食べ物から徐々に減らしていく
・主食に含まれる塩分に注意。白米、パン、麺類のうち、塩分を含んでいないのは白米
・塩分カットの食塩やミネラル豊富な天然塩、減塩しょうゆ、ポン酢などを積極的に使用
・みそ汁は、カリウムや食物繊維を多く含む野菜や海藻をたっぷり入れること
【(2)肥満は血圧を上げ、合併症も増やす】
高血圧に限らず、肥満はすべての生活習慣病の原因になりますし、動脈硬化や心臓病などの合併症を起こしやすくなります。特に、男性に多い『内臓脂肪型肥満』は、より動脈硬化のリスクが高く要注意です。
適正体重は、身長と体重から算出される体格指数『BMI(ボディー・マス・インデックス)』の『18.5以上25.0未満』を目指しましょう。この範囲であれば生活習慣病になりにくいと言われています。1キロの減量につき収縮期血圧で約1.1ミリHg、拡張期血圧で約0.9ミリHgの血圧低下が期待できますが、急激な減量には弊害もあるので、長期的な計画を立てるようにしましょう。
【(3)運動は「軽い有酸素運動」と「程よい筋トレ」を組み合わせるのがコツ】
運動は、ウオーキングや軽いジョギングなど酸素を取り入れながら行う全身運動である『有酸素運動』と、筋力トレーニングを中心とした『レジスタンストレーニング』を組み合わせて行います。あまり負荷を上げ過ぎると、長続きしないだけでなく、場合によっては急激に血圧を上げてしまうこともあり逆効果です。『無理なく』『楽しく』続けられるメニューを組んでください。次のポイントを押さえておきましょう。
・運動量の目安は1日30分以上、週3日以上が目安。食後1時間ごろが効果的。運動開始当初はやや血圧が上がり気味になることも。10週以上の継続で効果を実感できる
・まずは自分が1日どの程度歩いているかを把握する。目標の歩数から現在の1日当たりの歩数を引いて、ウオーキングの目標歩数を決める。歩数は1日8000歩が理想だが、最初は3000歩程度から始める
・歩く際は『顎をひいて』『胸を張って』『かかとから着地』がポイント。ゆったり歩きと早歩きを交互に行う『インターバル速歩』がお勧め
・筋トレを長続きさせるコツは“ながら体操”。洗面や歯磨き中、通勤中、家事をしながらなど、日常生活の隙間時間を活用
【(4)適度に楽しむお酒はOK! 適正な飲酒量を知ること】
仕事の疲れやストレスを解消するためにも、適量のアルコール摂取は決して悪くありません。ただ、この『適量』がくせ者です。高血圧の人の1日の飲酒量は、エタノール換算で男性20~30ミリリットル以下(ビール中瓶1本、日本酒1合、焼酎0.5合程度)、女性1日10~20ミリリットル以下に制限されています。肝臓の疲労も考えて、週2日程度の休肝日も必要です。なお、心筋梗塞や脳梗塞のリスクが高くなる『早朝高血圧』は、晩酌と関連するので、深酒にも十分気を付けてください。
【(5)禁煙に取り組もう】
喫煙は百害あって一利なしです。特に血圧に関しては、ニコチンによる血管収縮、一酸化炭素上昇による心臓への負担増加により、喫煙直後から急激に血圧を上げてしまいます。
ニコチンや一酸化炭素は血液中の遊離脂肪酸を増やして血栓を作ったり、悪玉コレステロールの酸化を促して血管の壁を傷つけ、動脈硬化を進めたりします。また、受動喫煙はさらにリスクが高いことが知られています。あなた自身の健康はもちろん、あなたの大切な人たちの健康のためにも、ぜひ禁煙に取り組みましょう」




















 2022年06月20日 子育て・教育 FacebookTwitterLine スマホを使っている子供たちは学力が低下し続ける――。この恐ろしい事実をご存じでしょうか。これは脳科学で知られる東北大学教授・川島隆太さんの研究で明らかになったものです。LINEやフェィスブックなどのSNSは、いまや現代人にとって欠かせないツールであり、それは子供たちも同じです。しかし、その世界に浸りきっていると、脳は大変なダメージを受けるというのです。SNSは人間の脳の働きにどのような影響を与えるのでしょうか? 明治大学教授の齋藤孝さんと語り合っていただきました。 SNSで記憶が消える? 〈齋藤〉 《前略》素読が脳にいいことはよく分かりました。では、例えば子供たち同士がお喋りをしたり、フェイスブック、ラインに代表されるSNSをやったりというのは、どうなのでしょうか。 〈川島〉 それが素読とはまるっきり逆なんですね。効果どころか、SNSをやっていると脳に抑制が掛かることが分かっています。見た目には手を動かしたり、頭を使ったりして脳を刺激しているように思えても、測定すると抑制、つまり眠った状態になります。 〈齋藤〉 眠った状態に。 〈川島〉 そのことはラインの文面を見ていただければ理解できると思いますが、極めてプアなコンテンツしか出てきません。「お昼何にする?」「カレー」「どこ行く?」といったように、まるで幼稚園児レベルの会話しか続かないんですね。物を考える人としての脳は積極的に寝てしまっている。ある意味、とても怖いツールでもあるんです。 〈齋藤〉 いま1日に5時間くらいSNSに掛かりっきりになっている高校生はザラだと思いますが、脳がほとんど抑制されているということなのですね。 〈川島〉 僕たちは7年間、仙台市の7万人の子供たちの脳を追いかけて調べていますが、スマホやSNSの利用と学力との関係が明らかになってきました。そこで分かったのは、これらを使えば使うほど学力は下がります。それは睡眠時間や勉強時間とは関係ありません。 例えば、家で全く勉強していない子供たちのグループがあります。スマホをいじらない子はある程度の点が取れるのですが、その先、使い始めると睡眠時間は一緒でも、そこから点が下がっていくんです。要はスマホを使ったことによって、脳の中の学習した記憶が消えたということです。 〈齋藤〉 記憶が消える。 〈川島〉 仙台市の子供たちのデータですから、一般則ではないかもしれませんが、例えばSNSを1時間やると、100点満点の5教科のテストで30点、一教科当たり5点分くらい点数が下がります。1時間で5点ですから4時間使えば20点下がるわけですね。 そこから分かるのは、本来なら総合点が高いはずの子供たちが、SNSをやっているばかりに勉強した大切な脳の記憶が消えているという現実です。 〈齋藤〉 恐ろしいことですが、ということは、見方を変えれば文章を素読するのは素朴なようでも、学習力をキープしていく上では、とてもいい方法なのですね。 〈川島〉 ポジティブなよい影響しかありません。かつ素読のコンテンツである名文や名詩には、それ自体にきちんと意味や中身があります。中身のないSNSとは全く違うんです。 SNSはよくコミュニケーションのツールという言い方をされますが、SNSでやりとりをする相手が人間ではなく人工知能を備えた機械であっても、そうとは気づかない、人だと思ってやりとりをしてしまうという具体的なデータもあります。つまり、人と人とのコミュニケーションが担保されていないわけです。 人間の脳を活性化させるもの 〈川島〉 いま、若者の脳についてお話しさせていただきましたが、素読によって脳が活性化するのは、お年寄りも同じです。僕たちはこれを学習療法と呼んで今日まで続けてきましたが、高齢になって脳機能や生活の質が低下する一番の要因は、記憶の容量が小さくなることにあります。 記憶の容量とは、作業をする時の机に例えると分かりやすいと思います。若い時は大きな机を持っているのでパソコンやノートを置いたり、資料を並べたりして自由自在に作業ができます。ところが、年をとると机が小さくなっていって最後にはノート1冊すら広げられなくなってしまう。若者でも、SNSばかりやる人はこのような状態になります。 この狭くなった机を何とか広げられないかというので、認知症のお年寄りに、美しい日本語の文章を声に出して読ませるトレーニングを取り入れました。認知症は薬を飲んでもよくはならないんです。悪くなるスピードを遅らせるだけです。 ところが、素読を続けると劇的な変化が見られます。認知症の進行が止まるだけではなく、改善していくんです。記憶の容量が大きくなり、先ほど申し上げたような脳そのものが可塑的な変化を遂げる。だから僕たちの中で素読はまさに劇薬扱いなんですね。 お年寄りの中には素読よりも数を扱うことを好む人もいますので、単純計算によるトレーニングも組み合わせていますが、こういうシンプルな方法でも続けることで確実に改善に結びついています。 〈齋藤〉 高齢者の多くの方が、年をとるにつれてゆっくりと喋るようになりますが、これも脳の老化現象とみてもよいのでしょうか。 〈川島〉 まさに脳の回転速度が遅くなった証拠です。 簡単なテストがありましてね。1から120まで順番に数えさせるんです。大学生であれば30秒を切るくらいで数え終わるのを、60代の方は50秒以上かかってしまいます。脳が衰えたことで言葉のスピードも遅くなっているわけです。 脳の回転速度が速ければ、判断を瞬時にできるので次の行動にも素早く移れます。これは予測の能力とも繋がっていて、速い判断ができないと予測もしづらくなり、事故を起こしやすくもなる。 〈齋藤〉 相手のペースにつられてオレオレ詐欺に騙されてしまう、というのもそれなのでしょうね。それを考えると、中身のある古典や名文を、ある程度の速さで素読し続けることは、お年寄りの脳にとってとても効果が大きいことが分かります。 親や教師の意識が読書離れを助長している 〈川島〉 それにしても気になるのは、日本人の読書離れです。このまま手をこまねいていたら手遅れになるのは間違いありませんね。 僕はこの問題を学校における努力と、家庭における努力と2つに分けて考えているんです。 あるアンケート調査によると、多くの小学生は1週間に1冊のペースで本を読んでいると言われます。ところが、中学校に進んだ途端、見事に読まなくなるんですね。 そこに何が起きているかをきちんと解析しなくてはいけないのですが、恐らく中学校の先生方が読書の大切さに気づいていないような気がするんですね。「読書をするくらいなら、もっと部活に精を出せ」「勉強をしろ」と子供たちを追い込んでいるのではないかと。 〈齋藤〉 なるほど。 〈川島〉 いま中学校教育に求めたいのは、小学生の時に身についた読書の習慣を失わせないでほしい、ということです。中学生まで読書習慣が継続できれば、その子たちは必ず本好きになります。 一方、家庭についてですが、いま家に本がない家庭が増えていて、改善すべきはそこからでしょうね。ただ、子供を授かった親御さんには教育に対する意欲がありますから、まずはしっかりと読み聞かせを行う。そうすれば、子供は本が好きになります。 次のステップは家庭の中に本があるのが当たり前という環境をつくることです。幸い僕の両親は読み終わった本を僕の部屋の本棚に置くという戦略を立てました。退屈すると本を読むしかない環境に追い込んでいったんですね(笑)。 それで僕も、家内が暇な時に、子供たちの前で読書をしてもらう、という戦略を立てました。そうすると「そんなものかな」と思って子供たちも自然と本を引っ張り出して読むようになったんです。 だけど、いまの家庭はそうじゃないでしょう? 親は本を読まない。それどころか子供と食事をしている時まで親たちがスマホをいじっている。そこを解決するのは並大抵ではないと思っています。 〈齋藤〉 それだけ家庭の責任が重要だということですね。 おっしゃるとおりスマホ中毒は深刻なわけですが、スマホを手にしていると勉強をしたり本を読んだりする時間が中断されるんですね。だから、精神的に深く潜っていくという作業ができずに、浅瀬でずっと生きている魚のような感覚の人が増えているように思うんです。 本当に読書で鍛えられた人は、たとえテレビがついていたとしても、それに惑わされずに深く高度な勉強や読書ができるでしょうが、鍛えられていない人はいつまでもお喋り空間のまま終わってしまう。それだと精神力も弱くなるでしょうね。 武士道精神もそうですが、日本人の精神は1つの文化であり、それは決してお喋りで継承されることはありません。その意味では素読は人を育てるとともに、精神文化を継承する上で重要な役割を果たしてきたわけです。 〈川島〉 確かにそうでしょう。 人を育てるということでいえば、大変難しい時代になったなというのが正直な実感です。かつてはこちらが背中を見せることで、後進は育ってくれていました。頑張る背中だけ見せておけば、多少軌道修正するくらいで勝手に育って独り立ちしてくれていたんですね。 ところが、僕はいまその信念を曲げなきゃいけないと考えるようになりました。手取り足取り教えないと、育ってくれない子がそれだけ多くなったんです。 だけど、そんなことをやっていたのでは僕を越える人材はいつまでも育たないわけでしょう? そこにも読書をしてこなかった世代とのギャップを感じざるを得ないわけですが、それだけに、素読や読書というものの意義を真剣に考えなくてはいけないという思いは強くなるばかりです。 (本記事は『致知』2016年12月号 特集「人を育てる」より一部を抜粋・編集したものです)
2022年06月20日 子育て・教育 FacebookTwitterLine スマホを使っている子供たちは学力が低下し続ける――。この恐ろしい事実をご存じでしょうか。これは脳科学で知られる東北大学教授・川島隆太さんの研究で明らかになったものです。LINEやフェィスブックなどのSNSは、いまや現代人にとって欠かせないツールであり、それは子供たちも同じです。しかし、その世界に浸りきっていると、脳は大変なダメージを受けるというのです。SNSは人間の脳の働きにどのような影響を与えるのでしょうか? 明治大学教授の齋藤孝さんと語り合っていただきました。 SNSで記憶が消える? 〈齋藤〉 《前略》素読が脳にいいことはよく分かりました。では、例えば子供たち同士がお喋りをしたり、フェイスブック、ラインに代表されるSNSをやったりというのは、どうなのでしょうか。 〈川島〉 それが素読とはまるっきり逆なんですね。効果どころか、SNSをやっていると脳に抑制が掛かることが分かっています。見た目には手を動かしたり、頭を使ったりして脳を刺激しているように思えても、測定すると抑制、つまり眠った状態になります。 〈齋藤〉 眠った状態に。 〈川島〉 そのことはラインの文面を見ていただければ理解できると思いますが、極めてプアなコンテンツしか出てきません。「お昼何にする?」「カレー」「どこ行く?」といったように、まるで幼稚園児レベルの会話しか続かないんですね。物を考える人としての脳は積極的に寝てしまっている。ある意味、とても怖いツールでもあるんです。 〈齋藤〉 いま1日に5時間くらいSNSに掛かりっきりになっている高校生はザラだと思いますが、脳がほとんど抑制されているということなのですね。 〈川島〉 僕たちは7年間、仙台市の7万人の子供たちの脳を追いかけて調べていますが、スマホやSNSの利用と学力との関係が明らかになってきました。そこで分かったのは、これらを使えば使うほど学力は下がります。それは睡眠時間や勉強時間とは関係ありません。 例えば、家で全く勉強していない子供たちのグループがあります。スマホをいじらない子はある程度の点が取れるのですが、その先、使い始めると睡眠時間は一緒でも、そこから点が下がっていくんです。要はスマホを使ったことによって、脳の中の学習した記憶が消えたということです。 〈齋藤〉 記憶が消える。 〈川島〉 仙台市の子供たちのデータですから、一般則ではないかもしれませんが、例えばSNSを1時間やると、100点満点の5教科のテストで30点、一教科当たり5点分くらい点数が下がります。1時間で5点ですから4時間使えば20点下がるわけですね。 そこから分かるのは、本来なら総合点が高いはずの子供たちが、SNSをやっているばかりに勉強した大切な脳の記憶が消えているという現実です。 〈齋藤〉 恐ろしいことですが、ということは、見方を変えれば文章を素読するのは素朴なようでも、学習力をキープしていく上では、とてもいい方法なのですね。 〈川島〉 ポジティブなよい影響しかありません。かつ素読のコンテンツである名文や名詩には、それ自体にきちんと意味や中身があります。中身のないSNSとは全く違うんです。 SNSはよくコミュニケーションのツールという言い方をされますが、SNSでやりとりをする相手が人間ではなく人工知能を備えた機械であっても、そうとは気づかない、人だと思ってやりとりをしてしまうという具体的なデータもあります。つまり、人と人とのコミュニケーションが担保されていないわけです。 人間の脳を活性化させるもの 〈川島〉 いま、若者の脳についてお話しさせていただきましたが、素読によって脳が活性化するのは、お年寄りも同じです。僕たちはこれを学習療法と呼んで今日まで続けてきましたが、高齢になって脳機能や生活の質が低下する一番の要因は、記憶の容量が小さくなることにあります。 記憶の容量とは、作業をする時の机に例えると分かりやすいと思います。若い時は大きな机を持っているのでパソコンやノートを置いたり、資料を並べたりして自由自在に作業ができます。ところが、年をとると机が小さくなっていって最後にはノート1冊すら広げられなくなってしまう。若者でも、SNSばかりやる人はこのような状態になります。 この狭くなった机を何とか広げられないかというので、認知症のお年寄りに、美しい日本語の文章を声に出して読ませるトレーニングを取り入れました。認知症は薬を飲んでもよくはならないんです。悪くなるスピードを遅らせるだけです。 ところが、素読を続けると劇的な変化が見られます。認知症の進行が止まるだけではなく、改善していくんです。記憶の容量が大きくなり、先ほど申し上げたような脳そのものが可塑的な変化を遂げる。だから僕たちの中で素読はまさに劇薬扱いなんですね。 お年寄りの中には素読よりも数を扱うことを好む人もいますので、単純計算によるトレーニングも組み合わせていますが、こういうシンプルな方法でも続けることで確実に改善に結びついています。 〈齋藤〉 高齢者の多くの方が、年をとるにつれてゆっくりと喋るようになりますが、これも脳の老化現象とみてもよいのでしょうか。 〈川島〉 まさに脳の回転速度が遅くなった証拠です。 簡単なテストがありましてね。1から120まで順番に数えさせるんです。大学生であれば30秒を切るくらいで数え終わるのを、60代の方は50秒以上かかってしまいます。脳が衰えたことで言葉のスピードも遅くなっているわけです。 脳の回転速度が速ければ、判断を瞬時にできるので次の行動にも素早く移れます。これは予測の能力とも繋がっていて、速い判断ができないと予測もしづらくなり、事故を起こしやすくもなる。 〈齋藤〉 相手のペースにつられてオレオレ詐欺に騙されてしまう、というのもそれなのでしょうね。それを考えると、中身のある古典や名文を、ある程度の速さで素読し続けることは、お年寄りの脳にとってとても効果が大きいことが分かります。 親や教師の意識が読書離れを助長している 〈川島〉 それにしても気になるのは、日本人の読書離れです。このまま手をこまねいていたら手遅れになるのは間違いありませんね。 僕はこの問題を学校における努力と、家庭における努力と2つに分けて考えているんです。 あるアンケート調査によると、多くの小学生は1週間に1冊のペースで本を読んでいると言われます。ところが、中学校に進んだ途端、見事に読まなくなるんですね。 そこに何が起きているかをきちんと解析しなくてはいけないのですが、恐らく中学校の先生方が読書の大切さに気づいていないような気がするんですね。「読書をするくらいなら、もっと部活に精を出せ」「勉強をしろ」と子供たちを追い込んでいるのではないかと。 〈齋藤〉 なるほど。 〈川島〉 いま中学校教育に求めたいのは、小学生の時に身についた読書の習慣を失わせないでほしい、ということです。中学生まで読書習慣が継続できれば、その子たちは必ず本好きになります。 一方、家庭についてですが、いま家に本がない家庭が増えていて、改善すべきはそこからでしょうね。ただ、子供を授かった親御さんには教育に対する意欲がありますから、まずはしっかりと読み聞かせを行う。そうすれば、子供は本が好きになります。 次のステップは家庭の中に本があるのが当たり前という環境をつくることです。幸い僕の両親は読み終わった本を僕の部屋の本棚に置くという戦略を立てました。退屈すると本を読むしかない環境に追い込んでいったんですね(笑)。 それで僕も、家内が暇な時に、子供たちの前で読書をしてもらう、という戦略を立てました。そうすると「そんなものかな」と思って子供たちも自然と本を引っ張り出して読むようになったんです。 だけど、いまの家庭はそうじゃないでしょう? 親は本を読まない。それどころか子供と食事をしている時まで親たちがスマホをいじっている。そこを解決するのは並大抵ではないと思っています。 〈齋藤〉 それだけ家庭の責任が重要だということですね。 おっしゃるとおりスマホ中毒は深刻なわけですが、スマホを手にしていると勉強をしたり本を読んだりする時間が中断されるんですね。だから、精神的に深く潜っていくという作業ができずに、浅瀬でずっと生きている魚のような感覚の人が増えているように思うんです。 本当に読書で鍛えられた人は、たとえテレビがついていたとしても、それに惑わされずに深く高度な勉強や読書ができるでしょうが、鍛えられていない人はいつまでもお喋り空間のまま終わってしまう。それだと精神力も弱くなるでしょうね。 武士道精神もそうですが、日本人の精神は1つの文化であり、それは決してお喋りで継承されることはありません。その意味では素読は人を育てるとともに、精神文化を継承する上で重要な役割を果たしてきたわけです。 〈川島〉 確かにそうでしょう。 人を育てるということでいえば、大変難しい時代になったなというのが正直な実感です。かつてはこちらが背中を見せることで、後進は育ってくれていました。頑張る背中だけ見せておけば、多少軌道修正するくらいで勝手に育って独り立ちしてくれていたんですね。 ところが、僕はいまその信念を曲げなきゃいけないと考えるようになりました。手取り足取り教えないと、育ってくれない子がそれだけ多くなったんです。 だけど、そんなことをやっていたのでは僕を越える人材はいつまでも育たないわけでしょう? そこにも読書をしてこなかった世代とのギャップを感じざるを得ないわけですが、それだけに、素読や読書というものの意義を真剣に考えなくてはいけないという思いは強くなるばかりです。 (本記事は『致知』2016年12月号 特集「人を育てる」より一部を抜粋・編集したものです)