
少子高齢化で若手人材が不足している。高卒者の求人倍率はバブル経済期直後以来の高水準だ。文筆家の御田寺圭さんは「高卒者の求人倍率上昇は、日本の偏差値至上主義的な世界観が終わり始めていることを示している。『大卒でなければ社会人として務まらない』というのは、人余りの時代に作られた神話だったのだ」という――。
【この記事の画像を見る】
■東京大学前で受験生たちを襲った事件
去年1月、大学入学共通テストの当日に会場となっていた東京大学前で受験生を刃物で刺傷した通り魔事件があったのを覚えているだろうか。その事件の犯人は当時高校2年生だった男子生徒で、偏差値至上主義的な考え方にとりつかれて猛勉強して高偏差値の大学を目指すも、成績が伸び悩み自暴自棄になっての犯行であることが裁判のなかで明らかになっていった。
----------
「偏差値や学歴、職業で人を上下に見ていた部分があった」。東京大前で2022年1月、3人を刺したなどとして、殺人未遂などの罪に問われた当時名古屋市の私立高校2年だった男(19)の裁判員裁判。東京地裁(中尾佳久裁判長)は17日、懲役6年以上10年以下(求刑懲役7年以上12年以下の不定期刑)の判決を言い渡した。
両親に対する証人尋問で浮かんだのは、中学時代から勉強にのめりこむようになり、高校受験のころから偏差値にこだわるようになった姿。父親は「人の意見に耳を傾けるような正常なコミュニケーションがとれず、自己肯定感が低い部分があった」と述べた。
(中略)
◆親にも出身大学を持ち出して反論
勉強漬けの日々のなか、両親がちょっとしたことで諭しても、2人の出身大学を持ち出し「○○大学出身の人の意見は聞かない」などと見下すように。父親が「人間は偏差値じゃない。テストの出来不出来で、人の(評価に)差をつけてはいけない」と言っても、響いていない様子だった。
(東京新聞「『人間は偏差値じゃない』諭したのに…息子は東大前で受験生たちを刺した 両親の後悔」2023年10月16日より引用)
----------
■「偏差値」はある種の呪縛になっている
本当に哀しいニュースだ。
大学受験という大きな「関門(コンプレックスとでもルビを振りたい)」に身も心も吞み込まれ、入学した大学・学部・学科の偏差値こそが人間の価値や序列を決めるという感覚に支配されてしまう人は、東大で凶行に及んだ彼にかぎらず世の中に少なからずいる。
むろん大学を卒業して世の中に出ると、たいていの人は自分の学歴をだれかに話したりそもそも自分でもわざわざ思い出したりする機会もなくなっていくのが自然だが、なかには大学を卒業してから何年たっても自分の卒業大学や他人の出身大学の偏差値の話を四六時中やめられないような人も本当に一定数いる。今日の日本社会において「偏差値」というのはある種の呪縛になってしまっていることを痛感させられる。
通り魔的な犯罪をしでかすほど偏差値に狂わされてしまう人が日本社会には依然としているその一方で、あまりにも皮肉で虚しいことだが「偏差値至上主義」的な世界観は、名実ともにいよいよ終わりの兆しを見せている。
■高卒者の求人倍率はバブル期直後以来の高水準
ご存知の方も多いだろうが、いま世の中では若者向けの求人が空前の売り手市場となっている。大卒者だけではその需要をとてもではないが賄いきれず、高卒者にまでその採用の幅を広げる企業がそれなりの規模と知名度を持つ企業のなかにも現れるようになっている。
私が比喩や誇張で言っているのではなく、2023年現在の高卒求人は全国各地の都市部を中心にして、驚くべきことにあの「昭和」の時代に匹敵するレベルにまで増加している。近年の物価上昇を受けて給与水準も高まっている。
----------
少子高齢化で大卒者の就活は学生優位の「売り手市場」となり、高卒者を対象に採用を始める中堅企業も出てきた。令和時代の「金の卵」を巡り、初任給を大卒者と同等にする動きもあるが、高卒者の求人倍率は50年ほど前の高度経済成長期、バブル経済期直後以来となる高水準だ。若手人材の確保に奔走する企業に就活探偵団が迫った。
(日本経済新聞「高卒採用者は令和の『金の卵』 バブル期以来の求人倍率」2023年10月4日より引用)
----------
企業側からすれば理工系や医薬系といった専門的スキルを持つ人材は別として、とりわけ文系の人材については「あえて大卒者を採用しなければならない理由」がそれほどないことに気づき始めている。
■わざわざ文系大卒者を採る理由はない
卒業大学の偏差値は学習能力や知的情報処理能力の高さをある程度は担保するという評価はできるかもしれないが、それはべつに卒業高校の偏差値でも十分に代用可能だし、そもそも文系にかぎっていえば、時間割が組まれて規則正しい生活をだれもが送っている高卒時点が「社会人適応性」のピークである人もそう珍しくはない(高校生の時分とくらべて、不規則で自堕落な生活を送ってしまう大学生は高偏差値の大学生でも少なくない)。
とりわけ営業職や接客職など対人コミュニケーションを主とした企業が「優秀で勤勉な、高校を卒業したばかりの若者」を欲しがるようになるのは当然の帰結だったと言えるのかもしれない(もちろん高卒者だってなるべく学業成績が良好な「ええとこの高校」が好まれる傾向はあるだろうが、しかし大学ほど厳然たる偏差値至上主義ではない)。大学側が行っている大学教育が、現代の企業が欲しがる人材と必ずしもマッチしておらず、また世の中のニーズに応じて教育をアップデートしなかったことのツケと見ることもできるかもしれない。
いずれにしても、わざわざ文系の大卒者を採用しなければならない理由がどんどん薄れていくにつれて高卒者に対する労働需要は高まっており、それは偏差値至上主義的な世界観の大前提となっていた「高偏差値でなければまともな仕事に就けない・まともな稼ぎを得られない」という物語を急速に突き崩していることは事実だ。
■「偏差値至上主義」は、人余りの時代の共同幻想だった
偏差値至上主義とは「人余りの時代」だからこそ実効性があった共同幻想だったのだ。
たとえば1990年代前半から2000年代前半に大学を卒業した初代氷河期世代は、同学年の人口の絶対数が多かった。結果として学歴競争がいまよりずっと苛烈だった時代でもあったのだが、デフレ型の不況によって「人余り(労働力の供給過剰)」が起こってしまってもいた。同学年に150~200万人もいてダブついていた人材を文字どおりの“ふるい”にかけて選別するために有効だったのが、出身大学のネームバリューや偏差値であった。だからこそ、この時代に一気に学歴競争は噴出して「偏差値至上主義」が世の中のヘゲモニーを握り、その余韻は都心部で色濃く残っている。
だが、ご存知のとおり現在はかつての「人余り不況期」とはまったく様相が異なっている。
少子化は当時よりもずっと加速しており、事業の好調にともなう事業展開の拡大を企図しても、現場で働いてくれる人手がまったく足りていない状況だ。人手不足のせいで会社や店が休業したり倒産したりする、就職氷河期時代には考えられなかったような事態も当たり前に見聞きするようになった。皆さんの暮らす街でも「人手不足のために休業します」という店先の張り紙をしばしば見るようになったのではないだろうか。掲示されたアルバイトの求人票も時給がどんどん上昇している。
■大卒と比べて「教育にかかるコストに差は感じない」
先述したとおり、これまで「大卒必須」としていた企業でも、そうしてしまうともはや人が集まらないためその学歴要件を緩和し、大卒並みの待遇や福利厚生はなるべく維持したまま高卒や専門卒でも門戸を開くような流れが生じている。そして実際に採用して働かせてみた人に話を聞けば「過去大卒の新卒を雇った時と、教育にかかるコストに大きな差は感じない」というのだから、これまで世の中に当たり前の前提とされていた大卒必須とはいったいなんだったのだろうかと思わずにはいられない。「大卒でなければ社会人として務まらない」とただなんとなくのムードが世の中にあっただけで、そこにはしっかりとした根拠などなかったのかもしれない。
こうなってしまえば「偏差値が高くなければ雇ってもらえない」「まともな仕事を選べない」といった人余り時代につくられた神話はますますその真実性を失ってしまう。「偏差値がすべてではない」というのは、冒頭のニュースでも報じられた裁判でも実際に被告人の父が語った言葉のようだが、それはこれまでのような気休めではなく本当にそうなりつつある。受験生を襲撃した彼がもしあと10年遅く生まれていたら、世の中はもっと違う景色になっていたし、彼も偏差値に呪われることなどなかったかもしれない。
■“泥臭い”仕事を嫌い、事務系職種に殺到する文系人材
長引くデフレ不況による人余りの時代につくられた「偏差値至上主義」的な神話は、若い労働力が加速的に不足する時代に直面し、急速にほころびを見せている。
上述したように高卒者の求人は昭和の時代を彷彿とさせる高水準である。とりわけ宿泊業や運輸配送業や飲食サービス業や建設業といった業種では若い人材が猛烈に不足しており、賃上げや福利厚生の拡充あるいは教育制度の見直しによって人材確保に躍起になっている。
だがこれらの採用枠は、下手に高等教育を受けてしまった文系人材では選びにくい仕事でもあるだろう。なぜならプライドが傷つくからだ。
中途半端に偏差値の高い文系の学生には、そうした“泥臭い”匂いのする仕事は「学のある人間がやるような仕事ではない」という観念や自尊心があるせいでなかなか選ばれないようだ。かれらはそうした泥臭い仕事を嫌がり、その代わりによりにもよって人手不足の時代でも猛烈な買い手市場のまま推移する都市部の事務職に殺到している〔ちなみに厚生労働省のデータによれば事務系職種の現在の有効求人倍率は0.32である(厚生労働省「一般職業紹介状況(令和5年9月)」2023年10月31日)〕。
■学歴コンプレックスを持つ文系が割を食う時代
おそらくこれからの時代は、偏差値至上主義的な神話コンプレックスを強固に内面化しているノースキルの文系がもっとも割を食う世の中へと変わっていくことになるだろう。別に大卒文系でなければ務まらない仕事は少ない。あったとしても先述したとおりそのポジションは求職者が飽和状態になっており雇用流動性も低い。その最たる例が出版業やテレビ業で、これは高偏差値文系学生にとって最高峰ともいえる憧れの就職先だが、倍率は毎年500倍近いとも言われている。
大学文系学部で過ごす4年という若い時間のキャリア的損失を埋められるような学生は、一部の超高偏差値・超エリート層を除けばそれほど多くない。とくに、毎年定員割れを起こすいわゆるFランク大学に通うくらいなら(すなわち、Fランク大なのに大卒者というプライドがついて就労可能性の幅を自発的に狭めてしまうくらいなら)活況を呈する高卒の売り手市場にさっさと身を投じてしまうか、あるいは専門学校で「手に職」をつける方がよほど合理的でさえあるだろう。
■「若い労働力」のプレミアが飛躍的に高まる時代だ
この記事がリリースされる11月といえば、大学受験でいえば「最後の追い込み」の時期に突入している。いまもきっと日本のどこかでは「いい大学に入らないと、まともな人生が送れない」という世界観を強固に内面化した子どもたちが、不安と期待、なにかに追い立てられるような焦燥感や恐怖感を入り混じらせた感情を抱えながら、必死に机に向かっているのかもしれない。
だが世の中は過渡期である。「大学を出なければ社会の正規ルートに乗れない」というデフレの時代の幻想は終わり、社会は変わりつつある。プライドや自尊心にさえ折り合いをつければ、いくらでも若者が身を立てる道は見つけることができる。
少子化の時代はたしかに社会保障の側面では若者にとって暗雲立ち込める時代だが、しかしこの時代は同時に、「若い労働力」のプレミアが飛躍的に高まる時代でもある。
問答無用の少子化とインフレの時代には、自分たち若者の労働力が市場では喉から手が出るほど欲しい「稀少財」としてもてはやされる明るい側面もあるのだ。そう、それは若者が「金の卵」として重宝された時代の形を変えた再演である。
「偏差値こそが人生」「偏差値が高くなければ人生はまともに歩めない」という共同幻想が支配した時代は本当に終わりを迎えようとしている。スマートではないかもしれないしカッコよくもないかもしれないが、泥臭く強かに生きることを厭わずに臨めば、その想いに応えてくれるような場所や機会は着実に増えている。
これから世に出る若者にとって、いまの日本はなにもかもが絶望というわけではなく、見方を変えればチャンスも広がっている。
----------
御田寺 圭(みたてら・けい)
文筆家・ラジオパーソナリティー
会社員として働くかたわら、「テラケイ」「白饅頭」名義でインターネットを中心に、家族・労働・人間関係などをはじめとする広範な社会問題についての言論活動を行う。「SYNODOS(シノドス)」などに寄稿。「note」での連載をまとめた初の著作『矛盾社会序説』(イースト・プレス)を2018年11月に刊行。近著に『ただしさに殺されないために』(大和書房)。「白饅頭note」はこちら。
----------

















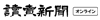




 [図表1]四年制大学および短期大学への進学率
[図表1]四年制大学および短期大学への進学率 [図表2]四大・短大の在籍者数
[図表2]四大・短大の在籍者数 [図表3]四大・短大数
[図表3]四大・短大数 [図表4]四大・短大に設置される学部・学科数
[図表4]四大・短大に設置される学部・学科数










