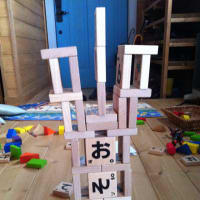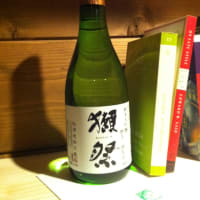誰が書いたか、今となってはわからないが、ワグナーとニーチェがヒットラーに貢献したことを非難する論文があった。
ニーチェの仕事はよく三期にわけられるが、これはある思考の発展である。理想主義に燃え、その後すべての体制や体系を否定し、最終的に行き着いたのは、「生命力」による活動を褒め称えることだった。「生きよう」という力が謳歌され、帝国主義さえ「金髪の野獣」として礼賛されたようにみえ、それがヒットラーによって「金髪の野獣」がゲルマン民族、そして忌むべき民族がユダヤと特定されたというのだ。
しかしあるニーチェ好き(ニーチェは学問対象にすると学者にはなれないという)によれば、「金髪の野獣」を帝国主義礼賛と結びつけることさえ疑問符がつくという。そもそもの問題は、ニーチェの仕事とその実人生を切り離すことだという。ヘーゲルの人間の理性を評価することへの反発からスタートした、ショーペンハウアーが仏陀と同じ結論を導き出したように、ニーチェも空海や理趣経のように生の力をただ肯定視したいからこそ弱者の杖としてのキリスト教を捨てたのではなかったろうか。
ど素人のニーチェ擁護にみえるかもしれないが、ニーチェの好きな言葉が「~ではあるがしかし」という相反する命題の両立だとするならそんな見方をしてもいいと思う。
ニーチェの仕事はよく三期にわけられるが、これはある思考の発展である。理想主義に燃え、その後すべての体制や体系を否定し、最終的に行き着いたのは、「生命力」による活動を褒め称えることだった。「生きよう」という力が謳歌され、帝国主義さえ「金髪の野獣」として礼賛されたようにみえ、それがヒットラーによって「金髪の野獣」がゲルマン民族、そして忌むべき民族がユダヤと特定されたというのだ。
しかしあるニーチェ好き(ニーチェは学問対象にすると学者にはなれないという)によれば、「金髪の野獣」を帝国主義礼賛と結びつけることさえ疑問符がつくという。そもそもの問題は、ニーチェの仕事とその実人生を切り離すことだという。ヘーゲルの人間の理性を評価することへの反発からスタートした、ショーペンハウアーが仏陀と同じ結論を導き出したように、ニーチェも空海や理趣経のように生の力をただ肯定視したいからこそ弱者の杖としてのキリスト教を捨てたのではなかったろうか。
ど素人のニーチェ擁護にみえるかもしれないが、ニーチェの好きな言葉が「~ではあるがしかし」という相反する命題の両立だとするならそんな見方をしてもいいと思う。