年末年始を四国の実家で過ごして札幌に帰ってくると、こちらの冬は深く、厳しくなっていました。雪の白さで暖かく感じる―なんて言ってみても程があるわけで、マイナス10度くらいになるとこれは凍えます。
ところでお正月には、実家の近所のお寺と神社に初詣に行きました。お寺は八栗(やくり)寺という五剣山の中腹にある古寺。神社の方は「幡羅(はら)八幡神社」と言って、八幡大明神を祀った氏神さんです。八栗寺で今回気づいたのは、参道に鳥居があること。お寺なのにです。これは明治初期までの神仏習合の名残なのでしょう。そのころまでお寺も神社も明確に分けられず、同居していたわけです。またここの境内には、役の小角の像もありましたから、修験道の流れを引くお寺でもあるようです。氏神さんに祀られている八幡大明神も、「八幡大菩薩」と仏教的に称されることがありました。
僕が神仏習合や神仏分離にアクチュアルな関心をもつようになったのは、昨年、奈良を何度か訪れてからです。特にハッとしたのは、「山の辺の道」沿いの長岳寺で聞いた話です―「この寺には48の坊があったのに、明治の廃仏毀釈で1つを残して全て取り壊されてしまいました。後は田んぼにされて、払い下げられたんです。田んぼの畔を良く見ると石垣になっている所があるでしょう。それは昔、坊であった証拠なんです」。「日本の“原風景”がまだ残っているなあ」くらいに思って歩いていた山の辺の道の風景が、実は近代になって大きく変えられたものだと分かって衝撃を受けました。
そんなこともあって、子どもの頃から行きつけていた八栗寺の鳥居に目が行ったわけです。廃仏毀釈や神仏分離の程度は県によっても異なっていたようで、香川県ではそれほど徹底的になされなかったのかもしれません。
北海道はまた話が違いますね。ここでは神仏習合の長い歴史はなく、神社と寺院はそもそも別のものとして明治以降に移入されたのでしょうから。北海道の宗教的風景はこの点で本州・四国・九州とはかなり違っていると思います。
神と仏を分離してきた日本の歴史の流れは、ひとつの岐路に差し掛かっているのかもしれません。今日の北海道新聞で山折哲雄氏が、京都の石清水八幡宮で仏教者と神道者が合同で行なった放生会(ほうじょうえ)再興のことに触れ、神仏習合の復活として評価しています。そしてその背景には関西独自の宗教的歴史があったのだとも述べています。また昨年世界遺産に加えられた熊野古道も、神仏習合の貫禄ある証左です。「熊野大権現」とは仏が神に姿を変えたということですから。
考えてみると、何か純粋な宗教というものはあるのだろうかと思います。キリスト教だって、ヨーロッパに拡大する過程で土着のさまざまな信仰と「習合」していったわけです。これは言い換えると宗教のハイブリッド(異種混交)性ということですね。宗教のハイブリッド性を積極的に評価することは、今日紛争の火種ともなっている宗教的ファンダメンタリズムに抗する道となるのでしょうか。
最新の画像[もっと見る]
-
 自発的治癒
10ヶ月前
自発的治癒
10ヶ月前
-
 新十津川のアイヌ・コタンのこと(1)
1年前
新十津川のアイヌ・コタンのこと(1)
1年前
-
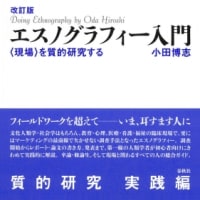 改訂版 エスノグラフィー入門
1年前
改訂版 エスノグラフィー入門
1年前
-
 高野山大学
3年前
高野山大学
3年前
-
 殺すなかれ
3年前
殺すなかれ
3年前
-
 小川隆吉エカシ
4年前
小川隆吉エカシ
4年前
-
 コロナ後の「生類の平和」のために
5年前
コロナ後の「生類の平和」のために
5年前
-
 プロフィール
6年前
プロフィール
6年前
-
 種のいのち
7年前
種のいのち
7年前
-
 森のイスキア
8年前
森のイスキア
8年前










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます