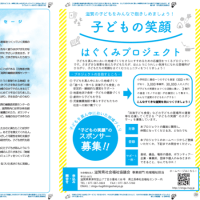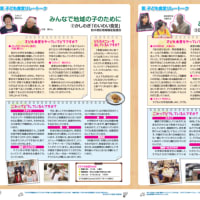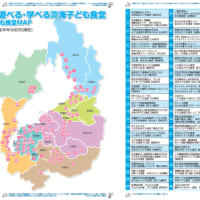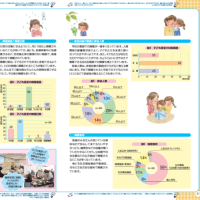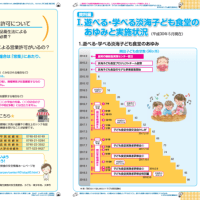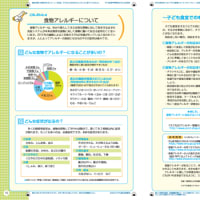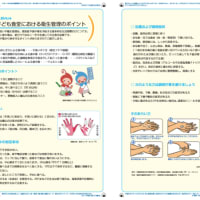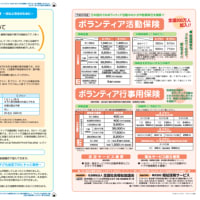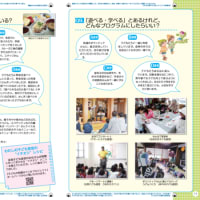ご教歌
よの人の さがなしごとを また人に つたへてわれに 罪なつくりそ
大意 (日晨上人「ご法門のかなめ」より)
世間のよくないことを見たり伝聞して、それをまた他に伝えてなんとも思わぬ人がいるが、
余りに他の迷惑を考えぬ無思慮で無情な心である。
そういう他の不詳を軽率にしゃべる信者になってはならぬ。
悪いことは自分で止め、善きことは他に伝える、そういう心が大事。
ご指南
人ヲカロシメテ功徳ヲ得ル事ナシ却テ罪業ノ因トナラン
(人を 軽しめて 功徳を 得ること なし かえって ざいごう の 因と ならん)
さがない( 形 ) さがな・し
①(多く「口さがない」の形で)他人が気を悪くしたり迷惑がるようなことを平気で言うさま。 「口-・い世間のうわさ」
②性質が悪い。 「 - ・きえびす心/伊勢 15」
③いたずらだ。手に負えない。 「 - ・きわらはべどもの仕りける/徒然 236」
な ( 副 ) 形容詞「なし」の語幹から派生した語という。
動詞の連用形(カ変・サ変は未然形)の上に付いて,その動詞の表す動作を禁止する意を表す。
特に,動詞の下にさらに「そ」「そね」を伴い,「な…そ」「な…そね」の形をとる場合が多い。
そ(終助) サ変・カ変動詞の未然形、その他の動詞の連用形に付く。中世には、サ変動詞の連用形にも付く。
1 副詞「な」と呼応して、禁止・制止の意を表す。…てくれるな。…なよ。
「な恨み給ひ―」〈徒然・六九〉
2 副詞「な」は用いないで、禁止・制止の意を表す。…てくれるな。…なよ。
「かく濫(みだり)がはしくておはし―」〈今昔・一九・三〉
[補説]上代は「な」だけで「そ」を伴わない例もあり、
禁止の意は「な」のほうにあって「そ」は軽く指示するにすぎなかったといわれるが、
院政期ごろから中世にかけて2の用法も現れた。
「な」と「そ」は禁止、制止の意味。
罪なつくりそ → 悪いことをいいふらして「罪をつくるな」