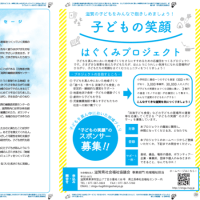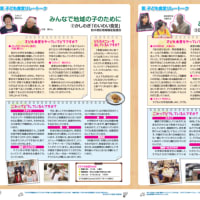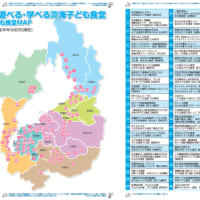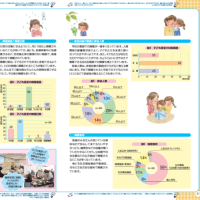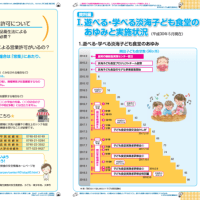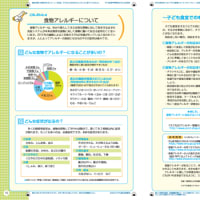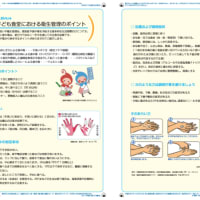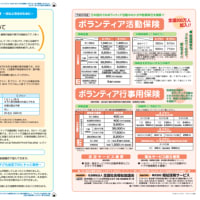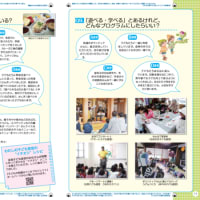ご教歌 きよがきの やや見事なり このごろは 心こめてや 手を習ふらし
大 意
『 清書を見ると段々と見事になってきた。この頃はきっと、心を込めて一生懸命、稽古に励んでいるのであろう。(これからも励んで行けよ。)』と、仰せであると拝します。(すなわち)ご信心ご奉公は、心を込めてさせていただくこと。日々つづけること。これが大事とお示しのご教歌です。
辞書を引きますと「手習い」は、お習字であり、お稽古、学問と記載されていました。すなわち、日々筆を持ち、心を込めてお稽古してこそ、やがて上達していくのです。それと同じようにご信心も日々の行(ぎょう)が大事で、想いを込めてさせていただく中で道が開けてまいります。
このご教歌は、自分自身のご信心をどのように高めていけるかをお諭し下さっていますから、みなさん、日々の朝参詣や朝夕のお看経、ご宝前のお給仕、お初をお供え申し上げるなど、心をこめてお敬いの心を以てさせていただきましょう。おなじお掃除をするのでも、「物ぐさそう」にするのではなく、「思いをこめて、やらせていただく」という気持ちで行う。毎日これの連続。ここが肝心とのお諭しです。
また、ほとけさまのお心(お経文に記される教え)を真似るのが信じる心=信心ですから、菩薩行を志さなければ、まことの信心に行き着きません。ですから、菩薩行という「人の為になるような働きかけ」が正しくできるように稽古をしたいのです。まことのぼさつ行とは、いかなるものかと。
菩薩行を志す者が、その道を成就するためには「凡夫のこころ丸出し」では叶うはずもなく、「み仏のお心を真似ようと志し」「すべてを慈しみ」「他の人にアプローチ」して行きたいのです。ですから人に対して「指導」や「命令」をするのではなく。「いっしょに学ぼうとする」「ともにお参りさせていただこうとする」。こういう姿勢を、行動で姿形にあらわして他人に示すのが、「お教務さん」や「ご信者の代表となる、事務局員。連合長。教区長。部長。」の、とるべき姿勢です。新入信徒へのアプローチを「育成」というコトバで表現しますが、ボクはこれが適当なコトバなのかと考えてしまうことがあります。「教えてやらなきゃ」と、指導者になろうとした時点で、ご信心をしている値打ちが底に落ちてしまうことでしょう。「させていただく」「手本となるように自身の姿勢を正す」のが、ご信心で言うところの「育成」のあり方です。
そんな姿勢が解決のヒントとなるような話題があります。本日は、ちょうど母の日ですので、それに因んで話題を出しました。

ちょっと、ゾッとするお話しですが、インターネットで「夫」と検索すると、続いて出てくるコトバが、「しね」であると聞きました。試しに検索してみると本当に出てきました。そして先の画像でご覧いただいたように「しね」「きらい」「大好き」「呼び方」とつづいています。なんだかあまりいい心地ではありません。
4月の末に本屋へ行きましたら、次の書籍が目にとまり、すぐ手にとって購入しました。タイトルは『 夫に死んでほしい妻たち 』です。こちらもゾッとしてしまうタイトルの本ですが、この手の書籍が多く発刊されていることを思えば、これらはいまの社会問題であり、知ってかねばとおもいます。

世の中の奥さん方は、夫の世話をして当たり前。家事をこなして当たり前。怒鳴られて、命令されて、使い走りをさせられて、という感情が積もっていく。子育てが済んでやがて定年を迎えて自由な時間ができた。もう、そのころには、いっしょに生活する理由がなくなるというところでしょうか。離婚は様々な問題があって自分にとってもマイナスになる要素が多い。だから、早く死んでもらった方が、お金も家も自由になるし、裁判などの煩わしさもない。周りの人々が同情してくれる。だから「いいことずくめ」だというのです。本当にさみしい話しですが、こういう風に思っている人が少なからず存在するという事実があります。世の男性は、これをどう捉えていくべきか。こんな話しを振りました。
深い不満を抱える女性の問題です。男性諸君は女性にこびへつらってご機嫌を取って生きていこう、などと申すつもりはありません。ただ、表面上だけでご信心をしているような場面で起こる摩擦とこの問題に、共通したところがあるように思えてならないのです。

人には煩悩があります。煩悩(ぼんのう)とは、
もし、言いしれぬ不安を感じている方があったならば、思い切って、いまよりもお参詣の回数や時間を長くする、あるいは優先順位を先頭にもってくるなど力を入れてみてほしいと思うのです。自宅のご宝前にお初をお供えしていますか?おそうじ・お給仕をまごころ込めてさせていただいているでしょうか?やったりやらなかったりということはないか?
夫婦の縁は、深遠なご縁で結ばれたものです。愛し合うのもご縁。憎しみあうのもご縁です。できれば、いやなご因縁はなくしたい。別れたり背を向けるのではなく、わるいご縁を排除できればいいですね。「相手を理解できる」「いつくしむ心」「尊敬しあえる関係」。きれい事をならべているようですが、母の日に感謝のコトバを伝えるに当たって、表面上でありがとうというのではなく、まごころとは何だと考え直すのも良いかもしれません。そんなことを考えた母の日でした。
最後に、本に載っていた「愛の三原則」をご紹介します。
愛の三原則
・「ありがとう」をためらわずに言おう。
・「ごめんなさい」を恐れずに言おう。
・「愛してる」と照れずに言おう。
非勝利三原則
・勝たない。・勝てない。・勝ちたくない。(負けるが勝ち、なんですね。)
語句の解説
きよがき=清書(せいしょ)。やや=だいぶ。いくらか。だんだんと。やがて。
手を習ふ=手習い(てならい)=① 文字を書くことを習うこと。習字。② けいこ。学問。「60(歳。高齢。)の手習い」
や=①~だろうか?(問いかけ)。②~せよ(呼びかけ)。