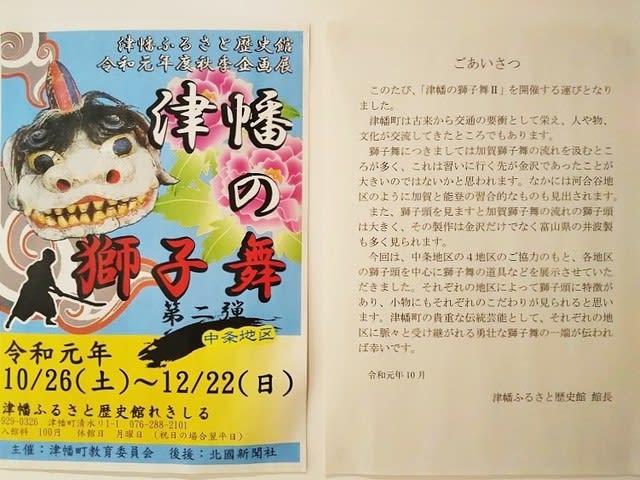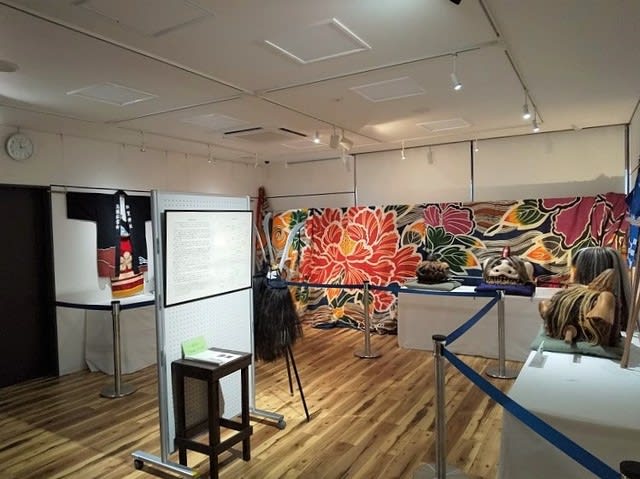ほんの手すさび手慰み。
不定期イラスト連載、第百二十三弾は「エスな女子」。

それまでの価値観を捨てて西洋化を目指した明治期、
女性の中等~高等教育の門戸が開かれた。
新しく「女学生」という社会層が誕生する。
彼女たちをターゲットに最初の雑誌が創刊したのは、明治35年(1902年)。
以後、昭和初期にかけ多数が刊行され「少女小説」が人気を博した。
題材は「エス(S)」。
「友情以上の強いつながり」で結ばれた少女たちの親密な関係で、
「姉妹」を表す英単語「Sister」の頭文字をとり、そう呼ばれた。
(旧制)高等女学校に通う生徒は、いわゆる富裕層が中心。
良妻賢母となるべくモラルを重んじながら、異性との交遊はご法度。
そこで少女たちは、上級生と下級生、同級生の間で、
手紙やプレゼントを交換したり、一緒に登下校したり、買い物にでかけたり。
お揃いの服装や髪型にしたりして、親交を温めた。
親主導による結婚までの限られた時間の中で育まれた「エス(S)」は、
思慕、敬愛、崇拝、憧れをベースにした、刹那的なファンタジーとも考えられる。
前述の少女小説を著したのは、
「与謝野晶子」、「吉屋信子」、後のノーベル賞作家「川端康成」など。
錚々たる作家陣のペンに、お嬢様方は盛大にのぼせた。
更に、読者モデルが主人公らになり切り、
小説のストーリーを実演する企画が大反響。
「エス」の流行に拍車をかけた。
しかし、太平洋戦争がはじまり、戦局悪化に伴って軍部からの圧力がかかる。
少女雑誌は路線変更。
恋愛テーマは消え、戦時色に塗りつぶされた。
少女たちの王国は滅亡した。