今回 遮断機式手すりを自分で取り付けました。
今までは、年老いた母の転落防止と手すり機能のために、天井に突っ張り式の遮断機式手すりを取り付けていたのですが、階段部に飛び出している部分があり、ショルダーバッグやコート等を引っ掛ける恐れがあり、健康な人が転落し大怪我や場合によっては死亡することもあり、それでは本末転倒になってしまうので、介護保険を使わずに自分で遮断機式手すりを取り付けることにしました。


また繋がりも悪く手前の手すりから、前のめりに中ほどの手すりを飛ばして、その先の遮断機式の手すりに手を伸ばしてつかまることが時々あり、転ぶのではないかと感じることもあります。

取り付けるところの幅が950mmあり、メーカーは900mmまでと指定しているので、手すりを取り付ける前に複数メーカーに問い合わせをしました。
あるメーカーは、900mmを超えると棒の重量が増し手すりが下がってしまうと言っていました。
また、別のメーカーは、手すり棒が長くなると重量が増え金具の耐久性に支障があると言っていました。なるほどと、その時は納得したのですがネットで調べるといろいろな事情が分かってきました。
まず、手すりの強度に付いては建築基準法等の関連法規では定められていないようです。
関連団体や協会が自主的に基準を設定していて、それを元に使用部位や人間行動により想定される荷重を適切に設定して設計を行ってくださいとのことです。
ちなみに日本建築学会 JASS13 金属工事における耐側圧性の基準を抜粋すると、グレード1の個人住宅等は特に規制を考えなくて良く、グレード3の集合住宅または事務所ビル等の標準的な建築物に採用するケースでは、床・階段等の手すりでは100以上150kgf/m未満となっています。中間にグレード2があり50以上100kgf/mがあります。
身障者用手すりでは、120kgf/m以上となっています。
kgfとはキログラムフォースと読み、地上1気圧のところで手すり棒1mの中央に120kgfの力を加えても壊れないことを意味します。手すりメーカーの基準は、手すり棒にブラケットを両端に付けて固定し、そのブラケットの芯々を900mmにして120kgfの力を加えてもブラケット・棒が壊れないと規定しているようです。
先に、手すりメーカーが900mmと言ったのは業界基準で、100mm短いのは手すりメーカーの基準はより安全を採用したと思われます。
そこで、先に書いたメーカー回答に疑問が生じます。120kgfの重量に耐えるものが棒の重量が増えて壊れるのかということです。棒の重量が200g増えたとすれば、120-0.2=119.8kgになるのではないかと考えます。また、長さが2倍の1800mmになった場合は60kgfになるのではと思います。
母の体重は52kgなので実用上は問題ないと考え自分で遮断機式手すりを取り付けることにしました。 ただし、これは私がネットで調べた範囲で得た情報なので、何かあっても自己責任で行うものです。
前置きが長くなりました。まず手すり受け部の壁裏に木がないのでベースプレートを取り付けるために木があるところを探します。
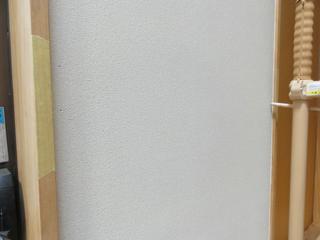
ベースプレートに手持ちの2.6mm(説明では2.8mm)のドリルで下穴を開け、水平になるようにネジで取り付けます。

ボード裏木材の奥に鉄骨があり、左側の付属ネジでは入らないので黒いドリルネジを使用しました。付属のネジ隠しを貼り付けプレートは終了です。


受け部の位置は、手前の手すり棒に購入した棒を吊るして決めました。

左の手すり棒の先に、遮断機式のブラケットを取り付けます。棒を立てると倒れないように止まるのですが階段側にはみ出します。また、手前にも倒れましたので壁際に倒れるようにブラケットの位置を修正しました。

手すり棒が階段側に倒れないように木材を削って取り付けました。
手すり棒を倒すときは、棒を上に持ち上げるとロック解除ができ倒すことが出来ます。持ち上げずに倒すとブラケットが破損するので注意です。


また、支点部ブラケットのガタが大きく、受け部を外れると床まで棒が落ちてしまうので、写真のようなガイドを両面テープで貼り付けました。 左の短い手すりは、階段を上がってきて遮断機式手すりを操作する時に体を支えるように市販品を取り付けました。これの安全荷重は80kgです。手すりメーカー製ですが120kgfを下回っています。


完成後です。突っ張り遮断機式手すりがなくなり 、ずいぶんスッキリしました。
母の移動もスムースになりました。

追記 取り付けて約2か月が過ぎ可動部の手すりの止まる位置が下がってきました。
この可動部は矢崎化工の跳ね上げ式ブラケットで、跳ね上げて止まった状態から一旦上に持ち上げてから手すり棒を倒す構造になっています。最初は70度くらいでしたが今は50度くらいで階段幅の中心まで来ます。短期間で使い勝手が悪くなっているので、何とか改造してみることにしました。

別メーカーの違うタイプのブラケットを購入し加工してみました。手すり棒の長さを加工する必要もありませんでした。

どの位置でも止まり、動かすときに上に持ち上げる必要もありません。使い勝手はとてもよくなりました。これで様子を見てみます。

階段の関係で可動部のブラケット間の長さは1100mm(手すり棒の長さは950mm)あり、室内の手すりでは業界基準をクリアーするものがありません。いろいろ探していたら屋外用で1200mmまで使用できる製品があり、施工業者に屋外の雨がかかる状態で使用できるので、屋内で使えるのではないかと話し、取付けを希望したのですが無視をされレンタルのツッパリ式の契約をすすめてきました。
メーカーにも問い合わせをしましたが、屋外用に1200mmまでの製品があると教えてもれえませんでした。
仕方がないので、全て自費で部品購入し取り付けた次第です。本来なら介護保険を使えるのですが、業者側にその気がないのが残念です。レンタルの契約は解除しました。もしレンタルを続けていたら、介護保険をずっと使うことになります。





























































































