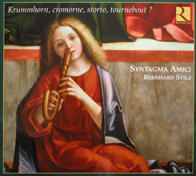
Krummhorn, cromorne, storto, tournebout ?
Ricercar RIC 262
演奏:Syntagma Amici
ドイツ語で「クルムホルン(Krummhorn)」と呼ばれる楽器は、ローマ字のJのように先が曲げられた木管楽器で、英語の”Crumhorn”、フランス語の”Cromorne, Tournebout”、イタリア語の”Cromorna, Storto”何れも「曲がった、湾曲した」という意味に由来する名称を有している。円筒形の内径を有し、先端がやや広げられている。製作は、内径を穿った後曲げられる。管の先が曲げられているのは、指が届くようにと言った技術的な理由ではない。2枚リードの楽器だが、リードは直接口で咥えるのではなく、木製のキャップがかぶせられ、これに息を吹き込むことによって音を出す。そのため、唇でリードへの圧力を調整したり、息の強さを変えてオーバーブローすることが出来ず、音域はせいぜい9度しかない。通常はソプラノ(c’- d”)、アルト(f - f’)、テノール(c - d’)、バス(F - f)、コントラバス(C - d)の5種が用いられていた(図版参照)。

Michael Praetorius, “Syntagma musicum Band II De Organographia”, Wolfenbüttel 1619, Faksimile-Nachdruck herausgegeben von Wilibald Gurlitt, Documenta musicologica Erste Reihe: Druckschriften-Faksimiles XIV, Bärenreiter Kassel•Basel•London•New York, MCMLVIIIより
クルムホルンは、中世の牛や山羊の角で作られた楽器をもとに15世紀頃に作られたと思われる。最も古い画像史料は、すでに「中世の歌謡を様々な木管楽器と打楽器で、ヨーロッパ人とアラブ人が競演」の中で触れた、”Cantigas de Santa Maria”の手稿にあるミニアチュアに画かれた湾曲した楽器であるが、これは先端が開いており、実際にクルムホルンを画いたものかどうか疑問がある。1514年頃のハンス・ブルクマイールによる「マキシミリアンの勝利(Triomphes de Maximilien)」には、クルムホルンを演奏する楽士の姿が画かれている。しかし、明確にクルムホルンの名前とともに画かれたのは、1511年にハンス・ヴィルドゥングによって出版された最初の楽器事典である”Musica Getutscht”においてである。ここには4種類の長さのクルムホルンが画かれている。その後上に掲げたミヒャエル・プレトリウスの音楽大全(Syntagma musicum)の第II巻の音楽図鑑(1619年)に掲載された。
クルムホルンは先端が開いたショームなどと比較すると小さいが、かなりの音量を有している。音の強弱の調整は出来ず、息の強さによって音程が変化するので、特にクロス・フィンガリングによる半音の音程の調整に用いられる。16世紀になってかなり普及したが、17世紀に入ってルネサンスからバロック時代になると、廃れていった。
ルネサンスの器楽のための音楽は、基本的に楽器の指定がされておらず、どの曲がクルムホルンのための作品かは、よく分からない。多くの場合、音域が9度以内の曲が、クルムホルンのためと思われることなど、間接的な要素によって判断することになる。
今回紹介するのは、Syntagma Amiciというグループによるクルムホルンの合奏を収録したリチェルカール・レーベルのCDである。Syntagma Amiciについてはほとんど情報が無く、リチェルカールに3枚のCDがあって、特に2枚リードの楽器の奏者が主体のグループと思われる程度のことしか分からない。主なメンバーとしては、クルムホルンとリコーダーを演奏する5人が挙げられ、6声と8声の曲にはさらに4人、それにソプラノとバスの歌手、リコーダー奏者、レガールの奏者が加わっている。指揮者として名前の挙げられているベルンハルト・シュティルツは、ザールブリュッケン音楽学校の管楽器、古楽の教師であることが分かっている。
演奏されている曲は、フランドルで最初の音楽出版者、ティールマン・スサートが1551年に出版した”Het derde musyck boexken... alderhande danserye”からの舞曲に始まり、続いて神聖ローマ皇帝マキシミリアンI世(Maximilian I, 1459 - 1519)周辺の音楽家、ハインリヒ・イザーク、ルートヴィヒ・ゼンフルをはじめ、モーリッツ・フォン・ヘッセン、トーマス・シュトルツァーなどのドイツの歌謡や舞曲が収録されている。これらの中で最も良く知られている曲は、ハインリヒ・イザークの「インスブルック、私は去らねばならない(Innsbruck, ich muß dich lassen)」で、ソプラノとバスによって歌われている。これらの曲の中では唯一、ピエール・ドゥ・マンシュクール(pierre de Manchicourt)による”Du fond de ma pensée”のバス声部に「クルムホルンで(guet auf den Khrumbhorn)」という指示が記されている。続いてジョスカン・デプレ、アドリアン・ウィラール、ジオルジオ・マイネリオなどイタリアの舞曲と歌謡、フィレンツェのフランチェスコ・コルテッチア、ロドヴィコ・ダ・ヴィアダナの作品、そして最後は「白鳥の歌(Schwannengesang)」と題され、まずヨハン・ヘルマン・シャインの「音楽の饗宴(Banchetto Musicale)」(1617年)の中に本編の付録として加えられた、クルムホルンと明確に指定された「4声のパドゥアーナ(Padouana à 4)」とミヒャエル・プレトリウスの「クルムホルン、あるいは他の楽器で(auff Krumbhörner oder anderen Instrumenten)」と記された「6声のパッサメッツェ(Passameze à 6)」および「5声のガリアルデ(Gaillarde à 5)」によって、クルムホルンの歴史を締めくくるという構成になっている。収録曲は以下の通りである。
In den Cromhorn:
1. Allemaigne I: Tielman Susato
2. Bergerette "Sans Roch": Tielman Susato
3. La Morisque 1:174: Tielman Susato
4. Ronde "Il estoit une fillette": Tielman Susato
5. Pavane et gaillarde "Mille ducats": Tielman Susato
Deutsche Lieder und Tänze:
6. T'andernaken: Petrus Alamire
7. Carmen in Fa: Heinrich Isaac
8. Ich kumm aus fremden Landen her: Anonymus
9. Die vollen Brüedern: Anonymus
10. Bruder Conrads Tantzmass: Moritz von Hessen
11. Es hett ein Biedermann ein Weib: Ludwig Senfl
12. Pavana: Anonymus
13. Innsbruck, ich muß dich lassen: Heinrich Isaac
14. Du fond de ma pensée: Pierre de Manchicout
15. Erzürne dich nicht: Thomas Stoltzer
Per i storti:
16. La Spagna à 5: Josquin Desprez
17. Chi la gagliarda: Da Nola/Baltasare Donato
18. Pavana "La cornetta": Anonymus
19. Saltarello "Zorzi": Anonymus
20. Cingari simo: Adrian Willaert
21. Pavana "El bisson": Anonymus
22. Saltarello "Tutu": Anonymus
23. Vecchie lettroseAdrian Willaert
24. Pavana "La morte de la ragione: Anonymus"
25. L'arboscello ballo furlano & Puta nera ballo furlano: Giorgio Mainerio
Intermezzi de Firenze:
26. Guardane almo pastore: Francesco Cortecci
27. La Fiorentina à 8: Lodovico da Viadana
Schwannengesang:
28. Padouana à 4: Johann Hermann Schein
29. Passameze à 6: Micheal Praetorius
30. Gaillarde à 5: Michael Praetorius
演奏に使用されているクルムホルンは、大部分がこの演奏の指揮をしているベルンハルト・シュティルツによってブリュッセルの楽器博物館所蔵のイタリア製の楽器をもとに復元されたもので、一部はイギリスのエリック・ムールダーの作、コントラバス(C管)のみドイツのメック社製である。ルネサンス・リコーダーは、アメリカのボブ・マーヴィンによる、ヴィーンの芸術史博物館所蔵の楽器をもとにした復元楽器を使用している。楽器のピッチは、a’ = 463 Hzである。
クルムホルンという、ルネサンスに短期間愛用された楽器の様々な曲をまとめて聴くことの出来るこのCDは、以前に紹介したヴィエル・ア・ルー(ハーディー・ガーディー)やコルネット(ツィンク) のような楽器のCDと同様、貴重な存在と言うことが出来る。
このリチェルカール・レーベルのCDは現在も発売中だが、ネット上のストアーによっては、取り寄せの手間を嫌って、なかなか入手出来ない場合もあるので注意が必要である。
発売元:Ricercar
注)クルムホルンに関しては、ウィキペディアドイツ語版の“Krummhorn”及び”Recorder Home Page”内の“Crumhorn Hame Page”を参考にした。
楽曲については、CDに添付の解説書を参考にした。なおこの解説書には、年数表記やトラック番号にいくつが誤植があるので要注意。筆者が気付いたところでは、図版説明(p. 31)の”p. 17 : Hans Burgmair : Maximilien Ier visitant l’atelier de lutherie (ca. 1416)”は、マキシミリアンI世の生きていた期間から、1516年の誤りである。トラック・リストで、13が重複しており、本来は、13と14のはず。それに加え、”Innsubruck, ich muss dich lassen”の歌詞は、トラック番号が13であるはずの所、14になっている。

クラシック音楽鑑賞をテーマとするブログを、ランキング形式で紹介するサイト。
興味ある人はこのアイコンをクリックしてください。

「音楽広場」という音楽関係のブログのランキングサイトへのリンクです。興味のある方は、このアイコンをクリックして下さい。
| Trackback ( 0 )
|
|