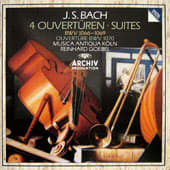
Johann Sebastian Bach, Ouvertüren
Archiv 415 671-2/4
演奏:Musica Antiqua Köln
バッハの管弦楽組曲は、ドイツ語ではOuvertüreと題されている。日本語に訳せば「序曲」という意味である。それはこれらの作品の冒頭の楽章が、フランス風序曲の様式で書かれていることによる。フランス風序曲は、ジャン・バティスト・リュリ(1632 - 1687)によって始められたオペラの序曲の形式である。付点8分音符と16分音符を単位とするリズムによる、ゆっくりとした荘重な導入部と、フーガで始まる速いテンポの第二部、そして短い導入部の繰り返しによる終結部からなっている。この序曲の後に何曲かの舞曲風の楽章が続いて、組曲となっている。
第1番ハ長調(BWV 1066)は、2本のオーボエ、ファゴットと弦楽合奏の編成で、序曲と6曲の舞曲風楽章からなっている。第2番ロ短調(BWV 1067)は独奏フルートと弦楽合奏からなる。第5楽章ポロネーズのフルートの変奏(ドゥーブル)が有名である。
第3番ニ長調(BWV 1068)は3本のトランペット、ティンパニ、2本のオーボエと弦楽合奏、第4番ニ長調(BWV 1069)は3本のトランペット、ティンパニ、3本のオーボエと弦楽合奏という編成である。第3番の第2楽章のアリアは、「G線上のアリア」の編曲でもよく知られている。第4番には、トランペットとティンパニがなく、メヌエットも含まない最初の姿があり、これは1725年以前に作曲されたものと思われる。そしてバッハは1725年の降誕節第1日目の礼拝のためのカンタータ、「私たちの口は笑いに満たされ」(BWV 110)の冒頭の合唱のためにこの序曲を転用し、第2部のアレグロの部分に合唱を組み込み、3本のトランペットとティンパニを追加した。その後メヌエットIとIIを加えて、最終的な形となったと考えられている。
「第5番」ト短調の組曲(BWV 1070)の最古の原典は、クリスティアン・フリートリヒ・ペンツェル(1737 ? 1801)によるパート譜である。 ペンツェルは、多くのバッハの作品の写譜を行った人物で、現在およそ80のバッハの作品の筆写譜が知られている。その多くが出所の明らかな原本からの写譜であるため、この曲もバッハの作と考えられるようになった。しかしこの写譜には、ただ”Bach”とだけ記されており、確実にヨハン・ゼバスティアン・バッハ作であるかどうかは、はっきりしない。
このト短調の組曲は、冒頭の楽章は確かにゆっくりとした導入部に速いテンポの曲が続くが、明らかにフランス風序曲とは異なっている。標題も「序曲」とは記されていない。その後に4曲の楽章が続くが、全体をまとめてみて、他の4作品とは明らかに作風が異なっており、聴いてみても、ヨハン・ゼバスティアン・バッハの作とは思えない。そのためこのト短調の作品は、1950年から刊行を始めた「新バッハ全集」からは除外されている。作風から見て、むしろ長男のヴィルヘルム・フリーデマン・バッハの作品のようにも思われるが、確実な証拠に乏しく、依然として「疑わしい作品」に分類されている。
このCDを取り上げたのは、単にこのト短調の組曲(BWV 1070)が含まれているという理由だけではない。ムジカ・アンティクァ・ケルンは1973年にラインハルト・ゲーベルがケルン音楽大学の同窓生たちを集めて結成したグループで、30年余りに渉って活動を続けていたが、2006年11月に解散してしまった。特に多くのドイツ・グラモフォンのアルヒーフ・レーベルでの録音で広く知られている。第2番と「第5番」は1983年、第1番、第3番と第4番は1985年の録音で、この当時はまだ創立以来のメンバーが多く含まれていた。従って、このグループ独特のクセの強い演奏スタイルが良く出ている。筆者は、このCDを聴く前は、カール・リヒター指揮、ミュンヘン・バッハ管弦楽団の演奏で親しんで来たので、最初聴いたときには、何かたどたどしい、奇妙な響きの演奏だな、という感想を懐いたが、多くのオリジナル楽器の演奏を聴いてきた今日になって聞き直してみると、そのような最初の印象は、もはや感じなくなった。
なお、第4番のトランペットとオーボエ抜きの演奏は、ラ・ストラヴァガンツァ・ケルンの演奏のCD(DENON CQ-78965-66)で聴くことが出来る。
なお、この管弦楽組曲のみのCDは、現在下記のサイトには掲載されておらず、ムジカ・アンティクァ・ケルンの演奏による、バッハの管弦楽曲や室内楽曲を収めた8倍組のボックス( 471 656-2 A B 8)が載っている。
発売元:Deutsche Grammophon/Archiv Produktion

クラシック音楽鑑賞をテーマとするブログを、ランキング形式で紹介するサイト。
興味ある人はこのアイコンをクリックしてください。
ドイツ語やフランス語の文字が文字化けする問題について
この「私的CD評」では、ドイツ人やフランス人の名前、それにそれらの国の作品や文書をそれぞれの国の言語で用いられているウムラウトやアクセント付きの文字を用い表記しています。これらの特殊文字は、HTMLの文字コードを用いなければ正しく表示されないため、これを用いて記述していますが、最近「私的CD評」をよく読んでくださっている方から、それらの特殊文字が正しく表示されないという事を知らせていただきました。この事に関してその方と何度か意見を交換した結果、Windowsの各ヴァージョン、Mac OSいずれに於いても、その純正のブラウザー、Internet Explorer 7やSafari Version 4では特殊文字が正しく表示されませんが、Mozilla Firefox 3.5.3を用いれば、Windows環境下でも、Mac OS環境下でも、問題なく表示されることが確認されました。この「私的CD評」をご覧いただいている方で、ドイツ語やフランス語の表示に文字化けが発生しておられる方は、Mozilla Firefoxのサイトで、無償でダウンロード出来ますので、一度お試しになることをおすすめします。
| Trackback ( 0 )
|
|