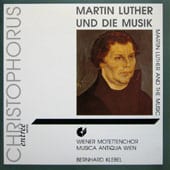
Martin Luther und die Musik
Christophorus CHE 0025-2
演奏:Wiener Motettenchor, Misica Antiqua Wien, Bernhard Klebel(指揮)
言い伝えによると、マルティン・ルター(Martin Luther, 1483 - 1546)は1517年10月31日、ヴィッテンベルク城の教会の扉に、95箇条の提言を貼り出した。実際に教会の扉に貼り出した訳ではなかったようだが、ルターはこの日に免罪符販売の弊害を取り除くための議論をもとめ、それを95箇条の提言にまとめた書簡を教会の幹部に提出したことは事実である。ルターはこの書簡の写しを聖職者の他には少数の友人に送っただけであったが、この年の終わりにはライプツィヒ、ニュルンベルク、バーゼルなどで印刷、流布され、ヒューマニズムの学者や若干の君主達の賛同を受ける一方で、ローマ教会側からの強い反発も呼んだ。翌1518年にはローマ教会が異端審問を始めるなど、カトリック内部での改革は不可能になってきた。そのためルターは、新たな教団を組織することとなり、ローマ教会に対立するプロテスタント教会が生まれた。
新たな教団としての教会の礼拝の式次第は、カトリックのミサを基本的には踏襲し、その内容をドイツ語化する努力がなされた。礼拝において常に朗唱されるミサの通常文は、最初はラテン語のままであったが、教会歴によって、日曜祝日ごとに変わる部分に関しては、早くからドイツ語の賛美歌(コラール)が導入された。それらのコラールは、新たに作曲されたもののほか、宗教改革以前から教会で歌われていた聖歌や当時流行していた世俗歌謡の旋律を採用したものなどがあった。
ルターは、個人的に非常に音楽を愛好していた。「私は神学者でなかったなら、音楽家になっていたかもしれない」と友人であり、音楽の面での助言者であったヨハン・ヴァルター(Johann Walter, 1496 - 1570)に語ったことがあった。ルターは、ヴァルターの助力を受けて、ドイツ語によるミサやコラールの整備を行った。宗教改革を象徴するコラールとして知られる「私たちの神は堅固な城(Ein feste Burg ist unser Gott)」は、歌詞だけでなく、作曲もルターであると言われている。そして1524年には、ヴィッテンベルクで、最初の賛美歌集が出版された。
ここで紹介するCDは、宗教改革者マルティン・ルターの音楽面での功績を、ルター派教会の創設当初からおよそ100年の間の、コラールを中心とする教会音楽の様々な形式を紹介するものである。
最初に、上述したコラール「私たちの神は堅固な城」の4種類の編曲が紹介される。ヨハン・ヴァルターとカスパー・オトマイール(Casper Othmayr, 1515 - 1553)のテノールに主旋律を置く4声の作品、オトマイールの声楽と器楽による2声の作品(ビチニウム)、そしてルーカス・オジアンダー(Lucas Osiander, 1534 - 1604)によるカンツィオナールザッツ(Kantionalsatz)である。カンツィオナールザッツというのは、ルネサンスの多声曲では、通常主旋律はテノール声部に置かれていたものを、教会で会衆と共に歌うために、4声で単一リズムの、コラールの旋律をソプラノにおいた形式のものである。この形式を創作したのがオジアンダーである。このほか、ルター派教会音楽の草創期に由来する、ルターが関わったコラールを様々な編曲で、さらにオルガンのためのコラールやモテットなどが紹介される。ルターが敬愛していた、フランスの音楽家ジョスカン・デプレ(Josquin Despres, 1440 - 1521)のモテット”Pange lingua”や、同じくカトリックの作曲家ルートヴィヒ・ゼンフル(Ludwig Sennfl, 1486? - 1542?)によるモテット”Non moriar, sed vivam”も収録されている。ジョスカン・デプレの作品は、純粋のカトリックの教会音楽であるが、ヴィッテンベルクでゲオルク・ラウ(Georg Rhaw, 1488 - 1548)によって出版された最初の福音派の音楽出版物に収められている。ヴァルターの唯一残っている非宗教曲「第7旋法によるフーガ(Fuga septimi toni)」、そして宗教改革後に生まれ,むしろ16世紀の音楽家といえる、ミヒャエル・プレトリウス(Michael Praetorius, 1571 - 1621)、ヨハン・ヘルマン・シャイン(1580 - 1630)、ザームエル・シャイト(Samuel Scheidt, 1587 - 1654)、ハインリヒ・シャイデマン(Heinrich Scheidemann, 1596? - 1663)等の作品も含まれている。
演奏しているヴィーン・モテット合唱団、ムジカ・アンティクァ・ヴィーンと指揮者のベルンハルト・クレーベルについて、添付の解説書には何も触れられていない。クレーベルについては、ヴィーン生まれで、ヴィーン音楽、演劇大学で音楽を学び、ヴィーン・モテット合唱団、ムジカ・アンティクァ・ヴィーンの指揮者であること、オペラの制作を行っていることが分かっている程度である。編成は、混声合唱と弦楽合奏にコルネット、トロンボーン、それにオルガンである。オルガン演奏は、ヨーゼフ・ホーファー(Joseph Hofer)とarkivmusic.comというサイトの、このCDの情報には書かれている。さらに録音は1982年5月、ヴィーンのバウムガルテン・ステュディオだそうだ。アナログ録音だが、音質は明瞭である。このCDのレーベルであるクリストフォルスのサイトは、現在存在しないようだが、このCDそのものは、いくつかのウェブCDショップで入手可能なようである。
発売元:Christophorus
入手可能なCDショップサイトの一例:CD Univers、AktivMusic

クラシック音楽鑑賞をテーマとするブログを、ランキング形式で紹介するサイト。
興味ある人はこのアイコンをクリックしてください。
| Trackback ( 0 )
|
|