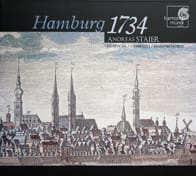
Hamburg 1734
Harmonia mundi France HMC 901898
演奏:Andreas Staier (Clavecin Anthony Sidey d’après Hass)
ヒエロニュムス・アルブレヒト・ハス(Hieronymus Albrecht Hass, 1689 - 1752)は、ハンブルクで生まれ、生涯同地で活動した、ドイツに於いて最初のそして最大のチェンバロ、クラヴィコード作者と考えられている。ハスによる多くの楽器が残っているが、これらの楽器を見ると、彼が様々な工夫によって楽器の可能性を追求していたことがうかがわれる。ハスの代表的なチェンバロとしては、ブリュッセルの楽器博物館に所蔵されている1734年製作のものと、パリの個人蔵の1740年製作の3段鍵盤のものが代表的である。今回紹介するCDは、このうち1734年製作のチェンバロを、パリに工房を構えるアンソニー・シデイが複製した楽器によって、アンドレアス・シュタイアーがハンブルクにちなんだ作品を演奏したフランス・ハルモニア・ムンディ盤である。
このCDに添付の解説書には、楽器の詳細は述べられていないので、レイモンド・ラッセルの「ハープシコードとクラヴィコード*」を参考に概要を述べる。この楽器は現在ベルギー、ブリュッセルの楽器博物館に所蔵されており、その響板に「ヒエロニュムス・アルブレヒト・ハス、ハンブルク、1734年(Hieronymus Albre Hass fecit Hamburg. Anno 1734)」と記されている。サイズは脚を除いて、長さ267 cm x 巾92.7 cm x 厚み28.6 cmあり、これがちょうど入る箱に収めるとすると、典型的なリュッカースの2段鍵盤のチェンバロのそれと比較して約1.5倍の容積が必要になる。高音側の側面の板の巾は99 cm有り、それに続く側板は、現在のピアノのように二重の曲線を描いている。
弦は16フィート弦1、8フィート弦2、14フィート弦1の4対ある。16フィートは8フィートより1オクターヴ低い音を出すので、その弦も2倍の長さが必要だが、それでは楽器の長さが非常に長くなるので、この楽器の場合、最低音のGGの16フィート弦は213.36 cmで、174 cmの8フィート弦の122.6 %しかない。しかし高音になるに従って長くなり、中間のc’では8フィートの倍の長さになっている。16フィート弦は、弦の張力に対応するため、独立した響板に張られている。鍵盤は2段で、音域はGGからd’’’までショート・オクターヴなしの半音階刻みで55鍵、プレクトラムはそれぞれの弦に加え、上段鍵盤の8フィート弦にもう一列リュート・ストップ用のものがある。これは、エンドピンのすぐ近く、最低音GGの場合約4.4 cm、最高音d’’’の場合約6 mmのところを弾く。それによって、弦の振動は少なく、プレクトラムが弦を弾く音が際立った響きが得られる。さらに下段鍵盤の8フィート弦と16フィート弦には、パッドをエンドピンの近くで弦に触れさせて振動を抑え、ピッツィカートの効果が得られるハープ・ストップが備えられている。全音の鍵盤は象牙で覆われており、現在のピアノのように白鍵になっている。キーの前面はアーチ状のエボニーが貼られている。半音の鍵盤は、真珠母貝と鼈甲による象眼模様が施されている。鍵盤上部に貼られたプレートには、「1858年にパリのピアノ工房フリューリにて修復された(Restauré par Fleury facteur de pianos à Paris en 1858)」と記されている。ケースはクリーム色に塗装されており、金と茶色の縁取りがある。蓋の内側には、風景画が描かれている。

1734年Hieronyumus Albrecht Hass製作のチェンバロ。ブリュッセル楽器博物館所蔵(Wikipedia Commons: File: Hieronymus Albrecht Hass, Hamburg, 1734 - clavecin - IMG 3894.JPG)
ハスが1740年に製作し、現在パリの個人所有のチェンバロは、さらに大型で、3段鍵盤、16フィート弦、2対の8フィート弦、4フィート弦、それにc’以上の2フィート弦を有し、最上段の8フィート弦にリュート・ストップも備えている。ハスの楽器はいずれも18世の中頃の作で、チェンバロ製作の後期に属している。リュッカースをはじめとしたフレミッシュ・チェンバロ、その影響下に発展したフレンチ・チェンバロの流れとは別に、ハスはチェンバロにオルガンの豊かで多様な響きを求めて、様々な工夫を施していったようだ。しかしチェンバロは、18世紀中頃から登場してくるピアノフォルテに、徐々にその地位を奪われて行くことになる。フランスのパスカル・タスカンやドイツのハス等のチェンバロは、こうした時代の流れの中で、チェンバロに最後の輝きを与えた。
アンソニー・シデイによる、ハスの1734年のチェンバロの複製は、機構的には元の楽器に忠実に行われているが、ケースの外側は茶色に塗装され、金色の枠が描かれている。響盤には、元の楽器同様草花が描かれ、蓋の裏側にも茶色の背景に草木が描かれている。鍵盤も全音キーは白で、前面に黒い木が貼られ、半音キーは象眼模様の濃い色の木が貼られている。
今回紹介するCDに収録されている曲は、この楽器が製作された1734年前後に作曲された、ハンブルクに何らかの関わりのある音楽家達の作品である。ヘンデルは1703年から1706年までハンブルクに滞在し、ラインハルト・カイザー(Reinhard Keiser, 1674 - 1739)が首唱するゲンゼマルクトのオペラ劇場のためにオペラを作曲し、ヨハン・マッテゾン(Johann Mattheson, 1681 - 1764)と交遊関係にあった。このCDに収録されている「シャコンヌト長調」(HWV 435)は、1733年に出版された曲の中に含まれるが、すでにハンブルクで作曲された可能性がある。マッテゾンの作品としては、「上級練習曲」の13番変ロ長調と7番変ホ長調が収録されている。いずれも短い曲である。ゲオルク・フィリップ・テレマン(Georg Philipp Telemann, 1681 - 1767)は、中部ドイツの生まれでライプツィヒ大学に学び、後にバッハも指揮をすることになる学生によるコレーギウム・ムジクムを組織し、その後ポーランドのゾーラウ、アイゼナハ、フランクフルト・アム・マインで活動した後、1721年にハンブルクのヨハネウム・ラテン学校のカントールに招かれた後、生涯ハンブルクで活躍した。テレマンは1728年11月13日から翌1729年11月1日まで、「忠実な音楽の師(Getreue Music-Meister)」と題する定期刊行物を2週間ごとに合計25回刊行した。それぞれの号には1曲のソナタ、トリオソナタなどの作品と、アリアやカノンなどの小曲が4ページの中に収められていた。このCDに収録されている「チェンバロのためのポロネーズ風序曲」ニ短調( TWV 32:2)は、「忠実な音楽の師」に掲載された曲のひとつで、「ポロネーズ風序曲」他計6曲からなっている。さらに、オーケストラのための「ハンブルクの潮の満ち干(Hamburger Ebb und Fluth)」ハ長調(TWV 55:C3)と「アルスター序曲(Alster-Ouvertüre)」ヘ長調(TWV 55:F11)を、シュタイアーが四つ手のチェンバロ用に編曲して演奏している。「アルスター序曲」の第2曲「蛙と鴉達の協奏(Die concertierenden Frösche und Krähen)」の編曲は、不協和音を交えた大胆な編曲である。これらの曲には、クリスティーネ・ショルンスハイムが加わっている。
ハンブルクの聖ヤーコビ教会のオルガニストであったマッティアス・ヴェックマン(Matthias Weckmann, c. 1616 - 1674)の「トッカータIV」イ短調、聖カタリナ教会のオルガニストであったハインリヒ・シャイデマン(Heinrich Scheidemann, c. 1596 - 1663)の「涙のパヴァーヌ」ニ短調、リュベックの聖マリア教会のオルガニストであったディートリヒ・ブクステフーデ(Dieterich Buxtehude, c. 1637 - 1707)の「前奏曲とフーガ」ト短調(BuxWV 163)、リューネブルクの聖ヨハネ教会のオルガニストで、バッハが教えを受けていたゲオルク・ベーム(Georg Böhm, 1661 - 1733)の「前奏曲とフーガ」ト短調等の作品は、いずれもオルガンのための作品と思われるが、ペダルなしで演奏可能で、ここではハスのチェンバロの響きの多様さを示すために取り上げられたのだろう。
これらに加え、1965年生まれのフランスの作曲家ブリス・プゼ(Brice Pauset)が、このハスの複製での録音のために特に作曲した短い前奏曲が最後に収録されている。その副題は「ヒエロニュムス・アルブレヒトの思い出に、アンドレアス(・シュタイアー)、アンソニー(・シデイ)、フレデリク(・バル)のために」とある。CDに添付の小冊子の、シュタイアーの解説によると、フレデリク・バルは、シデイとともにチェンバロの製作に関わった人物のようだ。
これらの収録曲によってシュタイアーは、ハスのチェンバロの多様な響きを示している。それによって、様々なレギスターの組み合わせ、リュート・ストップやハープ・ストップの響き、16フィート弦を加えた雄大な響きを聴くことが出来る。新しく製作された楽器だけに、機械的雑音もなく、明確で鮮明な音を聞くことが出来る。録音は2005年5月にベルリンのスタジオに於いて行われた。演奏のピッチや調律については何も記されていない。
発売元:Harmonia mundi France
Raymond Russell, “The Harpsichord and Clavichord. An Introductory Studey”, Faber and Faber, London 1959, 図版85.および86.の解説。

クラシック音楽鑑賞をテーマとするブログを、ランキング形式で紹介するサイト。
興味ある人はこのアイコンをクリックしてください。
| Trackback ( 0 )
|
|