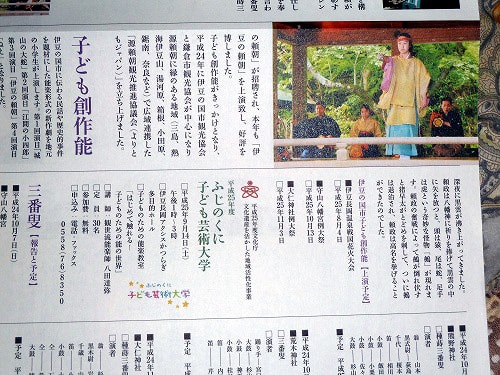能の囃子。。とくに笛の調子が陰陽五行説に則って性格づけられていることは前述しましたが、実際には能の笛の調子には黄鐘調と盤渉調の二つしかなく(双調、平調もあるけれど、例外と言ってよい扱い)、しかも能には旋律楽器の合奏は行われず、そのためか唯一の旋律楽器である笛も合奏に向くように均一に精巧に、というよりはむしろ反対の、1管1管の個性を重視して作られているように思えます。。すなわち能の音楽の中での「調子」というものは多分に観念的なものだと言うことができます。
これは何も能に限ったことではありませんで、先行芸能である雅楽の六調子も、中国から伝来した割には楽典よりもむしろ観念の輸入を重視したかのように中国のそれとは独立したものらしい。
しかし能に現れるこの二つの調子が、観念的に正反対の性格を持つものである事は注意したいと思います。
前述のように能の二つの調子のうち、多数派である「黄鐘」が表すものは「火、夏、南、赤」なのであり、少数派の「盤渉」は「水、冬、北、黒」。まさに正反対であって、また「黄鐘」に比べて「盤渉」には どことなくネガティブなイメージがつきまとっています。ところが実演に接すると、むしろその印象は逆で、舞の「黄鐘」のかっちりとして、ややフォーマルな感じと比べると、「盤渉」には浮きやか・華やかで ちょっとくだけたイメージがあるように思います。
この観念と実演とのギャップが「早舞」が、能『当麻』『海士』といった重厚、あるいは浄化をテーマとする能で使われる一方、『融』『須磨源氏』『玄象』のような遊舞の曲で舞われる理由のひとつなのでしょう。こうして冬や北。。要するに「死」のイメージ。。というよりはそこから昇華して現世から浄土へ移行して浄化される魂の表現としての「早舞」と、それとは別に遊舞のために舞われる「早舞」に大別されているのだと思います。そうして遊舞としての「早舞」には小書や替エとして様々なバリエーションも用意されていますし、現実には現在では小書と同様の扱いにはなっていますが、シテの裁量で型を変化させることによって囃子も舞も大きく変わる「クツロギ」という大変面白い舞のバリエーションがあるのもこの「早舞」だけです。
『融』もまた遊舞の「早舞」の曲であって、いや、邸宅に塩竃の景物を移して楽しんだ風流人描くこの曲はまさに遊舞の「早舞」が最もふさわしい曲なのであって、そのため観世流の小書にも「十三段之舞」「舞返」「酌之舞」。。と多くのバリエーションがあり、実演ではお客さまに楽しんで頂ける舞だと思います。シテが僧の読経や回向さえも願わず、ワキも弔いを行わない『融』であってみれば、まさにこれは遊舞のための曲なのであって、小書ではないけれども「替エノ型」など面白い型の上演が似合うと思います。
そういえば『融』の「早舞」は、冒頭にこの曲独特の譜が吹かれて始まりますね。「融掛カリ」と呼ばれる「ヒヤウラウラウラ。。」という譜で始まるのがそれ。『海士』の「早舞」もまた独特の「イロエ掛カリ」という始まり方をするのですが、こちらが子方に経巻を渡す型の必要上を考慮されて作曲された印象であるのとは対照的に『融』の掛カリは、特に型の上でその譜である必要がないので、これは演出上の聴覚的な効果か、あるいは前述のような「早舞」にまつわる観念的な意味を考慮したのではないかと ぬえは考えています。
すなわち、常の「早舞」。。『融』『海士』以外の曲の「早舞」は「ヲヒャ、ヲヒャーーラ、」と始まる譜で、笛方森田流では「破掛カリ」とも称されているようで、この譜からすぐに呂中甲の四クサリを吹き返す、「神舞」や「中之舞」などと同じ構成になっています。ところが一噌流では上記の譜のあとに「ヲヒャ、ヲヒヤリ、ヒウヤラリ」という譜が挿入されて、それより繰り返しの譜となっていて、この構成は俗に「段掛カリ」と呼ばれることがあります。
「段掛カリ」という名称は、この2クサリの譜が、舞の中の区切り。。「段」の冒頭に多用される譜であることから名付けられたものだと思います。これは ぬえの憶測でしかありませんけれども、この「段掛カリ」が「早舞」の「格式」のようなものを表わしているのではないか、と思っています。
総じて重厚で長大な舞。。たとえば「真ノ序之舞」「序之舞」「楽」「神楽」には「序」という、やや儀式的なプロローグのような譜が冒頭に付与されていて、「段掛カリ」はこれに次ぐ位置に置かれているのではないか。。すなわち「段」の冒頭の譜を吹き初めの「掛カリ」から吹くことで、いわばフォーマルな舞であることを表現しているのではないか、ということです。「神舞」は「段掛カリ」ではありませんが、急調な舞であることで、略された「段掛カリ」なのではないかと考えています。
このフォーマルな舞、という意識が『当麻』『海士』のような、菩薩や神をイメージさせる舞にも、また『融』『玄象』『須磨源氏』のような貴人の遊舞の舞にも使われる理由なのではないか。そうして遊舞の舞のまさに典型たる『融』の「早舞」には、このフォーマルさを少し崩して遊舞の雰囲気を強調するために専用の掛カリが用意された。。ぬえはこのように考えています。
これは何も能に限ったことではありませんで、先行芸能である雅楽の六調子も、中国から伝来した割には楽典よりもむしろ観念の輸入を重視したかのように中国のそれとは独立したものらしい。
しかし能に現れるこの二つの調子が、観念的に正反対の性格を持つものである事は注意したいと思います。
前述のように能の二つの調子のうち、多数派である「黄鐘」が表すものは「火、夏、南、赤」なのであり、少数派の「盤渉」は「水、冬、北、黒」。まさに正反対であって、また「黄鐘」に比べて「盤渉」には どことなくネガティブなイメージがつきまとっています。ところが実演に接すると、むしろその印象は逆で、舞の「黄鐘」のかっちりとして、ややフォーマルな感じと比べると、「盤渉」には浮きやか・華やかで ちょっとくだけたイメージがあるように思います。
この観念と実演とのギャップが「早舞」が、能『当麻』『海士』といった重厚、あるいは浄化をテーマとする能で使われる一方、『融』『須磨源氏』『玄象』のような遊舞の曲で舞われる理由のひとつなのでしょう。こうして冬や北。。要するに「死」のイメージ。。というよりはそこから昇華して現世から浄土へ移行して浄化される魂の表現としての「早舞」と、それとは別に遊舞のために舞われる「早舞」に大別されているのだと思います。そうして遊舞としての「早舞」には小書や替エとして様々なバリエーションも用意されていますし、現実には現在では小書と同様の扱いにはなっていますが、シテの裁量で型を変化させることによって囃子も舞も大きく変わる「クツロギ」という大変面白い舞のバリエーションがあるのもこの「早舞」だけです。
『融』もまた遊舞の「早舞」の曲であって、いや、邸宅に塩竃の景物を移して楽しんだ風流人描くこの曲はまさに遊舞の「早舞」が最もふさわしい曲なのであって、そのため観世流の小書にも「十三段之舞」「舞返」「酌之舞」。。と多くのバリエーションがあり、実演ではお客さまに楽しんで頂ける舞だと思います。シテが僧の読経や回向さえも願わず、ワキも弔いを行わない『融』であってみれば、まさにこれは遊舞のための曲なのであって、小書ではないけれども「替エノ型」など面白い型の上演が似合うと思います。
そういえば『融』の「早舞」は、冒頭にこの曲独特の譜が吹かれて始まりますね。「融掛カリ」と呼ばれる「ヒヤウラウラウラ。。」という譜で始まるのがそれ。『海士』の「早舞」もまた独特の「イロエ掛カリ」という始まり方をするのですが、こちらが子方に経巻を渡す型の必要上を考慮されて作曲された印象であるのとは対照的に『融』の掛カリは、特に型の上でその譜である必要がないので、これは演出上の聴覚的な効果か、あるいは前述のような「早舞」にまつわる観念的な意味を考慮したのではないかと ぬえは考えています。
すなわち、常の「早舞」。。『融』『海士』以外の曲の「早舞」は「ヲヒャ、ヲヒャーーラ、」と始まる譜で、笛方森田流では「破掛カリ」とも称されているようで、この譜からすぐに呂中甲の四クサリを吹き返す、「神舞」や「中之舞」などと同じ構成になっています。ところが一噌流では上記の譜のあとに「ヲヒャ、ヲヒヤリ、ヒウヤラリ」という譜が挿入されて、それより繰り返しの譜となっていて、この構成は俗に「段掛カリ」と呼ばれることがあります。
「段掛カリ」という名称は、この2クサリの譜が、舞の中の区切り。。「段」の冒頭に多用される譜であることから名付けられたものだと思います。これは ぬえの憶測でしかありませんけれども、この「段掛カリ」が「早舞」の「格式」のようなものを表わしているのではないか、と思っています。
総じて重厚で長大な舞。。たとえば「真ノ序之舞」「序之舞」「楽」「神楽」には「序」という、やや儀式的なプロローグのような譜が冒頭に付与されていて、「段掛カリ」はこれに次ぐ位置に置かれているのではないか。。すなわち「段」の冒頭の譜を吹き初めの「掛カリ」から吹くことで、いわばフォーマルな舞であることを表現しているのではないか、ということです。「神舞」は「段掛カリ」ではありませんが、急調な舞であることで、略された「段掛カリ」なのではないかと考えています。
このフォーマルな舞、という意識が『当麻』『海士』のような、菩薩や神をイメージさせる舞にも、また『融』『玄象』『須磨源氏』のような貴人の遊舞の舞にも使われる理由なのではないか。そうして遊舞の舞のまさに典型たる『融』の「早舞」には、このフォーマルさを少し崩して遊舞の雰囲気を強調するために専用の掛カリが用意された。。ぬえはこのように考えています。