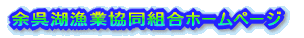【ふなずしを味わう】
鮒寿しに付いた飯を軽くしごき取り、おおよそ3か
ら5ミリ位の厚さに切りそのまま、ひと切れを口に
運び吟醸酒を含み飲む。鮒寿しと吟醸酒がその芳醇
で深い味わいはまさに絶品。ことに、鮒寿しの仕込
みと同じ水を使って醸した吟醸酒「竹生嶋」(吉田
酒造)との相性は格別という。本当においしいのは
身の締まった筋肉質の尾びれの近くともいわれる。
噛めば噛むほど旨味が出て「やみつきになる味」「
はまる味」。
鮒寿しの切り身を熱いご飯の上に乗せ、まわりにた
っぷりついている「飯」を少し乗せて、軽く塩をふ
り、熱い目のお茶をかけます。鮒寿しの熟成された
コクのある酸味が、おいしいお茶漬けをつくる。寒
いときには、ほかほかと身体の芯からあたたまる。
鮒寿し(ふなずし)は、風邪を引いたとき、熱いお
湯をかけて飲むとそれが持つ乳酸菌の作用により発
汗を促し楽になるともいわれ、鮒寿し自身のもつビ
タミン、天然の抗生物質もそれに一役かっていると
か。お腹の調子の悪い時などは、鮒寿しの乳酸菌が
調子を整える手助けするという。
鮒寿しはそれぞれの店によって味がそれぞれ違う。
抵抗感のある方も、先入観をもたずにいろいろため
して好みに合った味の店を選ぶのが大切。作家の遠
藤周作や子母澤寛、元清水寺貫主の大西良慶和上も
この海津大崎の専門店「魚治」や料亭「湖里庵」を
訪れている。
「湖里庵」は作家の狐狸庵先生こと遠藤周作から名
をいただいたということだが。先生からは「湖里庵
へ来たら食べられるもの、湖里庵に来なければ食べ
られないものを名物料理として考えなさいよ」との
ヒントから「鮒寿し懐石」がうまれまれたとか。
「鮒寿し懐石」は、いろんなかたちで鮒寿しがいた
だける上、風光明美な海津の素晴らしさを堪能でき
る。

【エピソード】
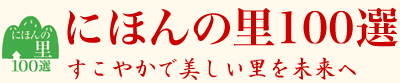
滋賀県はすぐれた身近な景観に恵まれているオンリ
ーワンの地勢をもつ。この価値にさらに磨きをかけ
宝物となすのは各地の住民だ。「にほんの里100
選」では「白王・円山」「甲南町杉谷新田」の2箇
所が選ばれているが、全国から百だけを選ぶとなる
とやもうえないかもしれない。その典型が高島市の
畑地区の棚田などがそうだ。ひとの手がかからなけ
れば直ちに荒廃する。里山が荒廃すれば海も荒廃す
ることは科学的に検証されているが、二箇所だけで
ない。それならということで来年から個人的に百箇
所を選定しに歩こうと思う...
そんなことを考えていたら、鮒寿しも創意工夫すれ
ばもっと洗練されたものができるはずだと思ったが
これは専門家の手がいる。

畦(あぜ)は常に草刈りされて美しい。動植物も多
様で自然豊か。東海自然歩道が通る。

ヨシ原特有の湿地生態系が残る琵琶湖最大の内湖、
西の湖の北西にある。ヨシ産業が昔から続き、湖中
の島には舟で通う水田も。
【脚注及びリンク】
------------------------------------------
1.にほんの里百選
2.おうみ棚田ネット
3.高島市の『百選』
4.魚治
5.湖里庵
6.周作クラブ
------------------------------------------