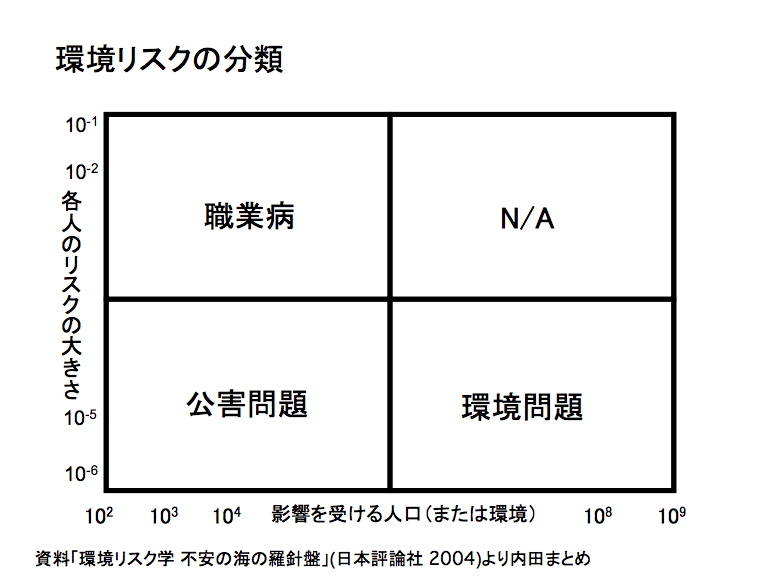■ 養父志乃夫
養父志乃夫
【環境保護と環境創造】
ビオトープ(独:Biotop)、バイオトープ(英:
biotope)は、生物群集の生息空間を示す言葉であ
る。訳す場合は生物空間、生物生息空間とされ
る。語源はギリシア語からの造語(bio(命)+
topos(場所))。ドイツ連邦自然保護局ではビ
オトープを「有機的に結びついた生物群。すな
わち生物社会(一定の組み合わせの種によって
構成される生物群集)の生息空間」と位置づけ
ている。別の表現をするならば「周辺地域から
明確に区分できる性質を持った生息環境の地理
的最小単位」であり、生態系とはこの点で区別
される。つまり、ビオトープ(環境)とその中
で生息する生物群集(中身)によって、生態系
は構成されていると言うこともできる。日本に
おいても自治体が行う事業に「ビオトープ」と
いう語を用いる場合にはこういった発想が一般
に援用されている。生物学における用法では、
例えばヘイケボタルが生息する典型的な環境を
ヘイケボタルのビオトープと呼ぶ。
そこには、気象条件、地勢や水系の特性、他の
生物の生息状況などが含まれる。ただし、この
言葉は特に生態系(Ecosystem)との違いが明確で
はなく、どちらでも使える場合もあり、現在で
は生態学の用語として使われる場面は多くない。
生態学の分野で使われる場合にも、以下の用法
で使われている例が多い。これに対して、この
用語を積極的に用いるようになったのは、自然
の開発の仕方の反省にたった所から始まる。
特にヨーロッパにおいて人工的に形作られた河
川などの形態をより自然に近い形に戻し、それ
によって多様な自然の生物を復活させるととも
に、本来の自然が持っていた浄化作用を利用す
る、といった観点から、多自然型河川護岸であ
るとか、親水工法といった言葉が使われるよう
になった。つまり、これまでは機械的に形作ら
れてきた河川護岸を、生物の生息場所であると
意識し、それを積極的に利用する方法が始めら
れたのである。このような、人為的に多様な生
物的環境を創造する試みのことを、エコアップ
などと称する場合もある。
【解説】
修景、借景という言葉を今風にいうとビオトー
プとなる。人工造景、人工造園は都市化や産業
による周辺景観の紊乱や自然破壊に対抗する是
正、修正の歴史的意味合いが込めらてもいる。
琵琶湖という修景の足下は、ゴミの不法投棄や
心ない住民マナーの欠落というミクロな積み重
ねや農林業政策や廃村といった社会構造のマク
ロな変容の影響に曝されており、どの様な切り
口から、どこから手をつけて行くのかという問
題を抱えているが、周辺河川や湖岸のゴミ拾い
や美化運動から手をつけていくのが自然な気が
する。
【外部リンク】


■