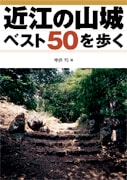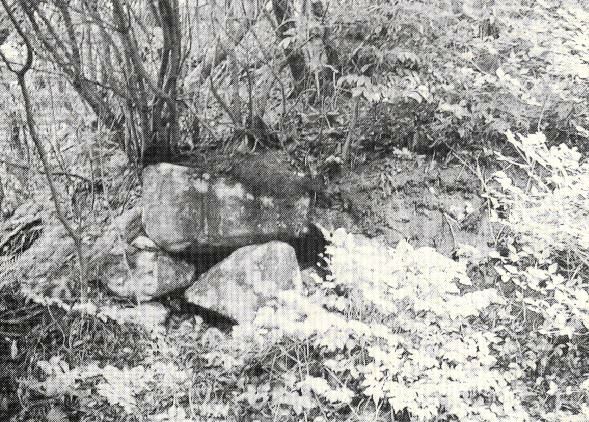北之庄城は、近江ハ幡市の北部にあるハ幡山の中央尾
根頂部に所在する,文献史料は、ほとんど見つかってい
ないが、江戸時代に八幡山を描いた絵図中に、「佐々木
六角の付城」という説明がつけられているものがあり、
また、『近江温故録』『近江輿地志略』に散見できるの
みである。ただし、『近江輿地志略』の中では、城郭の
記述はなく、『・・・阿弥陀寺繁昌の時の寺院跡なるべし』
と言う寒川辰清の推測が述べられており、城郭としての
意識はこのときにはなかったようである,『近江温故録』
の中では、「屋形氏綱の二男ヲハ幡左馬頭義昌ト号シ後
目ノ岩崎山二在住ニテ八幡宮ヲ守護セラレシ申也義昌ノ
息川端左近太夫輝綱ハ公方光源院殿ノ近習ニテ即同事二
討死山一六角判官崇永ハ此岩崎山二城ヲ築キ在城ノ由也
石垣等昔ノ跡今ニアリ」という記述があり、北之庄城が
佐々木六角氏の手によって、観音寺城の付城として築城
されたことが記されている。尚、岩崎山という呼称につ
いてであるが、地元では、ヴォーリズ記念病院の裏手に
ある山周辺のことをそう呼んでいることから、北之庄城
に関する記載であると言える史料である。

本城の主な遺構としては、上下に分かれた曲輪、それ
をそれぞれ取り囲む土塁、切岸、掘切、空堀、土橋、櫓
台、あるいは狼煙台、それと虎口などである。
曲輪は、上下に分離しており、上部にあるものが、約
50メードル四方の方形のプランを持つもので、内側の
平坦部との比高差が最も大きい西側で、約4メートル、
東側で約1.6メートルに及ぶ土塁によって固められて
いる。『・・・虎口は北側に開口しており、その前面には、
虎口受けが備えられている。そこから通路が下部の曲輪
に通いじていたようである。この通路の両側には、不明
瞭ではあるが、左右に三段ずつ計六つの区画を配してお
り、この通跡を守っていたようで、部分的に土塁も確認
できる。

下段の曲輪であるが、まず東側に、本城の最大の見所
である内枡型の虎口が設けられている。これは高さ約3
メートルを測る土塁と一体になったもので、その人目に
は、門柱跡の可能性のある窪みが二つ存在する。スロー
プ状に傾斜面がつけられている虎口の外側には、幅約6
メートルの平坦地が造られ大手近となっている。この大
手近は、そのまま南に伸び、空堀の東側で析れて、そこ
からヴオーリズ記念病院に下る尾根に通じていたようで
ある。現在は途中の土砂崩落や後世の改変などにより確
定はできない。

その虎口から入って右手に当たる、下段の曲輪の北側
には、長方形の区画群が存在している。それらは、十数
区に区画されており、それぞれ長辺15~20メートル、
短辺10メートル前後の規模を持つもので、二股から三
段で構成されている,一部に有積みを確認でき、それぞ
れ曲輪の比高差は、約70センチ前後で、内側平坦地か
らの高さ約70センチ程度の土塁が巡っているものも数
箇所存在する。これらは、長辺をすべて最下部の平坦地
に向ける形で配置されており、平虎口を有するものにつ
いても、最下部平坦部に向けて開口するようにして作ら
れている。
下段の曲輪の北側には、東西二つのピークが存在する。
西側のものには頂部に約6メートル程度の平坦地が存在
し、そのほぽ中央には、凹みがあり、あるいは狼煙台か
と考えられる。この平坦部の南側の土塁上は、幅10メ
ートル前後と広く作られている。
東側のものは、約七メートル程度の平坦地が頂部に造
られ、その東側には、平入りの虎口が開いており、その
脇には武者隠しと考えられるものが作られている。
最下部平坦地には、六つの円形の窪みが存在する。大
きなものでは幅約5メートルをはかり、現状では深さ約
一メートル前後である。この窪みは、前述したように
『近江輿地志略』によると、「(七つ池)北庄村の裏山
にあり。柱礎の跡多くあり。思うに古、阿弥陀寺繁昌の
時の寺院跡なるべし。」と記述されており、江戸期には
既に存在していたようであるが、そもそもこの地が城跡
と認識はされていなかったようである。なぜか、ここで
は七つ池とされているが、現状では六つの窪みしか確認
できない。この窪みについては、すり鉢状になっている
下段の曲輪の最下部にあり、当然のように水が集まると
ころに掘られているため、水溜めの可能性もあるが、詳
細については不明である。
本城については詳細な記録がなく、その築城年代につ
いても、下段曲輪東側の内枡型の虎口など史料とは年代
観にズレが生じる遺構もあり、詳細についてはこれから
の成果を待ちたい。 (三尾次郎)

【エピソード】
【脚注及びリンク】
---------------------------------------------
1. 滋賀県近江八幡市(西の湖周辺)、2008.11.20
2. 近江 北之庄城 /城跡巡り備忘録 滋賀県
3. 近江輿地志略(寒川辰清自筆本)
4. ヴオーリズ記念病院
5. ウィリアム・メレル・ヴォーリズ
6. 近江・北之庄城写真館
--------------------------------------------------