
滋賀県愛知郡愛知川町、彦根市を流れ、
琵琶湖に注ぐ川。一級河川の起点は愛
知郡愛知川町愛知川の中川原、流原川。
愛知川町西部で愛知川の東方沿いを北
流、彦根市に入ってからは北西流し彦
根市柳川町の柳川漁港で琵琶湖東岸に
注ぐ。20号柳川能登川線が沿う田園地
帯のクリーク。愛知川の名産、びんて
まりのモニュメントが載っている不飲
橋を渡ると中山道は不飲橋の信号で国
道と合流する。
【文禄川】
宇曽川を南北に琵琶湖に流入する川が
数本ある。宇曽川は愛荘町・東近江市
境の山中に発し西流、宇曽川ダム(ロ
ックフィルダム)に水を溜めたあと、
愛荘町に扇状地を開く。以降は北西流
し愛荘町を貫流、豊郷町と愛荘町の境
を流れ彦根市に入り、荒神山の東縁を
めぐり彦根市三津屋町と須越町の境で
琵琶湖に注ぐ(河口右岸に宇曽川漁港。
一級河川の起点は東近江市下一色町(旧
湖東町地区)の押立山・内奥山、愛荘町
松尾寺(旧秦荘町地区)の秦川)。その
一つが文禄川で、愛知郡愛知川町長野
の、愛知川と宇曽川が近接して流れる
あたりに発し彦根市南部を北西流、薩
摩町と石寺町の境で琵琶湖に注ぐ(一
級河川の起点は彦根市野良田町の東川、
平貝)。
※宇曽川は、古くから水量豊富で舟運
が盛んであったために”運槽川”と称
し、時の流れと共に転訛して「うそ川」
と呼ばれるようになったといわれる。
【室戸川】
彦根市南部を流れ、琵琶湖に注ぐ川。
一級河川の起点は彦根市薩摩町美ノ淵、
高畔。田園地帯のクリーク。これ以外
に八坂町~須越町~石寺町~薩摩町の
湖岸には大川、石川、今川などの小さ
な川が流入し荒神山を背景とした独特
の景観をつくり四季折々楽しめる。
【山崎山城址】
彦根市南部の湖岸近くに所在する荒神
山の南東側に位置する比高50m程度の
小さな独立丘陵。
山崎山城跡は発掘調査の結果、尾根の
中央に大きな堀切を設け、その東側半
分(東西約90m、南北約20m)を城
域とする小規模ながら、石垣を設けた
戦国期の城であることが分かり、また
石垣は、西側斜面と、掘切に面した尾
根のもっとも高い位置を中心に2~3
段残され、掘切に面した高所は石垣が
方形に巡っており、入口を固める桝形
であったと考えられている。
石垣は、いずれも自然石を粗割にした
石材を横位に置き、目地が通るように
積み上げ、隙間には間詰石が裏面には
栗石が詰められ、石垣は、郭の高低差
や栗石の残存状況から、本来は2.5m
程度の高さであったされる。
いずれにしろ、彦根のこの地区の景観
が欧州風の田園都市空間に似ているよ
うに思えるといっても、景観の将来が
良くも悪くも住民本位にあるというこ
とに違いはないのだろう。
---------------------------------
※「不飲川 流域治水を考える会」
※「湖東土木事務所 組織目標」




















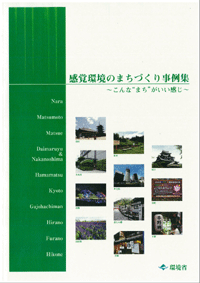






 平田川
平田川 北川
北川
 神明神社
神明神社
 彦根市大藪町 上流
彦根市大藪町 上流 彦根市大藪町 下流望
彦根市大藪町 下流望



