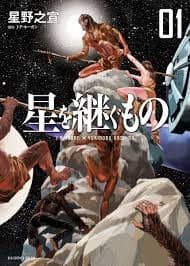はやぶさが地球に帰還した当時、かなり話題になったのですが、映画まで出来てたんですね。
「はやぶさ 遥かなる帰還」(東映 2011年)
Huluにあったので見てみました。
この映画、2時間16分と長尺なので途中でちょっと疲れるのだけど、はやぶさの全行程を知ってから見ると、
感慨深いものがあります。
特に、はやぶさがぼろぼろになりながら、ようやくイトカワの岩石サンプル入りのカプセルを地球に届けた後、本体は燃え尽きてしまうのですが、その直前にコントロールセンターに地球の写真を送ってきます。
地球が半分だけ写った写真を。
ああ、はやぶさは地球に帰りたかったんだろうなあ、と思うともうぼろぼろ泣けてね。
(実際はこの動画にあるように、管制室からはやぶさに指示を出して最後に地球の写真を撮らせた、ということのようですが、はやぶさの意思も感じられます)
はやぶさのプロジェクトを率いる山口という科学者(渡辺謙)を中心に、プロジェクトチームの面々(江口洋介、吉岡秀隆他)が登場しますが、いずれも実在するモデルがいるそうです。
もちろん、はやぶさの打ち上げから地球帰還までの行程も丹念に描かれているので、これを見るとはやぶさ(初号機)がどんな経緯を経て、地球にイトカワの岩石サンプルを届けたかがよくわかります。
最後は満身創痍の状態でやっと地球に帰還したようです。
それから、はやぶさについて取材する朝日新聞の記者(夏川結衣)と彼女の父親が経営している町工場(山崎努)の風景などを交互に挟みながら進む、言ってみればロードムービーのような映画です。
2003年、内之浦宇宙空間観測所からはやぶさが打ち上げられたとき、アメリカのNASAの職員が訪ねてくるシーンがありますが、センター内の椅子はボロボロで、NASAの職員が顔を見合わせます。
「私たちはNASAの十分の一の予算で、今回のプロジェクトを運用しています」とスタッフが言います。
また別のシーンでは、
「ロケットの失敗のたびに予算が削られる」とも言っています。
これはたぶん今もあまり変わらないのではないかと思います。
先日のH3ロケットの打ち上げ失敗で、もしかすると予算が削られるのかもしれない。そうならないことを願うばかりですが。
宇宙にかける想いというのは人類共通で、日本だろうとアメリカだろうと中国だろうと、実際にロケットや衛星などに携わっている人たちの基本的な想い(なぜその職業についたのかという根本的なところ)は、そう変わらない気がするのですが、どうなんだろうか。
はやぶさが帰還してから早13年が過ぎました。はやぶさの宇宙滞在は7年にも及びました(2003年~2010年)。
現在、「はやぶさ」の後継機である「はやぶさ2」が小惑星リュウグウから 5,4gほどの砂粒の回収に成功し、今ふたたび別の小惑星に向かって順調に飛行を続けています。
「ロケット開発に失敗はない」という台詞も出てきます。
「糸川博士は失敗とは言わずに『成果』と言った」
「宇宙兄弟」でムッタが「失敗を知って乗り越えたものなら、それはいいものだ」と言ったように、技術開発というのは失敗の連続で、その積み重ねの上に宇宙へ飛び立つ技術が生まれてくるのですから。
私たちは今この時代ではなく、次の世代、その次の世代を見据えて、長い目で宇宙開発を応援していきたいと思っています。