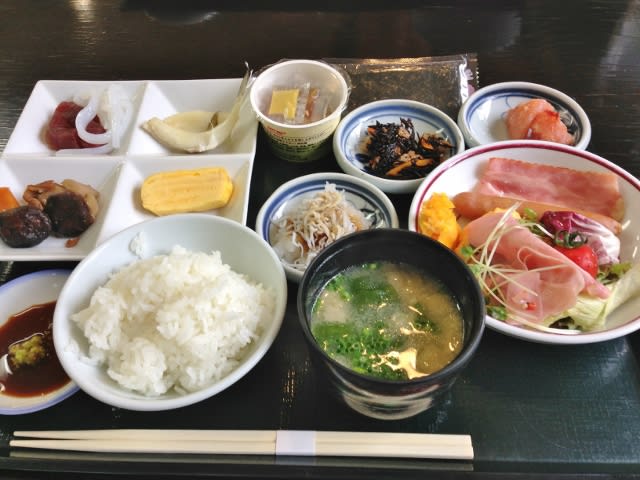秋月城跡の内堀に沿って続く桜並木
江戸時代にはこの辺りに杉の並木があり
この道で武士たちが馬術の稽古などを行っていたことから
『杉の馬場』と呼ばれるようになりました
しかし明治38年の日露戦争戦勝記念として植えられた桜が
現在の見事な桜並木へと変化していったそうです
道沿いには多くの土産店や茶屋が並び
観光客で賑わいをみせています
秋月城跡前の『杉の馬場』

映画でのワンシーン

光枝が寅さんを近くまで見送るシーンです
瓦坂

瓦を縦に並べて土砂の流失を防ぐ工法で造られています
当時、この瓦坂の奥に秋月城の大手門がありました
映画でのワンシーン

映画の時には瓦坂のすぐ上に秋月中学校の
木造校舎が建っていました
映画の中では常三郎もこの中学の出身だったそうです
この木造校舎はすでに取り壊されてますが
杉の馬場からは見えない少し奥の方に
新しい木造校舎が建てられていました
現在の秋月中学校

秋月城の始まりは鎌倉時代の1200年台
原田種雄(たねかつ) が筑紫郡原田郷からこの地に移り
秋月姓を名乗って標高860mの古処山山頂に城を建てました
居住地をその山麓に建て、その1つが現在の秋月城の前身と
言われています
その後400年続いた秋月氏ですが、
豊臣秀吉の九州征伐に敗れ秋月城の前身も廃城となります
その後時代は江戸時代へと移り
1623年(元和9年)筑前福岡藩の第2代藩主
黒田忠之(くろだ ただゆき)が、弟の長興(ながおき) に
秋月周辺の5万石を与え秋月藩という支藩が誕生しました
そして廃城となっていた秋月城を大幅に改修し
陣屋を置きました
秋月中学の校庭がある場所でかつて藩の政治が
行われていたとのことです
その後明治時代の廃城令によって廃城となるまで
黒田氏が12代に渡ってこの地を治めました
時代は昭和に移り陣屋跡に秋月中学校の校舎が建てられました
また1980年(昭和55年)「秋月城跡」として県の史跡に指定されています
秋月郷土館

旧藩士(戸波家)の邸宅と藩校(稽古館)跡を利用した
美術館と歴史資料館です
映画でのワンシーン

秋月郷土館の門から見た杉の馬場

映画でのワンシーン

寅さんと光枝はここを通って行きました
光枝は寅さんをこの先まで送り
別れ際に夫の恒三郎があとひと月ももたないと
医者から言われていることを寅さんに伝えます
寅さんが亭主に会いに来てくれた最後の友達だろうと
言い残し、光枝は泣きながら去っていきました

寅さんはこの後常三郎と冗談で交わした
約束のことを考えます
旅館に戻り愛子と最後の酒を交わし
翌朝置手紙をして愛子を残して旅館を立ち去りました
このあと寅さんは柴又に戻り
常三郎との約束を真剣に考えるようになるのです
この続きはDVDでご覧ください
愛子との再会、光枝との再会
そして常三郎との約束は・・・
見どころ満載です
以上にて男はつらいよロケ地巡り
大分・福岡編は終了です