 ここ数日、気になっているものがあった。
ここ数日、気になっているものがあった。お店の窓際に、こうして置かれているフシギな木...


お正月の飾りかなぁ...と思ったりしたが、それだけがぽつねんと置いてあるところがほとんど。何だろ、これ...
...と、思っていたら、昨日夫の実家から荷物が届いた。鹿児島からだ。
果物などの他に、紅白のお餅によもぎ餅にあんころ餅、お餅だけでも色とりどり。そして、手紙が添えてあった。
 1月15日の小正月について、長女に解説してあるものだ。
1月15日の小正月について、長女に解説してあるものだ。『小さく切った、赤や白の「もち」を「小えだ」につきさし、家のかべや、おはかなどにかざりつけます。「メのモチ」とよんでいます。お米などの のうさくもつが 秋には一ぱいみのるように、そして みんなが この一年元気すごせるように 神さまに おねがいする 行事です。』
あー!これだ。これに違いない。なーるほどー!「メのモチ」っていうのだ。でも、鹿児島にいる時には気づかなかったし、教えてもらったこともない。今より観察眼がなかったのかなぁ。
すると、今日。
 「ぶぶの木」とはまた聞いたこともない名前。しかも「なりもち」だ。奄美では「なりもち」と言うらしい。
「ぶぶの木」とはまた聞いたこともない名前。しかも「なりもち」だ。奄美では「なりもち」と言うらしい。それで、家に戻って色々検索してみた。
まどろっこしい展開で申し訳なかったけれど、あまみ便りblogさんにバッチリ説明されていた。
→こちら!
そして、今朝は南日本新聞に鹿児島のメノモチについての記事も載っていた。→こちら
...と、いうわけでこれは鹿児島ではメノモチ、奄美ではナリモチという同じ意味合いの行事だったのだ。はースッキリ!
ぶぶの木は、リュウキュウエノキというんだそうで。(なぜぶぶの木なんだろう?)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
さて、「ぶぶの木」を見たあと、この「ナリモチ」を売っている

店も発見したので覗いてみた。お店の中では、ちょうど女性二人がナリモチ製作の真っ最中。ここは引っ込み思案の私も、写真撮影の許可をいただくと共に、勇気を出して突撃インタビュー!
この時点では、まだネット検索していなかったので、根堀葉堀...「鹿児島の人?」と言われたので、「いえ、元々関東で」と言ったら「それじゃぁ知らないでしょうねぇ。」と大変親切に教えて下さった。

まず、どうやってお餅を枝につけるのか。これは、まだ柔らかいお餅ゆえ、はさみで切ってお餅の粘りでぺたぺたと直接貼り付けるのみ。到って簡単!
でも気になったのは、その後のお餅。これ、この後どうするのですか?
「18日にお芋と混ぜて食べるのよ。ヒキアゲって言うの。」え?ヒキャゲ?ですか?ヒキアゲ?ヒッキャゲ?
※これについては、奄美便りblogさんが記事内でリンクされているが、『幕末奄美遠島生活』というブログに詳しく書かれている。(→こちら)
こちらのブログは、幕末に奄美に島流しになり、「南島雑話」という本を記した名越左源太という人の日記「大島遠島録」を現代訳してある、とっても面白くてためになるブログだ。(しかし、私は最初から読んでいたので、まだ昨年11月の記事まで追いついていなかったー^^;)
お芋と混ぜて食べる、というのがよくわからなかったので聞いてみると、サツマイモとこのナリモチのお餅を混ぜて(餅米を入れると一層おいしい、とも教えて下さった。)ふかし、それをお餅のようについて食べるとのこと。「今はほとんどそうする人もいなくなりましたけどね。」とも。「えーとね、鹿児島も同じようにして食べるはずなんだけど、ヒキアゲとは言わないで何か別の言い方をするのよねぇ。」(今度義母に聞いてみようっと!)
→(追記)「ねったぼ」でした。そうそう、聞いたことありました。
「昔はおかきにして食べたりもしましたよ。」それは簡単そう!
いずれにせよ、木に直接つけて汚くなってどうするんだろうなどと思っていたのだが...考えてみたら付ける前に木をササっときれいにして、後は食べる時に熱を加えてしまえばお腹は痛くならないわけだ。この話を聞いて密かに昨今の過度の清潔志向を反省してみたりもした。4日ぐらいなら、ホコリもそんなにはつかないだろうし。でもやはり気にする人もいて、「今はそうする人もほとんどいなくなった」のかな。
さて、そこまで聞いたらやらないわけにはいかない。

日頃「食べ物で遊んではいけません。」と言われている娘達にとって、こんな楽しいことがあるだろうか。お餅をぺたぺたと、粘土みたいにしてくっつけていいのだ。

完成!
ちょっと木の根元が無粋かもしれないけれど...
どうか今年一年、良い年でありますよう!
白
s
s
s
s
さて、あまみ便りblogさんでも、全国の似たような風習を紹介してありますが、このブログを読んで下さる全国の皆様、皆様の地域にも、似たような風習はありますか?ぜひ教えて下さいね!
【追記2008年1月14日】→2008年のナリムチはこちら










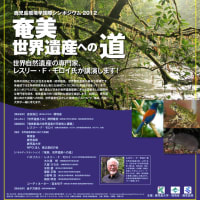










今度はできるかな?と心配しつつ今、書いてます。
飛騨高山で、こんな木見たことあります。
お餅をくっつけるやつ。
瀬戸内町では、見たことないなあ。。。
呼び方は忘れましたが、小正月にやはり豊作祈願したものと、記憶しています。
ただし、飾り方は、部屋の中で鴨居に木を差していたと思います。(庭が無かったせいかも知れません)
やはり、紅白のおもちでしたが、おもちは丸めていたと思います。 南の方からの伝わったのかも??
>勉強になりました。
いえいえ、私はみなさんの情報をぺたぺた貼っただけなので...私も大変勉強になりました。
奄美の人は、こういう行事をまだまだ守っていらっしゃる方が多く良いですね。廃れてほしくないなと思います。てふてふさんの生徒さんはきっと受け継いでくれますね!
鹿児島のメノモチは、奄美のナリモチほど見かけなかった気がします。
★takaさん★
よかった~こちらの記事には入れたのですね。ひさ倉さんの記事はどうしてだったのか...申し訳ありません。
瀬戸内ではあまりないのですね。TBいただいた「何でもあり」さんの情報からして、やっぱりあるとしても北大島から流れたものくらいなんでしょうか。
でも、全国的には似たようなことがいっぱいありそうで、飛騨のもそのひとつなんでしょうか。おもしろいですね!
★ヨットマンさん★
北海道と岩手のご両親がされていたとは!!
これまた面白い情報をありがとうございます。
リンクしている「あまみ便りblog」さんの記事によれば、新潟には「繭玉」とか「舞玉」といって、あるようなので、北にもあるのかもしれませんよ。
鴨居(神棚前ですが)にかけてある写真も載っていました。
(→こちら)
取材場所は菱刈町。五穀豊穣と千客万来を祈願する恒例の催し,とありました。使う木はエノキ。写真では餅に袋がかぶせてあったので,fortuneさんのかかれたとおり,後で食べるのかもしれませんね。
名瀬のお店のショーウィンドウが賑やかでいいですね。古仁屋はお店自体が少ないワ。
FORTUNE家のナリモチが一番存在感があっていいですよ! オオガネモチになれるかも♪
ブログ本文には南日本新聞の方をリンクしましたが同じですね。木も奄美と同じ(奄美はリュキュウエノキ)エノキなんですね。何かいわれがあるのかしら。
両紙とも菱刈町の話題ですが、今は他の地域ではあまりやらないのでしょうか。私は以前住んでいた時には存在そのものも知りませんでした。
菱刈町でもやはり食べるのでは?捨ててしまってはかえってバチがあたりそうですもん。私も最初はラップに包んでセロテープで貼ろうかと思ってましたw
★何でもありさん★
『お米などの のうさくもつが 秋には一ぱいみのるように、そして みんなが この一年元気すごせるように 神さまに おねがいする 行事です』とちゃんとおじいちゃんが教えてくれているのに、母はなんて欲深なんでしょう...
大きいつづらと小さいつづらがあったら、小さいほうを選ぶようにしまーす ^^(って、コレも下心があってはダメですね)