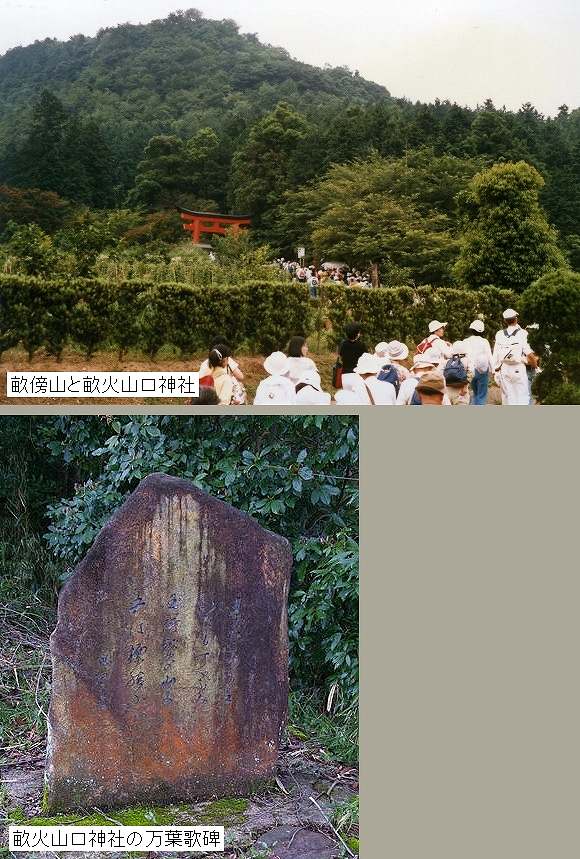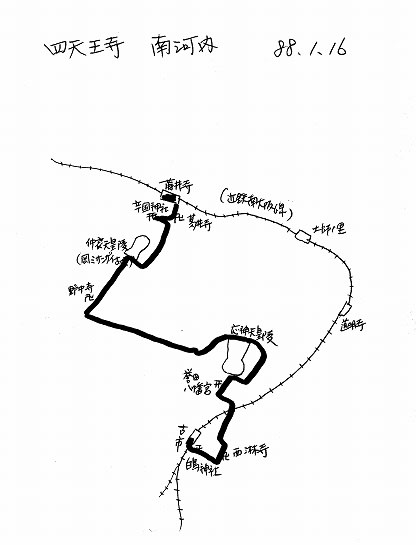JR大和路線の天王寺駅から2つ目の「平野駅」で下車、杭全(くまた)神社と大聖勝軍寺を訪ねる。

平野駅

杭全(くまた)神社 入り口
大阪市平野区平野宮町にある神社。
「杭全」と書いて、関西人ならこれを「くまた」と読めるだろうが、関東人には難解な地名である。語源は、このあたりが渡来してきた百済(くだら)人たちが住んでいた地域で、「くだら」が訛って発音され「くまた」という地名が定着したという説がある。だが、杭全という表記にされた理由がわからない。

杭全(くまた)神社の大樟
大門の横に聳える大阪府の天然記念物の大樟。
幹周7.85m、樹高19.5m

杭全(くまた)神社 拝殿
貞観4年(862年)、征夷大将軍・坂上田村麻呂の孫で、この地に荘園を有していた坂上当道が素盞嗚尊を勧請し、社殿を創建したのが最初と伝えられている。

杭全(くまた)神社 本殿

大聖勝軍寺 山門
大聖勝軍寺は、八尾市立病院近くの国道25号線に面した市街地の真ん中にある。
かってこの地は渋川の阿刀と呼ばれた。我が国の仏教創生期に、仏教の導入に反対したと伝えられる物部守屋の別宅が、ここにあった。587年(用明2)4月、瀕死の病床で仏教に帰依することを用明天皇が群臣たちに諮問したことから、廃仏派の物部守屋は身の危険を感じてこの地に退いた。用明天皇の殯が明けるのを待って、崇仏派の蘇我馬子は諸王子と群臣とに勧めて、守屋を滅ぼそうと謀った。そして7月下旬の暑い盛りに、蘇我馬子に賛同した崇仏軍は、渋川の阿刀で守備を固める守屋を攻めた。その攻防戦の主戦場となったのがこの地である。


大聖勝軍寺 守屋池
大聖勝軍寺の境内には、物部守屋の首を洗ったという守屋池や馬蹄石がある。

大聖勝軍寺 仏殿

大聖勝軍寺 当山の山号の由来の「神妙椋樹」
聖徳太子の軍勢は守屋の軍勢の前に3度敗退、大軍に包囲され絶体絶命の窮地に陥った時、椋の大木が真っ二つに割れ、太子はその幹の空洞に身を潜め、九死に一生得たという。

大聖勝軍寺の太子堂
太子町の叡福寺が「上の太子」と呼ばれるのに対して、「下の太子」の名で親しまれている。
聖徳太子が、渋川の阿刀の館にいた物部守屋を滅ぼすにあたり、信貴山の毘沙門天に祈願して四天王をまつり、その加護により守屋を討って戦勝を得ることが出来たので、ここに一寺を建てて勝軍寺と称したという。

平野駅

杭全(くまた)神社 入り口
大阪市平野区平野宮町にある神社。
「杭全」と書いて、関西人ならこれを「くまた」と読めるだろうが、関東人には難解な地名である。語源は、このあたりが渡来してきた百済(くだら)人たちが住んでいた地域で、「くだら」が訛って発音され「くまた」という地名が定着したという説がある。だが、杭全という表記にされた理由がわからない。

杭全(くまた)神社の大樟
大門の横に聳える大阪府の天然記念物の大樟。
幹周7.85m、樹高19.5m

杭全(くまた)神社 拝殿
貞観4年(862年)、征夷大将軍・坂上田村麻呂の孫で、この地に荘園を有していた坂上当道が素盞嗚尊を勧請し、社殿を創建したのが最初と伝えられている。

杭全(くまた)神社 本殿

大聖勝軍寺 山門
大聖勝軍寺は、八尾市立病院近くの国道25号線に面した市街地の真ん中にある。
かってこの地は渋川の阿刀と呼ばれた。我が国の仏教創生期に、仏教の導入に反対したと伝えられる物部守屋の別宅が、ここにあった。587年(用明2)4月、瀕死の病床で仏教に帰依することを用明天皇が群臣たちに諮問したことから、廃仏派の物部守屋は身の危険を感じてこの地に退いた。用明天皇の殯が明けるのを待って、崇仏派の蘇我馬子は諸王子と群臣とに勧めて、守屋を滅ぼそうと謀った。そして7月下旬の暑い盛りに、蘇我馬子に賛同した崇仏軍は、渋川の阿刀で守備を固める守屋を攻めた。その攻防戦の主戦場となったのがこの地である。


大聖勝軍寺 守屋池
大聖勝軍寺の境内には、物部守屋の首を洗ったという守屋池や馬蹄石がある。

大聖勝軍寺 仏殿

大聖勝軍寺 当山の山号の由来の「神妙椋樹」
聖徳太子の軍勢は守屋の軍勢の前に3度敗退、大軍に包囲され絶体絶命の窮地に陥った時、椋の大木が真っ二つに割れ、太子はその幹の空洞に身を潜め、九死に一生得たという。

大聖勝軍寺の太子堂
太子町の叡福寺が「上の太子」と呼ばれるのに対して、「下の太子」の名で親しまれている。
聖徳太子が、渋川の阿刀の館にいた物部守屋を滅ぼすにあたり、信貴山の毘沙門天に祈願して四天王をまつり、その加護により守屋を討って戦勝を得ることが出来たので、ここに一寺を建てて勝軍寺と称したという。