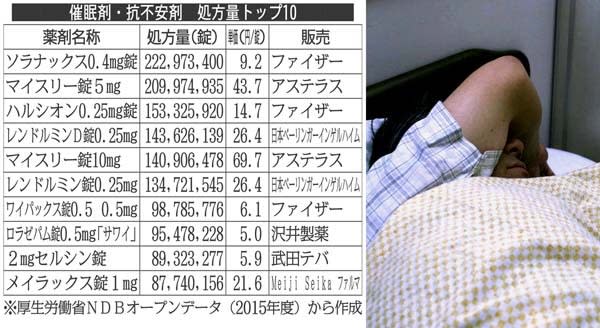「中小企業2000万人」の雇用が超危ない
プレジデントオンライン2017.12.13
中小企業を経営する60歳以上のうち66.1%は「後継者不在」だという。日本全体の事業所の数をかけあわせると、約2000万人の雇用が潜在的な危機にあるといえる。どうすれば危機を防げるのか。ひとつは経営者に「廃業」ではなく「事業譲渡」を決断してもらうことだ。中小企業の「事業承継M&A」に取り組むFUNDBOOKの畑野幸治社長が、現状に警鐘を鳴らす――。
「事業を承継できる人材がいない」
この数年、中小企業で親族や従業員以外の「第三者への承継」が増えています。「中小企業白書2017年版」によれば、5年以内に承継した中小企業の内、第三者への承継は、39.3%。20年前は5.5%、10年前は10.9%だったので、着実に増えています。
親族や従業員のなかに「事業を承継できる人材がいない」という問題がある一方で、見逃されている事実があります。大企業のM&Aとは異なり、中小企業のM&Aは、従業員の雇用がそのまま維持されるなど、友好的なM&Aになりやすいという点です。
中小企業は株式を非公開としているケースがほとんどです。上場している大企業では、M&AでTOB(公開買い付け)のような「敵対的買収」が行われるケースがあります。大株主になってしまえば、従業員の意向を無視して、リストラや資産売却を進めることができます。
しかし非公開企業であれば、いくら買収を希望しても、譲渡企業の株主が納得しなければ、M&Aは成立しません。「従業員の雇用を維持してくれ」と約束を取り交わすこともできます。
これまでは、後継者がみつからないという理由で、「廃業」という選択肢を選ぶ経営者が少なくありませんでした。しかし廃業は従業員や顧客、仕入先などに影響を与えます。結果的には日本経済全体に悪影響を及ぼすとも考えられるはずです。
このため私はFUNDBOOKという企業で、中小企業を対象にした「事業承継M&A」の事業に取り組んでいます。多くの中小企業は、事業承継の問題に早期に取り組む必要に迫られています。いまどんな状況にあるのか。大きな課題は以下の3点です。
日本の中小企業が抱える3つの課題
1点目は、急速な少子高齢化に伴う日本市場の縮小です。日本では現在、少子高齢化が進んでいます。このままでは2050年までに人口は3分の1の9708万人になると予測されています。つまり、現在の市場が3分の2になるのです。
2点目は、後継者問題の深刻化です。日本の起業率は5%程度にとどまっており、経営者の平均年齢が上がりつづけています。1998年には56歳だったボリュームゾーンは2016年に66歳となっています。一方で、帝国データバンクの調査によると60歳以上の経営者のうち66.1%が「後継者不在」と回答しています。現在70歳前後の「団塊の世代」が、これから次々と引退していきます。そのとき廃業を余儀なくされる中小企業が続出する恐れがあります。
3点目は、グローバル化に伴う競争の激化です。日本市場の縮小を予想し、大企業は数十年前から着実かつ積極的に海外市場を開拓してきました。たとえばキッコーマンはしょうゆを海外で売るために、1974年に米国で工場をつくっています。一方、中小企業の海外進出は思うように進んでいません。
今後の企業経営はこれまで以上に複雑性が高く、資金的な体力が必要になってくると考えられます。ところが日本の99.7%を占める中小企業の大半は、その準備ができていません。規模が大きく、成長意欲のある第三者に事業承継を行うことは、日本経済にとって重要な課題だと考えています。
企業の大量廃業で損をするのは誰か
もし中小企業が大量廃業に追い込まれれば、最も深刻な影響を被るのは地域経済です。『中小企業白書2016年版』によれば、日本の中小企業の企業数は380万社。それに前述の後継者不在率の66.1%をかけると、約250万社の企業が後継者不在と推計できます。中小企業の平均従業員数は8.8人となるので、これから30年の間に、潜在的には2210万人の雇用が危機にあるといえます。これは日本の労働人口の半分に達する数値です。
「ハッピーリタイア」をむかえる方法
では第三者への事業承継とはどのように行われるのか。2つの事例を紹介させてください。最初の事例は、調剤薬局のワタナベドラッグ(仮称)です。開業は1994年。夜間営業など地域密着型経営で業績を拡大し、直近の店舗数は3店舗になっていました。ところが2016年の薬価改定で売上が減少。自身の両親介護の不安もあり、事業承継を考えるようになりました。
しかし息子は大手商社の社内弁護士で、退職は考えられません。そこで事業譲渡を検討し、最終的には大手薬局チェーンに譲渡しました。ワタナベドラッグのオーナーは「独自で進めていたらいつまでたっても事業承継が進まず、最終的には廃業していたのではないか」と振り返ります。
2つ目の事例は、廃業からM&Aに切替えたタナカ物流(仮称)です。35年前に田中社長が創業したタナカ物流は、トラック30台と自社倉庫を保有する年商5億円の中小物流会社です。安定した業績を残してきましたが、田中社長も65歳となり、気力や体力の面で徐々に衰えを感じ始めていました。一人息子がいましたが、東京の大企業に就職しており、後を継ぐ気がありません。役員や幹部社員に後を託すという事業承継の道も模索しましたが、銀行に1億5000万円の借入金があり、その全額を田中社長が個人で連帯保証していました。また、自宅も借入金の担保にしており、こうした負債を役員や幹部社員が肩代わりするのはほとんど不可能です。
田中社長は最終的に吉田物流(仮称)にタナカ物流の株式を100%譲渡することを決めました。吉田物流の売上高は約10億円。経営者はまだ40代で、田中社長は息子に会社を託すような思いで譲渡を決めました。その後、役員や従業員はいっさい変わらず、待遇も維持されました。グループ力が強化されたため、今まで以上に仕事が増え、業績も右肩上がり。田中社長は、経営から身を引き、株式譲渡代として2億円あまりを手にして、「ハッピーリタイア」を迎えることができました。
選択肢は、親族内承継、上場、廃業、M&Aの4つ
中小企業の廃業は深刻な社会問題です。M&Aは廃業を防ぐ有効な手立てですが、その後、グループ企業として結果が出なければ、譲る側、譲り受ける側のお互いが損をすることになります。トラブルを避けるためには、知識や経験をもったM&Aアドバイザーが必要です。
FUNDBOOKはM&Aアドバイザリーの専門会社ですが、ほかにも地域の会計事務所や銀行・信用金庫などがM&Aを仲介するケースもあります。
事業承継におけるオーナー社長がとれる選択肢は、親族内承継、上場、廃業、M&A(親族外承継)の4つしかありません。廃業してしまうと、お客様や従業員をはじめ仕入先など、関係者に迷惑をかけ、長年培ってきた技術やノウハウもすべて失われてしまいます。日本経済にとってもマイナスです。前もって事業承継に備え、ぜひ廃業することだけは避けてください。
畑野 幸治(はたの・こうじ) FUNDBOOK 代表取締役CEO
1983年生まれ。大学在学中に株式会社Micro Solutionsを創業し、2016年11月より株式会社BuySell Technologiesの代表取締役に就任。翌年に同社の全株式を譲渡、2017年9月に株式会社FUNDBOOKの代表取締役に就任。M&Aプラットフォーム事業を展開している。