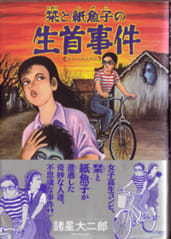「異界への旅4」にこの作品が載っている。
この本は呉智英が<水木しげる作品集>として作品を選んだもの。
時は戦国時代。
孤児になった子どもたちが、
自分たちの幸福は自分たちで作らなければならないと考えて自ら「こどもの国」を作り生活を始める。
しかし、自分のことしか考えない大統領<ニキビ>
平民の<三太>はクーデターを起こし政権をとる。
その後、こしまきデザイナー<カルダン>(この役はねずみ男)が「くさった政治」を提案し、
再び<ニキビ>が大統領に返り咲く・・・。
ところが、・・・
「子供の国」っていうタイトルだが、これは勿論現実の大人の国を風刺した作品。
「子供の・・・」と、したのは、そもそも大人たちがやってることって子供のケンカと同じレベルだっていう意味もあるのかもしれない。
これをガロに掲載した頃、ちょうど白土三平の「カムイ伝」もガロに連載されていたようだ。
「異界への旅」の2巻で呉智英氏との巻末対談が載っている。
呉:でも、その怒りが水木さんは風刺の方に向かいましたが、白土三平さんのように直截的に表現する人もいます。
水木:農民一揆とかね。
あれも怒りです。
しかし、水木先生はね、集団ということがキライなんだな。
集団はツマラン。
ひとりでやろう、ひとりで自由にやれることが好き。
(中略)
呉:そのあたりが白土三平さんとのちがいですかね。
水木:「みんなで」というのが自分の性に合わんのです
「みんなに共通」のものを作らなきゃならんっていうのが、どうもねぇ。
「カムイ伝」と「子供の国」を読み比べるのも面白そうだ。
水木さんの、飄々としたとぼけた味わいのある風刺漫画、
呉智英氏の言葉を借りれば
「明るいニヒリズム」
は水木さんの生き方そのものなのかもしれない。
この本は呉智英が<水木しげる作品集>として作品を選んだもの。
時は戦国時代。
孤児になった子どもたちが、
自分たちの幸福は自分たちで作らなければならないと考えて自ら「こどもの国」を作り生活を始める。
しかし、自分のことしか考えない大統領<ニキビ>
平民の<三太>はクーデターを起こし政権をとる。
その後、こしまきデザイナー<カルダン>(この役はねずみ男)が「くさった政治」を提案し、
再び<ニキビ>が大統領に返り咲く・・・。
ところが、・・・
「子供の国」っていうタイトルだが、これは勿論現実の大人の国を風刺した作品。
「子供の・・・」と、したのは、そもそも大人たちがやってることって子供のケンカと同じレベルだっていう意味もあるのかもしれない。
これをガロに掲載した頃、ちょうど白土三平の「カムイ伝」もガロに連載されていたようだ。
「異界への旅」の2巻で呉智英氏との巻末対談が載っている。
呉:でも、その怒りが水木さんは風刺の方に向かいましたが、白土三平さんのように直截的に表現する人もいます。
水木:農民一揆とかね。
あれも怒りです。
しかし、水木先生はね、集団ということがキライなんだな。
集団はツマラン。
ひとりでやろう、ひとりで自由にやれることが好き。
(中略)
呉:そのあたりが白土三平さんとのちがいですかね。
水木:「みんなで」というのが自分の性に合わんのです
「みんなに共通」のものを作らなきゃならんっていうのが、どうもねぇ。
「カムイ伝」と「子供の国」を読み比べるのも面白そうだ。
水木さんの、飄々としたとぼけた味わいのある風刺漫画、
呉智英氏の言葉を借りれば
「明るいニヒリズム」
は水木さんの生き方そのものなのかもしれない。