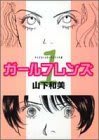(2008年1月31日発行)
アタゴオルの世界に入って生活してみたい。
そういう風に思った読者はきっと多いはず。
葉っぱの傘をさしたり、火山草の車に乗って空を飛んだり、巨大葉っぱの上で昼寝したり、腰掛けて魚を釣ったり・・・。
こんな世界で個性的な仲間と毎日不思議な体験が出来たらステキだろうなあって思う。
この作品は設定が独創的ですばらしいのだが、キャラももちろん非常に個性的。
特にヒデヨシのめちゃくちゃな性格には脱帽するしかない。
フト思ったんだけど、ヒデヨシと「ゲゲゲの鬼太郎」に出て来るねずみ男ってちょっと似てるよね。
自分の欲望に忠実で、周りの人が困っても全く気にしない。
ただ・・・ねずみ男は大人のずるさって言うものがあるけれど、
ヒデヨシは子供のままの天真爛漫さがあるってことかな?
えっ?それって大きな違いだろって?
あ、そうかもしれない。(笑)
この巻に収録されている「モワモワ」で、
ヒデヨシの身体に世界中の悲しみが流れ込む。
なんでもかんでも悲しくなって涙が出て来るヒデヨシ。
ヒデヨシに悲しみなんて似合わない、どうなるんだろうと思ってたら、
やっぱりヒデヨシだ。
「オレはよォ
悲しみなんかと
遊んでるヒマ ありませーん」
そうなんだ。そうやって悲しみなんかぶっとばしてしまえばいいのだ。
作者は後書きでこう書いている。
「さあ、みなさん、ご一緒にご唱和を。
せーのっ。
『悲しみなんか、ぶちのめすのよおおお』。」
悲しくなった時はこの言葉をつぶやいてみよう。
そう思った私です。
アタゴオルの世界に入って生活してみたい。
そういう風に思った読者はきっと多いはず。
葉っぱの傘をさしたり、火山草の車に乗って空を飛んだり、巨大葉っぱの上で昼寝したり、腰掛けて魚を釣ったり・・・。
こんな世界で個性的な仲間と毎日不思議な体験が出来たらステキだろうなあって思う。
この作品は設定が独創的ですばらしいのだが、キャラももちろん非常に個性的。
特にヒデヨシのめちゃくちゃな性格には脱帽するしかない。
フト思ったんだけど、ヒデヨシと「ゲゲゲの鬼太郎」に出て来るねずみ男ってちょっと似てるよね。
自分の欲望に忠実で、周りの人が困っても全く気にしない。
ただ・・・ねずみ男は大人のずるさって言うものがあるけれど、
ヒデヨシは子供のままの天真爛漫さがあるってことかな?
えっ?それって大きな違いだろって?
あ、そうかもしれない。(笑)
この巻に収録されている「モワモワ」で、
ヒデヨシの身体に世界中の悲しみが流れ込む。
なんでもかんでも悲しくなって涙が出て来るヒデヨシ。
ヒデヨシに悲しみなんて似合わない、どうなるんだろうと思ってたら、
やっぱりヒデヨシだ。
「オレはよォ
悲しみなんかと
遊んでるヒマ ありませーん」
そうなんだ。そうやって悲しみなんかぶっとばしてしまえばいいのだ。
作者は後書きでこう書いている。
「さあ、みなさん、ご一緒にご唱和を。
せーのっ。
『悲しみなんか、ぶちのめすのよおおお』。」
悲しくなった時はこの言葉をつぶやいてみよう。
そう思った私です。