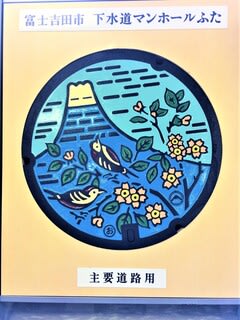※2021.05.22更新 公共下水道関係の蓋8枚、上水道関係の蓋3枚を追加しました。
旧本庄市の沿革は、明治22年4月1日に町村制施行により本庄宿が「児玉郡本庄町」となりました。その後、昭和29年7月1日、本庄町と周辺の藤田村、仁手村、旭村、北泉村が新設合併し、旧本庄市が誕生しました。
その後、平成18年1月10日旧児玉郡児玉町との合併により、旧本庄市は消滅しました。
市章は、本庄市の頭文字となる「ホ」を三方より円形に図案化したものです。(昭和30年11月21日制定)
市の花は「ツキミソウ」、市の木は「モクセイ」です。
前置きはこれ位にして、マンホール蓋の整理に移ります。
旧本庄市にもデザインマンホール蓋(「ムサシトミヨ」をデザイン)が存在しましたが、新たに誕生した本庄市でも引き続き設置されているので、本庄市の蓋として整理しました。
そこで、こちらでは旧本庄市の市章が入っている蓋を整理する事にします。
最初は、公共下水道関係の蓋です。
こちらは、JIS規格模様の用途記載がない蓋です。
こちらは、枠付きです。
こちらは雨水蓋です。
 (2021.05.22追加)
(2021.05.22追加)
こちらは汚水蓋です。
 (2021.05.22追加)
(2021.05.22追加)
次は、毘沙門亀甲模様の蓋です。
こちらの蓋には用途記載がありません。
こちらの蓋には用途記載があります。
左は雨水蓋、右は汚水蓋です。
 (2021.05.22追加)
(2021.05.22追加)
こちらは、菱形模様の蓋です。
左は雨水蓋、右は汚水蓋です。
 (2021.05.22追加)
(2021.05.22追加)
こちらは、幾何学模様の蓋です。
こちらの蓋には用途記載がありません。 (2021.05.22追加)
(2021.05.22追加)
こちらは、スリップ防止模様の汚水蓋です。
右は小型蓋です。いずれも、中央に市章、市章の下部に「お」の文字があります。

こちらも、スリップ防止模様でしょうか?
こちらは、グレーチング(格子)型の蓋です。 (2021.05.22追加)
(2021.05.22追加)
以下は、小型マンホール蓋です。
こちらは、あみだ模様の汚水蓋です。
こちらは、コンクリート製の汚水蓋です。
こちらは、雨水枡や雨水集積枡の蓋です。
 (2021.05.22追加)
(2021.05.22追加)
以下は、上水道関係の蓋になります。
最初は消防関係で消火栓の蓋です。
こちらは角蓋です。




こちらは丸蓋です。
こちらは、防火貯水槽の蓋です。 (2021.05.22追加)
(2021.05.22追加)
次は、制水弁の蓋です。



こちらは、空気弁の蓋です。 (2021.05.22追加)
(2021.05.22追加)
こちらは、減圧弁室の蓋です。 (2021.05.22追加)
(2021.05.22追加)
以上で、旧本庄市の蓋の整理は終了です。
次回、その4.では旧大里郡児玉町の蓋の整理をします。