※2025.07.14更新 市の木「イチョウ」の葉をデザインした親子蓋2枚、小型蓋1枚を追加しました。
※2025.06.05更新 新しいデザイン蓋1枚、市の木「イチョウ」の葉をデザインした小型蓋2枚、スリップ防止型の蓋1枚、インターロッキング型の蓋1枚、防火水槽の蓋1枚、電線共同溝の蓋3枚を追加しました。
浦安市の経緯は、明治22年4月、町村制の施行にともない、堀江、猫実、当代島の3村が合併して「浦安村」となり、明治42年9月に「浦安町」となりました。
昭和39年から海面埋め立て事業が行われ、急速に都市化が進んた結果、昭和56年4月に待望の市制施行し「浦安市」が誕生し、現在に至っています。
浦安市は、東京湾の奥部に位置し、東と南は東京湾に面し、西は旧江戸川を隔てて東京都江戸川区と対峙し、北は市川市と接しています。市域は、東西6.06キロメートル、南北6.23キロメートルで、その面積は16.98平方キロメートルとなっています。
土地は、旧江戸川の河口に発達した沖積層に属する低地と、その約3倍に及ぶ公有水面埋め立て事業によって造成された埋め立てからなっており、おおむね平坦でです。令和3年6月1日現在で人口は49.2万人超、世帯数は23.4万超となっています。
市章は、URAYASUの「U」を身近な海、東京湾のイメージでかたどり、それに、今まさに昇ろうとする「太陽」を組み合わせて図案化したものです。左右に配置された3本の線の変化が、「心の和の広がり」「緑あふれる大地の広がり」「輝く未来への広がり」を表しており、豊かな海と緑に囲まれて、人の心を大切にしながら、未来へ向かって発展する浦安市の姿と願いが込められています。(平成3年4月1日制定)
市の花は「ツツジ」、市の木は「イチョウ」です。(以上は、浦安市HPより)
前置きはここまでとし、次は公共下水道に係わる情報です。
浦安市の公共下水道は、雨水と汚水を別々に処理する分流方式を採用しています。汚水は、千葉県の江戸川左岸流域下水道に接続し、市川市にある「江戸川第一・第二終末処理場」で最終処理され旧江戸川に放流されます。
最初はマンホールカードの紹介です。
こちらは、令和2年4月25日に第12弾として配布開始となったマンホールカードです。

カード裏面のデザインの由来は以下の通りです。
かつて漁師まちとして栄え、今でも昔ながらの面影が残る元町地域を流れる「境川」と旧江戸川へと繋がる「境川西水門」が桜並木とともに眺められる風景と、都心近郊型の居住地として開発され、爽やかな海風の香るアーバンリゾート風の街並みが演出された新町地域の風景を対照的に配置し、1枚にあしらったデザインマンホール鉄蓋となっています。 埋め立て事業により市の面積を徐々に拡大させ発展し続けた浦安市は、同じ市内であってもその地域ごとに特徴豊かな風景や魅力に溢れており、このデザインはそのような多くの彩を持つ浦安市を表現したものになっています。
それでは、マンホール蓋の整理です。
最初は、2025年3月に浦安公園内の図書館に続く歩道に設置されたデザイン雨水蓋です。
中央に市章、蓋面を三分割し左上は市の花火大会、右上は舞浜駅、下は旧江戸川と旧江戸川に架かる架かる江戸川第一橋梁と浦安市郷土資料館のマスコットキャラクター「あっさり君」が描かれています。
「あっさり君」は、べか舟、ねじりはちまきと、漁師町だった浦安の伝統的なスタイルに、名産のあさりを組み合わせた浦安らしさを感じることができるかわいらしいキャラクターです。(浦安市郷土資料館HPより)
 (2025.06.05追加)
(2025.06.05追加)
こちらは、マンホールカードに描かれたデザイン蓋です。
カードに示された雨水蓋は、浦安市役所敷地内の浦安市文化会館側に設置されているようです。
こちらは、東京メトロ東西線・浦安駅南口付近に設置されている雨水蓋です。

こちらは、JR京葉線・新浦安駅近くの浦安音楽ホールの入るビルと駅の間を通る道路に設置されている汚水蓋です。

もう一種類、以下のデザインマンホール蓋を見つけました。
中央に市章、その周りを市の木「イチョウ」の葉をたくさん散りばめられた蓋です。
こちらは雨水蓋です。


こちらは親子蓋です。 (2025.07.14追加)
(2025.07.14追加)
こちらは汚水蓋です。



こちらは親子蓋です。 (2025.07.14追加)
(2025.07.14追加)
こちらは、上記デザインの小型マンホール蓋や枡蓋です。
こちらは雨水蓋です。
こちらは、周囲に「URAYASU CITY」の文字がありません。
 (2025.06.05追加)
(2025.06.05追加)
こちらは汚水蓋です。
こちらはマンホール蓋と同様のデザインです。


 (2025.06.05追加)
(2025.06.05追加)
こちらは、周囲に「URAYASU CITY」の文字がありません。

こちらの蓋は、「おすい」の文字が左は少し湾曲しているいますが右蓋は真すぐに並んでいます。
 (2025.07.14追加)
(2025.07.14追加)
以降は、規格模様と呼ばれるマンホール蓋です。
こちらは、スリップ防止タイプの雨水蓋です。
右下に「うすい」の表記があります。 (2025.06.05追加)
(2025.06.05追加)
こちらは、インターブロッキングタイプの雨水蓋です。 (2025.06.05追加)
(2025.06.05追加)
こちらは、グレーチング(格子)タイプの蓋です。
こちらは、毘沙門亀甲模様の蓋です。
圧力対応のため四カ所がボルト締め(一カ所が外れているようです)されています。
こちらは、マンホールアンテナ(無線通信用のアンテナとバッテリーを内蔵)装備のマンホール蓋と思われます。
管きょ情報(水位、臭気など)の計測した各種情報が、マンホールアンテナから無線通信により、クラウドサーバ内に収集され、浦安市の担当課に提供されているのではないでしょうか。
蓋の中央には、「MA02」(管理番号?)と管理者(浦安市道路整備課)と連絡先の電話番号が書かれています。
マンホールアンテナは、東京都下水道サービス(株)、日之出水道機器(株)、 および(株)明電舎との共同開発品との事です。
こちらは、コンクリート製の枡蓋ではないかと思います。
上水道関係他の蓋を中心に整理します。
浦安市は、全域が千葉県営水道の給水区域となっているようです。そのため、上水道に係わる浦安市の蓋は設置されていないようです。なお、千葉県水道局千葉県営水道に係わる蓋は別途千葉県のマンホール蓋の中で整理する事にします。
こちらは、防火貯水槽の蓋です。
中央に市章、その周りを四分割し赤と白の市の花「ツツジ」がデザインされています。
こちらは、インターロッキングブロック型の「貯水槽」表記の蓋です。
こちらは、他自治体でも見かける消防車を描いた「防火水槽」表記の蓋です。 (2025.06.05追加)
(2025.06.05追加)
こちらは、電線共同溝(CCBOX)の蓋です。
市役所通りで撮りました。

 (2025.06.05追加3)
(2025.06.05追加3)
以上で、その1.浦安市のマンホール蓋の整理は終了です。















 (2025.07.13追加)
(2025.07.13追加)
 (2025.07.13追加2)
(2025.07.13追加2)  (2025.07.13追加)
(2025.07.13追加) 






 (2025.07.13追加)
(2025.07.13追加) (2025.07.13追加)
(2025.07.13追加)







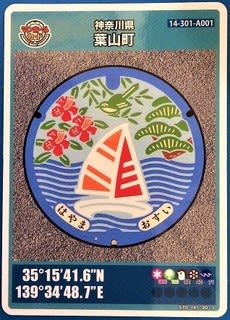


 (2025.06.23追加)
(2025.06.23追加)
 (2025.06.23追加)
(2025.06.23追加)














 (2025.06.23追加)
(2025.06.23追加)












 (2025.06.23追加)
(2025.06.23追加)


















































































































































































































































