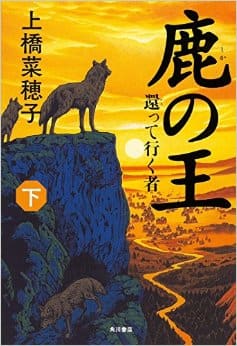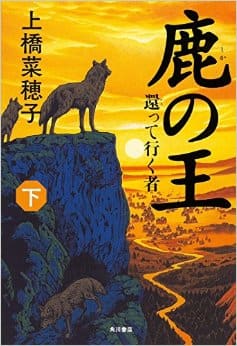
久々に本のレビューです。
昨年、上橋菜穂子さんの新刊が出たと知り、思わず買って読み終えたのが10月。
もう一度読み直してからレビューを書こう、と思っていたら腰痛でパソコンに向かえず、
そうこうしているうちに年末・お正月を迎え・・・とうとうこんな時期になってしまいました

それというのも(弁解ですが)、この作品はそう簡単にレビューが書けそうにない、
いろんな読み方のできる深く壮大な物語なのです。
感染症が一つの大きなテーマで、それに国・部族間の関係やそれぞれの文化が大きく
関わり、登場人物の利害関係もけっこう複雑で・・・
一度読んだくらいでは、到底このタンジュンな私の頭では整理がつきそうもなかったのです。
内容は簡単に言うと、ある謎の病に医者として、あるいは患者として、あるいは
それを利用しようとして、関わった人たちの物語、ということになります。
といっても、もちろんこの作品もこれまでの作品と同じように全く異世界のファンタジー。
ですが、そこで国や人々が抱える問題や思いは、現在の私たちとほとんど同じ。
戦いの後の国の統治のあり方、民族あるいは部族間の対立、未知の病の恐ろしさ、
そしてそれらに否応なく巻き込まれ、理不尽な生き方を強いられる人々・・・
それらを、不思議な犬に襲われその謎の病に侵された元戦士団の頭ヴァンと、
その病の治療法を懸命に探そうとする天才医術師ホッサルの二人を中心に展開していきます。
彼らと、彼らを支える二人の女性が、なかなか魅力的なのですよ

ヴァンは、強大な帝国にのみこまれていく故郷を守るため、戦いを繰り広げる戦士団の
頭でしたが、囚われ岩塩鉱の奴隷となり絶望的な日々を送っています。
ある日その岩塩鉱が不思議な黒い犬に襲われますが、ヴァンと一人の幼子だけが助かり、
その幼子をユナと名づけ共に生き延びます。
しかし、謎の病に罹りその身に異変が生じるのです。
なぜ、病に罹る者と罹らぬ者がいるのか。
病で愛する妻と子を失ったヴァンは問います。
病に罹らぬ人もいるのに、なぜ、妻と子は罹ってしまったのか。・・・
長く生きることができる者と、長く生きられぬ者が、なぜ、いるのか。
長く生きられぬなら、なぜ生まれてくるのか。
一方、その謎の病で滅びた王国の子孫である医術師ホッサルは、なんとかその病の治療法を
見つけようと、唯一生き残った男ヴァンを探そうとします。
その任を命じられたのが、女性でありながら素晴らしい腕を持つ跡追い狩人のサエ。
ホッサルの従者マコウカンと共に、わずかな手がかりをもとにヴァンを追います。
しかし、再びあの黒い犬たちが襲来し、多くの人がその病に感染し命を落とします。
なんとかその病の原因を探り、治療法を見つけようと必死になるホッサルと助手のミラル。
が、移住民だけが罹ると噂されるその謎の病の背景には、征服され土地を奪われた民や
それを利用しようとした為政者など、様々な文化を持つ国や部族の異なる人々の思惑が
複雑に絡み合っていたのです・・・
しかし、この作品に「悪者」は出てきません。
戦いは描かれても、敵の王や為政者も、謎の病を流行らせようと意図した者も、
ひとりの人間として描かれているからです。
それは、異文化の共生を願う作者の思いからなのでしょう。
ヴァンもホッサルも「悪」に立ち向かうわけではなく、己の生き方に
真正面から立ち向かっていったのだと思います。
たしかに病は神に似た顔をしている。
いつ罹るのかも、なぜ罹るのかもわからず、助からぬ者と助かる者の境目も定かではない、
己の手を遠く離れたなにか―神々の掌に描かれた運命のように見える。
(・・・だが)
だからといって、あきらめ、悄然と受け入れてよいものではなかろう。
なぜなら、その中で、もがくことこそが、多分、生きる、ということだからだ。
・・・
この世に生まれ落ちたときにもらった身体で、生き物はみな、命を繋ぐための、無数の、
小さな戦いと葛藤を繰り広げている。
他者の命を奪おうとするもの、他者の命を支えて生きるもの、雑多な生き方がせめぎ合い、
交じり合い、流れて行く、このすべてが、生きる、ということなのだろう。
この作品は感染症を扱った医療の物語であり、国のあり方を描いた物語であり、
人と生き物を描いた物語であり、父と子、あるいは家族の物語であり、男と女の物語であり・・・
とにかくいろんな視点で読むことができる壮大な物語なのです。
それにしても、どうやったらファンタジーでこのようなリアルな世界を作り出し、
読者が共感できる生き生きとした人物が描けるのか。
作者の上橋菜穂子という人はどんな人物なのだろう、とファンとして
いつも興味を抱いていました。
で、一昨日のこと。
たまたまBSの番組で上橋菜穂子さんの特集があるのを知り、ご本人が出演されて
生い立ちから物語を紡ぎだすまでのいろいろな興味深い話を聞くことができ、
なるほどなあ~と、すとんと納得したしだいです。
この作品は感染症が大きなテーマだと書きましたが、以前何かである研究者のような人が
言ったことがとても印象的で、最近それをよく思い出します。
その人は「人類にとって何が一番恐ろしいか」というような質問に対して、
「近い将来、人類にとって感染症が脅威になるだろう」と答えたのです。
それを聞いたとき、ちょっと意外な気がしました。
人類の脅威と言ったら、やはり「核」だし、病気でいうと癌、心臓病などがありますよね。
ひと昔まえじゃあるまいし、なんで感染症が?って。
でも、確かに最近になって恐ろしいと感じるのは、遠く離れた国で発症しじわじわ
と各国に広がっていったエボラ出血熱であったり、新型インフルエンザのバンデミックの脅威であったり。
昨年はデング熱でも大騒ぎになりました。
そう、目に見えないウィルスがもたらす感染症は、どこに存在するのか、どこで感染するのか、
わからないだけに恐ろしい。
たまたま毎日そんなニュースが流れているときにこの本を読んだので、よけいに
感染症の恐ろしさというものを痛感したのでした。
上橋さんが興味深いことをおっしゃっています。
人間はウィルスや細菌の共生体で、それは森や国家も同じではないか、と。
たとえば自分の腸の中に悪玉菌と善玉菌がいて、消化吸収を助けたり、免疫力を
つけてくれたりするのもいれば、お腹をこわしたり悪さをするヤツもいる。
自然や人間の社会もそれと同じように、共生と葛藤を繰り返しているわけですよね・・・
ふぅ~。
なんともスケールの大きな話で、おおまかなことしか書けませんでしたが、
この先何度でも読み返してみようと思います。
守人シリーズもテレビドラマになるようだし、また上橋作品を最初から読み直してみたいな~
本を開けたらそこには全く違う世界が待っている、って、今の私には救いのようです。
だから、ファンタジー大好き