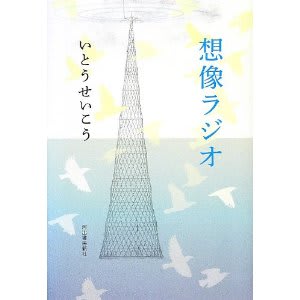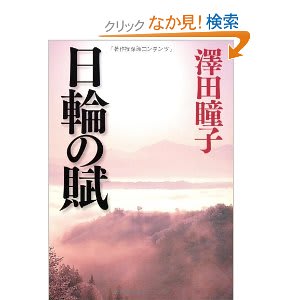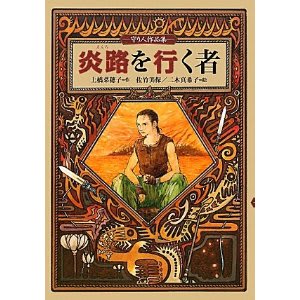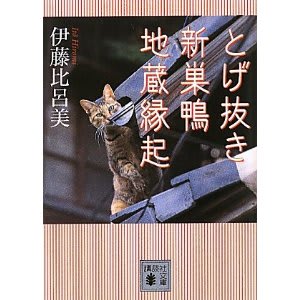
この本を読んだのは、まだ残暑厳しい9月。
すでに一ヶ月以上経ってしまいました。
読み終えたときの衝撃を忘れないうちに書きあげようと思いつつ、
あれやこれやでこんなに日が経ってしまっておりました

・・・ ・・・ ・・・
この本は『閉経記』を図書館で借りたとき、ちょっと気になったので
Amazonで購入しました。
私は『閉経記』のほうを先に読みましたが、書かれたのはこの『とげ抜き
新巣鴨地蔵縁起』の方が5~6年先になります。
つまり、寝たきりのお母さまも生きておられて、まだ小さな三女を連れ
カリフォルニア~熊本間を往復されていた当時のこと。
それだけでも、いかに大変な時期であったかがわかります。
う~ん、この本は何と言ったらいいのでしょう。
文庫本のあとがきに上野千鶴子さんが書いておられるのですが、
そして彼女は、他の誰もまねのできないまったくオリジナルな
文体に到達した。『とげ抜き 新巣鴨地蔵縁起』・・・これはひとつの達成だ。
詩でもなく散文でもなく、フィクションでもノンフィクションでもない。
「作品」というほかないものだ。
そうなんです。
書かれてある内容は確かに比呂美さん自身の話。
脳梗塞になった母親の介護とひとり暮らしの父のこと、
イギリス人のご主人のこと、心の病で大学に行けなくなった娘のこと、
飼っている犬のこと、自分の病気のことなどなど・・・
けれど、登場する娘の名は彼女の娘のものではありません。
なのでこれまで読んだエッセイのようではなく、かといって小説かというと
やはりどこか違う。
おそらく実体験であろうことを書きながら、だんだんと暗喩に満ちてきて
読み手にはどこまでが本当のことやらわからなくなってしまうのです。
しかも私の場合、だんだん自分の体験とシンクロして、覗き込んだ
深~い深~い穴の中に堕ちていくような、そんな感覚でした。
というのも、彼女の文章は古事記や宮沢賢治や中原中也や謡曲や・・・
いろんなものを取り入れて、独特の節回し・リズム感で、
何とも言えない不思議な世界を作り出しているからでしょう。
内容は容赦なく過激です。
介護する母と娘の関係や、ユダヤ系イギリス人のご主人との文化的差異から
生じる(それだけではないでしょうが)夫婦喧嘩。
どれも生々しく、ここまで書いていいの?と心配になるほどですが、
夫婦のことは途中から古事記のイザナギ、イザナミの話と重なって
ちょっとブラックでコミカルな感じもします。
一方ご両親のことは、読んでいてとてもつらくなります。
病院で寝たきりの母親と、ひとり家で暮らす父親。
そんな両親を日本に残し、夫のいるアメリカへ帰らなければならないつらさ、
心苦しさ。
アメリカへ帰ったら帰ったで、律儀に親に国際電話をかけて
何度も同じことを繰り返す親の話を聞き、これまた同じ返事を繰り返す。
このしんどさは経験したものでないとわからないかもしれませんが、
彼女はそれを続けているのです。
ひとり娘とはいえ、そこまでやれることに頭が下がりました。
次々と襲いかかる様々な困難や葛藤を、彼女は書くことによって、
書いて吐き出すことによって、これまでの壮絶ともいえる人生を
乗り越えていけたのでしょう。
こんな文章がありました。
月一回の締め切りは、まるで月経です。
・・・(中略)・・・それならば、月1回、「群像」に出す「とげ抜き」も、
おなじやりかたで迎えればよいと考えまして、終わらぬ月経を先へ先へ
つなげていくような心持ちで語りついでいくうちにふと気がついた。
母の苦、父の苦、夫の苦。
寂寥、不安、もどかしさ。
わが身に降りかかる苦ですけれど、このごろ苦が苦じゃありません。
降りかかった苦はネタになると思えばこそ、見つめることに忙しく、
語ることに忙しく、語るうちに苦を忘れ、これこそ「とげ抜き」の、
お地蔵様の御利益ではないか。
親の老いや病に向き合い、文化も宗教観も食べ物も違う夫と向き合い、
それだけでも大変なときに今度は娘の危機が訪れます。
そのときの彼女の悲痛な叫び。
老いの話どころではなくなりました。子どもが危機です。
しのびないのは子どもの苦。
自分の身にふりかかる苦は。
あさましい暗闇をひとりでのたうちまわっておれば、やがて抜けていくのです。
親の身にふりかかる死の苦は。
粛々と受け止めていくしかありません。
しかし子どもの苦はちがいます。
・・・(中略)・・・
苦しむ子ども。
ほんとを申せば、見たくありません。
見てるふりをして見ないでいられるものならそうしていたい。
でも、目をそむけてはいられないのです。
子どもは「見て」「見て」と。そして「助けて」「助けて」と。
この身を投げ出してても助けてやりたい。
でも、見ててやるしかないことがあるのです。
他人は見てくれませんからせめてたらちねの
母が見よう。
子どもの苦しむありさまは。
せつなすぎて涙もでません。
・・・(略)・・・
読んでいて、こちらまで胸が痛くなります。
そして、いろんなことが重なって
泣きっつらに蜂というのは、昔の人がこの日のわたしのために
作り置きしたことばかと思えた日彼女はとうとう声を出して泣くのです。
あゝ怖かった怖かった。
わたしは声に出していってみました。
あゝ怖かった怖かった。
たらちねの母といえども生身であります。
むかしは小さな女の子でありました。
怖いときは泣いてました。
父や母や夫や王子様に、助けてもらいたいと思っておりました。
何べんも何べんも助けてもらいました。
父にも母にも、夫や王子様にも。
でも今はだーれもおりません。
父は老いて死にかけです。
母も死にかけて寝たきりです。
夫や王子様には、もう頼れません。
このごろじゃすっかり垂れ乳で、根元からゆあーんよゆーんと
揺すれるほどになりまして、
足を踏ん張り、歯をくいしばり、
ちっとも怖くないふりをして、
苦に、苦に、苦に、
苦また苦に、
立ち向かってきたんですけど、
あゝあ、ほんとに怖かったのでございます。
ここまで読むと、もうこちらまで泣きたくなってしまいます。
そう、年を重ねた女性なら誰しも、もう誰も頼れないんだと悟って
足を踏ん張り、歯を食いしばり、怖くないふりをして生きていますよね。
今でこそ私もこうやってのほほんと、あるいはふてぶてしく生きていますが、
ある時期は私なりにしんどい時期がありまして。
比呂美さんほど壮絶な経験ではありませんが、やはり親を看ている時期というものは、
まるで孤立無援のような日々、ひとりで空回りしているような状態でした。
この本を読んでいると、自分のそんな時期が蘇ってくるのです。
普段はそんなこと意識してなかったのに、ここを読んで、
ああ比呂美さんが自分のかわりに泣いてくれたんだー
と思ってしまいましたよ。
こんなふうに、書かれてある内容は女の感情むき出しの過激さがありながら、
常につきまとうのが「死」のイメージです。
それも物理的な死というより、黄泉の国や西方浄土といった日本的あるいは
仏教的なイメージ。
そもそも題名からして地蔵縁起ですものね。
若いときからずっと闘い続けた比呂美さんも、苦のとげを抜くお地蔵様に
救いを求めたということでしょうか。
このあと、比呂美さんは般若心経の現代語訳を出されたようですが、
できるならまだまだ悟ってほしくはないですよね。
私たちの先輩として、この先老いてもなお生々しく、戦う女の姿を見せてほしいものです。