Western Electricの後期のアンプWE140Aについての資料は少ない。わかっていることは発表は1947年、スピーカー再生専用としてFM局で755A、またはテレホンラインで756A,728Bなどのパンケーキ型スピーカーのドライブアンプとして多用された。1台あたり複数のスピーカーをオートトランスを介してドライブする電圧伝送型として使用されたため生産台数が少ない。出力:10W(歪率5%、AC動作)、6W(歪率5%、DC動作) WE140AはKS13678キャビネットに入れるとWE1140Aと名前を変える。

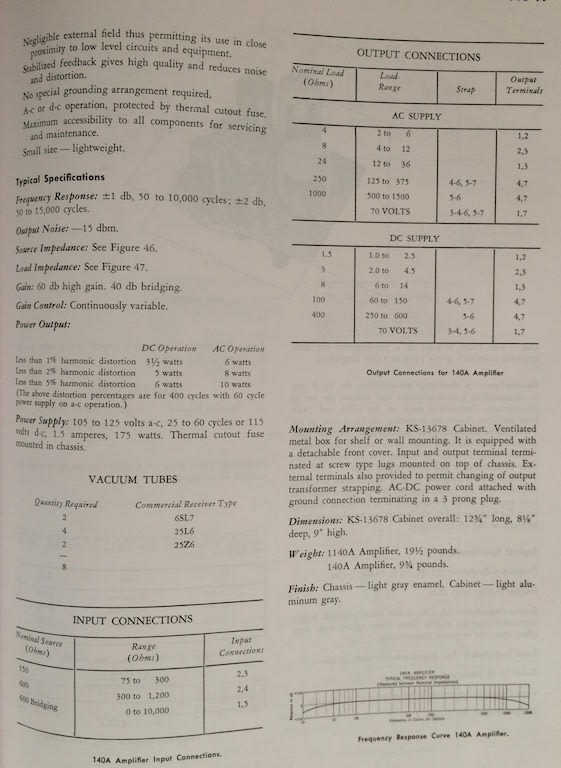

回路図を見て気づくのは電話業務で使われたWE100Fによく似ていること。トランスレス、使用真空管は同一。異なるのはシングルアンプがパラプッシュプルになって位相反転回路が加わり電源が25Z6の倍電圧整流になっていること、出力トランスが「WE91B」「WE124A」などに採用された171系トランスの171Dになっていること、入力トランスが広帯域の285系になった。こういったバリエーションはWestern Electricのアンプではよく見かけます。WE140Aはインターステージトランスを使っていないのを見ても近代的なアンプだなと改めて思う。ところでこの位相反転回路は何という名前なのか?下のグリッドの入力が無いではないか?と思っていたがどうもミスプリントのようで。上プレートから0.05μFで直結(!)される。これは一体??
上側は通常の自己バイアスの増幅回路、位相の反転したプレート出力を直に下グリッドへ。下はプレート電圧を2MΩと510KΩで分圧しグリッドに対アースで40Vかかっているがカソード抵抗が39KΩで42Vの電位があり差し引き2Vのバイアスがかかる、、。上下の利得はどうなっているのだろうか。
WE100F回路図







トランスレスなのでシャーシとケース、また手に触れる部分は絶縁されている。












ハーネスはやはりWestern Electric特有のオーラを感じる。こんな小さなアンプでも迫力に目を奪われる。ハンダ付けの力量は高くネジ類もしっかりと締め付けられている。
音は出ますがハムが多い。以前は動作していましたが久しぶりの稼働でいろいろと問題ありそうです。整流用電解コンデンサーのベーク基板が割れている

このコンデンサーは感電防止の紙筒が被っています。またシャーシには接続されていない。容量、電圧表示はこの紙筒に書いてあるのでなんとか外したかったが上手くいかず破れてしまいました。外してチェックするとやはりご臨終。仕方ないので根本付近で切り離して分解して適当なコンデンサーを入れる事にします。

2階建。端子への接続は(やはり内部では難しいので

底に穴を開けて端子とケースをベーク基板に留めるツイスト端子に半田付けまた組み立てました。容量は1.5倍になってしまってます。もう1ヶ所の電解コンデンサーは無事でした。

電源部は復旧したが各部の電圧は回路図記入のものとかなり異なっています(この回路図はマチガイがありそうだが、、)カップリングコンデンサーはWestern Electricネイム入りだが全滅のよう。

交換してもまだおかしい、、。おっと2MΩが断線している。数個の抵抗をつないで置き換えてみると正常値になりました。

しかし初段のチリチリノイズが消えない、真空管換えてもダメ。なぜ??とりあえず部品を注文した。

せっかくの休日(秋分の日)がまったりと過ぎていく、、。もう夕方か〜。
苦節数時間(?)ノイズの原因が分かりました。初段の抵抗を交換していくとR3のカソード抵抗2KΩが原因でした。A&B抵抗は劣化してくると抵抗値が高くなる傾向が出ますのでチェックしていて分かりました。古い機器の原因不明のノイズを解決するのに「ハンダを押さえていく」というのはプロから教わったことがありますが電圧が2Vしかかかっていない抵抗器が原因だったとは、、。とにかく原因がつかめてよかったです。手持ちのものと交換して今日はここまであとは部品待ち。
この状態でWE755Aを鳴らしてみると、、なかなかの音です。

WE755Aは比較的鳴らすのが難しいスピーカーです。大型アンプで蹴飛ばすようにすればそれなりですが、小型アンプでそよそよと鳴らすのはけっこう面倒。WE140Aは地味なアンプですが素性は宜しいよう。
部品交換しようやく完了。結構時間がかかりました。


改めてWE755Aの良さに嬉しくなりました。大きな音が出ますが貴重なスピーカーなので過大入力には注意です。
WE140AはトランスレスやWEtubeを使ってないなどあまり人気の無いアンプだそうです。今回改めてメンテナンス、試聴してみてとても好感を持ちました。出力は10Wですのでホームユースの使用には全く問題はなくその品格ある音質からメインシステムとして十分に通用すると思います。パラプッシュはWE118AやWE143A,Langevin101Dなどと同様ですが通常は大出力を求められる場面に用いられる。しかしWE140Aは10Wです。WE124Aとどう棲みわけたかはわからないが(多分FM局の廉価アンプとしての位置付け)小出力管をパラプッシュとして動作させたことに注目します。個人的にこういう設計にはとても好感を持っています。古典的なアンプほど、パーツの個性が際立って名真空管、名トランスなど神話とともに君臨する。近代的な回路になるほどその傾向は薄れていき、真空管も「WEでなくてはダメ」な世界ではなくなっていく。「Marantz Model 9」のEL34を現代流通しているものに取り替えた時もそれを強く感じました。tubeをアンプの消耗部品としていて多少銘柄が変わってもアンプの骨格はびくともしない。それだけ技術進歩が匠にとってかわるということではないかと。(といいながら入出力トランスにはやはり感心するが)電力増幅管を多数パラプッシュにしたアンプも存在しますがまだ聞いたことがありません。こういう世界はアマチュアの特権かと思ってましたが登場した時は驚きました。
お読みいただきありがとうございました。
後日談 1
手持ちの資料の中にWE140Aの別回路図がありました。

やはり前出のものはミスプリントがあるようです。記入の電圧も実測値に近いです。

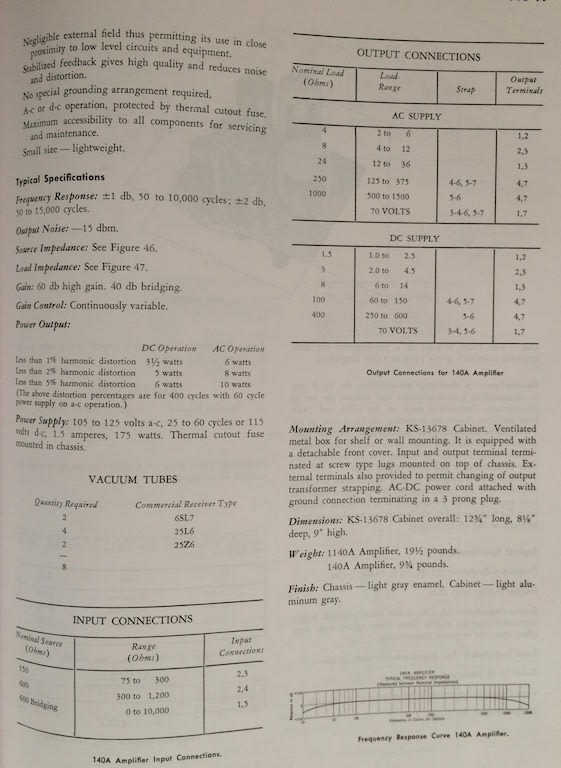

回路図を見て気づくのは電話業務で使われたWE100Fによく似ていること。トランスレス、使用真空管は同一。異なるのはシングルアンプがパラプッシュプルになって位相反転回路が加わり電源が25Z6の倍電圧整流になっていること、出力トランスが「WE91B」「WE124A」などに採用された171系トランスの171Dになっていること、入力トランスが広帯域の285系になった。こういったバリエーションはWestern Electricのアンプではよく見かけます。WE140Aはインターステージトランスを使っていないのを見ても近代的なアンプだなと改めて思う。ところでこの位相反転回路は何という名前なのか?下のグリッドの入力が無いではないか?と思っていたがどうもミスプリントのようで。上プレートから0.05μFで直結(!)される。これは一体??
上側は通常の自己バイアスの増幅回路、位相の反転したプレート出力を直に下グリッドへ。下はプレート電圧を2MΩと510KΩで分圧しグリッドに対アースで40Vかかっているがカソード抵抗が39KΩで42Vの電位があり差し引き2Vのバイアスがかかる、、。上下の利得はどうなっているのだろうか。
WE100F回路図







トランスレスなのでシャーシとケース、また手に触れる部分は絶縁されている。












ハーネスはやはりWestern Electric特有のオーラを感じる。こんな小さなアンプでも迫力に目を奪われる。ハンダ付けの力量は高くネジ類もしっかりと締め付けられている。
音は出ますがハムが多い。以前は動作していましたが久しぶりの稼働でいろいろと問題ありそうです。整流用電解コンデンサーのベーク基板が割れている

このコンデンサーは感電防止の紙筒が被っています。またシャーシには接続されていない。容量、電圧表示はこの紙筒に書いてあるのでなんとか外したかったが上手くいかず破れてしまいました。外してチェックするとやはりご臨終。仕方ないので根本付近で切り離して分解して適当なコンデンサーを入れる事にします。

2階建。端子への接続は(やはり内部では難しいので

底に穴を開けて端子とケースをベーク基板に留めるツイスト端子に半田付けまた組み立てました。容量は1.5倍になってしまってます。もう1ヶ所の電解コンデンサーは無事でした。

電源部は復旧したが各部の電圧は回路図記入のものとかなり異なっています(この回路図はマチガイがありそうだが、、)カップリングコンデンサーはWestern Electricネイム入りだが全滅のよう。

交換してもまだおかしい、、。おっと2MΩが断線している。数個の抵抗をつないで置き換えてみると正常値になりました。

しかし初段のチリチリノイズが消えない、真空管換えてもダメ。なぜ??とりあえず部品を注文した。

せっかくの休日(秋分の日)がまったりと過ぎていく、、。もう夕方か〜。
苦節数時間(?)ノイズの原因が分かりました。初段の抵抗を交換していくとR3のカソード抵抗2KΩが原因でした。A&B抵抗は劣化してくると抵抗値が高くなる傾向が出ますのでチェックしていて分かりました。古い機器の原因不明のノイズを解決するのに「ハンダを押さえていく」というのはプロから教わったことがありますが電圧が2Vしかかかっていない抵抗器が原因だったとは、、。とにかく原因がつかめてよかったです。手持ちのものと交換して今日はここまであとは部品待ち。
この状態でWE755Aを鳴らしてみると、、なかなかの音です。

WE755Aは比較的鳴らすのが難しいスピーカーです。大型アンプで蹴飛ばすようにすればそれなりですが、小型アンプでそよそよと鳴らすのはけっこう面倒。WE140Aは地味なアンプですが素性は宜しいよう。
部品交換しようやく完了。結構時間がかかりました。


改めてWE755Aの良さに嬉しくなりました。大きな音が出ますが貴重なスピーカーなので過大入力には注意です。
WE140AはトランスレスやWEtubeを使ってないなどあまり人気の無いアンプだそうです。今回改めてメンテナンス、試聴してみてとても好感を持ちました。出力は10Wですのでホームユースの使用には全く問題はなくその品格ある音質からメインシステムとして十分に通用すると思います。パラプッシュはWE118AやWE143A,Langevin101Dなどと同様ですが通常は大出力を求められる場面に用いられる。しかしWE140Aは10Wです。WE124Aとどう棲みわけたかはわからないが(多分FM局の廉価アンプとしての位置付け)小出力管をパラプッシュとして動作させたことに注目します。個人的にこういう設計にはとても好感を持っています。古典的なアンプほど、パーツの個性が際立って名真空管、名トランスなど神話とともに君臨する。近代的な回路になるほどその傾向は薄れていき、真空管も「WEでなくてはダメ」な世界ではなくなっていく。「Marantz Model 9」のEL34を現代流通しているものに取り替えた時もそれを強く感じました。tubeをアンプの消耗部品としていて多少銘柄が変わってもアンプの骨格はびくともしない。それだけ技術進歩が匠にとってかわるということではないかと。(といいながら入出力トランスにはやはり感心するが)電力増幅管を多数パラプッシュにしたアンプも存在しますがまだ聞いたことがありません。こういう世界はアマチュアの特権かと思ってましたが登場した時は驚きました。
お読みいただきありがとうございました。
後日談 1
手持ちの資料の中にWE140Aの別回路図がありました。

やはり前出のものはミスプリントがあるようです。記入の電圧も実測値に近いです。



















