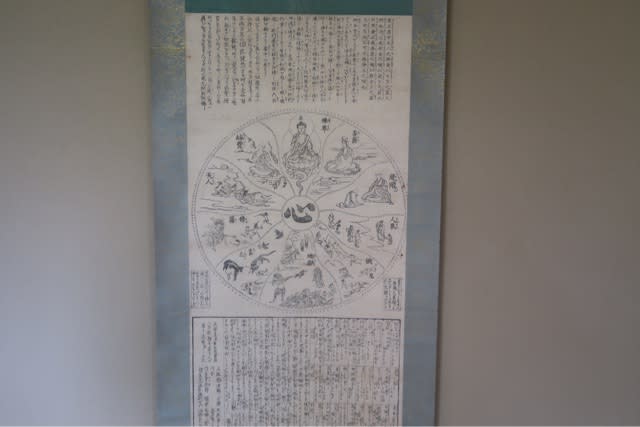次に紫明通、堀川通を渡り玄武神社を訪ねます。こちらは初訪問です。
その前に紫明通は、京都を「山紫水明の地」と言った事に由来します。元々は琵琶湖疎水の第二疏水分線で、蹴上から松ヶ崎・下鴨を経て賀茂川をサイホンでくぐり堀川まで繋がっていました。

その後、賀茂川以西は埋め立てられ、第二次大戦中の防火帯設置のため強制疎開が行われ紫明通となりました。
しかし、平成21年に第二疏水分線を復活させ、紫明通、堀川通を経由して今出川通から御池通の堀川の開渠部に導水し、せせらぎを復活させ、水辺空間の整備がおこなわれました。


堀川
平安京の一条通東北部には平安京以前に自然の河川が流れており、その川床を利用して平安時代に堀川を造り、これを東堀川と名付けられました。同時に西堀川(現在の紙屋川)も掘られました。東西両堀川の開削は、京都の北部の山林で伐採した平安京造営に必然な木材の運搬が目的であり、この両河川に挟まれた地域に大内裏が建設されました。
玄武神社
祭神は惟喬親王。
駒札によると元慶年間、星野茂光が惟喬親王を祭神として創建したとあります。

惟喬親王は第55代文徳天皇の皇子でしたが母の身分が低く皇太子になれませんでした。
親王には腹違いの弟、惟仁親王がいて、生母は藤原良房の娘、明子(あきらけいこ)で生後9か月で皇太子になりました。
父、文徳天皇が崩御した時はまだ9歳でしたが天皇に即位しています。


父、文徳天皇は惟喬親王を深く愛し、天皇位を継がせたかったのですが藤原氏の勢力に従わざるを得ませんでした。

失意の惟喬親王は晩年出家し、比叡山の西麓小野に隠棲しました。「伊勢物語」に冬の雪深い小野の地に在原業平が惟喬親王に逢いにやってきて歌を詠んだことが書かれています。
忘れては夢かとぞ思ふ 思ひきや
雪ふみわけて 君を見むとは
(古今和歌集十八巻)
最後の目的地の大徳寺塔頭 雲林院です。
雲林院
天長年間(824〜834)、淳和天皇が紫野に造営された離宮・紫野院の跡地です。


淳和天皇はたびたび紫野院に行幸し、釣殿を見物、雅楽の演奏、文人に作詞等をさせました。
天長9年(832)には皇后正子が行啓し、周辺で耕作する様子を見物。
淳和天皇が退位され上皇となった後に仁明天皇のなり、その後に仁明天皇の第七皇子の常康親王に伝領されました。


仁明天皇の崩御後、常康親王は出家し雲林院に隠棲しました。貞観11年(869)親王没後に遍昭僧正に付託されました。
遍昭は、仁和2年(886)に毎年3月21日に仁明天皇の忌日に金戒明経を転読する勅許を得て、花山元慶寺の別院としました。
遍昭亡き後、子の素性法師が住みました。
釣殿は930年に廃絶。村上天皇の御願により多宝塔が応和3年に落慶し興隆しましたが、中世以降、寺運は衰微し、後醍醐天皇の御代に寺地は大徳寺に施入され、消滅するに至ります。
往事の雲林院は4町四方の寺領を有し、桜や紅葉の名所として知られていました。
中世には謡曲「雲林院」の題材にもなり、また、源氏物語の「賢木」の巻や「大鏡」にも登場しています。
少しレアな内容になりましたが、それぞれの神社、寺社には様々な紆余曲折な歴史があり今日まで存続している事を学びました。
都草 歴史探訪会西部会の皆様、お疲れ様でした。
その前に紫明通は、京都を「山紫水明の地」と言った事に由来します。元々は琵琶湖疎水の第二疏水分線で、蹴上から松ヶ崎・下鴨を経て賀茂川をサイホンでくぐり堀川まで繋がっていました。

その後、賀茂川以西は埋め立てられ、第二次大戦中の防火帯設置のため強制疎開が行われ紫明通となりました。
しかし、平成21年に第二疏水分線を復活させ、紫明通、堀川通を経由して今出川通から御池通の堀川の開渠部に導水し、せせらぎを復活させ、水辺空間の整備がおこなわれました。


堀川
平安京の一条通東北部には平安京以前に自然の河川が流れており、その川床を利用して平安時代に堀川を造り、これを東堀川と名付けられました。同時に西堀川(現在の紙屋川)も掘られました。東西両堀川の開削は、京都の北部の山林で伐採した平安京造営に必然な木材の運搬が目的であり、この両河川に挟まれた地域に大内裏が建設されました。
玄武神社
祭神は惟喬親王。
駒札によると元慶年間、星野茂光が惟喬親王を祭神として創建したとあります。

惟喬親王は第55代文徳天皇の皇子でしたが母の身分が低く皇太子になれませんでした。
親王には腹違いの弟、惟仁親王がいて、生母は藤原良房の娘、明子(あきらけいこ)で生後9か月で皇太子になりました。
父、文徳天皇が崩御した時はまだ9歳でしたが天皇に即位しています。


父、文徳天皇は惟喬親王を深く愛し、天皇位を継がせたかったのですが藤原氏の勢力に従わざるを得ませんでした。

失意の惟喬親王は晩年出家し、比叡山の西麓小野に隠棲しました。「伊勢物語」に冬の雪深い小野の地に在原業平が惟喬親王に逢いにやってきて歌を詠んだことが書かれています。
忘れては夢かとぞ思ふ 思ひきや
雪ふみわけて 君を見むとは
(古今和歌集十八巻)
最後の目的地の大徳寺塔頭 雲林院です。
雲林院
天長年間(824〜834)、淳和天皇が紫野に造営された離宮・紫野院の跡地です。


淳和天皇はたびたび紫野院に行幸し、釣殿を見物、雅楽の演奏、文人に作詞等をさせました。
天長9年(832)には皇后正子が行啓し、周辺で耕作する様子を見物。
淳和天皇が退位され上皇となった後に仁明天皇のなり、その後に仁明天皇の第七皇子の常康親王に伝領されました。


仁明天皇の崩御後、常康親王は出家し雲林院に隠棲しました。貞観11年(869)親王没後に遍昭僧正に付託されました。
遍昭は、仁和2年(886)に毎年3月21日に仁明天皇の忌日に金戒明経を転読する勅許を得て、花山元慶寺の別院としました。
遍昭亡き後、子の素性法師が住みました。
釣殿は930年に廃絶。村上天皇の御願により多宝塔が応和3年に落慶し興隆しましたが、中世以降、寺運は衰微し、後醍醐天皇の御代に寺地は大徳寺に施入され、消滅するに至ります。
往事の雲林院は4町四方の寺領を有し、桜や紅葉の名所として知られていました。
中世には謡曲「雲林院」の題材にもなり、また、源氏物語の「賢木」の巻や「大鏡」にも登場しています。
少しレアな内容になりましたが、それぞれの神社、寺社には様々な紆余曲折な歴史があり今日まで存続している事を学びました。
都草 歴史探訪会西部会の皆様、お疲れ様でした。