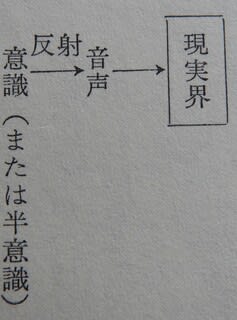「ネイピア対数を読み解く」はすでに提示している。
「ネイピア対数を読み解く」(PDF)
これを読みやすくするために「はじめに」を前置きし、あいまいな個所を補完するために「あとがき」を添えることにした。いずれPDFに取り込むつもりだが、とりあえず、「はじめに」と「あとがき」をブログ上に公開しておくことにした。「はじめに」と「あとがき」を読んだ後、「ネイピア対数を読み解く」をクリックして本論を読んでほしい。
はじめに
ネイピアの対数の定義は難解だった。志賀浩二『数の大航海』や 山本義隆『小数と対数の発見』に定義が引用されていたが、さっぱりわからなかった。それでも定義とその解説を行き来しているうちに、なんとか読みとれるようになってきた。「定義」に至る「等比数列と等差数列の対応」からたどると分かりやすくなるのではないかと思う。
ネイピア対数の全貌はこの2著に詳しいが、ここでは全体ではなく、数直線(線分と半直線)上の点の運動として「対数」を定義するネイピアの「発想」の1点に絞って考察する。
等差数列の進行に時間の規則的な経過を対応させたことが跳躍点だったと考える。そして、この観点は前2著に欠けているのではないかと思う。時間の規則的な進行は、ネイピア以降、小数表記の確立とともに、間隔が縮小し、そして連続していくようになる。ここに実数と関数の考えが確立していき、無限解析が可能になっていった。
10^7から0へと減少していく等比数列が、減衰していく指数関数になる過程に着目する。
あとがき
等比数列と等差数列の対応が関数の最初の姿だった。この対応を点の運動として表象するとき、ネイピアは数列の進行に時間を導入した。ここに定義が成立した。そしてこの時間を離散的なものから連続的なものへと稠密していく過程でネイピア数eが現れてきた。
時間とともに減少する等比数列が減衰する指数関数に変化する過程を次の2節で構成した。
1 ネイピア対数の定義を導く
2 ネイピア数eが現れる
1はネイピアの対数の発想を端的に捉えたもの、2は「運動現象の数学的取扱い」の端緒(ガリレイの先駆者)を着目したものである。2に、ネイピアが想定した等比数列を小数表記(小数点の位置を7桁左に移動する)する際の式変形が出て来るが、この変形の背景にふれる必要があると感じるようになった。ここを補完しておきたい。
ネイピアの対数概念の提出以降、対数は2つの道に分かれている。常用対数と自然対数である。
ネイピアによる対数の提起は数計算を簡略することにあった。しかし、ネイピア対数は十進記法と相性が悪かった。例えば、同じ数字の配列の数で小数点の位置が違う数に対する補整が複雑になっていた。改善が求められた。数計算の方はブリッグスの常用対数にとって代わった。常用対数にはネイピアも関係していた。(このとき、ネイピアは等比数列と等差数列の対応というアイデアを放棄していると志賀浩二は述べている。)
常用対数は、底・指数・対数・真数の関係を明確にしていく契機となっていると思う。
ab=c(a^b=c)、logac=b(log_ac=b)
において、aは底、bは指数=対数、cは真数である。これは等比数列のなかから、初項1、公比a、項の順番bの等比数列の項cに着目したものである。それは等比数列と等差数列の対応を1点で取り上げたものとみることができる。
他方、等比数列と等差数列の直接の連続的な対応は、数ではなく幾何(直角双曲線の面積と横座標)に現れてきた。ヴンセント(発見、端緒)にはじまり、メンゴリは区間縮小法によって対数の存在を実数上で確認する。また、メルセンヌは対数を無限級数で表し、双曲線のグラフの面積として与えられる対数を自然対数と述べる。そして、ニュートンは双曲線の面積を無限級数と積分を通して明確にした(志賀浩二『数の大航海』6章無限解析への序曲、参照)。こちらの方から、連続複利の形(ヤコブ・ベルヌーイ,1683 年)として、また,対数が1 となる数c(ヨハン・ベルヌーイ,1697 年)として、ネイピア数は出現してきている。
常用対数から底・指数・対数・真数への流れを「等比数列と等差数列の対応」の抽象としてみることができるだろう。他方、自然対数による双曲線の面積の把握は「等比数列と等差数列の対応」の「具体」化とみることができる。
ネイピアの等比数列(初項10^7)を小数表記(小数点の位置を7桁左に移動する)する際の式の変形は、2つの「等比数列と等差数列の対応」が合流することによって可能になったといえるだろう。
「ネイピア対数を読み解く」(PDF)
「ネイピア対数を読み解く」(PDF)
これを読みやすくするために「はじめに」を前置きし、あいまいな個所を補完するために「あとがき」を添えることにした。いずれPDFに取り込むつもりだが、とりあえず、「はじめに」と「あとがき」をブログ上に公開しておくことにした。「はじめに」と「あとがき」を読んだ後、「ネイピア対数を読み解く」をクリックして本論を読んでほしい。
はじめに
ネイピアの対数の定義は難解だった。志賀浩二『数の大航海』や 山本義隆『小数と対数の発見』に定義が引用されていたが、さっぱりわからなかった。それでも定義とその解説を行き来しているうちに、なんとか読みとれるようになってきた。「定義」に至る「等比数列と等差数列の対応」からたどると分かりやすくなるのではないかと思う。
ネイピア対数の全貌はこの2著に詳しいが、ここでは全体ではなく、数直線(線分と半直線)上の点の運動として「対数」を定義するネイピアの「発想」の1点に絞って考察する。
等差数列の進行に時間の規則的な経過を対応させたことが跳躍点だったと考える。そして、この観点は前2著に欠けているのではないかと思う。時間の規則的な進行は、ネイピア以降、小数表記の確立とともに、間隔が縮小し、そして連続していくようになる。ここに実数と関数の考えが確立していき、無限解析が可能になっていった。
10^7から0へと減少していく等比数列が、減衰していく指数関数になる過程に着目する。
あとがき
等比数列と等差数列の対応が関数の最初の姿だった。この対応を点の運動として表象するとき、ネイピアは数列の進行に時間を導入した。ここに定義が成立した。そしてこの時間を離散的なものから連続的なものへと稠密していく過程でネイピア数eが現れてきた。
時間とともに減少する等比数列が減衰する指数関数に変化する過程を次の2節で構成した。
1 ネイピア対数の定義を導く
2 ネイピア数eが現れる
1はネイピアの対数の発想を端的に捉えたもの、2は「運動現象の数学的取扱い」の端緒(ガリレイの先駆者)を着目したものである。2に、ネイピアが想定した等比数列を小数表記(小数点の位置を7桁左に移動する)する際の式変形が出て来るが、この変形の背景にふれる必要があると感じるようになった。ここを補完しておきたい。
ネイピアの対数概念の提出以降、対数は2つの道に分かれている。常用対数と自然対数である。
ネイピアによる対数の提起は数計算を簡略することにあった。しかし、ネイピア対数は十進記法と相性が悪かった。例えば、同じ数字の配列の数で小数点の位置が違う数に対する補整が複雑になっていた。改善が求められた。数計算の方はブリッグスの常用対数にとって代わった。常用対数にはネイピアも関係していた。(このとき、ネイピアは等比数列と等差数列の対応というアイデアを放棄していると志賀浩二は述べている。)
常用対数は、底・指数・対数・真数の関係を明確にしていく契機となっていると思う。
ab=c(a^b=c)、logac=b(log_ac=b)
において、aは底、bは指数=対数、cは真数である。これは等比数列のなかから、初項1、公比a、項の順番bの等比数列の項cに着目したものである。それは等比数列と等差数列の対応を1点で取り上げたものとみることができる。
他方、等比数列と等差数列の直接の連続的な対応は、数ではなく幾何(直角双曲線の面積と横座標)に現れてきた。ヴンセント(発見、端緒)にはじまり、メンゴリは区間縮小法によって対数の存在を実数上で確認する。また、メルセンヌは対数を無限級数で表し、双曲線のグラフの面積として与えられる対数を自然対数と述べる。そして、ニュートンは双曲線の面積を無限級数と積分を通して明確にした(志賀浩二『数の大航海』6章無限解析への序曲、参照)。こちらの方から、連続複利の形(ヤコブ・ベルヌーイ,1683 年)として、また,対数が1 となる数c(ヨハン・ベルヌーイ,1697 年)として、ネイピア数は出現してきている。
常用対数から底・指数・対数・真数への流れを「等比数列と等差数列の対応」の抽象としてみることができるだろう。他方、自然対数による双曲線の面積の把握は「等比数列と等差数列の対応」の「具体」化とみることができる。
ネイピアの等比数列(初項10^7)を小数表記(小数点の位置を7桁左に移動する)する際の式の変形は、2つの「等比数列と等差数列の対応」が合流することによって可能になったといえるだろう。
「ネイピア対数を読み解く」(PDF)