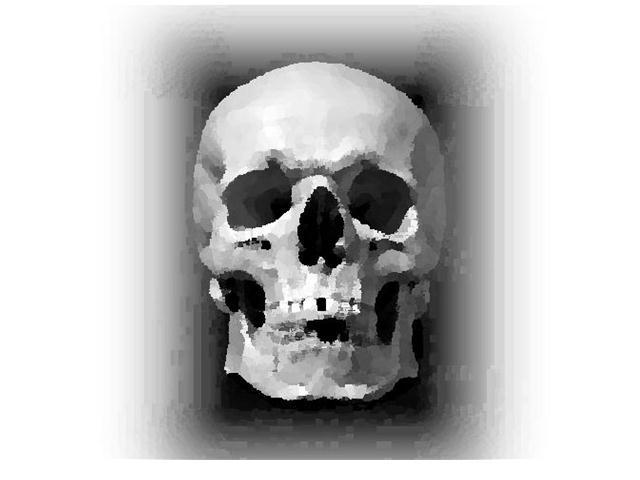前回と同じ土器です。湧き水の色を「ヒスイ色」と飛躍した呼び方にしています。
なぜ、このような色を付けているのか「水場遺構」という祭祀場に行って見ました。縄文時代の現状展示の場です。
この場所から、水場の地面を見ると油がわいているのです。縄文時代から涌いていたと思います。火が付くような濃さは無いのですが、確かに油です。
石ばかりの遺跡ですが、その地下から開設以来 . . . 本文を読む
北黄金貝塚公園の土器です。湧き水の流れ(川)と思う個所に色がついているように見えます。下から蛍光灯の光が照らしていることが原因だとしていましたが、この土器はどのように見えるでしょう。
土器に色が塗られている様に思います。
はっきりとした色が見られます。
これは「ヒスイ」の色であり「命の再生」を願っていると考えられます。この水もその意味を含んだ「命の水」としていたのでしょうか。
「ヒ . . . 本文を読む
北黄金貝塚の土器です。
縄文中期の縄文時代の盛んだったころの土器と言えます。背景が気になります。
日常的に使われていた土器だとよくわかります。
「山」と「海」の境界線を拡大してみました。少し青っぽい色が見られるように感じます。下から蛍光灯で照らしているので、その影響かと思いましたが、どうも異なるようにも見えます。はっきりとしません。
土器の模様を拡大して見る . . . 本文を読む
「土器模様は生活環境」と設定していますので、この土器の環境を推定することも可能と思ったのです。
ところが、縄文模様であるようで、縄文模様ではないのです。
縄文(網目)の模様といえるだろうか。
「草木」としたところは「網目」の模様だとすると海になるのでこの土器全体が海になります。
土器の上部にあるので、海でなく草木としました。今の丘の風景のように大きな木がなく笹などの丘で . . . 本文を読む
縄文中期の縄文時代最盛期の時の土器です。
円筒型土器は(深い)海を生活環境としていることが分かります。
上辺が「山」(陸)で下方が「海」の領域とします。
土器紋様には生活環境が記されているのです。
山と海の境に「〇」がありますが、これは「水」を示していて連続していて「川」と解釈できそうです。
今でも「湧水が」あり小さな川が3本もあります。縄文時代には3本の川があったとは思 . . . 本文を読む
秋晴れの好天です。北海道の地震や台風の影響で、延期になった小学校が修学旅行で来ていました。丘に子どもたちの声が聞こえるのは、活気を感じていいものです。
そうはいっても、小規模校だったのか伸び伸びと時間が足りないくらいになってしまいました。
特に感心したのは、「ありがとうございました」と一人一人が言葉をかけて帰って行ったことです。ガイドにとっては、何よりの御馳走です。
登別の「時代村」によ . . . 本文を読む
住居の入口がまっすぐになっていた。中に入ってみたが、柱は、まだ大丈夫のようだ。出るときに頭を上の垂木にぶつけてしまった。悪いことを思っていたからだろう。出るときに来園者は頭をぶつける。 . . . 本文を読む