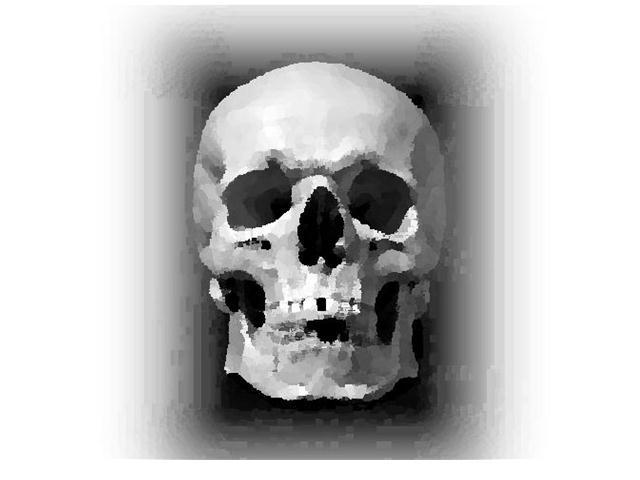北黄金・物語(煮炊き)
土器は「煮炊きの用具」
実際に縄文土器で煮炊きをした人がいるだろうか。
今まで縄文土器で煮炊きをした実践を見ているがお湯は沸騰までしない。
最後は焼けた石をいくつか入れて沸騰させる。
それから土器は煤で真っ黒になっている。
今見ている遺物の縄文土器は真っ黒になっていない。一部に黒いところがあったとしてもあれは祭祀用の行為であろう。
とにかく煮炊きして黒く煤 . . . 本文を読む
北黄金・物語(はじめに)
縄文土器の解読を試みて縄文人の生き方や感じ方が少し分かってきた気がします。
何分にも事例も証拠もない解読をしてきました。
解読してきた縄文の見方を再度、北黄金貝塚の遺物に焦点を合わせて考えてみるつもりです。
縄文人の視点に合わせて北黄金貝塚の遺物、遺構の解説ができるでしょうか?
「縄文物語」と題して何回か続けたいと思います。
何しろ「縄文楽 . . . 本文を読む
この土器の解説は模様が理解できなくて無理だと思っていました。
「北黄金2遺跡(北側の丘)の発掘調査の画像を見て気づいたことがありました。
この遺跡には、貝塚もありお墓も出土している丘です。向かい側の丘になります。
下の画像が発掘したときの堆積層です。
「駒ヶ岳火山灰」は1640年の駒ヶ岳の大噴火で山頂が崩壊したときに海を越えて降ったといいますが、その時の津波が押 . . . 本文を読む
縄文土器の模様で「縄文」(海)が上にあるのに戸惑いを覚える。
「縄文」と思っていたところは、「草地」と仮定しました。
角ばっている印は「樹木」と想定しています。
口縁の無地の所が見られますが「祭祀場」として考えると「貝塚」が当てはまるように思えます。
丸い穴が空いているのは、土器を補修して再利用を試みたと言えます。
課題を含んだ土器と言えます。補修をしながら大切に使用して . . . 本文を読む
この土器の体型は「筒」でなく「鉢」に似ています。深い海との関わりが少ないことを示しているのです。
模様も「波」と思っていましたが、土器の上から下まで「波」とは考えられない。津波とも浮かんだが現実性が低い。
だが、調べてみる可能性は残る。
海岸が遠のいて砂丘化した時期の土器と想像できます。
実際に砂丘は海岸線に平行に4本あると聞いています。
仮説としていくつか挙げてみました。
「草地 . . . 本文を読む
北黄金貝塚公園の「水場の祭祀場」と呼んでいる場所が土器の面に描かれているようです。
少し青っぽい所が見られます。これは、土器の修復時に付けられたと迷うとこですが当時のものと考えます。
なんと、青い所が湧き水近くの「水場の祭祀場」が当てはまるのです。「ヒスイ水」と勝手な呼び方ですが、重要な意味を含んでいるのです。油に関係があるのか検証はしていませんが驚きの事実と期待しています。
「命の水 . . . 本文を読む
円筒型をしている北黄金貝塚の縄文土器です。上下の「山と海」に分かれれています。
山の部分では、幾何学的模様が独特です。海は縄文模様に見えますが、拡大して見ると「クサビ状」の模様に見えます。
通常の縄文(波)の模様でないのが気になります。
「海」の模様はどのようにして施文したのだろうか。波を表現したのだろうが、方法は未解決です。
きっと、下地に繊維を織り込んでいるようなのです。繊維土器と . . . 本文を読む
北黄金貝塚の土器に「縄文は縄目」と異なる模様もあるようだ。土器形態の基本は「深い海との生活」であり茶筒型の円筒土器である。長めの円筒土器を基本にして考えていきます。
「草地」は横線の波を打つような感じで模様が付けられています。草地の中間地点あたりに少し薄くなった所が見られます。これを「祭祀場」と考えています。
「貝塚」が当てはまるようです。また、湧き水の近くにある無地の所を「石 . . . 本文を読む
長い形の土器です。腰が少し曲がっている様に見えます。
円筒型土器として何の不思議さもなく見ていましたが、模様が不可解なのです。
土器を上下に「山・海」に二分化して検証しますが、手が止まりました。
山も海も同じ施文具で模様が付けられているのです。「山・海」が海という設定には普通はならないので、山として扱うしかないのかと思いました。この土器は「山」の生活をする人の土器と言えます。 . . . 本文を読む
北黄金貝塚では「湧水」が今でも3か所もあります。
「縄文の丘」の風景を説明できそうな土器があります。
上部は「山(丘)」で下部は「海」と設定しています。
丘にある「草地」の模様が「ススキやササ」のように風になびいている様に感じます。
「貝塚」(聖地)としたのは無地で模様を描かないか消しています。命を失った物の意味だと思います。
「丘に貝塚が広がっているという風景です。」
. . . 本文を読む