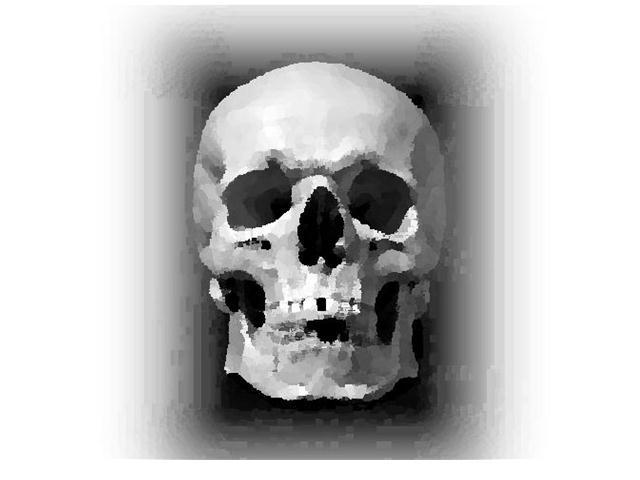縄文楽・貝塚=星座
星の輝いて見える 夜空を見上げる。
北黄金貝塚の 丘の上には広々とした貝塚が 白く浮かんで見えることだろう。
縄文時代に人々は太陽が西に沈むと丘で火を炊いて その周りに集まり一族のことを語り合ったりしたことだろう。
天空の星空をどのように眺めていただろう。
❮フランスのラスコー壁画(1万5千~1万年前)に描かれたいくつかの黒い点々が、おうし座のスバルを、また夏の大 . . . 本文を読む
縄文の心
「縄文の心」とは
「全てが生きる」ということなのです。
その証拠として 両手を 合わせた「合掌 の姿」があります。
それは片方の手は「 自力」で、もう一方の手は「他力」とこれを自他共に合わせると「合掌の姿」で「縄文の心」と考えています
ところで 三内丸山遺跡に巨大な6本柱があります。
これも 両手を 合わせる合掌の姿と思えるのです。
これは 10本指を6本に省略 . . . 本文を読む
縄文余話・世界観
縄文人と現代人と世界観がそんなにちがうものだろうか
縄文人を特別扱いしている感じがする。
「縄文楽」は縄文人と現代人とちがいないという意識で 特別扱いは していない。
世界観は縄文人と現代人と変わりない同じ人間であると考えている。
縄文人と 現代人の世界観というものを比較できないものだろうか。
まず 述べる前に「世界観」を自分なりに . . . 本文を読む
能登半島に 震度7 という大地震が発生した。
縄文土器にも 断層のある 土器が見られる
これは、日本列島の継ぎ目と言われるフォッサマグナの谷に沿って日本海に注ぐ姫川の河口から南東へ約三キロ、標高九十メートル前後の丘陵上に位置する、縄文時代中期の集落遺跡です。
ヒスイの産地でもある。
この土器を見て「口縁」がずれていた。人為的にずらしている . . . 本文を読む
縄文余話・世界観
縄文人と現代人と世界観がそんなにちがうものだろうか
縄文人を特別扱いしている感じがする。
「縄文楽」は縄文人と現代人と そんなにちがいないという意識で 特別扱いは していない。
意識は縄文人と現代人と変わりない同じ人間であると考えている。
現代人と 縄文人のちがいが多少あることは認めるが。
縄文人と 現代人の世界 . . . 本文を読む
縄文余話・人間の行動
進化論から言えばアメーバから人間に進化したと言われている
人間の行動を同じように進化と思われる順で考えてみた
三種類の人間の生活行動を設定して進化と思う順で考えてみました。
三種類の人の行動とは
・本能的行動 本能から発する行動
・生活的行動 生きるための行動
・遊び的行動 . . . 本文を読む
縄文余話・現代人思考
現実に縄文土器はたくさん存在する。
その中でも火焔型土器 の器面からは派手に踊った感じの変化が見られる 。
器形や模様の着想は 思いもつかないので現代人は神話的思考といってしまう。
縄文人思考でなく反対の現代人思考でないのか。
現代人思考が縄文土器を煮炊きの鍋と決めて解釈してしまったと思う。
縄文時代の人の立場になって考えられなかったといえる。
次の土器はどうだ . . . 本文を読む
縄文土器・湖底・送り
1、はじめに「土器が見つかったのは本栖湖の東南岸、沖合い50m、水深5〜15mの場所でした。」
「湖底から発見された土器はその形を残したままの状態だった。」
2、土器の解読
「なぜ湖底から大量の土器が、しかも形状が保たれたまま発見されたのか。」
水は命を 産み 育てる 源と思われます。
その水が湖となって大きな器状(土器の形)で存在していま . . . 本文を読む
縄文余話・地・形
1、はじめに 縄文土器というのは、 その地域の 地形、環境 を土で形に作り環境を模している ものと考えています。
しかし、土器の器形はどこから姿に現れるのか?
これが問題でしたが、実際には、目に見たものしか描けないはずだと気がついたのです。
2、土器の解読
今、北黄金貝塚の丘に立って見えているものは何か
箇条書きに書いてみました。
①見えるモノは
・ . . . 本文を読む
縄文余話・蝶形・サカナ
「蝶形骨製品はジュゴンの骨を加工してチョウの形をなすもので、沖縄県でみられる特徴的な遺物です。その用途は装身具としての利用のほかに、何らかのシンボル的な要素があると考えられています(島袋 1991)」以上は説明文です。
沖縄県は海となれば、サンゴにサカナがうかびます。
この骨製品はサカナと考えました。
口に特徴のあるサカナかな?
見たものしか製作できないと作品 . . . 本文を読む