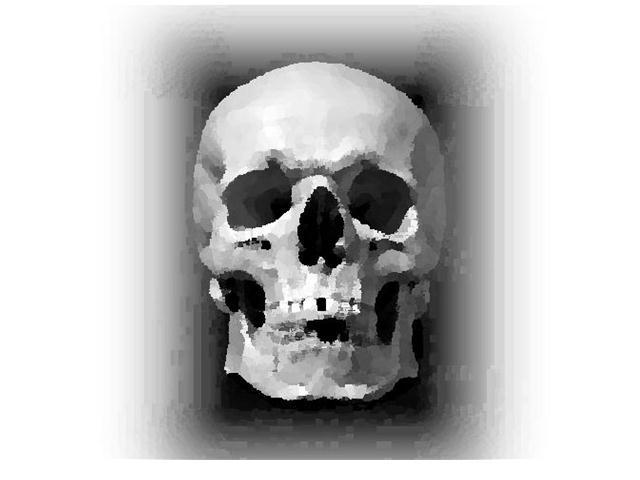天の川天の川は年中見えるのかと思っていたがそうでなかった。
夏と秋が良く見える。
環状列石 に大きい円と少し小さい円がセットになってると思っていた。
つまり よく見える時とそうでない時の2つの時期の 天の川(銀河) かもしれないのだ。
他の意味があるとも考えれないか。
課題になるが今は夏と冬二つの時期のちがいと設定しておく。
環状列石は天の川(銀河)をモデルにしたことも . . . 本文を読む
見たものを作る(天の川)
最近 夜の星空の銀河の存在を意識するようになって今までの縄文観が変化してしまったような気がする。
ナスカの地上絵まで銀河としてしまった。
それは、貝塚の形がセンベイ状になっていると思うからだ。
東京湾の加曽利貝塚は広大なセンベイ状を呈しているようだが銀河をモデルにしているかもしれない。
この考えは何の根拠もないと言われるかもしれない。
貝塚は銀 . . . 本文を読む
亀ケ岡土器地上に楽園を作るには あの世の楽園である「銀河」を地上に作ろうと考えています。
宇宙を土器で作って再生を願うと考えるのです。
ここに漆塗りの真っ黒な丸みを帯びた土器が中央にあります。
当初は太陽土器と思っていましたがどうも真っ黒な宇宙に星が浮かぶ天球を表現している気がするのです。
唐草模様は「銀河」とか「星座」などと想像してみました。
土器の首の部分は天 . . . 本文を読む
見たものを作る(土器)
福満虚空藏菩薩 円蔵寺
「福島県柳津町は町内で出土した推定約5000年前の縄文土器を復元した結果、取っ手部分に土偶2体が装飾された珍しい形状をしていることが判明したと発表した。」
解説文です。
当時の縄文人は当然 見ている風景なのです。そこで 何を見てこのような土器を作っているのかネットで風景を探すのです。
崖の壁面に張り付くように作られたお寺の画像がありまし . . . 本文を読む
見たものを作る(姿)
人間は物を作る時には 実際に目で見たものを作っていると考えています。
縄文時代に「土偶」も「土器」も 形や模様など目で見たものを作っている ことになるのです。
「土偶」は生きものの効き目を人化にした姿に作っているのです。
「土器」は地形を器形に作り環境は模様として表現しているのです。
これらのものは常に普段も目で見ているものです。
今 考えていることは環状列石 で . . . 本文を読む
縄文余話 銀河・列石・輝き
環状列石が銀河をモデルにしていたなら どの遺跡からでも同じ方角や模様も同じに造られていることになるだろう。
その後は各地域の人々がどのように銀河をながめてデホルムしてデザインしているかのちがいである。
おもしろい!
何を言われても見る気になれば誰でも 実物の銀河が夜空に輝いている。
立石のある時計型サークルは銀河の光の強い耀き部分を表現していると思います。
. . . 本文を読む
縄文余話(三内・銀河)
三内丸山遺跡遺跡全体が「送り場」の雰囲気です。
星空の「銀河」をながめて送りをしたと思います。
だれもが同じ夜空の原画を見ています。
「 銀河」を地上に 作るのです。
そして、生きる場である
というようなことにならないか
・再生を願う場・あの世に送る場・生きる場・生産する場 など
昼間の三内丸山遺跡を考えて . . . 本文を読む
縄文余話(大湯環状列石・銀河)
大湯川左岸の台地に営まれた縄文時代後期の大規模な祭祀遺跡です。
万座、野中堂の2つの環状列石が代表的な物で、ほかに環状、方形などの配石があります。万座環状列石の直径は52m、野中堂環状列石は42mで、これらを囲むように掘立柱建物跡があります。
環状列石は、十数個の組石遺構が群をなし二重の環状に配置されており、それを囲んで規則的に配置された掘立柱建物は、 . . . 本文を読む
縄文余話・環状列石(伊勢堂岱遺跡)
「伊勢堂岱遺跡は、秋田県北秋田市脇神にある縄文時代後期(約4,000年前)の環状列石を主体とする遺跡です。 国内では唯一、4つの環状列石が発見され、遺跡の保存状態がよく====」
以上が解説文です。
これも何を見て作ったのか想像するのです。
このような大きな遺物は星空をながめて作ったと考えました。
私たちは「銀河(天の川)」をじっくりながめることは . . . 本文を読む
縄文余話・貝塚と天の川
北黄金貝塚公園には 貝塚が 二つ特徴的なのがあります
1つは 6000年前と言われる 縄文前期のハマグリのB貝塚です
これは 丘の頂上に「マンジュウ状」に 盛られているように堆積して作られています。
もう1つは 4500年前の縄文中期のA 貝塚です
カキとウニが交互に 丘の上に巾広く「センベイ状」にベタッと堆積してい . . . 本文を読む