裁判所に勤務して刑事裁判の法廷に出ていたとき、自動車運転過失致死傷罪の裁判で、「不幸な事故」という単語をよく耳にしました。主に弁護人の最終弁論の中で使われる単語です。私も最初の頃は、この「不幸な」という単語の中に、言葉にならない万感の思いが凝縮されているように感じていました。幸・不幸の感情は人間だけが持ち得るところ、非人称の「事故」という抽象名詞に対して「不幸な」という形容詞句が冠せられていることが、言語の限界に突き当たった人間の苦悩であるように感じたからです。
ところが、次々と「不幸な事故」が流れ作業のように目の前を過ぎてゆくうちに、私の認識は徐々に変わってきました。言葉に思いを込めるということは、人間が言葉を自由自在に操れるという前提に立っているわけですが、この認識自体が転倒しているように思われてきたからです。
私の狭い経験からですが、事故で最愛の人を失った者の万感の思いは、「不幸な事故」という言葉で納得させられることはまずありません。人間の細かい心の襞のようなところを絞りに絞って単語を厳選した場合、「不幸な」という修飾語は失格だということです。
私がこれまで聞いた中で、現実を言語によって正確に描写していると感じた表現には、「全身を踏みつけられて内臓を引っぱり出されている状態」「魂を抜かれた人間の抜け殻が自殺もできずに虚脱している状態」「心の底から笑ったり喜んだりすることは一生できず、してはならず、したくもない状態」などがありました。そこでは、「事故」という非人称の出来事は脱落し、「死者の無念」という表現すら比喩の限界に耐えることができず、消去法によって、遺された者がその状態を他人事のように記述しているものだけが残っているように感じます。
ところが、刑事裁判の法廷という場は、上記のような人間の苦悩の正確な描写を好みません。裁判の品位や、法廷の権威の維持といった要請からは、「不幸な事故」のような当たり障りのない表現のほうに圧倒的に分があるからです。私も刑事裁判の法廷において、自分の「起立!」の一声で満員の傍聴席が新聞記者も含めて一斉に立ち上がるなどの経験を通じて、この権威の力を肌で感じてきました。
起訴状が朗読され、黙秘権が告知される頃には、もはや儀式の場に相応しくない言語のほうが非常識に感じられてきます。「不幸な事故」は品位のある言葉であるのに対し、「魂を抜かれた人間の抜け殻が自殺もできずに虚脱している状態」は品位のない言葉となります。そして、弁護人の最終弁論において、「本件は一瞬の不注意による不幸な事故であり被告人は二度と事故を起こさないことを誓っている」「被告人は不幸な事故を乗り越えて立派な社会人として更生することを決意している」などと述べられ、法廷はつつがなく終わります。
私は現在、法律事務所で最終弁論を書くほうに回っていますが、「不幸な事故」という単語の使い勝手の良さに改めて驚かされています。刑事裁判のテーマは事実認定と量刑であり、執行猶予の相場を調べる仕事などに追われている際には、個々人の内心に立ち入っている暇はありません。また、量刑の前提となる示談における慰謝料の額ですら、過去の事例を検索して妥当な金額をはじき出すシステムが確立されており、実際に精神的苦痛を感じている者の内心を深く掘り下げることは、事務処理上有害となります。
もちろん、世の中の問題は法律などで解決できないものの方が多く、客観的・科学的言語はすぐに行き止まりとなります。そこで、「不幸な事故」という単語の出番がきます。恐らく、全国で忙しく働いている弁護士は、山積みの仕事を効率よく終わらせるために、自動車運転過失致死傷罪の最終弁論の難しいところは「不幸な事故」で片を付け、先に進んでいることが多いのでしょう。
私が現在、自分自身に対して恐れていることは、「不幸な事故」という言い回しに対して、感覚が麻痺してしまうことです。特に、裁判が終わって判決も確定し、事故が社会的には過去のものとなったとき、つい世間的な枠組みに流されそうになります。世間的な幸・不幸の基準からすれば、事故を克服して立ち直ることは幸福であり、事故が乗り越えられずに立ち直れないことは不幸です。そして、事故それ自体の衝撃は過去の歴史的事実として人々の記憶から消えていくとなれば、「不幸な」という形容詞は、事故を離れて、人間に取り付くことが避けられなくなります。
そして、「不幸な被害者遺族」に対して、幸福にならなければならないという無形の暴力が生じるのは、この場面であると思います。「いつまでも悲しんでいると亡くなった人が浮かばれない」「恨みや憎しみからは何も生まれない」という励ましに対する違和感は、「不幸な事故」という表現に対する違和感と似ているような気もします。
ところが、次々と「不幸な事故」が流れ作業のように目の前を過ぎてゆくうちに、私の認識は徐々に変わってきました。言葉に思いを込めるということは、人間が言葉を自由自在に操れるという前提に立っているわけですが、この認識自体が転倒しているように思われてきたからです。
私の狭い経験からですが、事故で最愛の人を失った者の万感の思いは、「不幸な事故」という言葉で納得させられることはまずありません。人間の細かい心の襞のようなところを絞りに絞って単語を厳選した場合、「不幸な」という修飾語は失格だということです。
私がこれまで聞いた中で、現実を言語によって正確に描写していると感じた表現には、「全身を踏みつけられて内臓を引っぱり出されている状態」「魂を抜かれた人間の抜け殻が自殺もできずに虚脱している状態」「心の底から笑ったり喜んだりすることは一生できず、してはならず、したくもない状態」などがありました。そこでは、「事故」という非人称の出来事は脱落し、「死者の無念」という表現すら比喩の限界に耐えることができず、消去法によって、遺された者がその状態を他人事のように記述しているものだけが残っているように感じます。
ところが、刑事裁判の法廷という場は、上記のような人間の苦悩の正確な描写を好みません。裁判の品位や、法廷の権威の維持といった要請からは、「不幸な事故」のような当たり障りのない表現のほうに圧倒的に分があるからです。私も刑事裁判の法廷において、自分の「起立!」の一声で満員の傍聴席が新聞記者も含めて一斉に立ち上がるなどの経験を通じて、この権威の力を肌で感じてきました。
起訴状が朗読され、黙秘権が告知される頃には、もはや儀式の場に相応しくない言語のほうが非常識に感じられてきます。「不幸な事故」は品位のある言葉であるのに対し、「魂を抜かれた人間の抜け殻が自殺もできずに虚脱している状態」は品位のない言葉となります。そして、弁護人の最終弁論において、「本件は一瞬の不注意による不幸な事故であり被告人は二度と事故を起こさないことを誓っている」「被告人は不幸な事故を乗り越えて立派な社会人として更生することを決意している」などと述べられ、法廷はつつがなく終わります。
私は現在、法律事務所で最終弁論を書くほうに回っていますが、「不幸な事故」という単語の使い勝手の良さに改めて驚かされています。刑事裁判のテーマは事実認定と量刑であり、執行猶予の相場を調べる仕事などに追われている際には、個々人の内心に立ち入っている暇はありません。また、量刑の前提となる示談における慰謝料の額ですら、過去の事例を検索して妥当な金額をはじき出すシステムが確立されており、実際に精神的苦痛を感じている者の内心を深く掘り下げることは、事務処理上有害となります。
もちろん、世の中の問題は法律などで解決できないものの方が多く、客観的・科学的言語はすぐに行き止まりとなります。そこで、「不幸な事故」という単語の出番がきます。恐らく、全国で忙しく働いている弁護士は、山積みの仕事を効率よく終わらせるために、自動車運転過失致死傷罪の最終弁論の難しいところは「不幸な事故」で片を付け、先に進んでいることが多いのでしょう。
私が現在、自分自身に対して恐れていることは、「不幸な事故」という言い回しに対して、感覚が麻痺してしまうことです。特に、裁判が終わって判決も確定し、事故が社会的には過去のものとなったとき、つい世間的な枠組みに流されそうになります。世間的な幸・不幸の基準からすれば、事故を克服して立ち直ることは幸福であり、事故が乗り越えられずに立ち直れないことは不幸です。そして、事故それ自体の衝撃は過去の歴史的事実として人々の記憶から消えていくとなれば、「不幸な」という形容詞は、事故を離れて、人間に取り付くことが避けられなくなります。
そして、「不幸な被害者遺族」に対して、幸福にならなければならないという無形の暴力が生じるのは、この場面であると思います。「いつまでも悲しんでいると亡くなった人が浮かばれない」「恨みや憎しみからは何も生まれない」という励ましに対する違和感は、「不幸な事故」という表現に対する違和感と似ているような気もします。










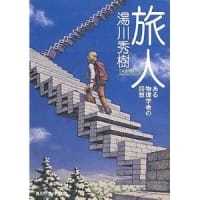
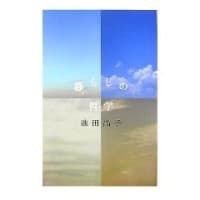
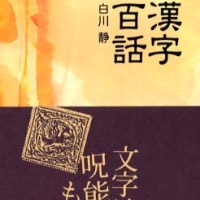
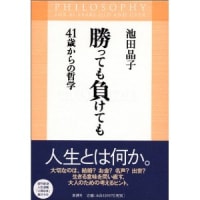
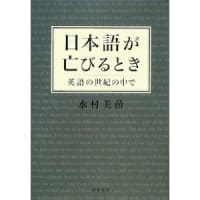
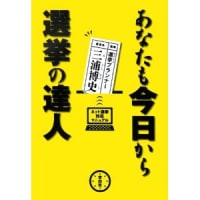
法の世界では、量ることの出来ない感情などは不要であり邪魔でしょうね。
不幸って何ですか?この問いに
「幸福では無いこと」と解釈すれば簡単ですね。
幸福のカタチはほぼ似ているわけですから、それの打ち消しをすれば、同じイメージの答えが得られるでしょう。
では実際にどんな気持ちのことを言うのですか?と、改めて不幸を主体に考えてみると
不幸によってカタチがそれぞれ違うということに初めて気がつきますね。
自分の不幸は 命同様に特別なものです。
法の世界が、
人間の尊厳とも思える感情部分の限界を知った上で、敢えて感情抜きにした言葉に限定しているのことが少しでも伺われるなら、同じ裁きでもまた違った印象を残すのかもしれないですが
初めから 不幸の主体が全く感じられないようなことであれば、極端な話、人間でなくても、機械にデータでも入れて裁いてもいいような・・・と冷めた気持ちになります。(世間を知らない私のたわごとです。)
「不幸な事故」という表現ではなく3つほどこれまでの印象に残っている表現を挙げていらっしゃいますね。読解力がない私なので、敢えてお聞きしますと、それは弁護側の表現なのでしょうか。
私は事件柄、被告人の罪状は少しずつ違うものの、何度も弁護側最終弁論や判決を聞いてきました。判決は恐ろしいくらい似た表現でした。被告人の名前だけを入れ替えているんじゃないかと思ったくらいです。
何人もの遺族が証言した時もそうです。誰も彼も同じような悲しみ無念の思いを引き出させる尋問が為されます。つい最近まで私は、私の悲しみとあの遺族の悲しみは違うだろうに、と思っていたものです。
でも、もし雄弁な弁護人による表現力豊かな、裁判所に対して説得力ある弁論によって刑罰が左右されるとしたら、遺族としてはこれほど悔しいことはありません。
あくまで証拠に基づく判決である以上、起きてしまった事実を修飾する巧みが表現は、弁護側には必要ないような気がします。
ただ、こういう一括りにする表現に感覚が麻痺してしまうのではないかと心配していらっしゃることに私は安堵しました。
法曹関係者の皆さんが同じであることを願っています。
「幸福な家庭はみな似通っているが不幸な家庭は不幸の相も様々である」というトルストイの有名な一節が、今さらながら残酷な真実のように思い出されます。
人間の実存が、情緒的存在として世界に投企され、言語的意識によって共同性に開かれている限り、人が言葉によってわかり合えたのであれば、それはいかなる場面においても、情緒的な同調の積み重ねから逃れることができないように思われます(ハイデガーの受け売りです)。
そして、情緒的な同調の限界を超える不幸の場合には、「言葉がどうしても通じない」ということになるのだと思います。これは、全く経験のない人に対して通じない場合と、似たような経験をしているのに通じない場合があって、そのどちらも派生的な絶望を生んでいように感じます。一般には、前者は「幸福に誘導するお節介」で、後者は「反論せずにはいられない憤慨」の形を取るのでしょうか。
不幸が情緒的な同調の限界を超え、言語的意識による共同性を求めて足掻いているとすれば、それは既存の言語によって、投企されている方向性の同調を求めているのだと思います(これもハイデガーの受け売りです)。ここに言語の齟齬の可能性が生じることを知っているのであれば、あえて「幸福に誘導するお節介」や、「反論せずにはいられない憤慨」を行う必要もないのでしょう。
世界の相互自己投企がこのようなものである限り、「言葉がどうしても通じない」という経験はお互い様でしょうが、なぜかすぐに他者を攻撃する人と、攻撃されても反撃しない人がいるようですね(笑)。このような攻撃が相互に人生の足場の崩し合いになることを知る人は、すべてを飲み込んで耐えるのでしょう。そこでは、孤独を怖れることもなく、言葉が通じたときの喜びだけが残されているように感じます。
私が挙げた3つの印象的な表現は、裁判とは全く関係のないところで読んだものです。現在の日本の法廷では、まずお目にかかれない表現でしょうね。法律家は言葉を操るプロだという自負がある者にとっては、これらの表現は断じて許し難いでしょう。法律用語は正確かつ冷静であり、日常用語は不正確かつ感情的であることが大前提だからです。
確かに、判決は恐ろしいくらい似た表現です。弁護側の弁論が「不幸な事故」なら、検察側の論告は「死者の無念は察するに余りある」で、判決は「遺族の被害感情は激烈である」に決まっています。刑事裁判において、情状は事実認定よりも一段低いので、法曹関係者は型通りの言い回しを変える必要性を感じていないようです。その意味で、被告人の名前だけを入れ替えているというのは、本当だと言えば本当でしょう。
雄弁な弁護人による表現力豊かな、裁判所に対して説得力ある弁論によって刑罰を左右することは、弁護人の仕事そのものです(笑)。特に私選弁護人にとっては、技巧を駆使して裁判所の刑罰を左右するくらいでなければ、国選弁護人と何ら変わらないということになり、3倍~5倍の報酬をもらう根拠がなくなってしまうので、真剣そのものです。
ですので、ここは犯罪被害者を法廷に入れたくない刑事弁護のシステムの急所であり、弁護士会が犯罪被害者の意見を絶対に聞き入れない部分だと思います。そして、ここから眼を逸らしたまま、「被告人の人権と被害者の人権は両立する」と言っても、やはり欺瞞に過ぎないでしょうね。「復讐心や憎悪からは何も生まれない」という一括りの表現も、人間の複雑な感覚を麻痺させるようで、私は好きではありません。