都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「日本のルソー 横井弘三の世界展」 練馬区立美術館
練馬区立美術館
「没後50年 日本のルソー 横井弘三の世界展」
4/17~6/5

練馬区立美術館で開催中の「没後50年 日本のルソー 横井弘三の世界展」を見てきました。
白髪を靡かせては口を開く一人の老人。頬は丸みを帯び、無数の皺が目筋と鼻筋を覆っています。右手で一切れのスイカを持っていました。既に殆ど食べ尽くしてしまったのでしょう。実は少なく、皮の部分が残っているに過ぎません。
やや無表情ながらも、どこか奔放な性格、ないしは人となりが伝わって来ないでしょうか。彼こそが今回の主人公である横井弘三。画家の自画像です。明治22年に長野の飯田に出生。その後、大正、昭和を通して、自らの意の趣くまま、表現の為すままに絵を描き続けました。
さてタイトルの「日本のルソー」。それを思わせる作品から展覧会も始まります。「花籠もてる子供」です。前景には二人の女の子。まっすぐ前を見ながら立っています。手にぶら下がるのは花籠です。背後には鬱蒼とした緑。小道の先に家が見えます。正面性の高い構図による花籠はボーシャンのようです。人形のような女の子の姿からはルソーを連想させる面も否めなくありません。
3歳の時に家族ととも上京した横井。大学を中退して独学で絵を学びます。大正4年には第2回二科展へ出展。新人賞である樗牛賞を受賞しました。続く第3回では二科賞を受賞。作品は「極上々機嫌」、ないし「微笑みを誘う、稚拙な味」(ともにキャプションより)として高い評価を得たそうです。
南の島への憧れがありました。大正期に父島へ旅行。3ヶ月滞在します。結果的に2度、小笠原に渡っては同地の風俗をスケッチや絵画に残しました。「カヌーのある港」も小笠原が舞台です。島の入江でしょうか。かなり引いた構図です。高い位置から俯瞰して描いています。海には多くのカヌーが浮かんでいました。小さな人影も見えます。レースの光景を表しているのかもしれません。

横井弘三「クジラのオモチャ」 1925年頃 個人蔵
早くから画壇で成功を掴んだ横井。しかし大正12年の関東大震災によって転機が訪れます。被災した子供たちを元気つけようと考えた横井は、自作を東京と横浜の小学校に寄贈し始めました。その名も「復興児童に贈る絵」です。モチーフは玩具や人形。子どもの身の回りのものを描いています。そして横井は一連の作品をまとめて二科展へ出品。ただしどういうわけか陳列を拒否されてしまいます。それを不服として二科展を離れてしまうのです。
画壇によほど幻滅したのでしょうか。横井はこの後、挑戦的ともいえる行動に出ます。「理想展」の設立です。二科展に対抗すべく、無審査、自由出品のアンデパンダン展を開催しました。
その際に宣言した「美術の革命」のテキストが凄まじい。「二科展は鑑別に残酷な態度をとり、無名作家をバカにし、差別主義者の固まりである。」とするなど、もはや過激とも言うべき表現を用いて攻撃しています。二科展関係者が読めば怒るのも無理はないかもしれません。
さらに「美術の革命そらきたぞ、上野の杜は火の嵐。」といった美術の革命歌なるものまで創作。相当に熱が入っています。ほかにも帝展の会場前で自らの落選作をあえて展示する行為にも出ます。ともかく既存の美術界に対して反発を繰り返しました。
とはいえ、横井は何も隠遁生活を送ろうとしていたわけではありません。意外なのはあれほど揉めた二科展に再度出品を試みていることです。「輝く夜景」です。輝くとはいえ、画面はまるで木版の版木のように黒い。ビルが立ち並ぶ都会の夜景を描いています。空には白や赤のネオンサイン。川面に反射していました。建物の壁は薄汚れているようにも見えます。場所は不明ですが、ひょっとすると大阪でしょうか。橋の上にはたくさんの人も行き交っていました。
横井は自らの信条なのか、絵を売らずに、古本屋や露店業などで生計を立てていました。また宮沢賢治の童話「グスコーブドリの伝記」の挿絵の仕事にも携わります。こうした半ばバイタリティーのある活動に共感した人物も少なくなかったそうです。

横井弘三「浅間山風景」 1949年頃 長野県信濃美術館
終戦の一年前、支援者の一人である画家の山崎武郎の招きで長野へ疎開。定住します。終戦後は長野工業学校の教員も務めました。生活も安定したことでしょう。以降、晩年の20年間は、地元の支援にも恵まれて旺盛に制作するようになりました。
学校や子どもを描いた作品が目立ちます。例えば「開校を祝して」は篠ノ井高校の開校の際に描いたもの。手前は千曲川でしょうか。赤いトラス橋も見えます。彼方には学校の校舎が望めました。手前には一人の老人。スケッチしています。横井本人かもしれません。その様子を子どもが覗き込んでいます。白い雲に水色の空。どこか開放感のある作品でもあります。
「楽しく遊ぶ子供達」の舞台も学校です。校庭でブランコに乗ったり、輪になって踊る子どもたち。空には鯉のぼりが泳いでいます。さらに「音楽室にて」では学校の音楽の授業の様子を描きました。中央にはグランドピアノ。先生が座っています。合唱の時間でしょうか。たくさんの子たちが皆、楽しそうに立っています。壁には音楽室では欠かせない作曲家の肖像画もずらりと並んでいます。誰もが一度は見た光景です。どことない郷愁も感じられました。
一時、長野を離れ、各地の支援者の元を訪ねながら絵を描いたこともあったそうです。「人生乃春」は広島の三原。現地の紡績工場を表しています。立ち並ぶ煙突越しのパノラマ。時期は春。花見の季節です。ゴザを敷いては宴会している人の姿も見えました。
マッカーサーに贈ったという「天工礼讃」も目を引きました。信州の里山を描いた一枚。横3メートル50センチです。かなり大きな作品です。屈曲してはのびる描線。まるで綿菓子のような雲が浮かんでいます。広がる田畑はまさに長閑。姥捨山あたりの光景だそうです。下部にテキストが付随していました。うち一節には「戦争では負けたが、美術では負けない。」の文言があります。かつての画壇に対して見せたような気概は歳を重ねても変わっていません。

横井弘三「月夜の踊り」 1956年 信州大学教育学部付属長野小学校
油彩を基本としながらも、木版、水彩、ペン、漆絵にガラス絵など、様々な技法に取り組んでいるのも横井の特徴と言えるかもしれません。とりわけ興味深いのは焼絵です。板や厚紙の表面を焦がし、さらに焦げ目で線を描いては、水彩やクレパスで仕上げるという焼絵。表面に独特の凹凸があります。かなり多くの作品を残しました。
「三輪の向日葵/飯綱山」でも焼絵の技法を用いています。タイトルが2つあるのは衝立だからです。つまり表に向日葵があり、裏面に山が描かれています。力強く、生命感に溢れた向日葵。それでいてやや妖しげな雰囲気があります。すぐさまゴッホを思い出しました。実際に横井はゴッホの影響を受けています。ゆえに向日葵のモチーフも多数。うねるような筆触はゴッホにも共通するものがあります。
76歳で亡くなった横井の作品の多くは個人蔵です。没後、堀内誠一らのイラストレーターに再評価されるものの、その後に忘れられてしまったこともあるそうです。
絵画「ひまわり」に記された「私は原始人の如く、子どもの如く、楽天的な世界に生きたい。」の言葉が印象に残りました。出品は200点。(展示替えあり)さらに資料が加わります。戦前の作品は戦火により失われてしまったものも少なくありませんが、晩年の長野の作品の多くは大切に保存されてきたそうです。

横井弘三「郷土玩具の品評会」 1961年 個人蔵
2008年には横井弘三のファンらによって「横井弘三とオモチャン会」なる会が結成されました。「オモチャン会」とは横井自身が生前、子どものための創作玩具つくりを目指して組織したもの。その名にあやかり、子息の一郎氏の協力も得て、横井再評価を目指して作られました。

後々は所縁の善光寺界隈に記念館を設ける構想もあるそうです。東京での横井弘三復権の切っ掛けとなる展覧会と言えるかもしれません。

6月5日まで開催されています。
「没後50年 日本のルソー 横井弘三の世界展」 練馬区立美術館
会期:4月17日(日)~6月5日(日)
休館:月曜日。
時間:10:00~18:00 *入館は閉館の30分前まで
料金:大人800(600)円、大・高校生・65~74歳600(500)円、中学生以下・75歳以上無料
*( )は20名以上の団体料金。
*ぐるっとパス利用で300円。
住所:練馬区貫井1-36-16
交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。
「没後50年 日本のルソー 横井弘三の世界展」
4/17~6/5

練馬区立美術館で開催中の「没後50年 日本のルソー 横井弘三の世界展」を見てきました。
白髪を靡かせては口を開く一人の老人。頬は丸みを帯び、無数の皺が目筋と鼻筋を覆っています。右手で一切れのスイカを持っていました。既に殆ど食べ尽くしてしまったのでしょう。実は少なく、皮の部分が残っているに過ぎません。
やや無表情ながらも、どこか奔放な性格、ないしは人となりが伝わって来ないでしょうか。彼こそが今回の主人公である横井弘三。画家の自画像です。明治22年に長野の飯田に出生。その後、大正、昭和を通して、自らの意の趣くまま、表現の為すままに絵を描き続けました。
さてタイトルの「日本のルソー」。それを思わせる作品から展覧会も始まります。「花籠もてる子供」です。前景には二人の女の子。まっすぐ前を見ながら立っています。手にぶら下がるのは花籠です。背後には鬱蒼とした緑。小道の先に家が見えます。正面性の高い構図による花籠はボーシャンのようです。人形のような女の子の姿からはルソーを連想させる面も否めなくありません。
3歳の時に家族ととも上京した横井。大学を中退して独学で絵を学びます。大正4年には第2回二科展へ出展。新人賞である樗牛賞を受賞しました。続く第3回では二科賞を受賞。作品は「極上々機嫌」、ないし「微笑みを誘う、稚拙な味」(ともにキャプションより)として高い評価を得たそうです。
南の島への憧れがありました。大正期に父島へ旅行。3ヶ月滞在します。結果的に2度、小笠原に渡っては同地の風俗をスケッチや絵画に残しました。「カヌーのある港」も小笠原が舞台です。島の入江でしょうか。かなり引いた構図です。高い位置から俯瞰して描いています。海には多くのカヌーが浮かんでいました。小さな人影も見えます。レースの光景を表しているのかもしれません。

横井弘三「クジラのオモチャ」 1925年頃 個人蔵
早くから画壇で成功を掴んだ横井。しかし大正12年の関東大震災によって転機が訪れます。被災した子供たちを元気つけようと考えた横井は、自作を東京と横浜の小学校に寄贈し始めました。その名も「復興児童に贈る絵」です。モチーフは玩具や人形。子どもの身の回りのものを描いています。そして横井は一連の作品をまとめて二科展へ出品。ただしどういうわけか陳列を拒否されてしまいます。それを不服として二科展を離れてしまうのです。
画壇によほど幻滅したのでしょうか。横井はこの後、挑戦的ともいえる行動に出ます。「理想展」の設立です。二科展に対抗すべく、無審査、自由出品のアンデパンダン展を開催しました。
その際に宣言した「美術の革命」のテキストが凄まじい。「二科展は鑑別に残酷な態度をとり、無名作家をバカにし、差別主義者の固まりである。」とするなど、もはや過激とも言うべき表現を用いて攻撃しています。二科展関係者が読めば怒るのも無理はないかもしれません。
さらに「美術の革命そらきたぞ、上野の杜は火の嵐。」といった美術の革命歌なるものまで創作。相当に熱が入っています。ほかにも帝展の会場前で自らの落選作をあえて展示する行為にも出ます。ともかく既存の美術界に対して反発を繰り返しました。
とはいえ、横井は何も隠遁生活を送ろうとしていたわけではありません。意外なのはあれほど揉めた二科展に再度出品を試みていることです。「輝く夜景」です。輝くとはいえ、画面はまるで木版の版木のように黒い。ビルが立ち並ぶ都会の夜景を描いています。空には白や赤のネオンサイン。川面に反射していました。建物の壁は薄汚れているようにも見えます。場所は不明ですが、ひょっとすると大阪でしょうか。橋の上にはたくさんの人も行き交っていました。
横井は自らの信条なのか、絵を売らずに、古本屋や露店業などで生計を立てていました。また宮沢賢治の童話「グスコーブドリの伝記」の挿絵の仕事にも携わります。こうした半ばバイタリティーのある活動に共感した人物も少なくなかったそうです。

横井弘三「浅間山風景」 1949年頃 長野県信濃美術館
終戦の一年前、支援者の一人である画家の山崎武郎の招きで長野へ疎開。定住します。終戦後は長野工業学校の教員も務めました。生活も安定したことでしょう。以降、晩年の20年間は、地元の支援にも恵まれて旺盛に制作するようになりました。
学校や子どもを描いた作品が目立ちます。例えば「開校を祝して」は篠ノ井高校の開校の際に描いたもの。手前は千曲川でしょうか。赤いトラス橋も見えます。彼方には学校の校舎が望めました。手前には一人の老人。スケッチしています。横井本人かもしれません。その様子を子どもが覗き込んでいます。白い雲に水色の空。どこか開放感のある作品でもあります。
「楽しく遊ぶ子供達」の舞台も学校です。校庭でブランコに乗ったり、輪になって踊る子どもたち。空には鯉のぼりが泳いでいます。さらに「音楽室にて」では学校の音楽の授業の様子を描きました。中央にはグランドピアノ。先生が座っています。合唱の時間でしょうか。たくさんの子たちが皆、楽しそうに立っています。壁には音楽室では欠かせない作曲家の肖像画もずらりと並んでいます。誰もが一度は見た光景です。どことない郷愁も感じられました。
一時、長野を離れ、各地の支援者の元を訪ねながら絵を描いたこともあったそうです。「人生乃春」は広島の三原。現地の紡績工場を表しています。立ち並ぶ煙突越しのパノラマ。時期は春。花見の季節です。ゴザを敷いては宴会している人の姿も見えました。
マッカーサーに贈ったという「天工礼讃」も目を引きました。信州の里山を描いた一枚。横3メートル50センチです。かなり大きな作品です。屈曲してはのびる描線。まるで綿菓子のような雲が浮かんでいます。広がる田畑はまさに長閑。姥捨山あたりの光景だそうです。下部にテキストが付随していました。うち一節には「戦争では負けたが、美術では負けない。」の文言があります。かつての画壇に対して見せたような気概は歳を重ねても変わっていません。

横井弘三「月夜の踊り」 1956年 信州大学教育学部付属長野小学校
油彩を基本としながらも、木版、水彩、ペン、漆絵にガラス絵など、様々な技法に取り組んでいるのも横井の特徴と言えるかもしれません。とりわけ興味深いのは焼絵です。板や厚紙の表面を焦がし、さらに焦げ目で線を描いては、水彩やクレパスで仕上げるという焼絵。表面に独特の凹凸があります。かなり多くの作品を残しました。
「三輪の向日葵/飯綱山」でも焼絵の技法を用いています。タイトルが2つあるのは衝立だからです。つまり表に向日葵があり、裏面に山が描かれています。力強く、生命感に溢れた向日葵。それでいてやや妖しげな雰囲気があります。すぐさまゴッホを思い出しました。実際に横井はゴッホの影響を受けています。ゆえに向日葵のモチーフも多数。うねるような筆触はゴッホにも共通するものがあります。
76歳で亡くなった横井の作品の多くは個人蔵です。没後、堀内誠一らのイラストレーターに再評価されるものの、その後に忘れられてしまったこともあるそうです。
絵画「ひまわり」に記された「私は原始人の如く、子どもの如く、楽天的な世界に生きたい。」の言葉が印象に残りました。出品は200点。(展示替えあり)さらに資料が加わります。戦前の作品は戦火により失われてしまったものも少なくありませんが、晩年の長野の作品の多くは大切に保存されてきたそうです。

横井弘三「郷土玩具の品評会」 1961年 個人蔵
2008年には横井弘三のファンらによって「横井弘三とオモチャン会」なる会が結成されました。「オモチャン会」とは横井自身が生前、子どものための創作玩具つくりを目指して組織したもの。その名にあやかり、子息の一郎氏の協力も得て、横井再評価を目指して作られました。

後々は所縁の善光寺界隈に記念館を設ける構想もあるそうです。東京での横井弘三復権の切っ掛けとなる展覧会と言えるかもしれません。

6月5日まで開催されています。
「没後50年 日本のルソー 横井弘三の世界展」 練馬区立美術館
会期:4月17日(日)~6月5日(日)
休館:月曜日。
時間:10:00~18:00 *入館は閉館の30分前まで
料金:大人800(600)円、大・高校生・65~74歳600(500)円、中学生以下・75歳以上無料
*( )は20名以上の団体料金。
*ぐるっとパス利用で300円。
住所:練馬区貫井1-36-16
交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
「素心 バーミヤン大仏天井壁画~流出文化財とともに」 東京藝術大学大学美術館・陳列館
東京藝術大学大学美術館・陳列館
「素心 バーミヤン大仏天井壁画~流出文化財とともに」
4/12~6/19

東京藝術大学大学美術館・陳列館で開催中の「素心 バーミヤン大仏天井壁画~流出文化財とともに」を見てきました。
現在、同じく上野の国立博物館で行なわれている「黄金のアフガニスタン」展。それに完全に連動する企画です。アフガニスタンから流出した文化財の保護運動を紹介しています。
「黄金のアフガニスタン展」 東京国立博物館・表慶館(はろるど)
2部構成です。まず1階では壁画の欠片。モチーフは仏座です。いずれも時代は7~8世紀頃のもの。かつてはバーミヤンやフォラディ石窟を飾っていました。ただし知られているようにバーミヤン大石仏は2001年、当時のタリバン政権下において破壊。かの歴史的な文化財は無残にも失われてしまいました。

「誕生図」 3~4世紀
ちょうどその頃、日本でもアフガニスタンの文化財の守ろうとする運動が起こります。同国外へ流出した美術品などを収集。ブラックマーケットから購入することもあったそうです。保存だけでなく、修復もなされました。結果的に102点の文化財を保護するに至りました。
これらの壁画もその時に保管されたものです。壁画の一部は彩色も鮮やかです。とは言え、ちょうど仏座の顔の部分のみが破壊されているものもあります。タリバンの為した果てなのでしょうか。痛ましい。また3~5世紀頃の仏像頭部なども見どころです。いずれも高さ20センチ弱ほどの小像ですが、甘美な顔立ちには独特の魅力がありました。
文化財の復元も重要なテーマです。一例が「ゼウス像」。紀元前3世紀の作品です。アフガニスタン北部のアイ・ハヌム遺跡より左足先のみ発掘されました。
足先だけで約50センチ。かなり大きい像です。断片は大理石で出来ていますが、他は漆喰で造られたとも言われています。その足先以外を芸大を拠点として活動するイノベーションセンターが復元。在りし日の姿に甦らせました。
実は足先の本物は東博の「黄金のアフガニスタン」展に出ています。復元品のみ芸大にあります。先に本物を見ておいてイメージを膨らませておくと面白いかもしれません。
さてハイライトも復元です。バーミヤン石窟の東大仏の天崖壁画が実寸大スケールで再現されています。

「バーミヤン東大仏天井壁画」 2016年東京藝術大学COI拠点による想定復元図
大壁は縦横7メートル程度。かなりの迫力です。再現というだけあって、実際に天井部分を覆う形で展示されていました。見上げての鑑賞です。壁画の名は「天翔る太陽神」。堂々というよりも優美と言った方が良いかもしれません。大仏を見下ろす太陽神の美しき姿。触れることは出来ませんが、石独特の質感までが表現されているように見えます。復元に際しては1970年代に撮影されたデータを使用しているそうです。それを一度、デジタル化した上で印刷。さらに修復師の手による彩色が加わります。造作を含め半年近くの時間をかけて完成しました。
復元壁画の正面にはバーミヤンの光景がスクリーンに広がっていました。雄大なる渓谷の一大パノラマ。大石仏の頭の部分から見た景色を映し出されています。臨場感も十分でした。
壁画断片や仏像頭部などをあわせると全部で90件弱。陳列館の手狭なスペースながらも意外に作品があります。なお文化財保護に関しては画家で故平山郁夫氏の尽力も多分にあったそうです。その旨を示す展示もありました。

「素心 バーミヤン大仏天井壁画」解説リーフレット表紙
会場ではアフガニスタンの文化財保護のための募金も受付中でした。500円を寄付するとリーフレット一部、さらに1000円以上を寄付するとカタログが頂けます。
東博と芸大。博物館の門を出てしまえば歩いて5分ほどです。「黄金のアフガニスタン」展にあわせて観覧されることをおすすめします。
なお今回公開されている文化財はアフガニスタン政府へ返還されることが決まっているそうです。未だ政情不安定のアフガニスタン。二度と破壊や散逸がないことを願うばかりでした。

入場は無料です。6月19日まで開催されています。
「東京藝術大学 アフガニスタン特別企画展 素心 バーミヤン大仏天井壁画~流出文化財とともに」 東京藝術大学大学美術館・陳列館
会期:4月12日(火)~6月19日(日)
休館:月曜日。但し5月2日(月)は開館。
時間:9:30~17:00 *入館は16時半まで。
料金:無料。
住所:台東区上野公園12-8
交通:JR線上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ千代田線根津駅より徒歩10分。京成上野駅、東京メトロ日比谷線・銀座線上野駅より徒歩15分。
「素心 バーミヤン大仏天井壁画~流出文化財とともに」
4/12~6/19

東京藝術大学大学美術館・陳列館で開催中の「素心 バーミヤン大仏天井壁画~流出文化財とともに」を見てきました。
現在、同じく上野の国立博物館で行なわれている「黄金のアフガニスタン」展。それに完全に連動する企画です。アフガニスタンから流出した文化財の保護運動を紹介しています。
「黄金のアフガニスタン展」 東京国立博物館・表慶館(はろるど)
2部構成です。まず1階では壁画の欠片。モチーフは仏座です。いずれも時代は7~8世紀頃のもの。かつてはバーミヤンやフォラディ石窟を飾っていました。ただし知られているようにバーミヤン大石仏は2001年、当時のタリバン政権下において破壊。かの歴史的な文化財は無残にも失われてしまいました。

「誕生図」 3~4世紀
ちょうどその頃、日本でもアフガニスタンの文化財の守ろうとする運動が起こります。同国外へ流出した美術品などを収集。ブラックマーケットから購入することもあったそうです。保存だけでなく、修復もなされました。結果的に102点の文化財を保護するに至りました。
これらの壁画もその時に保管されたものです。壁画の一部は彩色も鮮やかです。とは言え、ちょうど仏座の顔の部分のみが破壊されているものもあります。タリバンの為した果てなのでしょうか。痛ましい。また3~5世紀頃の仏像頭部なども見どころです。いずれも高さ20センチ弱ほどの小像ですが、甘美な顔立ちには独特の魅力がありました。
文化財の復元も重要なテーマです。一例が「ゼウス像」。紀元前3世紀の作品です。アフガニスタン北部のアイ・ハヌム遺跡より左足先のみ発掘されました。
足先だけで約50センチ。かなり大きい像です。断片は大理石で出来ていますが、他は漆喰で造られたとも言われています。その足先以外を芸大を拠点として活動するイノベーションセンターが復元。在りし日の姿に甦らせました。
実は足先の本物は東博の「黄金のアフガニスタン」展に出ています。復元品のみ芸大にあります。先に本物を見ておいてイメージを膨らませておくと面白いかもしれません。
さてハイライトも復元です。バーミヤン石窟の東大仏の天崖壁画が実寸大スケールで再現されています。

「バーミヤン東大仏天井壁画」 2016年東京藝術大学COI拠点による想定復元図
大壁は縦横7メートル程度。かなりの迫力です。再現というだけあって、実際に天井部分を覆う形で展示されていました。見上げての鑑賞です。壁画の名は「天翔る太陽神」。堂々というよりも優美と言った方が良いかもしれません。大仏を見下ろす太陽神の美しき姿。触れることは出来ませんが、石独特の質感までが表現されているように見えます。復元に際しては1970年代に撮影されたデータを使用しているそうです。それを一度、デジタル化した上で印刷。さらに修復師の手による彩色が加わります。造作を含め半年近くの時間をかけて完成しました。
復元壁画の正面にはバーミヤンの光景がスクリーンに広がっていました。雄大なる渓谷の一大パノラマ。大石仏の頭の部分から見た景色を映し出されています。臨場感も十分でした。
壁画断片や仏像頭部などをあわせると全部で90件弱。陳列館の手狭なスペースながらも意外に作品があります。なお文化財保護に関しては画家で故平山郁夫氏の尽力も多分にあったそうです。その旨を示す展示もありました。

「素心 バーミヤン大仏天井壁画」解説リーフレット表紙
会場ではアフガニスタンの文化財保護のための募金も受付中でした。500円を寄付するとリーフレット一部、さらに1000円以上を寄付するとカタログが頂けます。
東博と芸大。博物館の門を出てしまえば歩いて5分ほどです。「黄金のアフガニスタン」展にあわせて観覧されることをおすすめします。
なお今回公開されている文化財はアフガニスタン政府へ返還されることが決まっているそうです。未だ政情不安定のアフガニスタン。二度と破壊や散逸がないことを願うばかりでした。

入場は無料です。6月19日まで開催されています。
「東京藝術大学 アフガニスタン特別企画展 素心 バーミヤン大仏天井壁画~流出文化財とともに」 東京藝術大学大学美術館・陳列館
会期:4月12日(火)~6月19日(日)
休館:月曜日。但し5月2日(月)は開館。
時間:9:30~17:00 *入館は16時半まで。
料金:無料。
住所:台東区上野公園12-8
交通:JR線上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ千代田線根津駅より徒歩10分。京成上野駅、東京メトロ日比谷線・銀座線上野駅より徒歩15分。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
「黄金のアフガニスタン」 東京国立博物館
東京国立博物館・表慶館
「黄金のアフガニスタンー守りぬかれたシルクロードの秘宝」
4/12~6/19

東京国立博物館・表慶館で開催中の「黄金のアフガニスタンー守りぬかれたシルクロードの秘宝」を見てきました。
中央アジアの多民族国家のアフガニスタン。シルクロードに位置し、先史以来、「文明の十字路」(チラシより)として様々な文化を生み出してきました。
1922年設立のアフガニスタン国立博物館には同国由来の考古遺物が多数収集されてきました。しかしながら1979年のソビエトによるアフガニスタン侵攻で状況は一変。その後に内戦が勃発するなど、政情は不安定となり、1989年には博物館自体も閉鎖を余儀なくされます。
しかしその時、博物館への襲撃を危惧した職員らが勇敢な行動に出ました。歴史的に価値が高い収蔵品を順に選別。極秘裏に運び出して、とある場所へ隠したのです。
その場所とは大統領府にある中央銀行の地下金庫でした。1993年には博物館へ砲弾が命中。建物は破壊されてしまいます。それでも隠し置かれた美術品は難を逃れました。そして2003年、アフガニスタン紛争の終結後に取り出され、無事であることが確認されたわけです。

「幾何学文脚付杯」 前2100年~前2000年頃 アフガニスタン国立博物館
戦禍を潜り抜けた美術品はアフガニスタンの古き歴史を物語ります。なにせはじまりは紀元前2100年です。アフガニスタン北東部のテペ・フロールより出土したのが「幾何学文脚付杯」。直径10センチほどの金のゴブレットです。外面には凸形のモチーフが施されていますが、これはアフガニスタン周辺で紀元前5000年頃から伝わった祭祀に関するものだそうです。
ギリシアの影響を強く受けた品が多数見られました。中でも象徴的なのがアイ・ハヌム由来の考古品です。そもそも同地域自体がギリシア人の植民都市です。紀元前300年頃に入植が進みました。「ヘラクレス立像」はどうでしょうか。ギリシア神話の英雄ことヘラクレス。怪力を示すのか胸には隆々たる筋肉もついています。左手に持つのはこん棒です。右手は耳のあたりにやっています。いわゆるギリシアの完全なコピーでないのも特徴です。とするのも頭に付けた葉の冠はこの近辺に独特の姿でもあるからです。

「キュベーレ女神円盤」 前3世紀 アフガニスタン国立博物館
女神も登場しました。「キュベーレ女神円盤」です。獅子に引かれるキュベーレ。小アジアからギリシアで信仰された大地の女神です。天空には三日月と太陽神ヘリオスの胸像が浮かんでいます。さらにニケもいました。ギリシアです。一方で戦車の形がペルシャの様式です。円盤は銀製。金でモチーフを表していました。

「襟飾」 1世紀 アフガニスタン国立博物館
タイトルの「黄金のアフガニスタン」。それを最も良く伝えるのがティリヤ・テペの出土品ではないでしょうか。ハイライトとしても過言ではありません。
時は紀元前1世紀から1世紀頃。遊牧民族の有力者の墓です。全部で6基。女性5名と男性1名が埋葬されました。衣服に散りばめた装飾品にはたくさんの金が使われています。1978年にほぼ手付かずの状態で発見されました。

「牡羊像」 1世紀 アフガニスタン国立博物館
驚くのは精緻な細工でした。例えば「牡羊像」です。立派な角を巻いては前を見据える牡羊が象られています。角の凹凸から体のあごひげ、さらに蹄にまで細やかな意匠が施されています。毛並みや関節も浮かび上がっていました。そして何が驚きかといえば、像の大きさが僅か5センチほどに過ぎないことです。にも関わらず、至極写実的に牡羊を表現しています。非常に高い技術があったことは容易に伺えるのではないでしょうか。
「ドラゴン人物文ペンダント」も見事です。冠をつけた男性が両手で左右のドラゴンが掴んでいます。そして何よりも美しいのはトルコ石、ガーネット、さらには真珠などの宝石です。ペンダントの随所にはめ込まれています。女性向けの髪飾りです。さぞかし映えて見えたのではないでしょうか。

「冠」 1世紀 アフガニスタン国立博物館
文字通り「冠」も美しい。直径は50センチ弱。樹形の立ち飾りはハートや三日月形に切り抜かれています。無数の金の円板がぶら下がっていました。一体何枚あるのでしょうか。飾りは取り外しも可能だそうです。ほかは最古の仏陀像とも言われる「インド・メダイヨン」も興味深い。装飾品が多いだけに、1点1点は小ぶりですが、「黄金」の名に相応しい品はたくさんやって来ています。タイトルに偽りはありません。
なおティリヤ・テペのセクションですが、出土品を墓毎に分けて展示しています。また墓の見取り図や埋葬時の復元なども分かりやすい。見せ方に一工夫ありました。
「文明の十字路」ことアフガニスタン。首都カブール北部のベグラムの都市遺跡からは、ローマやエジプトをはじめ、インド、中国の考古品が数多く発掘されたそうです。
うち「マカラの上に立つ女性像」が魅惑的でした。腰をくねらせては立つ女性像。まるで踊っているようにも見えたのは私だけでしょうか。マカラとは彼女の足の下にあるインド神話由来の怪魚を意味します。素材は象牙です。もちろんインド製。時期は1世紀です。大変に珍重されていたそうです。

「脚付彩絵杯」 1世紀 アフガニスタン国立博物館
象牙に並んでガラス器も多く出土しています。鮮やかなのは「脚付彩絵杯」でした。透明のガラスに花輪を編む女性などを描いています。黄色や赤の色も美しい。エナメルで絵付けしているそうです。元はエジプトの由来です。先に地中海世界に広まり、中央アジアへやって来ました。
一枚の奇妙な形をした円形盤が忘れられません。「魚装飾付円形盤」です。直径は50~60センチほどでしょうか。作りは青銅です。さらに鍍金。とはいえ金はかなり失われています。
円形は海を表しているそうです。盤の上には魚のヒレを模した板がたくさん付いています。面白いのが可動式であることです。下を覗いてみました。するとたくさんの重しがついていることが分かります。それらを揺らすとちょうど魚がピチピチと跳ねるように動くのです。もちろん実際に触れることは出来ませんが、嬉しいことに復刻模型が作品横に設置されていました。そちらは動かすことが可能です。確かにヒレが揺れては魚が泳ぐような仕草に見えました。玩具だったのでしょうか。一体何故にこのような盤を制作したのか不思議でなりません。
ラストはアフガニスタンの混乱に伴って国外へと流出した文化財の展示です。約15件。全て日本で保護されたものばかりです。なおこの流出文化財については東博のお隣、芸大美術館で開催されている「素心 バーミヤン大仏天井壁画~流出文化財とともに」でも紹介されています。そちらには87件ほど出ていました。
事実上、二つで一つの展示と捉えて差し支えありません。次回のエントリで改めてご紹介したいと思います。
「素心 バーミヤン大仏天井壁画~流出文化財とともに」 東京藝術大学大学美術館・陳列館(はろるど)

GW中に出掛けたからか、館内はなかなか賑わっていました。
6月19日まで開催されています。
「黄金のアフガニスタンー守りぬかれたシルクロードの秘宝」(@goldafghan) 東京国立博物館・表慶館(@TNM_PR)
会期:4月12日(火)~6月19日(日)
時間:9:30~17:00。
*毎週金曜日は20時まで開館。
*土・日・祝日、及び5月2日(月)は18時まで開館。
*入館は閉館の30分前まで。
休館:月曜日。但し5月2日(月)は開館。
料金:一般1400(1100)円、大学生1000(700)円、高校生600(300)円。中学生以下無料
*( )は20名以上の団体料金。
住所:台東区上野公園13-9
交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。
「黄金のアフガニスタンー守りぬかれたシルクロードの秘宝」
4/12~6/19

東京国立博物館・表慶館で開催中の「黄金のアフガニスタンー守りぬかれたシルクロードの秘宝」を見てきました。
中央アジアの多民族国家のアフガニスタン。シルクロードに位置し、先史以来、「文明の十字路」(チラシより)として様々な文化を生み出してきました。
1922年設立のアフガニスタン国立博物館には同国由来の考古遺物が多数収集されてきました。しかしながら1979年のソビエトによるアフガニスタン侵攻で状況は一変。その後に内戦が勃発するなど、政情は不安定となり、1989年には博物館自体も閉鎖を余儀なくされます。
しかしその時、博物館への襲撃を危惧した職員らが勇敢な行動に出ました。歴史的に価値が高い収蔵品を順に選別。極秘裏に運び出して、とある場所へ隠したのです。
その場所とは大統領府にある中央銀行の地下金庫でした。1993年には博物館へ砲弾が命中。建物は破壊されてしまいます。それでも隠し置かれた美術品は難を逃れました。そして2003年、アフガニスタン紛争の終結後に取り出され、無事であることが確認されたわけです。

「幾何学文脚付杯」 前2100年~前2000年頃 アフガニスタン国立博物館
戦禍を潜り抜けた美術品はアフガニスタンの古き歴史を物語ります。なにせはじまりは紀元前2100年です。アフガニスタン北東部のテペ・フロールより出土したのが「幾何学文脚付杯」。直径10センチほどの金のゴブレットです。外面には凸形のモチーフが施されていますが、これはアフガニスタン周辺で紀元前5000年頃から伝わった祭祀に関するものだそうです。
ギリシアの影響を強く受けた品が多数見られました。中でも象徴的なのがアイ・ハヌム由来の考古品です。そもそも同地域自体がギリシア人の植民都市です。紀元前300年頃に入植が進みました。「ヘラクレス立像」はどうでしょうか。ギリシア神話の英雄ことヘラクレス。怪力を示すのか胸には隆々たる筋肉もついています。左手に持つのはこん棒です。右手は耳のあたりにやっています。いわゆるギリシアの完全なコピーでないのも特徴です。とするのも頭に付けた葉の冠はこの近辺に独特の姿でもあるからです。

「キュベーレ女神円盤」 前3世紀 アフガニスタン国立博物館
女神も登場しました。「キュベーレ女神円盤」です。獅子に引かれるキュベーレ。小アジアからギリシアで信仰された大地の女神です。天空には三日月と太陽神ヘリオスの胸像が浮かんでいます。さらにニケもいました。ギリシアです。一方で戦車の形がペルシャの様式です。円盤は銀製。金でモチーフを表していました。

「襟飾」 1世紀 アフガニスタン国立博物館
タイトルの「黄金のアフガニスタン」。それを最も良く伝えるのがティリヤ・テペの出土品ではないでしょうか。ハイライトとしても過言ではありません。
時は紀元前1世紀から1世紀頃。遊牧民族の有力者の墓です。全部で6基。女性5名と男性1名が埋葬されました。衣服に散りばめた装飾品にはたくさんの金が使われています。1978年にほぼ手付かずの状態で発見されました。

「牡羊像」 1世紀 アフガニスタン国立博物館
驚くのは精緻な細工でした。例えば「牡羊像」です。立派な角を巻いては前を見据える牡羊が象られています。角の凹凸から体のあごひげ、さらに蹄にまで細やかな意匠が施されています。毛並みや関節も浮かび上がっていました。そして何が驚きかといえば、像の大きさが僅か5センチほどに過ぎないことです。にも関わらず、至極写実的に牡羊を表現しています。非常に高い技術があったことは容易に伺えるのではないでしょうか。
「ドラゴン人物文ペンダント」も見事です。冠をつけた男性が両手で左右のドラゴンが掴んでいます。そして何よりも美しいのはトルコ石、ガーネット、さらには真珠などの宝石です。ペンダントの随所にはめ込まれています。女性向けの髪飾りです。さぞかし映えて見えたのではないでしょうか。

「冠」 1世紀 アフガニスタン国立博物館
文字通り「冠」も美しい。直径は50センチ弱。樹形の立ち飾りはハートや三日月形に切り抜かれています。無数の金の円板がぶら下がっていました。一体何枚あるのでしょうか。飾りは取り外しも可能だそうです。ほかは最古の仏陀像とも言われる「インド・メダイヨン」も興味深い。装飾品が多いだけに、1点1点は小ぶりですが、「黄金」の名に相応しい品はたくさんやって来ています。タイトルに偽りはありません。
なおティリヤ・テペのセクションですが、出土品を墓毎に分けて展示しています。また墓の見取り図や埋葬時の復元なども分かりやすい。見せ方に一工夫ありました。
「文明の十字路」ことアフガニスタン。首都カブール北部のベグラムの都市遺跡からは、ローマやエジプトをはじめ、インド、中国の考古品が数多く発掘されたそうです。
うち「マカラの上に立つ女性像」が魅惑的でした。腰をくねらせては立つ女性像。まるで踊っているようにも見えたのは私だけでしょうか。マカラとは彼女の足の下にあるインド神話由来の怪魚を意味します。素材は象牙です。もちろんインド製。時期は1世紀です。大変に珍重されていたそうです。

「脚付彩絵杯」 1世紀 アフガニスタン国立博物館
象牙に並んでガラス器も多く出土しています。鮮やかなのは「脚付彩絵杯」でした。透明のガラスに花輪を編む女性などを描いています。黄色や赤の色も美しい。エナメルで絵付けしているそうです。元はエジプトの由来です。先に地中海世界に広まり、中央アジアへやって来ました。
一枚の奇妙な形をした円形盤が忘れられません。「魚装飾付円形盤」です。直径は50~60センチほどでしょうか。作りは青銅です。さらに鍍金。とはいえ金はかなり失われています。
円形は海を表しているそうです。盤の上には魚のヒレを模した板がたくさん付いています。面白いのが可動式であることです。下を覗いてみました。するとたくさんの重しがついていることが分かります。それらを揺らすとちょうど魚がピチピチと跳ねるように動くのです。もちろん実際に触れることは出来ませんが、嬉しいことに復刻模型が作品横に設置されていました。そちらは動かすことが可能です。確かにヒレが揺れては魚が泳ぐような仕草に見えました。玩具だったのでしょうか。一体何故にこのような盤を制作したのか不思議でなりません。
ラストはアフガニスタンの混乱に伴って国外へと流出した文化財の展示です。約15件。全て日本で保護されたものばかりです。なおこの流出文化財については東博のお隣、芸大美術館で開催されている「素心 バーミヤン大仏天井壁画~流出文化財とともに」でも紹介されています。そちらには87件ほど出ていました。
事実上、二つで一つの展示と捉えて差し支えありません。次回のエントリで改めてご紹介したいと思います。
「素心 バーミヤン大仏天井壁画~流出文化財とともに」 東京藝術大学大学美術館・陳列館(はろるど)

GW中に出掛けたからか、館内はなかなか賑わっていました。
6月19日まで開催されています。
「黄金のアフガニスタンー守りぬかれたシルクロードの秘宝」(@goldafghan) 東京国立博物館・表慶館(@TNM_PR)
会期:4月12日(火)~6月19日(日)
時間:9:30~17:00。
*毎週金曜日は20時まで開館。
*土・日・祝日、及び5月2日(月)は18時まで開館。
*入館は閉館の30分前まで。
休館:月曜日。但し5月2日(月)は開館。
料金:一般1400(1100)円、大学生1000(700)円、高校生600(300)円。中学生以下無料
*( )は20名以上の団体料金。
住所:台東区上野公園13-9
交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
「吉澤野球博物館寄贈記念野球史料展」 船橋市民ギャラリー
船橋市民ギャラリー
「吉澤野球博物館寄贈記念野球史料展~明治から平成まで、野球の歴史が一堂に」
5/4~5/8

船橋市民ギャラリーで開催中の「吉澤野球博物館寄贈記念野球史料展」を見てきました。
大正2年に東京の神田に生まれ、関東大震災により、船橋市の本中山へ移住。幼少期に見た六大学野球に感銘を受けたことから、約80年に渡って、主にアマチュアの野球資料を収集してきた吉澤善吉氏。昨年の9月に満102歳を迎えられたそうです。
昭和54年に本中山の自宅跡に「吉澤野球博物館」を開館します。以来、自らのコレクションを展示してきましたが、一昨年に閉館。所蔵資料をまとめて地元の船橋市に寄贈しました。
その吉澤氏のコレクションが寄贈後に初めて一般に公開されました。出品数は全700点。黎明期の明治にはじまり、大正、そして昭和の野球に関する写真や新聞資料、ユニフォームやバット、さらに近年のイチローなどのサインボールまでを網羅しています。
さて吉澤コレクション、切っ掛けが六大学にあるだけに、戦前の六大学野球の資料が多いのが特徴です。例えば大正時代の入場券。全て六大学のリーグ戦のチケットです。明治後期の早大野球部の米国遠征時の写真なども目を引きます。さらに大正時代のグラブやミット、そして同時期に創刊された雑誌「野球界」の資料と続きます。ほか優勝トロフィーなどもありました。
ラジオと野球に関する展示もポイントです。大正14年に始まったラジオ放送。昭和2年には野球中継も開始されます。当時、使用されたものでしょうか。年代物のラジオ受信機や真空管アンプなどが並んでいました。
明治時代に文士らが結成したスポーツ団体「天狗倶楽部」のユニフォームも見どころの一つ。さらにビックネームではベーブ・ルースです。昭和9年の日米野球での訪日時に記したサインなども出ていました。
吉澤氏の六大学野球に対する思い入れは並大抵ではありません。とするのも、氏は昭和54年から平成元年にかけて、往時の六大学野球の選手たちにインタビューを敢行。ハイライトシーンなどのエピソードをカセットテープに記録しているのです。全部で38人。巻数で69本もあります。相当な労力もかかったことでしょう。そもそも日本の野球史を牽引したのが六大学野球。戦前はプロ野球よりも人気があったと言われています。会場でテープの録音を聞くことは出来ませんが、これこそ日本の野球史を伝える貴重な記録ではないでしょうか。
巨人の水原茂元監督の資料も目立ちます。家族から寄託を受けたそうです。直筆の野球理論。事細かに記しています。日記帳はドジャースのものでした。愛用の品だったのかもしれません。
水原元監督が六大学時代にあった通称「リンゴ事件」にも言及がありました。早慶戦での判定の問題から起きた乱闘騒ぎ。何でも興奮した応援団がグランドにゴミを投げ入れ、それを水原氏が投げ返したというから激しいものです。ちなみにこの件があったゆえに互いの応援席が固定されました。言わば野球の一つの歴史を作った事件でもあります。

時代を下れば巨人V9のフラッグや、松井やイチローといった名選手のサインボールやスパイクもあります。会場は船橋駅南口から徒歩5分ほどの市民ギャラリー。船橋スクエアビル21の3階です。がらんとしたスペースでの展示ですが、野球ファンには興味深いものがありました。

「船橋スクエアビル21」 *会場へはエレベーターが便利です。
吉澤氏のコレクションは全部で4300点にも及びます。よって船橋市ではH29年以降、市総合体育館である船橋アリーナに展示室を設けて順次紹介していくそうです。
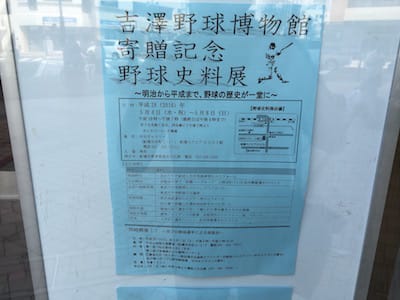
GW限定の公開です。5月8日まで開催されています。入場は無料でした。(最終日は16時まで)
「吉澤野球博物館寄贈記念野球史料展~明治から平成まで、野球の歴史が一堂に」 船橋市民ギャラリー
会期:5月4日(水・祝)~5月8日(日)
休館:会期中無休。
時間:10:00~19:00。*最終日は16時で閉場。
料金:無料。
住所:千葉県船橋市本町2-1-1 船橋スクエアビル21 3階
交通:JR船橋駅南口から徒歩約7分。京成線京成船橋駅から徒歩約5分。
「吉澤野球博物館寄贈記念野球史料展~明治から平成まで、野球の歴史が一堂に」
5/4~5/8

船橋市民ギャラリーで開催中の「吉澤野球博物館寄贈記念野球史料展」を見てきました。
大正2年に東京の神田に生まれ、関東大震災により、船橋市の本中山へ移住。幼少期に見た六大学野球に感銘を受けたことから、約80年に渡って、主にアマチュアの野球資料を収集してきた吉澤善吉氏。昨年の9月に満102歳を迎えられたそうです。
昭和54年に本中山の自宅跡に「吉澤野球博物館」を開館します。以来、自らのコレクションを展示してきましたが、一昨年に閉館。所蔵資料をまとめて地元の船橋市に寄贈しました。
その吉澤氏のコレクションが寄贈後に初めて一般に公開されました。出品数は全700点。黎明期の明治にはじまり、大正、そして昭和の野球に関する写真や新聞資料、ユニフォームやバット、さらに近年のイチローなどのサインボールまでを網羅しています。
さて吉澤コレクション、切っ掛けが六大学にあるだけに、戦前の六大学野球の資料が多いのが特徴です。例えば大正時代の入場券。全て六大学のリーグ戦のチケットです。明治後期の早大野球部の米国遠征時の写真なども目を引きます。さらに大正時代のグラブやミット、そして同時期に創刊された雑誌「野球界」の資料と続きます。ほか優勝トロフィーなどもありました。
ラジオと野球に関する展示もポイントです。大正14年に始まったラジオ放送。昭和2年には野球中継も開始されます。当時、使用されたものでしょうか。年代物のラジオ受信機や真空管アンプなどが並んでいました。
明治時代に文士らが結成したスポーツ団体「天狗倶楽部」のユニフォームも見どころの一つ。さらにビックネームではベーブ・ルースです。昭和9年の日米野球での訪日時に記したサインなども出ていました。
吉澤氏の六大学野球に対する思い入れは並大抵ではありません。とするのも、氏は昭和54年から平成元年にかけて、往時の六大学野球の選手たちにインタビューを敢行。ハイライトシーンなどのエピソードをカセットテープに記録しているのです。全部で38人。巻数で69本もあります。相当な労力もかかったことでしょう。そもそも日本の野球史を牽引したのが六大学野球。戦前はプロ野球よりも人気があったと言われています。会場でテープの録音を聞くことは出来ませんが、これこそ日本の野球史を伝える貴重な記録ではないでしょうか。
巨人の水原茂元監督の資料も目立ちます。家族から寄託を受けたそうです。直筆の野球理論。事細かに記しています。日記帳はドジャースのものでした。愛用の品だったのかもしれません。
水原元監督が六大学時代にあった通称「リンゴ事件」にも言及がありました。早慶戦での判定の問題から起きた乱闘騒ぎ。何でも興奮した応援団がグランドにゴミを投げ入れ、それを水原氏が投げ返したというから激しいものです。ちなみにこの件があったゆえに互いの応援席が固定されました。言わば野球の一つの歴史を作った事件でもあります。

時代を下れば巨人V9のフラッグや、松井やイチローといった名選手のサインボールやスパイクもあります。会場は船橋駅南口から徒歩5分ほどの市民ギャラリー。船橋スクエアビル21の3階です。がらんとしたスペースでの展示ですが、野球ファンには興味深いものがありました。

「船橋スクエアビル21」 *会場へはエレベーターが便利です。
吉澤氏のコレクションは全部で4300点にも及びます。よって船橋市ではH29年以降、市総合体育館である船橋アリーナに展示室を設けて順次紹介していくそうです。
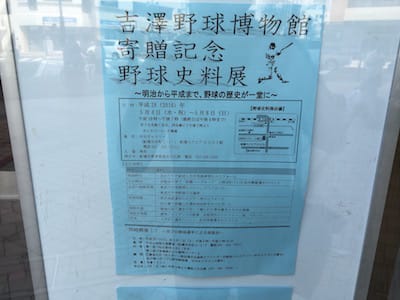
GW限定の公開です。5月8日まで開催されています。入場は無料でした。(最終日は16時まで)
「吉澤野球博物館寄贈記念野球史料展~明治から平成まで、野球の歴史が一堂に」 船橋市民ギャラリー
会期:5月4日(水・祝)~5月8日(日)
休館:会期中無休。
時間:10:00~19:00。*最終日は16時で閉場。
料金:無料。
住所:千葉県船橋市本町2-1-1 船橋スクエアビル21 3階
交通:JR船橋駅南口から徒歩約7分。京成線京成船橋駅から徒歩約5分。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
「光琳とその後継者たち」 畠山記念館
畠山記念館
「尾形光琳没後300年記念 光琳とその後継者たち」
4/2~6/12

茶道具のほか、日本の古美術コレクションで定評のある畠山記念館。光琳の没後300年を期し、館蔵の琳派作品をまとめて公開しています。
さてタイトルに「その後継者たち」のあるように、光琳の後の琳派について参照しているのがポイントです。筆頭格は渡辺始興。京都に生まれ、晩年には光琳に師事したとも言われています。

渡辺始興「四季花木図屏風」(部分) 重要美術品
作品は「四季花木図屏風」でした。右に松と桜。春でしょう。左には紅葉に白菊。春夏秋冬の光景を表しています。興味深いのは構図です。どこか弧を描くように左右対称になっています。花木の種類は全部で45種類。かなり綿密に写生したのでしょうか。写実性が高いのも特徴です。
また対象によって細かに筆触を変化させているのにも注目です。菊は胡粉を盛って立体的に示す一方、松の幹や岩はたらし込みを用いて瑞々しく描いています。元は原三渓の旧蔵品としても知られていたそうです。一際色彩の美しい大作の屏風絵。さすがに見入るものがありました。

尾形乾山「色絵牡丹文四方皿」
弟の乾山の優品が目立っています。「色絵藤透鉢」はとうでしょうか。まさに時候の品。ちょうど見頃を迎えた藤をモチーフにしています。口縁部はやや開き、さも花が咲いているようでもあります。藤は器の内と外の両方に展開していました。白と紫の藤の取り合わせ。透かしの効果か、藤棚を立体的に表したように見えるのも面白いところでした。
「黒楽茶碗 銘 武蔵野」にも惹かれました。色彩の透鉢から一転してのモノトーンの楽茶碗。武蔵野とあるように、側面に野の草を示す線が流麗に描かれています。ほか絵画では「立葵図」も魅惑的です。すくっと伸びる白と赤の立葵。花は写実というよりも図像的です。幾分可愛らしい。立葵は光琳も得意としたモチーフです。兄の作に倣っては描いたのかもしれません。
その立葵を取り入れた光琳の工芸に優品がありました。「紅葵花蒔絵硯箱」です。身と蓋に連続しては硯箱全体を覆う立葵とヤエムグラ。花は錫で表し、蕾は螺鈿で描きます。それゆえかキラキラと光を放っていました。一方で葉は鉛と金の蒔絵です。技法を巧みに変えては様々な表情を作り出しています。

尾形光琳「躑躅図」 重要文化財 展示期間:4/26~5/8
さらに光琳では良く知られた「躑躅図」も美しい。可憐に咲くツツジが緩急の付いた筆で軽妙に表されています。
最後に今回、特に惹かれた作品を挙げたいと思います。それが伝宗達の「芥子図屏風」です。
屏風の形式は6曲1隻。横へと広がっていますが、高さはおそらく60センチ前後。背丈の低い作品でもあります。
モチーフは文字通り芥子です。色は白と赤。左は高く、右はやや低いといったように、位置に変化をつけて描いています。花は正面を向いていたり、また上を向いたりしています。さらに蕾のみ、あるいはしおれているものもありました。
何が個性的といえば屏風の地です。金とおそらくは銀(ただし黒化しています。)の正方形の面が前後左右へタイル状に広がり、さながら市松模様を描いています。
こういった地の表現、私は初めて見ました。もちろん本作も初見です。畠山記念館の琳派コレクションはそれなりに追いかけているつもりですが、そもそも同館の琳派のカタログにも掲載されていません。
金と銀の市松模様の屏風絵。ほかに類例はあるのでしょうか。まさか伝宗達画にこのような作品があるとは思いませんでした。

尾形光琳「白梅模様小袖貼付屏風」(右隻) 重要美術品 展示期間:4/2~5/5
展示替えの情報です。会期中に一部の作品が入れ替わります。
「尾形光琳没後300年記念 光琳とその後継者たち」出品リスト(PDF)

酒井抱一「水草蜻蛉図」 展示期間:5/7~6/12
宗達の「蓮池水禽図」や抱一の「水草蜻蛉図」はGW以降、5月7日からの展示です。ご注意下さい。

お庭は新緑も真っ盛りです。静まり返った館内で、じっくりと琳派の優品を味わうことが出来ました。

6月12日まで開催されています。
「尾形光琳没後300年記念 光琳とその後継者たち」 畠山記念館
会期:4月2日(土)~6月12日(日)
休館:月曜日、 5月6日(金)。
時間:10:00~17:00(入館は16時半まで)
料金:一般700(600)円、学生500(300)円、中学生以下無料。
*( )内は20名以上の団体料金。
住所:港区白金台2-20-12
交通:都営浅草線高輪台駅A2出口より徒歩5分。東京メトロ南北線・都営三田線白金台駅1番出口より徒歩10分。
「尾形光琳没後300年記念 光琳とその後継者たち」
4/2~6/12

茶道具のほか、日本の古美術コレクションで定評のある畠山記念館。光琳の没後300年を期し、館蔵の琳派作品をまとめて公開しています。
さてタイトルに「その後継者たち」のあるように、光琳の後の琳派について参照しているのがポイントです。筆頭格は渡辺始興。京都に生まれ、晩年には光琳に師事したとも言われています。

渡辺始興「四季花木図屏風」(部分) 重要美術品
作品は「四季花木図屏風」でした。右に松と桜。春でしょう。左には紅葉に白菊。春夏秋冬の光景を表しています。興味深いのは構図です。どこか弧を描くように左右対称になっています。花木の種類は全部で45種類。かなり綿密に写生したのでしょうか。写実性が高いのも特徴です。
また対象によって細かに筆触を変化させているのにも注目です。菊は胡粉を盛って立体的に示す一方、松の幹や岩はたらし込みを用いて瑞々しく描いています。元は原三渓の旧蔵品としても知られていたそうです。一際色彩の美しい大作の屏風絵。さすがに見入るものがありました。

尾形乾山「色絵牡丹文四方皿」
弟の乾山の優品が目立っています。「色絵藤透鉢」はとうでしょうか。まさに時候の品。ちょうど見頃を迎えた藤をモチーフにしています。口縁部はやや開き、さも花が咲いているようでもあります。藤は器の内と外の両方に展開していました。白と紫の藤の取り合わせ。透かしの効果か、藤棚を立体的に表したように見えるのも面白いところでした。
「黒楽茶碗 銘 武蔵野」にも惹かれました。色彩の透鉢から一転してのモノトーンの楽茶碗。武蔵野とあるように、側面に野の草を示す線が流麗に描かれています。ほか絵画では「立葵図」も魅惑的です。すくっと伸びる白と赤の立葵。花は写実というよりも図像的です。幾分可愛らしい。立葵は光琳も得意としたモチーフです。兄の作に倣っては描いたのかもしれません。
その立葵を取り入れた光琳の工芸に優品がありました。「紅葵花蒔絵硯箱」です。身と蓋に連続しては硯箱全体を覆う立葵とヤエムグラ。花は錫で表し、蕾は螺鈿で描きます。それゆえかキラキラと光を放っていました。一方で葉は鉛と金の蒔絵です。技法を巧みに変えては様々な表情を作り出しています。

尾形光琳「躑躅図」 重要文化財 展示期間:4/26~5/8
さらに光琳では良く知られた「躑躅図」も美しい。可憐に咲くツツジが緩急の付いた筆で軽妙に表されています。
最後に今回、特に惹かれた作品を挙げたいと思います。それが伝宗達の「芥子図屏風」です。
屏風の形式は6曲1隻。横へと広がっていますが、高さはおそらく60センチ前後。背丈の低い作品でもあります。
モチーフは文字通り芥子です。色は白と赤。左は高く、右はやや低いといったように、位置に変化をつけて描いています。花は正面を向いていたり、また上を向いたりしています。さらに蕾のみ、あるいはしおれているものもありました。
何が個性的といえば屏風の地です。金とおそらくは銀(ただし黒化しています。)の正方形の面が前後左右へタイル状に広がり、さながら市松模様を描いています。
こういった地の表現、私は初めて見ました。もちろん本作も初見です。畠山記念館の琳派コレクションはそれなりに追いかけているつもりですが、そもそも同館の琳派のカタログにも掲載されていません。
金と銀の市松模様の屏風絵。ほかに類例はあるのでしょうか。まさか伝宗達画にこのような作品があるとは思いませんでした。

尾形光琳「白梅模様小袖貼付屏風」(右隻) 重要美術品 展示期間:4/2~5/5
展示替えの情報です。会期中に一部の作品が入れ替わります。
「尾形光琳没後300年記念 光琳とその後継者たち」出品リスト(PDF)

酒井抱一「水草蜻蛉図」 展示期間:5/7~6/12
宗達の「蓮池水禽図」や抱一の「水草蜻蛉図」はGW以降、5月7日からの展示です。ご注意下さい。

お庭は新緑も真っ盛りです。静まり返った館内で、じっくりと琳派の優品を味わうことが出来ました。

6月12日まで開催されています。
「尾形光琳没後300年記念 光琳とその後継者たち」 畠山記念館
会期:4月2日(土)~6月12日(日)
休館:月曜日、 5月6日(金)。
時間:10:00~17:00(入館は16時半まで)
料金:一般700(600)円、学生500(300)円、中学生以下無料。
*( )内は20名以上の団体料金。
住所:港区白金台2-20-12
交通:都営浅草線高輪台駅A2出口より徒歩5分。東京メトロ南北線・都営三田線白金台駅1番出口より徒歩10分。
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
「柴田敏雄写真展:Bridge」 キヤノンギャラリーS
キヤノンギャラリーS
「柴田敏雄写真展:Bridge」
3/31~5/17

キヤノンギャラリーSで開催中の「柴田敏雄写真展:Bridge」を見てきました。
「構造物」(チラシより)を撮影しては、人間が自然の中に作り上げる景色を切り取る写真家の柴田敏雄(1949~)。かつて都内では2009年に東京都写真美術館で個展を開催。また2012年には国立新美術館で「与えられた形象」と題し、画家の辰野登恵子との2人展に参加したこともありました。
今回、被写体となったのは橋です。とはいえ、不特定多数の橋ではなく、ある特定の橋に限られます。
と言うのも、とある建築家の依頼を受けたからです。柴田はおおよそ3年前、ベルギーのローラン・ネイに、自作の橋の写真を「作品化」(チラシより)出来ないかと持ちかけられました。
そもそも柴田はかつてベルギーに住んでいたことがあったそうです。その意味では幾分は土地勘があり、また縁もあったのでしょう。ベルギーほか、ルクセンブルク、オランダなどに点在するローラン・ネイ設計の橋を写し出しています。
柴田のカメラを通すと橋自体が何かのオブジェのようになって浮かび上がってきます。橋の「かたち」が強く際立ってくるとも言えるかもしれません。屈曲し、大きく宙を割き、また影を伸ばしては、風景に介在するいくつもの橋。フォルムは力強いまでに迫り、色彩もクリアに輝いています。橋の「かたち」の生み出す躍動感を感じたのは私だけでしょうか。そして美しい。特にチラシ表紙にもある夜の橋の作品が魅惑的でした。闇から強いライトを受けては眩しいまでにせり上がる橋は、さも何らかのモニュメントのように堂々と空間を支配してもいます。
柴田は本プロジェクトに際してデジタルカメラを用いたそうです。デジタルカメラの写真を発表するによる初めての大規模な展覧会でもあります。
 ランドスケープー柴田敏雄 2008~2009」
ランドスケープー柴田敏雄 2008~2009」
キヤノンギャラリーは日曜と祝日がお休みです。GW中のお出かけの際はご注意下さい。

5月17日まで開催されています。
「柴田敏雄写真展:Bridge」 キヤノンギャラリーS
会期:3月31日(木)~5月17日(火)
休廊:日・祝日。及び4月30日(土)。
時間:10:00~17:30
料金:無料
住所:港区港南2-16-6 キヤノンSタワー1階
交通:JR品川駅港南口より徒歩約8分、京浜急行線品川駅より徒歩約10分
「柴田敏雄写真展:Bridge」
3/31~5/17

キヤノンギャラリーSで開催中の「柴田敏雄写真展:Bridge」を見てきました。
「構造物」(チラシより)を撮影しては、人間が自然の中に作り上げる景色を切り取る写真家の柴田敏雄(1949~)。かつて都内では2009年に東京都写真美術館で個展を開催。また2012年には国立新美術館で「与えられた形象」と題し、画家の辰野登恵子との2人展に参加したこともありました。
今回、被写体となったのは橋です。とはいえ、不特定多数の橋ではなく、ある特定の橋に限られます。
と言うのも、とある建築家の依頼を受けたからです。柴田はおおよそ3年前、ベルギーのローラン・ネイに、自作の橋の写真を「作品化」(チラシより)出来ないかと持ちかけられました。
そもそも柴田はかつてベルギーに住んでいたことがあったそうです。その意味では幾分は土地勘があり、また縁もあったのでしょう。ベルギーほか、ルクセンブルク、オランダなどに点在するローラン・ネイ設計の橋を写し出しています。
柴田のカメラを通すと橋自体が何かのオブジェのようになって浮かび上がってきます。橋の「かたち」が強く際立ってくるとも言えるかもしれません。屈曲し、大きく宙を割き、また影を伸ばしては、風景に介在するいくつもの橋。フォルムは力強いまでに迫り、色彩もクリアに輝いています。橋の「かたち」の生み出す躍動感を感じたのは私だけでしょうか。そして美しい。特にチラシ表紙にもある夜の橋の作品が魅惑的でした。闇から強いライトを受けては眩しいまでにせり上がる橋は、さも何らかのモニュメントのように堂々と空間を支配してもいます。
柴田は本プロジェクトに際してデジタルカメラを用いたそうです。デジタルカメラの写真を発表するによる初めての大規模な展覧会でもあります。
 ランドスケープー柴田敏雄 2008~2009」
ランドスケープー柴田敏雄 2008~2009」キヤノンギャラリーは日曜と祝日がお休みです。GW中のお出かけの際はご注意下さい。

5月17日まで開催されています。
「柴田敏雄写真展:Bridge」 キヤノンギャラリーS
会期:3月31日(木)~5月17日(火)
休廊:日・祝日。及び4月30日(土)。
時間:10:00~17:30
料金:無料
住所:港区港南2-16-6 キヤノンSタワー1階
交通:JR品川駅港南口より徒歩約8分、京浜急行線品川駅より徒歩約10分
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
5月の展覧会・ギャラリー
5月中に見たい展覧会をリストアップしてみました。
展覧会
・「国宝 燕子花図屏風 歌をまとう絵の系譜」 根津美術館(~5/15)
・「没後40年 高島野十郎展」 目黒区美術館(~6/5)
・「没後50年 日本のルソー 横井弘三の世界展」 練馬区立美術館(~6/5)
・「複製技術と美術家たちーピカソからウォーホルまで」 横浜美術館(~6/5)
・「尾形光琳没後300年記念 光琳とその後継者たち」 畠山記念館(~6/12)
・「原安三郎コレクション 広重ビビッド」 サントリー美術館(~6/12)
・「開館50周年記念 美の祝典2ー水墨の壮美」 出光美術館(5/13~6/12)
・「MIYAKE ISSEY展:三宅一生の仕事」 国立新美術館(~6/13)
・「旅するルイ・ヴィトン展」 旅するルイ・ヴィトン展特設会場(~6/19)
・「黄金のアフガニスタンー守りぬかれたシルクロードの秘宝」 東京国立博物館(~6/19)
・「竹中工務店400年の夢ー時をきざむ建築の文化史」 世田谷美術館(~6/19)
・「フランスの風景 樹をめぐる物語」 東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館(~6/26)
・「いま、被災地からー岩手・宮城・福島の美術と震災復興」 東京藝術大学大学美術館(5/17~6/26)
・「Seed山種美術館日本画アワード2016ー未来をになう日本画新世代」 山種美術館(5/31~6/26)
・「メディチ家の至宝ールネサンスのジュエリーと名画」 東京都庭園美術館(~7/5)
・「世界遺産 ポンペイの壁画展」 森アーツセンターギャラリー(~7/3)
・「みんな、うちのコレクションです展」 原美術館(5/28~8/21)
・「ルノワール展」 国立新美術館(~8/22)
・「サイ・トゥオンブリーの写真ー変奏のリリシズム」 DIC川村記念美術館(~8/28)
ギャラリー
・「小泉明郎展 空気」 無人島プロダクション(~5/15)
・「水野里奈展」 第一生命ギャラリー(~5/20)
・「大岩オスカール展」 アートフロントギャラリー(~5/22)
・「大田黒衣美 channel」 KAYOKOYUKI(~5/29)
・「浦上みゆき 時の景、つなぐとき」 ポーラ・ミュージアム・アネックス(~5/29)
・「武田陽介 Arise」 タカ・イシイギャラリー東京(5/14~6/11)
・「椿会展2016ー初心」 資生堂ギャラリー(~6/19)
・「神谷徹 Modest Engagement」 SCAI THE BATHHOUSE(5/20~6/25)
・「大竹伸朗」 Take Ninagawa(5/14~6/30)
・「トランス/リアルー非実体的美術の可能性 vol.2 牛膓達夫」 ギャラリーαM(5/28~7/2)
・「和田真由子 隣人」 児玉画廊東京(5/28~7/2)
4月にはじまる展覧会が多かったせいか、5月スタートのそれはあまり多くありません。
今年は震災から5年。東京藝術大学大学美術館で「いま、被災地からー岩手・宮城・福島の美術と震災復興」が開催されます。

「いま、被災地からー岩手・宮城・福島の美術と震災復興」@東京藝術大学大学美術館(5/17~6/26)
いわゆる被災地のおける美術資料の復興事業に焦点を当てた展覧会です。修復のプロセスの紹介のみならず、東北に所縁のある近現代作家の作品も展示されます。
震災に関する展覧会といえば、今年の「気仙沼と、東日本大震災の記録」や、昨年の「1462days~アートするジャーナリズム」に「3.11大津波と文化財の再生」のほか、一昨年の「平成の大津波被害と博物館」などがありました。
「気仙沼と、東日本大震災の記録」 目黒区美術館
「1462days~アートするジャーナリズム」 河北ビル5~9F(銀座)
「3.11大津波と文化財の再生」 東京国立博物館
「平成の大津波被害と博物館」 江戸東京博物館
先月には熊本でも大きな地震があり、多くの文化財が被害を受けたことも報告されています。改めて災害や復興を考える機会となりそうです。
山種美術館の新シリーズです。「Seed山種美術館日本画アワード2016」が開催されます。

「Seed山種美術館日本画アワード2016ー未来をになう日本画新世代」@山種美術館(5/31~6/26)
45歳以下の日本画家を対象とした公募展です。既に今年の1月から2月にかけてエントリーがあり、その後、複数の専門家による審査を経て、大賞以下、受賞作品が選定されました。
山種美術館では70年代から90年代にかけても同様の公募展を行っていたそうです。その装いを変えての「日本画アワード」。新たな才能が見出されるチャンスでもあります。日本画専門を称する同美術館ならではの切り口に注目したいと思います。

最後のGW中の美術館の情報です。「カラヴァッジョ展」と「ピクサー展」が一部日程に限り延長開館されます。
「カラヴァッジョ展 開館時間延長のお知らせ(4月30日(土)・5月1日(日)」@国立西洋美術館
4月30日(土)は20時、5月1日(日)は18時まで延長開館。
「夜間開館延長のお知らせ」@東京都現代美術館
4月29日(祝)、30日(土)、5月3日(祝)、4日(祝)、5日(祝)、以降、5月中の金土曜日は20時まで延長開館。
人気沸騰中の「若冲展」もGW期間中のお休みがありません。通常、月曜の閉館日扱いとなる5月2日(月)も開館します。

横浜美術館は5月5日(木・祝)が全館規模で開放されます。企画展「複製技術と美術家たち」も無料で観覧可能です。
「2016年5月5日(木・祝)は無料開館日!」@横浜美術館
DIC川村記念美術館は5月5日(木・祝)、子どもの日のため、高校生以下の入館料が無料となります。
「5月5日(木・祝)はこどもの日につき高校生以下の入館が無料です」@DIC川村記念美術館
それでは今月も宜しくお願いします。
展覧会
・「国宝 燕子花図屏風 歌をまとう絵の系譜」 根津美術館(~5/15)
・「没後40年 高島野十郎展」 目黒区美術館(~6/5)
・「没後50年 日本のルソー 横井弘三の世界展」 練馬区立美術館(~6/5)
・「複製技術と美術家たちーピカソからウォーホルまで」 横浜美術館(~6/5)
・「尾形光琳没後300年記念 光琳とその後継者たち」 畠山記念館(~6/12)
・「原安三郎コレクション 広重ビビッド」 サントリー美術館(~6/12)
・「開館50周年記念 美の祝典2ー水墨の壮美」 出光美術館(5/13~6/12)
・「MIYAKE ISSEY展:三宅一生の仕事」 国立新美術館(~6/13)
・「旅するルイ・ヴィトン展」 旅するルイ・ヴィトン展特設会場(~6/19)
・「黄金のアフガニスタンー守りぬかれたシルクロードの秘宝」 東京国立博物館(~6/19)
・「竹中工務店400年の夢ー時をきざむ建築の文化史」 世田谷美術館(~6/19)
・「フランスの風景 樹をめぐる物語」 東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館(~6/26)
・「いま、被災地からー岩手・宮城・福島の美術と震災復興」 東京藝術大学大学美術館(5/17~6/26)
・「Seed山種美術館日本画アワード2016ー未来をになう日本画新世代」 山種美術館(5/31~6/26)
・「メディチ家の至宝ールネサンスのジュエリーと名画」 東京都庭園美術館(~7/5)
・「世界遺産 ポンペイの壁画展」 森アーツセンターギャラリー(~7/3)
・「みんな、うちのコレクションです展」 原美術館(5/28~8/21)
・「ルノワール展」 国立新美術館(~8/22)
・「サイ・トゥオンブリーの写真ー変奏のリリシズム」 DIC川村記念美術館(~8/28)
ギャラリー
・「小泉明郎展 空気」 無人島プロダクション(~5/15)
・「水野里奈展」 第一生命ギャラリー(~5/20)
・「大岩オスカール展」 アートフロントギャラリー(~5/22)
・「大田黒衣美 channel」 KAYOKOYUKI(~5/29)
・「浦上みゆき 時の景、つなぐとき」 ポーラ・ミュージアム・アネックス(~5/29)
・「武田陽介 Arise」 タカ・イシイギャラリー東京(5/14~6/11)
・「椿会展2016ー初心」 資生堂ギャラリー(~6/19)
・「神谷徹 Modest Engagement」 SCAI THE BATHHOUSE(5/20~6/25)
・「大竹伸朗」 Take Ninagawa(5/14~6/30)
・「トランス/リアルー非実体的美術の可能性 vol.2 牛膓達夫」 ギャラリーαM(5/28~7/2)
・「和田真由子 隣人」 児玉画廊東京(5/28~7/2)
4月にはじまる展覧会が多かったせいか、5月スタートのそれはあまり多くありません。
今年は震災から5年。東京藝術大学大学美術館で「いま、被災地からー岩手・宮城・福島の美術と震災復興」が開催されます。

「いま、被災地からー岩手・宮城・福島の美術と震災復興」@東京藝術大学大学美術館(5/17~6/26)
いわゆる被災地のおける美術資料の復興事業に焦点を当てた展覧会です。修復のプロセスの紹介のみならず、東北に所縁のある近現代作家の作品も展示されます。
震災に関する展覧会といえば、今年の「気仙沼と、東日本大震災の記録」や、昨年の「1462days~アートするジャーナリズム」に「3.11大津波と文化財の再生」のほか、一昨年の「平成の大津波被害と博物館」などがありました。
「気仙沼と、東日本大震災の記録」 目黒区美術館
「1462days~アートするジャーナリズム」 河北ビル5~9F(銀座)
「3.11大津波と文化財の再生」 東京国立博物館
「平成の大津波被害と博物館」 江戸東京博物館
先月には熊本でも大きな地震があり、多くの文化財が被害を受けたことも報告されています。改めて災害や復興を考える機会となりそうです。
山種美術館の新シリーズです。「Seed山種美術館日本画アワード2016」が開催されます。

「Seed山種美術館日本画アワード2016ー未来をになう日本画新世代」@山種美術館(5/31~6/26)
45歳以下の日本画家を対象とした公募展です。既に今年の1月から2月にかけてエントリーがあり、その後、複数の専門家による審査を経て、大賞以下、受賞作品が選定されました。
山種美術館では70年代から90年代にかけても同様の公募展を行っていたそうです。その装いを変えての「日本画アワード」。新たな才能が見出されるチャンスでもあります。日本画専門を称する同美術館ならではの切り口に注目したいと思います。

最後のGW中の美術館の情報です。「カラヴァッジョ展」と「ピクサー展」が一部日程に限り延長開館されます。
「カラヴァッジョ展 開館時間延長のお知らせ(4月30日(土)・5月1日(日)」@国立西洋美術館
4月30日(土)は20時、5月1日(日)は18時まで延長開館。
「夜間開館延長のお知らせ」@東京都現代美術館
4月29日(祝)、30日(土)、5月3日(祝)、4日(祝)、5日(祝)、以降、5月中の金土曜日は20時まで延長開館。
人気沸騰中の「若冲展」もGW期間中のお休みがありません。通常、月曜の閉館日扱いとなる5月2日(月)も開館します。

横浜美術館は5月5日(木・祝)が全館規模で開放されます。企画展「複製技術と美術家たち」も無料で観覧可能です。
「2016年5月5日(木・祝)は無料開館日!」@横浜美術館
DIC川村記念美術館は5月5日(木・祝)、子どもの日のため、高校生以下の入館料が無料となります。
「5月5日(木・祝)はこどもの日につき高校生以下の入館が無料です」@DIC川村記念美術館
それでは今月も宜しくお願いします。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
| 次ページ » |









