都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「ミュシャ展」 森アーツセンターギャラリー
森アーツセンターギャラリー
「ミュシャ財団秘蔵 ミュシャ展-パリの夢 モラヴィアの祈り」
3/9-5/19
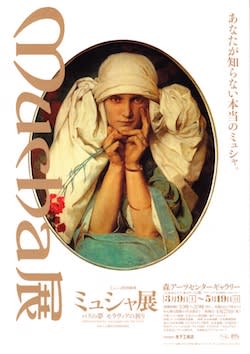
森アーツセンターギャラリーで開催中の「ミュシャ財団秘蔵 ミュシャ展-パリの夢 モラヴィアの祈り」のプレスプレビューに参加してきました。
日本で大人気のアール・ヌーヴォーの巨匠、アルフォンス・ミュシャ。1978年に国内で初めてのミュシャ展が行われて以来、大小様々な回顧展が開催されてきましたが、今回ほど言わば「知られざるミュシャ」にスポットを当てたことはなかったかもしれません。
ずばりミュシャのスラブ魂、故国チェコへの熱き想いを知ることが出来る展覧会です。

右:「第8回ソコル祭」1925年 カラーリトグラフ
左:「1918-1928:チェコスロヴァキア独立10周年記念」1928年 カラーリトグラフ
と言うのも、そもそもミュシャの「パリのアール・ヌーヴォー」の時代は、サラのポスターを描いて一世を風靡した1894年からおおよそ10年間あまり。1904年に渡米すると、シカゴの美術学校で教え、さらに祖国チェコへと。その後はおおよそ20年あまりかけて「スラブ叙事詩」の制作に没頭。78歳にて没するまでスラブ民族の歴史や平和を願った作品を描き続けているのです。

右:「母と子:子守唄(プラハ・ハラホル合唱教会の壁画のための習作」1921年頃 油彩・カンヴァス
左:「希望の光」1933年 油彩・カンヴァス
ミュシャは紛れもなくスラブ人であり、スラブを愛していた。ミュシャは新生チェコの切手、紙幣のデザインも無償で引き受けています。もちろんパリ時代の華麗なポスターも出品されていますが、ともすれば固定化された感もあるミュシャのイメージを覆すような展示でした。
第1章 チェコ人ミュシャ
第2章 サラ・ベルナールとの出会い
第3章 ミュシャ様式とアール・ヌーヴォー
第4章 美の探求
第5章 パリ万博と世紀末
第6章 ミュシャの祈り
さて冒頭の自画像から早速チェコ人としてのミュシャが。着ているのはロシア風のルパシカと呼ばれる上着。自画像に限らずミュシャは自作にロシア風デザインをいくつも取り込んでいます。

左:「パレットを持った自画像」1907年頃 油彩・カンヴァス
そして直ぐさまパリへ。かの有名な「ジスモンダ」です。これこそ1894年、大人気の女優サラ・ベルナールのためにデザインした宣伝ポスター。なんとミュシャはこの作品以前に本格的なポスター制作をしたことがありませんでしたが、ともかくいきなりの大ヒット。出世作です。得意とするビザンティン風の艶やかな衣装が目を引きます。

右:「ジスモンダ」1894年 カラーリトグラフ
中央:「ロレンザッチオ」1896年 カラーリトグラフ
左:「椿姫」1896年 カラーリトグラフ
ちなみにサラは以降、6年にわたってミュシャにポスター制作を依頼。彫刻家でありコレクターでもあったサラとの交流は、ミュシャの芸術表現をより高めることにも繋がりました。

中央:「カサン・フィス印刷所」1896年 カラーリトグラフ
このようにしてパリのアート・シーンの寵児となったミュシャですが、「アール・ヌーヴォ」におけるミュシャ様式を完成させたのもこの時期です。会場にはミュシャをミュシャたらしめたポスター群がずらり。煙草、香水、ビスケット、そして自転車など、次々と企業宣伝ポスターを手がけていきます。

右:「装飾資料集 図67の最終習作」1901-02年 鉛筆、白のハイライト、紙
左:「装飾資料集 図43の最終習作」1901-02年 鉛筆、インク、淡彩、白のハイライト、紙
また興味深いのは「装飾資料集」。ミュシャは若いデザイナーのために参考書として出版。リトグラフの完成版はもちろん、ミュシャ直筆の素描(最終習作)も展示。これが実に繊細な線描です。ミュシャの高い表現力を知ることが出来ます。
さらにミュシャの名声を不動のものとした装飾パネル画もあわせて紹介。これは広告用の文字を取り除き、室内装飾の観賞用として作られたポスターです。もちろん大ヒット。

左:「夢想」1897年 カラーリトグラフ
しかしながらここで見逃せないのはスラブ的なモチーフです。確かにミュシャは優美な女性、曲線を多用した調和的構図、また花や自然などのモチーフを取り込み、自らの様式を確立させましたが、例えば「夢想」ではチェコの伝統的な刺繍の意匠もさり気なく挿入。円形モチーフもスラブ教会の聖画の光輪に似た構図となっています。
そうしたミュシャがスラブへの想いを新たにしたのが1900年のパリ万博です。ここでボスニア=ヘルツェゴヴィナのパヴィリオンの内装を請け負ったミュシャですが、その準備のために訪れたバルカン半島の地にて、改めてスラブ民族の置かれた過酷な状況を認識。そもそもチェコはパヴィリオンの依頼者、つまりはオーストリア=ハンガリー帝国の植民地でもあったのです。

右:「主の祈り」1899年 パリ、ピアッツァ社により出版 挿絵本
左:「フリーメイソンのコブレット」(ミュシャによるデザイン)1923年 クリスタル・カット・ガラス
さらに興味深いのはこの時期にフリーメイソンに入団。当時流行していた神智学にのめりこみ、人間の精神世界を見つめ直したことです。

右:「ボスニア伝説:ハサンガ嫁の死」1899年 木炭、紙
左:「ボスニア伝説:死神ムルシア」1899年 木炭、紙
この近辺から作風に変化が生じます。精神の奥底へ向き合った「ボスニア伝説」や「死者たち」の暗鬱な気配は、おおよそ知られるミュシャ画とは異なる世界。

「月と星」シリーズ(下絵) 1902年 インク、水彩、紙
特徴的な女性と花ではなく、天体をテーマにした「月と星」シリーズも実に神秘的。光よりも闇が空間を支配しています。
展覧会のハイライトは「スラブ叙事詩」として差し支えないでしょう。1910年パリからチェコへと戻ったミュシャは、スラブの歴史を扱う本シリーズの制作に着手。1918年にチェコは一次大戦によって悲願の独立を果たしますが、作品はそれから数えること10年、つまり独立10周年の1928年になってプラハ市に寄贈されました。
完成作はなんと横8メートル、縦6メートル、それが全部で20点。さすがにそれらがやってきているわけではありません。

「スラブ叙事詩 第9番『クジージュキの集会』下半分の下絵」1916年 チョーク、紙
しかしながらこのプロジェクトに関する下絵が何点も来日。中でも注目は「スラブ叙事詩 第9番『クジージュキの集会』下半分の下絵」ではないでしょうか。
本作は3年前の修復を経て世界初公開。下絵といっても高さ3メートルの迫力。ミュシャの力強い筆致を見て取ることが出来ます。

「スラブ叙事詩」紹介映像
ちなみに「スラブ叙事詩」の本画は会場内の映像で紹介。BGMにはミュシャが制作にあたって大いに感化されたというスメタナの「わが祖国」も。高らかなる民族愛が歌い上げられます。正直感動ものです。

左上「ヒランダル修道院、聖アトス山」1924年 ガラスネガからプリント 他 (いずれもミュシャ撮影写真)
日本はおろか、世界初公開を含む、全240点の作品で辿るミュシャの人生。リトグラフだけでなく素描や油彩、そしてステンドグラス原画や店舗内装デザイン、さらにはミュシャ自身が作品を作るために撮った写真も数多く公開。これまでと一味も二味も違うミュシャ展です。

参考図「プラハ聖堂ヴィート大聖堂のステンド・グラスの窓」 他
スラブを愛し続けたアルフォンス・ミュシャ。パリ以降のミュシャにこれほど注目した展覧会が今まであったでしょうか。誤解を恐れずに申し上げればまさかミュシャの作品から目頭が熱くなるとは思いもよりませんでした。
 「ミュシャ作品集―パリから祖国モラヴィアへ/東京美術」
「ミュシャ作品集―パリから祖国モラヴィアへ/東京美術」
5月19日までの開催です。強くおすすめします。
「ミュシャ展-パリの夢 モラヴィアの祈り 巡回情報」
[東京展]2013年3月9日(土)~5月19日(日) 森アーツセンターギャラリー
[新潟展]2013年6月1日(土)~8月11日(日) 新潟県立万代島美術館
[松山展]2013年10月26日(土)~2014年1月5日(日) 愛媛県美術館
[仙台展]2014年1月18日(土)~3月23日(日) 宮城県美術館
[札幌展]2014年4月5日(土)~6月15日(日) 北海道立近代美術館
 「もっと知りたいミュシャ/千足伸行/東京美術」*本展監修の千足先生のミュシャ本です。
「もっと知りたいミュシャ/千足伸行/東京美術」*本展監修の千足先生のミュシャ本です。
「ミュシャ財団秘蔵 ミュシャ展-パリの夢 モラヴィアの祈り」(@Mucha2013) 森アーツセンターギャラリー
会期:3月9日(土)~5月19日(日)
休館:4月25日(木)
時間:10:00~20:00(火曜日は17時まで) *3/23(土)はアートナイト開催のため22時まで。入館は閉館時間の30分前まで。
料金:一般1500(1300)円、大学生1200(1000)円、中・高校生800(600)円。小学生以下無料。
*( )内は15名以上の団体料金
住所:港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階
交通:東京メトロ日比谷線六本木駅1C出口徒歩5分(コンコースにて直結)。都営地下鉄大江戸線六本木駅3出口徒歩7分。
注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。
「ミュシャ財団秘蔵 ミュシャ展-パリの夢 モラヴィアの祈り」
3/9-5/19
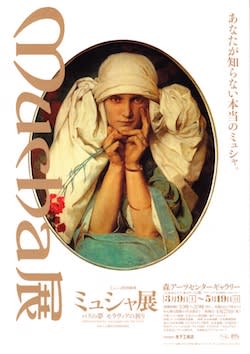
森アーツセンターギャラリーで開催中の「ミュシャ財団秘蔵 ミュシャ展-パリの夢 モラヴィアの祈り」のプレスプレビューに参加してきました。
日本で大人気のアール・ヌーヴォーの巨匠、アルフォンス・ミュシャ。1978年に国内で初めてのミュシャ展が行われて以来、大小様々な回顧展が開催されてきましたが、今回ほど言わば「知られざるミュシャ」にスポットを当てたことはなかったかもしれません。
ずばりミュシャのスラブ魂、故国チェコへの熱き想いを知ることが出来る展覧会です。

右:「第8回ソコル祭」1925年 カラーリトグラフ
左:「1918-1928:チェコスロヴァキア独立10周年記念」1928年 カラーリトグラフ
と言うのも、そもそもミュシャの「パリのアール・ヌーヴォー」の時代は、サラのポスターを描いて一世を風靡した1894年からおおよそ10年間あまり。1904年に渡米すると、シカゴの美術学校で教え、さらに祖国チェコへと。その後はおおよそ20年あまりかけて「スラブ叙事詩」の制作に没頭。78歳にて没するまでスラブ民族の歴史や平和を願った作品を描き続けているのです。

右:「母と子:子守唄(プラハ・ハラホル合唱教会の壁画のための習作」1921年頃 油彩・カンヴァス
左:「希望の光」1933年 油彩・カンヴァス
ミュシャは紛れもなくスラブ人であり、スラブを愛していた。ミュシャは新生チェコの切手、紙幣のデザインも無償で引き受けています。もちろんパリ時代の華麗なポスターも出品されていますが、ともすれば固定化された感もあるミュシャのイメージを覆すような展示でした。
第1章 チェコ人ミュシャ
第2章 サラ・ベルナールとの出会い
第3章 ミュシャ様式とアール・ヌーヴォー
第4章 美の探求
第5章 パリ万博と世紀末
第6章 ミュシャの祈り
さて冒頭の自画像から早速チェコ人としてのミュシャが。着ているのはロシア風のルパシカと呼ばれる上着。自画像に限らずミュシャは自作にロシア風デザインをいくつも取り込んでいます。

左:「パレットを持った自画像」1907年頃 油彩・カンヴァス
そして直ぐさまパリへ。かの有名な「ジスモンダ」です。これこそ1894年、大人気の女優サラ・ベルナールのためにデザインした宣伝ポスター。なんとミュシャはこの作品以前に本格的なポスター制作をしたことがありませんでしたが、ともかくいきなりの大ヒット。出世作です。得意とするビザンティン風の艶やかな衣装が目を引きます。

右:「ジスモンダ」1894年 カラーリトグラフ
中央:「ロレンザッチオ」1896年 カラーリトグラフ
左:「椿姫」1896年 カラーリトグラフ
ちなみにサラは以降、6年にわたってミュシャにポスター制作を依頼。彫刻家でありコレクターでもあったサラとの交流は、ミュシャの芸術表現をより高めることにも繋がりました。

中央:「カサン・フィス印刷所」1896年 カラーリトグラフ
このようにしてパリのアート・シーンの寵児となったミュシャですが、「アール・ヌーヴォ」におけるミュシャ様式を完成させたのもこの時期です。会場にはミュシャをミュシャたらしめたポスター群がずらり。煙草、香水、ビスケット、そして自転車など、次々と企業宣伝ポスターを手がけていきます。

右:「装飾資料集 図67の最終習作」1901-02年 鉛筆、白のハイライト、紙
左:「装飾資料集 図43の最終習作」1901-02年 鉛筆、インク、淡彩、白のハイライト、紙
また興味深いのは「装飾資料集」。ミュシャは若いデザイナーのために参考書として出版。リトグラフの完成版はもちろん、ミュシャ直筆の素描(最終習作)も展示。これが実に繊細な線描です。ミュシャの高い表現力を知ることが出来ます。
さらにミュシャの名声を不動のものとした装飾パネル画もあわせて紹介。これは広告用の文字を取り除き、室内装飾の観賞用として作られたポスターです。もちろん大ヒット。

左:「夢想」1897年 カラーリトグラフ
しかしながらここで見逃せないのはスラブ的なモチーフです。確かにミュシャは優美な女性、曲線を多用した調和的構図、また花や自然などのモチーフを取り込み、自らの様式を確立させましたが、例えば「夢想」ではチェコの伝統的な刺繍の意匠もさり気なく挿入。円形モチーフもスラブ教会の聖画の光輪に似た構図となっています。
そうしたミュシャがスラブへの想いを新たにしたのが1900年のパリ万博です。ここでボスニア=ヘルツェゴヴィナのパヴィリオンの内装を請け負ったミュシャですが、その準備のために訪れたバルカン半島の地にて、改めてスラブ民族の置かれた過酷な状況を認識。そもそもチェコはパヴィリオンの依頼者、つまりはオーストリア=ハンガリー帝国の植民地でもあったのです。

右:「主の祈り」1899年 パリ、ピアッツァ社により出版 挿絵本
左:「フリーメイソンのコブレット」(ミュシャによるデザイン)1923年 クリスタル・カット・ガラス
さらに興味深いのはこの時期にフリーメイソンに入団。当時流行していた神智学にのめりこみ、人間の精神世界を見つめ直したことです。

右:「ボスニア伝説:ハサンガ嫁の死」1899年 木炭、紙
左:「ボスニア伝説:死神ムルシア」1899年 木炭、紙
この近辺から作風に変化が生じます。精神の奥底へ向き合った「ボスニア伝説」や「死者たち」の暗鬱な気配は、おおよそ知られるミュシャ画とは異なる世界。

「月と星」シリーズ(下絵) 1902年 インク、水彩、紙
特徴的な女性と花ではなく、天体をテーマにした「月と星」シリーズも実に神秘的。光よりも闇が空間を支配しています。
展覧会のハイライトは「スラブ叙事詩」として差し支えないでしょう。1910年パリからチェコへと戻ったミュシャは、スラブの歴史を扱う本シリーズの制作に着手。1918年にチェコは一次大戦によって悲願の独立を果たしますが、作品はそれから数えること10年、つまり独立10周年の1928年になってプラハ市に寄贈されました。
完成作はなんと横8メートル、縦6メートル、それが全部で20点。さすがにそれらがやってきているわけではありません。

「スラブ叙事詩 第9番『クジージュキの集会』下半分の下絵」1916年 チョーク、紙
しかしながらこのプロジェクトに関する下絵が何点も来日。中でも注目は「スラブ叙事詩 第9番『クジージュキの集会』下半分の下絵」ではないでしょうか。
本作は3年前の修復を経て世界初公開。下絵といっても高さ3メートルの迫力。ミュシャの力強い筆致を見て取ることが出来ます。

「スラブ叙事詩」紹介映像
ちなみに「スラブ叙事詩」の本画は会場内の映像で紹介。BGMにはミュシャが制作にあたって大いに感化されたというスメタナの「わが祖国」も。高らかなる民族愛が歌い上げられます。正直感動ものです。

左上「ヒランダル修道院、聖アトス山」1924年 ガラスネガからプリント 他 (いずれもミュシャ撮影写真)
日本はおろか、世界初公開を含む、全240点の作品で辿るミュシャの人生。リトグラフだけでなく素描や油彩、そしてステンドグラス原画や店舗内装デザイン、さらにはミュシャ自身が作品を作るために撮った写真も数多く公開。これまでと一味も二味も違うミュシャ展です。

参考図「プラハ聖堂ヴィート大聖堂のステンド・グラスの窓」 他
スラブを愛し続けたアルフォンス・ミュシャ。パリ以降のミュシャにこれほど注目した展覧会が今まであったでしょうか。誤解を恐れずに申し上げればまさかミュシャの作品から目頭が熱くなるとは思いもよりませんでした。
 「ミュシャ作品集―パリから祖国モラヴィアへ/東京美術」
「ミュシャ作品集―パリから祖国モラヴィアへ/東京美術」5月19日までの開催です。強くおすすめします。
「ミュシャ展-パリの夢 モラヴィアの祈り 巡回情報」
[東京展]2013年3月9日(土)~5月19日(日) 森アーツセンターギャラリー
[新潟展]2013年6月1日(土)~8月11日(日) 新潟県立万代島美術館
[松山展]2013年10月26日(土)~2014年1月5日(日) 愛媛県美術館
[仙台展]2014年1月18日(土)~3月23日(日) 宮城県美術館
[札幌展]2014年4月5日(土)~6月15日(日) 北海道立近代美術館
 「もっと知りたいミュシャ/千足伸行/東京美術」*本展監修の千足先生のミュシャ本です。
「もっと知りたいミュシャ/千足伸行/東京美術」*本展監修の千足先生のミュシャ本です。「ミュシャ財団秘蔵 ミュシャ展-パリの夢 モラヴィアの祈り」(@Mucha2013) 森アーツセンターギャラリー
会期:3月9日(土)~5月19日(日)
休館:4月25日(木)
時間:10:00~20:00(火曜日は17時まで) *3/23(土)はアートナイト開催のため22時まで。入館は閉館時間の30分前まで。
料金:一般1500(1300)円、大学生1200(1000)円、中・高校生800(600)円。小学生以下無料。
*( )内は15名以上の団体料金
住所:港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階
交通:東京メトロ日比谷線六本木駅1C出口徒歩5分(コンコースにて直結)。都営地下鉄大江戸線六本木駅3出口徒歩7分。
注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。
コメント ( 5 ) | Trackback ( 0 )









