「最近射精したのは、覚えてないぐらい前です」
「ただ食べて寝るだけの生き物になったみたいな」
ある日を境に身体障害者になった人たち。感じるのは今までできていたことが突然できなくなるもどかしさや無力さ。それは性に対しても同じだ。
彼らは欲求があっても、セックスどころか自力での射精すらできず苦しんでいる。しかも、本人の苦しみに反して周囲から理解を得ることは難しい。かといって、一般的な風俗では障害者を中々受け入れてくれないのが現実。
そういった場合のサポートとして「射精介助」がある。射精介助も含め、障害者の性問題に取り組む一般社団法人「ホワイトハンズ」代表理事の坂爪真吾氏。自らの性に関して誰にも話せず、絶望している当事者を何人も目の当たりにしてきた。「男性としての自信をなくしてしまったとか、一生性的なことができないのであれば生きていてもしょうがないという方もいる。そういった方が自分でできないことをケアしてサポートしていくことができれば、最低限度の性と健康の権利の支援につながっていくと思う」。
海外では、障害者の性欲処理も含めたサポートなど制度が確立されている国もある。しかし、日本では障害者の性自体、話すことさえ憚られるのが現状だ。
■旅行先のバリアフリーの宿でデリヘルを利用
山田修さん(仮名・29)は今から約7年前の22歳の時、突然の心肺停止により1カ月半の間、脳死状態になった。奇跡的に回復したものの、残ったのは両手足の麻痺という障害。山田さんは「起きたらどこも動かない体になっていたので、(自分は)障害者だと…」と当時の心境を明かす。
体が不自由になっても、当然これまでと変わらず性欲は存在する。それは人としてごく自然なこと。当時はまだ22歳で、わずかに残る右手の感覚を頼りに自慰行為を試したが、力加減や手を動かすことが困難で射精には至らなかった。

セックスはおろか自慰行為ができなくなってしまった山田さん。「射精は今年の夏、デリヘルの方を呼んでやっていただいた」というように、旅行先で身体障害者でも利用可能なデリヘルを利用しているという。
障害者年金で手にできるのは、2カ月で約7万円。両親と生活していることもあり、お金を貯めて実家でサービスを受けることは難しい。わずかな段差や階段でも車椅子では通ることができず、旅行先でバリアフリーの宿を予約し、デリヘルを利用するしか方法がないという。
障害者という立場になった今、射精は年に2、3回で、この7年間で20回ほど。山田さんは、「性欲は障害者・健常者関係なく男性が持っているもの。それは人としてやはり当たり前のことだと思うし、苦しさというかもどかしさ的なものはある。別のことを考えて、飲んだりとか遊んだりとかして気を紛らわしている。そうしないと無理」と苦しい胸の内を明かした。
■難病で体に障害、妻とはセックスレスに「生きる屍になったような感じ」
障害者が抱えるのは性の問題だけではない。都内で一人暮らしをしている川上弘さん(仮名・55)。過去に射精介助を利用した結果、射精することが性のすべてではないと感じたといい、「性全体を考えたら、やっぱり相手の女の子とハグしたりとかそんなこともあったほうが楽しい」と話す。
川上さんは20代から手足の不調を感じ、38歳で難病「脊髄小脳変性症」と診断された。歩行障害や手の震えなどの症状に苦しんでいる。「診断される頃になると、いわゆる正常位で腰を動かすというのは結構苦痛になった。これはやばいなと。いきなり生きる屍になったような感じ」。
病気を受け入れてもらえず、セックスをする機会もなくなる。それは家族が離れる要因にもなってしまう。「ショックですね。ただ食べて寝るだけの生き物になったみたいな。喪失感もある」。
黙殺された障害者の性、この問題は当事者だけのものではない。今日本の福祉施設で働く現場スタッフの多くは女性が担っている。あるケアスタッフは、「射精だけじゃなくて、抱きたいとかキスしたいとか、性的な言葉だけでなく手を出されたこともある。心が苦しいと懇願されて」「やっぱり(射精介助を)望んでいる。終わったあとの利用者さんとの関係性であったりとか、いろいろと考えることはある」と話す。
一方で、福祉が性の問題に対応することに疑問を感じる人も。長年障害と向き合ってきた現場でも、性の問題となると答えが見つからないのが現状だ。障害者施設職員の男性は、「『(自慰行為を)わー見ちゃった』『こういうことをしていた』というくらいで黙認していた。そこを支援しなさいなんて言葉は中々かけづらい」と語った。
乙武氏「夢精してもパンツすら洗えない。地獄の苦しみだった」
当事者だけでなく、福祉の現場や家族にまで及ぶ性の問題。射精介助を含めたサポートを行うホワイトハンズの坂爪氏は、取り組みを始めた経緯について「現行の制度は、障害のある人は射精しない、生理はこない、恋愛はしない、結婚も妊娠もしないという、性がないという前提で仕組みができてしまっている面があると思う。そこに、射精という限定的な部分ではあるが一石を投じようという思いがあった。利用者からは、射精だけでなく性のことを話せる場所があってよかったという声も聞く。やはり言いづらい部分があると思う」と話す。
ホワイトハンズは2008年4月に設立。全国19都道府県で計714人が利用してきた。料金は寄付を活用し、現在は無料。女性は着衣したままで、利用者から触ってはいけない決まりがある。利用者の声としては、「男としての自信、健全な思考を取り戻すことができ、精神的ストレスが減った」「食事・排泄介助と同様に行われるケアとして普及してほしい」「できれば服を脱いでほしいし、体にも触れたい」という意見もある。

これに対し、作家の乙武洋匡氏は「服を脱いでほしいということは別で論じていかなければならない」と言及。「この問題を語る時に、健常者とどこが違うのかということはひとつ重要なものさしになってくると思う。男性の場合、彼女やパートナーがいる・いないに関わらず、自慰で性欲を処理することが健常者にはできて重度障害者にはできない。物理的にどうしてもできない部分には、他者のケアが必要だというのは正論だと思う。しかし、相手に服を脱いでほしい・体に触れたいというのは健常者も思うことだし、それが人間関係などの問題で叶わない人もたくさんいる。なぜ障害者だけ支援してもらえるのかというのはややこしい話になるので、明確に分けて語るべき」と述べた。
ホワイトハンズで射精介助を行っているスタッフは、東京と大阪で現在4名。ケアをする側からは「恥ずかしいという意識がなく『ケア』と考えている」「性欲を解消することで周囲とのコミュニケーションが豊かになっている」「生活の質を上げる支援となる」といった前向きな意見があがる。一方、世間からは「一般的な風俗と同じだ」「福祉サービスを金儲けに使うな」という批判の声と、「当事者だけでなく家族からも感謝される」という賛成意見も。
賛否の声に坂爪氏は「風俗は娯楽がメインだが、射精介助は健康や自立、尊厳の視点から。娯楽目的ではなく介護的な枠組みでやっているスタンス」だと説明する。
利用者の多くは、家族に中々言えないことで悩んでいるという。乙武氏は自身が当事者だとしたうえで、「利用者にとってホワイトハンズは神様のような存在。僕も10代の頃は自分で自慰行為はできず、数週間に一度、気づくと夢精していた。そして、そのパンツを自分で脱ぐことも洗うこともできない。恐らくそれを母が無言で洗濯をしてくれていた。やはり、地獄の苦しみなんですよ。若い頃に聞いた話だと、母親が自分の息子は一生女性と関わることはないだろうと心配して、かわいそうに思って、母親本人が息子の人生で唯一になる性の相手をするケース。施設に入っていて首から上しか動かない方は、当然自慰行為をすることができないので、恋愛対象が本来は女性であるにも関わらず、他に手段がないために男性同士で相手のものを口でしてあげるという現実もある。それを10代で聞いた時には、自分の将来に対して不安も抱いたし焦りもあった。僕の場合は比較的コミュニケーションが図れ、表に出ていくタイプの人間だったので、自分で切り開いていくことがたまたま可能だった。しかし、言語の状態によってそれが叶わない方もいるわけで、そういう方にとって坂爪さんのサービスは神様」と話す。
また、視聴者からの「乙武氏はモテている」という意見については、「数年前の騒動で私は“性の問題を克服した人”として捉えられているのかもしれないが、それは僕の中では肯定できない。もしかすると来月、僕もホワイトハンズにサービスをお願いしているかもしれない。いつそうなるか分からないという背中合わせの立場にいることは変わらなくて、一生抱え続ける問題なんだろうなと思っている」と答えた。
元AV女優でタレントの麻美ゆまは「ホワイトハンズの活動が10年前からで、もっと前から出てきてもおかしくない話だったと思う。私自身、病気で子宮と卵巣をとって、女性としての自信をなくした時期があった。やはり女性と男性は全く違うと思っていて、男性は本能的に出したいという欲求、女性はホルモンバランスがある。男性の出すという行為は治療の一環だと思う。AV業界でもヘルスケア部門ができてきていて、福祉に介入していくという話に発展していけばいいと思う」と期待を寄せた。
■性的サービスに保険適用、介護の一貫に含まれている国も
障害者の性問題は、身体に障害のある人だけでなく知的障害者にも該当する。知的障害者の主な性問題は、人前で性器をいじる、自慰行為、女性への抱きつき行為、親への非難、(身体・知的)女性障害者への暴力などがある。
性暴力について、障害福祉専用のeラーニングを提供しているLean on Me代表の志村駿介氏は「性暴力を愛されていると勘違いする人もいる。愛情表現と素直に勘違いすると、性暴力は見えづらい」と指摘。障害者の性教育については、「教育だけで解決するのは難しくて、本人が性について教えてもらう場所を作らなければならない。例えば15年前だと、支援学校の修学旅行のお風呂の時間などで熱心な先生が教えてあげて、性の自立ができたという声も聞いていた。最近はなかなか少ない現状があるので、事業所や施設で保護者に情報を伝えていかなければならないし、それができる環境を作っていかなければならないと思う。eラーニングではそのような情報を提供していて、学習してくれた現場のスタッフからは、保護者に自分から教えてあげられるようになったという声も出てきている。小さなことかもしれないが少しずつ広めていければいいと思う」と話す。
障害者の性に対する声は国によって異なる。WHO(世界保健機関)は、障害者の性の問題について福祉の現場で相談に応じることなどを推奨。オランダでは障害者が性的なサービスを受ける場合、地域によって保険が適用されるようになっていたり、スウェーデンでは障害者が自慰行為をする際、介護の一貫として補助具の装着や服を脱がすことが認められていたりする。
志村氏はアメリカのオレゴン州で体験した話として、「スタッフが言っていたのは、障害者同士がラブホテルなどに行って、服を脱がせてあげて、避妊具を付けたら外で待ってあげるというのも支援の1つとして組まれている」と紹介。「日本ではこのレベルにいけていないのでそこまで持っていきたい。日本では、障害者の性はないものにされていたし、母親や祖母が制御してしまっている部分もある」と指摘した。
乙武氏は当事者の立場から、「性欲は、食欲、睡眠欲と合わせて3大欲求と言われるが、食事や睡眠と違って生死に関わるものではないということで後回しにされたのだと思う。ただし、ここが封じられると周りが思っている以上にしんどいんだということは理解してほしい」と訴えた。
最後に坂爪氏は「障害のある方が性的に生きやすい社会というのは誰にとっても生きやすい社会だと思う。障害者の性を自分ごととして捉えてほしい」、志村氏は「障害者に必要な配慮をしたうえでノーマルに接することができる社会を実現したい」と述べた。
(AbemaTV/AbemaPrimeより)
AbemaTIMES 2018年12月26日















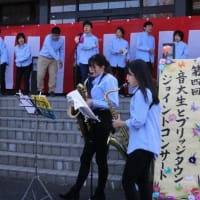




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます